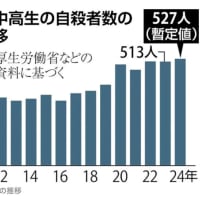日本のコメ作りが、海外で元気である。一つはビジネスとして、もう一つは国家的な支援、協力によって食料生産に多くの成果を上げている。
日本人はコメを食べなくなった。一つは畜産への大きなシフトである。コメを食べない代わりに、アメリカのトウモロコシを与えた家畜の、肉や卵や牛乳を食べるようになったからである。
日本人はコメを食べなくなって、農村は人的にも環境的にもあるいは経済的にも、コメ依存体制から大きく変わった。
コメ生産にかかわる技術は、減反という理不尽な政策によって、国内的には衰退の一途をたどってきた。人的にも政策的にも支援者や後継者もなくなってきた。
ところが、連綿と引き継がれ蓄積された技術、あるいは味覚は失われていないのである。
日本のコメ生産技術は、今や中南米、中東、そしてアフリカへと広がっている。日本のおコメは、我々が食べ慣れて無関心になってはいても、味覚としてはどの国のものより優れているのである。
とりわけ中国が裕福になるにつれて、日本米の作付を本気になりだしてきた。あるいは、亜熱帯地域の台湾での試行錯誤も、いい結果を生んでいる。生産量も成果を上げている。
高地や暖地あるいは乾燥地帯などでの、コメの作りに日本技術者が奔走し、成果を上げている。ネパールでは、20年にわたりコメ生産に携わり成果を上げ、国家の最高勲章を授与された技術者もいる。
海外で活躍し成果を上げる技術者たちであるが、後継者がいない悩みがある。ある技術者は、牛丼を例に挙げ、コメの味覚が途上国並みに下がっている、現状を嘆いていた。
つぶれたコメは不味いのであるが、安価なコメをタレなどで誤魔化している業者によって、これまで培われてきたコメの鋭い日本人の味覚が、なくなってきているというのである。
国内では、不要の技術のように扱われてきた、主食のコメ生産技術であるが、世界の食糧事情を変えるかもしれない。
食料危機は必ず起きる。それは食べ物の支援によって解決する問題なのではない。それぞれの国が、食糧を自給することでしか解決しない問題なのである。
日本はもう一度自国の食料を見直し、農業国家への道をたどるべきなのではないか。技術は培われているのである。