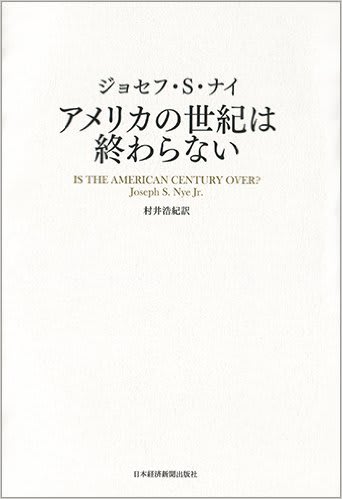
この本のタイトルは、「IS THE AMERICAN CENTURY OVER? アメリカの世紀は終わったのか」と言う事だが、日本語版のタイトルは、ナイ教授の結論をとって、「アメリカの世紀は終わらない」となっている。
著者は、
アメリカの世紀とは何かを検証しながら、ヘゲモニーに挑む可能性のあるヨーロッパ、日本、ロシア、インド、ブラジルの国力等を分析し、更に、中国については、1章を費やして比較検討して、これらの国が、アメリカを追い越して、アメリカが世界のパワーバランスの中心にいる構図を早く終わらせてしまうことは不可能ではないにしても、殆どありえない。
アメリカが、軍事、経済、そして、ソフトパワーの資源で傑出し、アメリカがグローバルなパワーバランスの働きの真ん中に構え、国際公共財の提供でも中心的な役目を果たしており、この時期がなお続くので、21世紀は中国の世紀だと宣言する人々とは違って、まだ、アメリカ後の世界を迎えていないし、アメリカの世紀は終わらない。と結論付けている。
しかし、これからも続くアメリカの世紀は、20世紀のものとは違って来る。
アメリカの世界経済に占める位置が低下して来ており、他国の台頭によって世界の構造が複雑化し、非国家アクターも勢力を拡大する中で、金融の安定、気候変動、テロリズム、そして、麻薬や感染症の世界的な流行への対応など、地球規模で検討されるべき課題が頻発して、如何なる超大国であっても、単独では国境を越えて立ち向かえないので、他の国と協力し合わなければならない。
各国は、ソフトパワーを駆使してネットワークを築き、国際機関を設立し、共通する脅威と挑戦に立ち向かくべきであり、アメリカは、国際システムで最大の国であり続けるので、軍事や経済など、国際公共財を提供する仕組み作りで、リーダシップを発揮しなければならない。と言うのである。
アメリカは、パワーのもととなるべき資源があるのに、それを現実のパワーにきちんと転換できていないと言う長年の非効率性が重大な問題であり、アメリカの「衰退」を口にすることが、結果的に他の国々に対して、例えば、ロシアが野心的な政策へと進み、中国が隣国へもっと自己主張を強めるなど、危険な政策を選ばせるよう刺激してしまっている。と言うのである。
これは、前にレビューしたように、ブレット・スティーブンズが、オバマの関与縮小の消極的外交が、ロシアや中国を付け上がらせていると言う論理と同列の主張であろう。
最大の問題は、イラク・トラウマの米国民の厭戦気質もあろうが、国内の政治的な膠着状況がしばしばリーダーシップの発揮を拒んでおり、このような状況が、アメリカが国際公共財に関して世界を主導する能力を弱め、結果的に、アメリカの世紀を持続して行くうえで重要となる信頼やソフトウエアを損なってきた。
優位性がやや後退し、世界がもっと複雑になる中で、アメリカがその地位を維持したいと考えるなら、内政でも外交でも、賢明で戦略的な選択を下すことが必要だ。と言うのである。
さて、中国に対するナイ教授の考え方だが、殆ど、脅威とは考えていないようである。
面白いのは、アンガス・マディソンの考え方を踏襲していて、二世紀前までは、中国の経済は最大であったのだから、「中国の台頭」は誤りで、「復興」が正確だと言っていることである。
経済については、中所得国の罠の問題もあり、行く手には厚い壁とも言うべき、非効率な国有企業、格差の拡大、環境の悪化、膨大な国内移住者、セーフティネットの不備、汚職、法の支配が確立していないことなど阻害要因があり、高齢化も著しく進むなど、成長も鈍化するであろうし、問題は、一人当たりの所得であり、アメリカを凌駕することはなかろう。
サービス分野の貿易では精彩を欠き、多くの輸出品は付加価値が低く、技術も、自前でイノベーションを引き起こすよりも、外国の技術を模倣するする戦略に多くを依存している。と、政治的な不備も含めて、民主的でイノベィティブで企業家精神の旺盛な、アメリカの比ではないと、論じている。
軍事力の差については、経済以上に歴然としている。
配備済みの軍備の規模では、アメリカは、中国に対して10対1の比率で優位であり、中国は、グローバルな規模で戦力を展開できるだけの能力を十分に持っていない。
人民解放軍にとっては、中東から東南アジアのマラッカ海峡まで続く円滑な航路の確保が現実的な問題となってくるが、ペルシャ湾の出口、ホルムズ海峡にいる米海軍が生命線を握り続けているし、空母など海軍力は何十年も遅れており、アメリカのような海外の各地に展開できる基盤は整っていない。 と言う。
尤も、現実には、米軍が中国の海岸線に近い近海に接近、介入することが難しくなりつつあり、アメリカが、この地域の同盟国に安全保障上の安心感を与え続けようとするならば、アメリカ側は、中国が進める領域拒否の戦略――自国のそばに米軍が接近し、自由に行動することを阻害する戦略――に対する戦力面での弱みを消すためには、投資がかさむであろう。と指摘している。
この辺りは、今回の南沙諸島の中国基地設営に対する米軍艦船の接近や日本政府の安保法案成立の推移などが、如実に現実を物語っている。
この中国のパワーの隆盛に対しては、インドと日本、そして、ベトナムが、競争相手になり、それは、アメリカにとって大いに有利となる。と言っているのが興味深い。
ナイ教授は、中国は、同盟国も海外の基地もなく、長距離の兵站を管理する仕組みも欠いていて、アメリカ軍のような遠征の経験も持たない。と中国の弱みを述べているが、アメリカが、はるかに、中国より優位に立つのは、世界の先進国の殆どと同盟関係なり友好関係にあることで、前述したように、エントロピーの増大で益々複雑化してくる国際情勢において、国境を越えて地球規模で対応しなければならなくなるので、
軍事、経済、そして、ソフト・パワーなどの資源で傑出したアメリカが、同盟国や友好国を糾合して協力体制を築き上げて有効な国際システムを確立することが最も重要であり、その中で、アメリカが、グローバルなパワーバランスの働きの真ん中に構えて、国際公共財の提供でも中心的な役目を果たすリーダーであるべきだと言う事であろう。
私は、殆ど、ナイ教授の見解には、異存はなく、ファリード・ザカリアの「アメリカ後の世界」やイアン・ブレマーの「「Gゼロ後」の世界」も興味深かったが、アメリカを、古代ローマと比較しながら、衰退論を展開したり、ヨーロッパや日本やBRIC's諸国と比較検討するなども
、また、文明論に踏み込んでの議論も面白かった。
地政学に対する、もう少し突っ込んだ議論もあればと思ったが、とにかく、今の日本の国防問題などを考えるのには、恰好の本ではないかと思う。
著者は、
アメリカの世紀とは何かを検証しながら、ヘゲモニーに挑む可能性のあるヨーロッパ、日本、ロシア、インド、ブラジルの国力等を分析し、更に、中国については、1章を費やして比較検討して、これらの国が、アメリカを追い越して、アメリカが世界のパワーバランスの中心にいる構図を早く終わらせてしまうことは不可能ではないにしても、殆どありえない。
アメリカが、軍事、経済、そして、ソフトパワーの資源で傑出し、アメリカがグローバルなパワーバランスの働きの真ん中に構え、国際公共財の提供でも中心的な役目を果たしており、この時期がなお続くので、21世紀は中国の世紀だと宣言する人々とは違って、まだ、アメリカ後の世界を迎えていないし、アメリカの世紀は終わらない。と結論付けている。
しかし、これからも続くアメリカの世紀は、20世紀のものとは違って来る。
アメリカの世界経済に占める位置が低下して来ており、他国の台頭によって世界の構造が複雑化し、非国家アクターも勢力を拡大する中で、金融の安定、気候変動、テロリズム、そして、麻薬や感染症の世界的な流行への対応など、地球規模で検討されるべき課題が頻発して、如何なる超大国であっても、単独では国境を越えて立ち向かえないので、他の国と協力し合わなければならない。
各国は、ソフトパワーを駆使してネットワークを築き、国際機関を設立し、共通する脅威と挑戦に立ち向かくべきであり、アメリカは、国際システムで最大の国であり続けるので、軍事や経済など、国際公共財を提供する仕組み作りで、リーダシップを発揮しなければならない。と言うのである。
アメリカは、パワーのもととなるべき資源があるのに、それを現実のパワーにきちんと転換できていないと言う長年の非効率性が重大な問題であり、アメリカの「衰退」を口にすることが、結果的に他の国々に対して、例えば、ロシアが野心的な政策へと進み、中国が隣国へもっと自己主張を強めるなど、危険な政策を選ばせるよう刺激してしまっている。と言うのである。
これは、前にレビューしたように、ブレット・スティーブンズが、オバマの関与縮小の消極的外交が、ロシアや中国を付け上がらせていると言う論理と同列の主張であろう。
最大の問題は、イラク・トラウマの米国民の厭戦気質もあろうが、国内の政治的な膠着状況がしばしばリーダーシップの発揮を拒んでおり、このような状況が、アメリカが国際公共財に関して世界を主導する能力を弱め、結果的に、アメリカの世紀を持続して行くうえで重要となる信頼やソフトウエアを損なってきた。
優位性がやや後退し、世界がもっと複雑になる中で、アメリカがその地位を維持したいと考えるなら、内政でも外交でも、賢明で戦略的な選択を下すことが必要だ。と言うのである。
さて、中国に対するナイ教授の考え方だが、殆ど、脅威とは考えていないようである。
面白いのは、アンガス・マディソンの考え方を踏襲していて、二世紀前までは、中国の経済は最大であったのだから、「中国の台頭」は誤りで、「復興」が正確だと言っていることである。
経済については、中所得国の罠の問題もあり、行く手には厚い壁とも言うべき、非効率な国有企業、格差の拡大、環境の悪化、膨大な国内移住者、セーフティネットの不備、汚職、法の支配が確立していないことなど阻害要因があり、高齢化も著しく進むなど、成長も鈍化するであろうし、問題は、一人当たりの所得であり、アメリカを凌駕することはなかろう。
サービス分野の貿易では精彩を欠き、多くの輸出品は付加価値が低く、技術も、自前でイノベーションを引き起こすよりも、外国の技術を模倣するする戦略に多くを依存している。と、政治的な不備も含めて、民主的でイノベィティブで企業家精神の旺盛な、アメリカの比ではないと、論じている。
軍事力の差については、経済以上に歴然としている。
配備済みの軍備の規模では、アメリカは、中国に対して10対1の比率で優位であり、中国は、グローバルな規模で戦力を展開できるだけの能力を十分に持っていない。
人民解放軍にとっては、中東から東南アジアのマラッカ海峡まで続く円滑な航路の確保が現実的な問題となってくるが、ペルシャ湾の出口、ホルムズ海峡にいる米海軍が生命線を握り続けているし、空母など海軍力は何十年も遅れており、アメリカのような海外の各地に展開できる基盤は整っていない。 と言う。
尤も、現実には、米軍が中国の海岸線に近い近海に接近、介入することが難しくなりつつあり、アメリカが、この地域の同盟国に安全保障上の安心感を与え続けようとするならば、アメリカ側は、中国が進める領域拒否の戦略――自国のそばに米軍が接近し、自由に行動することを阻害する戦略――に対する戦力面での弱みを消すためには、投資がかさむであろう。と指摘している。
この辺りは、今回の南沙諸島の中国基地設営に対する米軍艦船の接近や日本政府の安保法案成立の推移などが、如実に現実を物語っている。
この中国のパワーの隆盛に対しては、インドと日本、そして、ベトナムが、競争相手になり、それは、アメリカにとって大いに有利となる。と言っているのが興味深い。
ナイ教授は、中国は、同盟国も海外の基地もなく、長距離の兵站を管理する仕組みも欠いていて、アメリカ軍のような遠征の経験も持たない。と中国の弱みを述べているが、アメリカが、はるかに、中国より優位に立つのは、世界の先進国の殆どと同盟関係なり友好関係にあることで、前述したように、エントロピーの増大で益々複雑化してくる国際情勢において、国境を越えて地球規模で対応しなければならなくなるので、
軍事、経済、そして、ソフト・パワーなどの資源で傑出したアメリカが、同盟国や友好国を糾合して協力体制を築き上げて有効な国際システムを確立することが最も重要であり、その中で、アメリカが、グローバルなパワーバランスの働きの真ん中に構えて、国際公共財の提供でも中心的な役目を果たすリーダーであるべきだと言う事であろう。
私は、殆ど、ナイ教授の見解には、異存はなく、ファリード・ザカリアの「アメリカ後の世界」やイアン・ブレマーの「「Gゼロ後」の世界」も興味深かったが、アメリカを、古代ローマと比較しながら、衰退論を展開したり、ヨーロッパや日本やBRIC's諸国と比較検討するなども
、また、文明論に踏み込んでの議論も面白かった。
地政学に対する、もう少し突っ込んだ議論もあればと思ったが、とにかく、今の日本の国防問題などを考えるのには、恰好の本ではないかと思う。
























