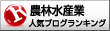日本は決められたことをやりたがる民族性がある。今日は土用の丑の日であるが、誰もがウナギを食わなけれならないと決めてかかっている。
メディアは高騰するウナギ価格ばかりを報道する。ウナギの資源が怖ろし勢いで枯渇しているが、そうした事実と背景には黙している。
ウナギは、日本が河口でシラスウナギ(稚魚)を捕獲し て養殖する技術を確立した。ご多分に漏れず、中国と台湾が安い労力で、これにとって変わることになる。今では、国内消費の半分以上が中国からの輸入である。
て養殖する技術を確立した。ご多分に漏れず、中国と台湾が安い労力で、これにとって変わることになる。今では、国内消費の半分以上が中国からの輸入である。
そこで食糧とは何かも考えず市場原理しか考えない業者は、枯渇に対して価格を釣り上げて、さらに中国依存を強くする。日本のシラスウナギが採れなくなり、中国はヨーロッパウナギの稚魚を輸入するようになった。
資源を荒らされたEUは、ヨーロッパウナギの保護に出て、ワシントン条約付属書Ⅱに指定した。今年4月からは輸出を禁止した。
そこで経済大国中国は、北米のアメリカウナギの稚魚を求めるようになった。EUを見習いアメリカは、ワシントン条約でウナギを付属書Ⅱにすることを、検討し始めたのである。
これがウナギが高騰することになった、経済的理由である。
しかし、もっと重要なことは、ウナギの稚魚が減少した原因である。日本人は少々高くなっても、ウナギを食べたがる。夏には土用の丑の日まで設けて食いたがる。こうしたことが、さらなる資源の枯渇へとつながるのである。
ウナギの稚魚の減少は 〇乱獲による 〇生息環境の悪化による 〇生態系に不明なことが多い、が考えられる。日本の開発した天然稚魚捕獲から養殖への技術は、環境悪化に拍車をかけることになったのである。
食糧を支えるのは環境である。高くなっても買い続けると、途上 国がお金もうけに走る。日本がそれ買い付け、悪化した環境をさらに悪化させることになる。
国がお金もうけに走る。日本がそれ買い付け、悪化した環境をさらに悪化させることになる。
バレンタインのチョコレートもそうであるが、このような煽られて買う風習が資源を枯渇させる。高くなると食べなければいいのである。価格を際限なく上げてでも食いたいと思うのは間違いである。
食糧が減少するのは、価格の問題ではない。食糧価格の高騰は資源減少の指標でもあり、警告でもある。TPPは食料を含めあらゆる商品を価格だけで評価する、無関税システムである。資源の枯渇や環境のことなど全く考えない制度でもある。