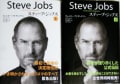このⅡ部には、アップルが、ソニーとの競争で何故勝ったのか、ソニーとのイノベーションとの取り組みに関する対応の差など、何ヵ所かで書かれていて、非常に興味を持った。
これまで、このブログで、ソニーのお家芸であった筈の破壊的イノベーションによる新製品の開発が止まってしまって、持続的イノベーションばかりに傾注して革新的なヒット商品を打ち出せずに、アップルや任天堂に先を越されたのみならず、コモディティに堕してしまったTVなどコンス―マー・エレクトロニクスをコアに事業を展開するなど、歌を忘れたカナリア状態にあることについて、何度も書いて来たので、特に、スティーブ・ジョブズのソニーに対する見解については、大変関心があった。尤も、どこまでがジョブズの考えなのかは、アイザックソンの文章なので推測するしかないのだが。
ソニーが、アップルに出し抜かれたのは、間違いなく、iPodとiTunesの新機軸が、ウォークマンを凌駕した時である。
2003年、アップルが、iTunesストア発表した週に開かれたソニーの新年度年頭訓示総会で、ソニーミュージックのトップになったアンディ・ラックが、iPodをポケットから出して、
「これがウォークマンキラーだ。怪しげなところなどどこにもない。こういうものが作れるように、ソニーは音楽会社を買ったんだ。君たちならもっと良いものが作れる。」と檄を飛ばしたが、しかし、ソニーには出来なかった。
ウォークマンでポータブル音楽プレイヤーの世界を拓いた実績もあれば、素晴らしいレコード会社を傘下に持っている。美しい消費者家電を作って来た長い歴史もある。ハードウエア、ソフトウエア、機器、コンテンツ販売を統合すると言うジョブズの戦略に対抗するために必要なものはすべてそろっているのに、何故、ソニーは失敗したのだろうか、と、アイザックソンは問いかけて、二つの理由を挙げている。
ひとつは、ALOタイムワーナーなどと同じように部門ごとの独立採算性を採用している点だろう。そのような会社では、部門間の連携で相乗効果を生むのは難しい。
アップルは、損益計算書を持つ部門はなく、会社全体で損益を持つと言うのだが、これは、損益の問題と言うよりは、部門間の連携がスムーズに行われないセクショナリズムが蔓延する日本の組織構造の典型であり、部分最適が幅を利かせて全体最適の文化に乏しい結果の表れであろう。
まして、出井信之氏さえ自身の意思命令を、全社的には勿論、技術部門などへも十分に伝達出来なかったと言うのであるから、ソニーそのものが、大企業病に侵されて制度疲労をしていたのだから、尚更であろう。
このソニーの部門間の調整不能現象については、ジョブズのiTunes交渉に加わっていたレコード会社のトップたちは、長い間同じような交渉をソニーとしていたのだが埒が明かず、ソニーではどうにもならないと縁を切って、アップルに乗り換えたのだが、ユニバーサル傘下のJ・イオヴォインなどは、「どうしてソニーがダメだったのか分からない。史上有数の失策です。アップルの場合、社内で協力しない部門は首が飛びます。でもソニーは社内で部門同士が争っていました。」と言っている。
もう一つは、ふつう会社はそういうものだが、ソニーも共食いを心配した。デジタル化した楽曲を簡単に共有できる音楽プレイヤーと音楽サービスを作ると、レコード部門の影響が出るのではないかと心配したのだ。と言う。
その点、ジョブズは”共食いを恐れるな”を事業の基本原則として、iPhoneを出せばiPodの売り上げが落ちるかも知れないし、iPadを出せばノートブックの売り上げが落ちるかも知れないが、躊躇せずに突き進んだのである。
イノベーションのためには、破壊しなければならないと、ドラッカーは、ずっと唱え続けていたし、GEのジェフリー・イメルトCEOなどは、昨年、HBRに”How GE Is Disrupting Itself”と言う過激とも言うべき論文を発表して、自社を破壊してでも、リバース・イノベーションを追求しなければ、新興国の巨人に駆逐されてしまうと危機感をつのらせて、新興国でのイノベーションの追及戦略を開陳していた。
このあたりの認識も、成熟に達して成長の止まった先進国においてではなく、真に価値ある破壊的イノベーションは、今や、巨大な市場として勃興しつつある新興国のBOTやMOPの中から生まれて来ると言う強い確信があるからであろう。
このアップルのiTunesの成功について、もう一つ、アイザックソンは、興味深い指摘をしている。
このチャンスを与えたのは、ソニーだと言うのである。
音楽ファイルを保護する標準技術が早期に確立され、音楽関連の企業が皆参加すれば、数多くのオンラインストアが次々に生まれた可能性がある。そうなっていたら、ジョブズがiTunesストアを生み出し、オンライン販売をアップルが一手に握るのは難しかったであろう。
ところが、クパチーノで行われた2002年1月のミーティング後、ソニーは、協力関係を解消して、使用料が徴収できる独自規格のに道を行くと決めたのである。
いずれにしろ、ソニーは、すべてにおいて、アップルを凌駕する技術も能力も持ち合わせていたにも拘わらず、ジョブズのエンドツーエンド戦略に負けてしまって、iTunesで曲が売れればiPodが売れ、更に、マッキントッシュが売れる相乗効果で益々独走を許した。
ラックにとって、悔やんでも悔やみきれないのは、同じことがソニーにも出来た筈なのに、ハードウエアとソフトウエアとコンテンツ部門を協力させられずに失敗したことである。
マイクロソフトのビル・ゲイツも歯軋りして残念がり、自分たちにはもっと上手にやれると言ったものの、それは、あくまで二番煎じの後追い戦略であって、オリジナリティで破壊的イノベーションを追及して革新的なビジネスモデルを立ち上げたジョブズの完全勝利であった。
もう一つ興味深いのは、最晩年のジョブズが、電子新聞で協力関係を確立したマードックとのディナーで、会社には起業家精神と機敏さを重んじる文化を植え付けなければならないと言う話が出て、ソニーは失敗したとマードックが指摘して、ジョブズも同意した。と言う記述がある。
また、ジョブズは、昔、大会社は明確な企業文化を持てないものだと思っていたが、マードックは実現したし、自分もアップルで実現できたので、今は、持たせられると思うと言っている。
結局、ソニーには、社内におけるベンチュアーと言うか、起業家を育む企業文化がなくなってしまったと言うことであろうか。
以前に、スライウォツキーが、ソニーの凋落は、ダブルベッティングに失敗したからだと述べていたことにコメントしたことがるが、ローエンドの破壊的イノべーしょんが発生した時点で、はっきりと、それと認知できるとは限らない。
ジョブズのiPodやピクサーなどにしても、最初から明確な意図があって順風満帆に成功したのではなく、紆余曲折やセレンディピティがあったのも事実で、要するに、眼前の困難を克服してブルーオーシャンを目指して突き進み、諦めずに戦い抜いた結果であって、企業の中に、そのような意思を持った経営者なり、起業精神に燃えたイノベーターを生み出す土壌があるのかどうかと言うことが重要ではないかと思う。
もう一つ、これは私の持論なのだが、ソニーのトップないし経営者の一人でも、クリステンセンの「イノベーションのジレンマ(本当はイノベーターのジレンマ」を真面に読んでいたら今日の凋落はなかったと思うのだが、
アイザックソンは、「クレイトン・クリステンセンは「イノベーターのジレンマ」と言う言葉で、「何かを発明した人は自分が発明したモノに最後までしがみ付きがちだ」と表現したけれど、僕らは時代に取り残されたくないからね。」とジョブが言ったことを引用している。
この差が、実は致命的な差なのである。
これまで、このブログで、ソニーのお家芸であった筈の破壊的イノベーションによる新製品の開発が止まってしまって、持続的イノベーションばかりに傾注して革新的なヒット商品を打ち出せずに、アップルや任天堂に先を越されたのみならず、コモディティに堕してしまったTVなどコンス―マー・エレクトロニクスをコアに事業を展開するなど、歌を忘れたカナリア状態にあることについて、何度も書いて来たので、特に、スティーブ・ジョブズのソニーに対する見解については、大変関心があった。尤も、どこまでがジョブズの考えなのかは、アイザックソンの文章なので推測するしかないのだが。
ソニーが、アップルに出し抜かれたのは、間違いなく、iPodとiTunesの新機軸が、ウォークマンを凌駕した時である。
2003年、アップルが、iTunesストア発表した週に開かれたソニーの新年度年頭訓示総会で、ソニーミュージックのトップになったアンディ・ラックが、iPodをポケットから出して、
「これがウォークマンキラーだ。怪しげなところなどどこにもない。こういうものが作れるように、ソニーは音楽会社を買ったんだ。君たちならもっと良いものが作れる。」と檄を飛ばしたが、しかし、ソニーには出来なかった。
ウォークマンでポータブル音楽プレイヤーの世界を拓いた実績もあれば、素晴らしいレコード会社を傘下に持っている。美しい消費者家電を作って来た長い歴史もある。ハードウエア、ソフトウエア、機器、コンテンツ販売を統合すると言うジョブズの戦略に対抗するために必要なものはすべてそろっているのに、何故、ソニーは失敗したのだろうか、と、アイザックソンは問いかけて、二つの理由を挙げている。
ひとつは、ALOタイムワーナーなどと同じように部門ごとの独立採算性を採用している点だろう。そのような会社では、部門間の連携で相乗効果を生むのは難しい。
アップルは、損益計算書を持つ部門はなく、会社全体で損益を持つと言うのだが、これは、損益の問題と言うよりは、部門間の連携がスムーズに行われないセクショナリズムが蔓延する日本の組織構造の典型であり、部分最適が幅を利かせて全体最適の文化に乏しい結果の表れであろう。
まして、出井信之氏さえ自身の意思命令を、全社的には勿論、技術部門などへも十分に伝達出来なかったと言うのであるから、ソニーそのものが、大企業病に侵されて制度疲労をしていたのだから、尚更であろう。
このソニーの部門間の調整不能現象については、ジョブズのiTunes交渉に加わっていたレコード会社のトップたちは、長い間同じような交渉をソニーとしていたのだが埒が明かず、ソニーではどうにもならないと縁を切って、アップルに乗り換えたのだが、ユニバーサル傘下のJ・イオヴォインなどは、「どうしてソニーがダメだったのか分からない。史上有数の失策です。アップルの場合、社内で協力しない部門は首が飛びます。でもソニーは社内で部門同士が争っていました。」と言っている。
もう一つは、ふつう会社はそういうものだが、ソニーも共食いを心配した。デジタル化した楽曲を簡単に共有できる音楽プレイヤーと音楽サービスを作ると、レコード部門の影響が出るのではないかと心配したのだ。と言う。
その点、ジョブズは”共食いを恐れるな”を事業の基本原則として、iPhoneを出せばiPodの売り上げが落ちるかも知れないし、iPadを出せばノートブックの売り上げが落ちるかも知れないが、躊躇せずに突き進んだのである。
イノベーションのためには、破壊しなければならないと、ドラッカーは、ずっと唱え続けていたし、GEのジェフリー・イメルトCEOなどは、昨年、HBRに”How GE Is Disrupting Itself”と言う過激とも言うべき論文を発表して、自社を破壊してでも、リバース・イノベーションを追求しなければ、新興国の巨人に駆逐されてしまうと危機感をつのらせて、新興国でのイノベーションの追及戦略を開陳していた。
このあたりの認識も、成熟に達して成長の止まった先進国においてではなく、真に価値ある破壊的イノベーションは、今や、巨大な市場として勃興しつつある新興国のBOTやMOPの中から生まれて来ると言う強い確信があるからであろう。
このアップルのiTunesの成功について、もう一つ、アイザックソンは、興味深い指摘をしている。
このチャンスを与えたのは、ソニーだと言うのである。
音楽ファイルを保護する標準技術が早期に確立され、音楽関連の企業が皆参加すれば、数多くのオンラインストアが次々に生まれた可能性がある。そうなっていたら、ジョブズがiTunesストアを生み出し、オンライン販売をアップルが一手に握るのは難しかったであろう。
ところが、クパチーノで行われた2002年1月のミーティング後、ソニーは、協力関係を解消して、使用料が徴収できる独自規格のに道を行くと決めたのである。
いずれにしろ、ソニーは、すべてにおいて、アップルを凌駕する技術も能力も持ち合わせていたにも拘わらず、ジョブズのエンドツーエンド戦略に負けてしまって、iTunesで曲が売れればiPodが売れ、更に、マッキントッシュが売れる相乗効果で益々独走を許した。
ラックにとって、悔やんでも悔やみきれないのは、同じことがソニーにも出来た筈なのに、ハードウエアとソフトウエアとコンテンツ部門を協力させられずに失敗したことである。
マイクロソフトのビル・ゲイツも歯軋りして残念がり、自分たちにはもっと上手にやれると言ったものの、それは、あくまで二番煎じの後追い戦略であって、オリジナリティで破壊的イノベーションを追及して革新的なビジネスモデルを立ち上げたジョブズの完全勝利であった。
もう一つ興味深いのは、最晩年のジョブズが、電子新聞で協力関係を確立したマードックとのディナーで、会社には起業家精神と機敏さを重んじる文化を植え付けなければならないと言う話が出て、ソニーは失敗したとマードックが指摘して、ジョブズも同意した。と言う記述がある。
また、ジョブズは、昔、大会社は明確な企業文化を持てないものだと思っていたが、マードックは実現したし、自分もアップルで実現できたので、今は、持たせられると思うと言っている。
結局、ソニーには、社内におけるベンチュアーと言うか、起業家を育む企業文化がなくなってしまったと言うことであろうか。
以前に、スライウォツキーが、ソニーの凋落は、ダブルベッティングに失敗したからだと述べていたことにコメントしたことがるが、ローエンドの破壊的イノべーしょんが発生した時点で、はっきりと、それと認知できるとは限らない。
ジョブズのiPodやピクサーなどにしても、最初から明確な意図があって順風満帆に成功したのではなく、紆余曲折やセレンディピティがあったのも事実で、要するに、眼前の困難を克服してブルーオーシャンを目指して突き進み、諦めずに戦い抜いた結果であって、企業の中に、そのような意思を持った経営者なり、起業精神に燃えたイノベーターを生み出す土壌があるのかどうかと言うことが重要ではないかと思う。
もう一つ、これは私の持論なのだが、ソニーのトップないし経営者の一人でも、クリステンセンの「イノベーションのジレンマ(本当はイノベーターのジレンマ」を真面に読んでいたら今日の凋落はなかったと思うのだが、
アイザックソンは、「クレイトン・クリステンセンは「イノベーターのジレンマ」と言う言葉で、「何かを発明した人は自分が発明したモノに最後までしがみ付きがちだ」と表現したけれど、僕らは時代に取り残されたくないからね。」とジョブが言ったことを引用している。
この差が、実は致命的な差なのである。