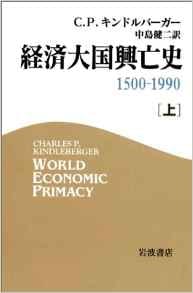
今回面白いと思ったのは、ベネチャほかのイタリア都市国家の凋落が、ヴァスコ・ダ・ガマのカリカットへの渡航成功にもかかわらず、それ程、直線的にストレートに行かなかった、すなわち、ベネチァが帆船効果を発揮して、抵抗して勢力を維持したと言うことである。
帆船効果とは、蒸気機関の開発により、駆逐されるべき筈であった帆船が、技術開発効率化の更なる推進よって長期に生き延びたように、例えば、
ガス灯会社が電球の発明によって生まれた電灯会社と競争するために、ガスの供給や配送、ガス灯システムの改良等で持続的イノベーションを追及して生産性のアップに努めて、確立した地位に守られた、豊富な資金を持った既存の業者が、「既存技術のイノベーション」で逆襲して、新技術の参入の事業に抵抗して生き延びようとしたケースである。
ヴァスコ・ダ・ガマがインド洋のカリカットまで航行したのは1497-1498年、
ポルトガルがペルシャ湾の入り口であるホルムズ海峡を占拠したのは、香料と絹布のヴェネツィアルートを断ち切り、喜望峰周りでヨーロッパに向かう貿易を自分たちで独占することを狙ったものであった。
ヴェネツィア・ルートとは、ガマ以前の東西交渉主要ルートで、インドからペルシャまでは船で、そこからシリアまではキャラヴァンを、それからはヴェネツィァまではガレー船を利用して通商貿易する交易ルートであった。
1504年に、レヴァントよりも早く、リスボン経由でヴェネツィアに胡椒が送られてきた時には、これらアドレア海のイタリア都市は破壊するものと考えられたが、しかし、そのようにはならなかったのである。
キャラヴァンによる「輝かしき行商交易」は、ペルシャ人の保護を受けて、また、ガレー船も帆船に切り替えられて、輸送コストが抑制されたので、17世紀にいたっても、ヴェネツィアのキャラバン・ルートは、ポルトガルのカラック船ルートに太刀打ちすることができた。
そうこうするうちに、どちらのルートとも、輸入胡椒の過剰を齎し、そのために、輸入品は、多種の香料や絹や木綿に切り替えられていったと言うから興味深い。
いずれにしろ、ポルトガルの喜望峰周りのアジアン交易ルートは、完全に、陸および海のシルクロードを駆逐できなかったのである。
ところで、もう一つ興味深いのは、今では、EUでも、低開発国で、経済的にも弱小であり、当時も、ポルトガルの人口は、僅か200万人、バルト海に向けて塩を出荷するセトゥバルとワインを輸出するオポルトの二つの港しか持たずに、概要経験のある船乗りも不足していたと言うポルトガルが、殆ど一世紀半も貿易大国として世界に君臨し多と言うのは、驚異と言う以外にはない。
ポルトガルの首都リスボンのベレンに、大航海時代の幕開けを記念した記念碑「発見のモニュメント パドラオン・ドス・デスコブリメントス」が立っている。
記念碑は52メートルの高さのコンクリート製で、キャラベル船の船首を模したモニュメントで、先頭に立ったエンリケ航海王子の雄姿がすべてを物語っており、広場の地面に巨大な世界地図が埋め込まれており、アジアの各都市に年代が打ち込まれていて、発見と言った調子で、記録されているのを見た時には、一寸、驚いた。
しかし、この何の変哲もない港町から、ヴァスコ・ダ・ガマが1497年にインドへ向けて、ペドロ・アルヴァレス・カブラルが、1499年にブラジルへ向けて旅だったのである。
私は、4年間ブラジルのサンパウロに住んでいたので、その故国であるポルトガルを2回訪れており、このベレン港に立った時には、何とも言えない程感動して、長い間佇んでいた。
帆船効果とは、蒸気機関の開発により、駆逐されるべき筈であった帆船が、技術開発効率化の更なる推進よって長期に生き延びたように、例えば、
ガス灯会社が電球の発明によって生まれた電灯会社と競争するために、ガスの供給や配送、ガス灯システムの改良等で持続的イノベーションを追及して生産性のアップに努めて、確立した地位に守られた、豊富な資金を持った既存の業者が、「既存技術のイノベーション」で逆襲して、新技術の参入の事業に抵抗して生き延びようとしたケースである。
ヴァスコ・ダ・ガマがインド洋のカリカットまで航行したのは1497-1498年、
ポルトガルがペルシャ湾の入り口であるホルムズ海峡を占拠したのは、香料と絹布のヴェネツィアルートを断ち切り、喜望峰周りでヨーロッパに向かう貿易を自分たちで独占することを狙ったものであった。
ヴェネツィア・ルートとは、ガマ以前の東西交渉主要ルートで、インドからペルシャまでは船で、そこからシリアまではキャラヴァンを、それからはヴェネツィァまではガレー船を利用して通商貿易する交易ルートであった。
1504年に、レヴァントよりも早く、リスボン経由でヴェネツィアに胡椒が送られてきた時には、これらアドレア海のイタリア都市は破壊するものと考えられたが、しかし、そのようにはならなかったのである。
キャラヴァンによる「輝かしき行商交易」は、ペルシャ人の保護を受けて、また、ガレー船も帆船に切り替えられて、輸送コストが抑制されたので、17世紀にいたっても、ヴェネツィアのキャラバン・ルートは、ポルトガルのカラック船ルートに太刀打ちすることができた。
そうこうするうちに、どちらのルートとも、輸入胡椒の過剰を齎し、そのために、輸入品は、多種の香料や絹や木綿に切り替えられていったと言うから興味深い。
いずれにしろ、ポルトガルの喜望峰周りのアジアン交易ルートは、完全に、陸および海のシルクロードを駆逐できなかったのである。
ところで、もう一つ興味深いのは、今では、EUでも、低開発国で、経済的にも弱小であり、当時も、ポルトガルの人口は、僅か200万人、バルト海に向けて塩を出荷するセトゥバルとワインを輸出するオポルトの二つの港しか持たずに、概要経験のある船乗りも不足していたと言うポルトガルが、殆ど一世紀半も貿易大国として世界に君臨し多と言うのは、驚異と言う以外にはない。
ポルトガルの首都リスボンのベレンに、大航海時代の幕開けを記念した記念碑「発見のモニュメント パドラオン・ドス・デスコブリメントス」が立っている。
記念碑は52メートルの高さのコンクリート製で、キャラベル船の船首を模したモニュメントで、先頭に立ったエンリケ航海王子の雄姿がすべてを物語っており、広場の地面に巨大な世界地図が埋め込まれており、アジアの各都市に年代が打ち込まれていて、発見と言った調子で、記録されているのを見た時には、一寸、驚いた。
しかし、この何の変哲もない港町から、ヴァスコ・ダ・ガマが1497年にインドへ向けて、ペドロ・アルヴァレス・カブラルが、1499年にブラジルへ向けて旅だったのである。
私は、4年間ブラジルのサンパウロに住んでいたので、その故国であるポルトガルを2回訪れており、このベレン港に立った時には、何とも言えない程感動して、長い間佇んでいた。
























