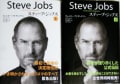シュンペーターが生きていれば狂喜するような判で押したようなイノベーターであった「スティーブ・ジョブズ」が逝ってしまった。
このスティーブ・ジョブ公認の自叙伝とも言うべきこのアイザックソンの本の中でも、「自分は長生きしないだろうと予言して、やりたいことを急いでやらなければならないので、せっかちで先を急ぐのだ」と言っていたと記しているが、あまりにも、早いあっけない最後であった。
まず、翻訳本1冊目しか読んでいないので、レビューをするのは早いと思うのだが、アップルを追われて立ち上げた「NeXT」の失敗や、「ピクサー」での「トイ・ストーリー」の成功の所まで終わっていることもあり、新鮮な所で、印象に残ったことだけでもメモ風に記しておきたいと思う。
以前に、ヤングとサイモンの「スティーブ・ジョブズ ICON:Steze Jobs」を読んでいるので、2005年くらいまでのスティーブ・ジョブズの業績や仕事などについては、しっかりとフォローしているのだが、この本には、ジョブズの恋の物語や里子に出された生い立ちや肉親との私生活など個人的な逸話などもかなり詳しく書かれていて、非常に面白くなっている。
まず、アップルを生み出した相棒のスティーブ・ウォズニャック共々、音楽に対する強い情熱を持っていて、特に、ボブ・ディランについては海賊版テープも含めてすべて収集して、TEACの高級テープデッキで楽しんでいたと言うことだが、正に、iPod、iTuneへの伏線であろうか。
二人の協力体制で、タダで電話を掛けられるブルー・ボックスを作って、ヘンリー・キッシンジャーを騙ってローマ法王に電話をするなど悪戯をしながら、作って売れば良いと言うビジネスに開眼したこと。最初からそうだが、アップルⅠを皆にタダであげるつもりだったと言う商売気の全くないウォズが、凄いものを設計して作り出し、ジョブズが、それでお金を儲ける方法を見つけ出すと言う二人三脚が功を奏することになる。
菜食主義に禅宗、瞑想にスピリチュアリティ、LSDにロックと言ったサブカルチュアの中で、奔放に青春を生きて来たジョブズの東洋思想への傾斜は、尋常ではなかった。
自分自身の探求のために師を訪ねてインドを放浪し、東洋思想やヒンズー教、禅宗など悟りを求めて呻吟していた19歳ころから、ずっと、ジョブスは、般若、心を研ぎ澄ますことによって体得する最高の知恵や認識など、東洋の宗教の教え精神を求め続けた。
毎日、朝晩瞑想し、禅を学び、途中で、時々、スタンフォード大学へ、物理や工学の授業を聴講しに出かけていたと言うのだが、人間が努力して習得した西洋の合理的思考とは違った、人間本来に備わる東洋の直観の力、体験に基づく知恵の力を信じていたと言う。
瞑想すれば、直観が花開き、物事がクリアに見え、現状が把握でき、ゆったりとした心で、隅々まで知覚出来、今まで見えなかったことが沢山見えるようになる、これこそ修行であり、そのためには修業が必要だと言うのである。
曹洞宗の僧侶知野弘文師が、ジョブズに禅宗を教えたのだが、1991年3月18日に、木魚をたたき、銅鑼を鳴らして、香をたいてお経をあげて結婚式を取り仕切った。
デザインに対して偏執狂とも思しき程拘ったジョブズは、デザイン感覚を磨く過程で、和のスタイルに引かれて、ミヤケ・イッセイなど有名な和風デザイナーとの付き合いを深めて行くのだが、特に、日本の禅宗は素晴らしく美的で、京都に沢山ある庭など、その文化が醸し出すものに深く心を動かされると言う。
そして、頂点を極めた筈のジョブズは、仏教を通じて、モノを持つと人生は豊かにならず、逆に乱してしまうことが多いと学んだので、ビル・ゲイツが、ここで、家族全員が住んでいるのかとびっくりしたほど質素な家に住んでいて、セクリティもなかったと言うのだから、驚異と言う外はない。
ところで、非常に興味深いのは、この本で、アイザックソンは、ジョブズとビル・ゲイツとの関わりや違いなどについて、ビビッドに描いていることである。
性格や生い立ちの違いは、好対照だが、ITの世界では、
ジョブズは、完璧主義者で総てをコントロールしたいと強く望み、アーティストのように一徹な気性で突き進み、アップルは、ハードウェアとソフトウエアのコンテンツを、シームレスなパッケージにしっかりとした統合するタイプの戦略を取ったが、
ビル・ゲイツは、頭が良くて計算高く、ビジネスと技術について現実的な分析を行い、様々なメーカーに対して、マイクロソフトとのオペレーティングシステムやソフトのライセンスを供与した。
ゲイツは、不本意ながらも、「技術は分からないのに何が上手く行くかについては驚くほど鼻が利く」とジョブズに敬意を払っていたが、ジョブズは、「基本的に想像力が乏しく、何も発明したことがない。いつも、他の人のアイデアをずうずうしく横取りしてばかり」とゲイツの強さを正当に評価しようとしなかったと言う。
その後、ジョブズは、マイクロソフトについて、「美的感覚がない。オリジナルなアイデアは生み出さないし、製品に文化の香りがない。悲しいのは、彼らが三流の製品ばかりを作ることだ。」と言っている。
アップルの方が革新的で創造的で、実装はエレガント、デザインは素晴らしかったが、不完全なコピーを作ったマイクロソフトが、最終的に、オペレーティングシステムの戦いを制してしまったのだから、ジョブズが、喚くのも無理からぬことであろうと言うのである。
やはり、問題は、ジョブズの場合、ハードとソフトもエンドツーエンドで総てを統合すべきと考えて、他との互換性を一切認めなかったことに問題があり、ゲイツの方が、互換性のあるマシンを多くの会社が作り、どのハードも、標準的なオペレーティングシステム(ウインドウズ)が走り、同じアプリケーション(ワードやエクセル)が使える世界を構築する方が利益になると考えたことが、世界標準を抑えたと言うことであろう。
他の追随を許さない断トツの破壊的イノベーションによる新製品やサービスの誕生で、市場を完全支配出来るのならいざ知らず、デジタル革命で、製造業のモジュラー化がますます進展して行き、テクノロジーの複雑さと総合化が益々進行して行くことを考えれば、世界は、正に、オープン化が進むのであって、囲い込みの独占戦略が時代遅れになるのは、必然ではなかろうかと思っている。
このスティーブ・ジョブ公認の自叙伝とも言うべきこのアイザックソンの本の中でも、「自分は長生きしないだろうと予言して、やりたいことを急いでやらなければならないので、せっかちで先を急ぐのだ」と言っていたと記しているが、あまりにも、早いあっけない最後であった。
まず、翻訳本1冊目しか読んでいないので、レビューをするのは早いと思うのだが、アップルを追われて立ち上げた「NeXT」の失敗や、「ピクサー」での「トイ・ストーリー」の成功の所まで終わっていることもあり、新鮮な所で、印象に残ったことだけでもメモ風に記しておきたいと思う。
以前に、ヤングとサイモンの「スティーブ・ジョブズ ICON:Steze Jobs」を読んでいるので、2005年くらいまでのスティーブ・ジョブズの業績や仕事などについては、しっかりとフォローしているのだが、この本には、ジョブズの恋の物語や里子に出された生い立ちや肉親との私生活など個人的な逸話などもかなり詳しく書かれていて、非常に面白くなっている。
まず、アップルを生み出した相棒のスティーブ・ウォズニャック共々、音楽に対する強い情熱を持っていて、特に、ボブ・ディランについては海賊版テープも含めてすべて収集して、TEACの高級テープデッキで楽しんでいたと言うことだが、正に、iPod、iTuneへの伏線であろうか。
二人の協力体制で、タダで電話を掛けられるブルー・ボックスを作って、ヘンリー・キッシンジャーを騙ってローマ法王に電話をするなど悪戯をしながら、作って売れば良いと言うビジネスに開眼したこと。最初からそうだが、アップルⅠを皆にタダであげるつもりだったと言う商売気の全くないウォズが、凄いものを設計して作り出し、ジョブズが、それでお金を儲ける方法を見つけ出すと言う二人三脚が功を奏することになる。
菜食主義に禅宗、瞑想にスピリチュアリティ、LSDにロックと言ったサブカルチュアの中で、奔放に青春を生きて来たジョブズの東洋思想への傾斜は、尋常ではなかった。
自分自身の探求のために師を訪ねてインドを放浪し、東洋思想やヒンズー教、禅宗など悟りを求めて呻吟していた19歳ころから、ずっと、ジョブスは、般若、心を研ぎ澄ますことによって体得する最高の知恵や認識など、東洋の宗教の教え精神を求め続けた。
毎日、朝晩瞑想し、禅を学び、途中で、時々、スタンフォード大学へ、物理や工学の授業を聴講しに出かけていたと言うのだが、人間が努力して習得した西洋の合理的思考とは違った、人間本来に備わる東洋の直観の力、体験に基づく知恵の力を信じていたと言う。
瞑想すれば、直観が花開き、物事がクリアに見え、現状が把握でき、ゆったりとした心で、隅々まで知覚出来、今まで見えなかったことが沢山見えるようになる、これこそ修行であり、そのためには修業が必要だと言うのである。
曹洞宗の僧侶知野弘文師が、ジョブズに禅宗を教えたのだが、1991年3月18日に、木魚をたたき、銅鑼を鳴らして、香をたいてお経をあげて結婚式を取り仕切った。
デザインに対して偏執狂とも思しき程拘ったジョブズは、デザイン感覚を磨く過程で、和のスタイルに引かれて、ミヤケ・イッセイなど有名な和風デザイナーとの付き合いを深めて行くのだが、特に、日本の禅宗は素晴らしく美的で、京都に沢山ある庭など、その文化が醸し出すものに深く心を動かされると言う。
そして、頂点を極めた筈のジョブズは、仏教を通じて、モノを持つと人生は豊かにならず、逆に乱してしまうことが多いと学んだので、ビル・ゲイツが、ここで、家族全員が住んでいるのかとびっくりしたほど質素な家に住んでいて、セクリティもなかったと言うのだから、驚異と言う外はない。
ところで、非常に興味深いのは、この本で、アイザックソンは、ジョブズとビル・ゲイツとの関わりや違いなどについて、ビビッドに描いていることである。
性格や生い立ちの違いは、好対照だが、ITの世界では、
ジョブズは、完璧主義者で総てをコントロールしたいと強く望み、アーティストのように一徹な気性で突き進み、アップルは、ハードウェアとソフトウエアのコンテンツを、シームレスなパッケージにしっかりとした統合するタイプの戦略を取ったが、
ビル・ゲイツは、頭が良くて計算高く、ビジネスと技術について現実的な分析を行い、様々なメーカーに対して、マイクロソフトとのオペレーティングシステムやソフトのライセンスを供与した。
ゲイツは、不本意ながらも、「技術は分からないのに何が上手く行くかについては驚くほど鼻が利く」とジョブズに敬意を払っていたが、ジョブズは、「基本的に想像力が乏しく、何も発明したことがない。いつも、他の人のアイデアをずうずうしく横取りしてばかり」とゲイツの強さを正当に評価しようとしなかったと言う。
その後、ジョブズは、マイクロソフトについて、「美的感覚がない。オリジナルなアイデアは生み出さないし、製品に文化の香りがない。悲しいのは、彼らが三流の製品ばかりを作ることだ。」と言っている。
アップルの方が革新的で創造的で、実装はエレガント、デザインは素晴らしかったが、不完全なコピーを作ったマイクロソフトが、最終的に、オペレーティングシステムの戦いを制してしまったのだから、ジョブズが、喚くのも無理からぬことであろうと言うのである。
やはり、問題は、ジョブズの場合、ハードとソフトもエンドツーエンドで総てを統合すべきと考えて、他との互換性を一切認めなかったことに問題があり、ゲイツの方が、互換性のあるマシンを多くの会社が作り、どのハードも、標準的なオペレーティングシステム(ウインドウズ)が走り、同じアプリケーション(ワードやエクセル)が使える世界を構築する方が利益になると考えたことが、世界標準を抑えたと言うことであろう。
他の追随を許さない断トツの破壊的イノベーションによる新製品やサービスの誕生で、市場を完全支配出来るのならいざ知らず、デジタル革命で、製造業のモジュラー化がますます進展して行き、テクノロジーの複雑さと総合化が益々進行して行くことを考えれば、世界は、正に、オープン化が進むのであって、囲い込みの独占戦略が時代遅れになるのは、必然ではなかろうかと思っている。