監督 呉美保 出演 宮崎あおい、大竹しのぶ、桐谷健太、絵沢萠子、國村隼
「酒井家のしあわせ」のときは気がつかなかったが、呉美保は暮らしのなかに静かに沈んでいる「ひかり」を丁寧にすくいあげている。冒頭の玄関の描写。深夜。それでもどこかにある「明かり」が引き戸をはじめとする家の細部に静かにたまっている。その静かに、まるで沈殿でもしているかのような「ひかり」の、不思議な安心感。ああ、ここに「くらし」というものがある。「いきている」ひとがいる--という感じ。
それは人間の「くらし」をつらぬく何かかもしれない。毎日食べている「もの」、料理。そして、毎日掃き清めている庭の--その「掃除」の仕方。たぶん「仕方」としかいいようのないもののなかに「ひかり」があるのだ。完成した料理ではなく、それをこしらえる「仕方」。何をどう下ごしらえをし、どんなふうに火にかけるか。その積み重ねの「仕方」。
これは「仕方」というものをすくい上げた映画なのだ。
ストーリーの奇抜さに目を奪われてしまうが、それよりも注意すべきなのは、大竹しのぶらの「くらし」の「仕方」である。大阪らしいが、古い街並みの、古い住宅。大家と間借りの家がくっついていて、まるで一家のように暮らしている。他人なのに家族のように行き来している。いまもこういう暮らしがあるのかどうかわからないが、たしかに昔はそういうくらしの「仕方」があった。
そして、その「仕方」になじむようにして、人間関係がつくられていた。拒絶しない。いっしょに何かをつくりあげるというのではないが、他人は他人と受け入れて、「間」を大切にして生きるという「仕方」。この「間」を象徴するのが、たぶん「中庭」なのだ。空間なのだ。「中庭」という空間越しに、隣の家を見る。いや、見守る。監視ではなく、「守る」に力点がある。何かあったら、隣の人を「支える」。ひとは、他人を支えるために生きている--そういうことを知らず知らずに身につける暮らしの「仕方」。
この「仕方」というのは、教科書のように「成文化」されていない。ときどきことばで説明する(喧嘩する、言い含める、なだめすかす、言い寄る……)けれど、そのことばにしたって「何ゆうてんの(という感じかな?)」と、頭で半分拒絶しながら、肉体で「ほんまやなあ」と受け入れる具合である。一回ですっきり通じ合うのではなく、何回も何回も繰り返し、繰り返すことで、互いの肉体のなかに沈殿してくるものを共有する。その共有した「仕方」が、人間のなかから静かな「ひとり」となってひろがってくる。
あたたかさ。ひとがら--というものかもしれない。
絵沢萠子、國村隼や、ちらっと顔を見せた友近らが感じさせる何か--その何かのなかにある「仕方」があるのだ。
大竹しのぶが宮崎あおいに伝えようとしているのも、そういう「仕方」である。「生き方」と言い換えることもできるけれど「生き方」と言ってしまうと、重苦しくなってしまう何か。「こんなふうにしたらええやんか」というときの「ふう」に通じる、ぼんやりしたもの。ぼんやりしているけれど、言っている本人にははっきりとわかっていることがら。わかりすぎているから、うまくことばにならない思想そのものとしての「仕方」。
それは、この映画の舞台になっている不思議な「街並み」(家の構造)そのものでもある。(あ、話がもとにもどってしまった……。)
クライマックスは、大竹しのぶが母にもかかわらず、娘の宮崎あおいに向かって「長い間お世話になりました」とあいさつするシーンである。結婚し、家を出る娘が両親にあいさつするように、大竹しのぶは宮崎あおいにあいさつする。「これまでしあわせだった。ありがとう」という、そのあいさつの「仕方」。そういう「仕方」でしか伝えられないものがあるのだ。
言われた宮崎あおいが、「何なの」という。大竹しのぶが「こういうの、いっぺんしてみたかったんよ」とこたえる。これは、もちろん、互いの「照れ隠し」のことばであるけれど、あいさつも含め、その照れ隠しも「仕方」なのである。その後の「白無垢に鼻水がついた」という話の転換も「仕方」なのである。
「仕方」がきちんとしていると、何かが伝わる。「仕方」をきちんと引き継いでいるのが「大阪」という土地かもしれない。派手さはないが、「大阪文化」というもの、その底力をていねいにすくいとった映画だと思う。
*
とても気に入っているのだが、採点が辛いのは、宮崎あおいがかかえる問題--その紹介の仕方が、ちょっと長すぎる。くどすぎる。説明しすぎる。「過去」をひとつづきの時間のなかで見せてしまうと、それは別の「映画中映画」のように浮き上がってしまう。「過去」はストーリーとしてではなく、役者の「肉体」として表現すべきものであると私は思う。
桐谷健太のジェームス・ディーン(金髪)と奇妙なジーンズスタイルも、おばあちゃんとの話を「ことば」でストーリーにしてしまっているのが残念である。
「過去」というストーリーは、國村隼と宮崎あおいの釣り堀での会話ぐらいの、さらっとしてもの、対話のなかでふっと浮き上がってくるものにしないと、映画の「いま」が壊れてしまう。(これが「-★」の理由。)
そういう意味では、絵沢萠子の描き方は、この映画にふさわしいと思う。「過去」はいっさい説明されない。けれど、大竹しのぶの家に、自分のつくったおかずを運んだり、宮崎あおいにあれこれ注意する「仕方」のなかに、そのひとの「過去」を感じさせる。それが、いい。
*
ラストシーンは、とても気に入っている。「酒井家のしあわせ」でもラストシーンにびっくりしたが、今回も、あ、 100点つたようかなあ、と思うくらい好きである。(これが「+★」理由--具体的には、以下のようなこと。)
大竹しのぶが結婚した--ということが、くらしに影響していない。大竹しのぶが、あと1年も生きられないということが、くらしに影響していない。自分の家でもないのに、國村隼は「眼鏡なかったか?」と朝の食卓(準備)に入り込む。まるで、その家の父親である。絵沢萠子も、おかずを持ってくる。何も変わっていないどころか、以前よりも濃密な人間関係になっている。くらしの「仕方」が全体をつらぬいて、人間ではなく「仕方」が生きている。生きつづける。
「眼鏡、あったよ」
宮崎あおいが見つけ出すのは、國村隼が置き忘れた眼鏡ではなく、いきることの「仕方」そのものである。
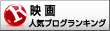
「酒井家のしあわせ」のときは気がつかなかったが、呉美保は暮らしのなかに静かに沈んでいる「ひかり」を丁寧にすくいあげている。冒頭の玄関の描写。深夜。それでもどこかにある「明かり」が引き戸をはじめとする家の細部に静かにたまっている。その静かに、まるで沈殿でもしているかのような「ひかり」の、不思議な安心感。ああ、ここに「くらし」というものがある。「いきている」ひとがいる--という感じ。
それは人間の「くらし」をつらぬく何かかもしれない。毎日食べている「もの」、料理。そして、毎日掃き清めている庭の--その「掃除」の仕方。たぶん「仕方」としかいいようのないもののなかに「ひかり」があるのだ。完成した料理ではなく、それをこしらえる「仕方」。何をどう下ごしらえをし、どんなふうに火にかけるか。その積み重ねの「仕方」。
これは「仕方」というものをすくい上げた映画なのだ。
ストーリーの奇抜さに目を奪われてしまうが、それよりも注意すべきなのは、大竹しのぶらの「くらし」の「仕方」である。大阪らしいが、古い街並みの、古い住宅。大家と間借りの家がくっついていて、まるで一家のように暮らしている。他人なのに家族のように行き来している。いまもこういう暮らしがあるのかどうかわからないが、たしかに昔はそういうくらしの「仕方」があった。
そして、その「仕方」になじむようにして、人間関係がつくられていた。拒絶しない。いっしょに何かをつくりあげるというのではないが、他人は他人と受け入れて、「間」を大切にして生きるという「仕方」。この「間」を象徴するのが、たぶん「中庭」なのだ。空間なのだ。「中庭」という空間越しに、隣の家を見る。いや、見守る。監視ではなく、「守る」に力点がある。何かあったら、隣の人を「支える」。ひとは、他人を支えるために生きている--そういうことを知らず知らずに身につける暮らしの「仕方」。
この「仕方」というのは、教科書のように「成文化」されていない。ときどきことばで説明する(喧嘩する、言い含める、なだめすかす、言い寄る……)けれど、そのことばにしたって「何ゆうてんの(という感じかな?)」と、頭で半分拒絶しながら、肉体で「ほんまやなあ」と受け入れる具合である。一回ですっきり通じ合うのではなく、何回も何回も繰り返し、繰り返すことで、互いの肉体のなかに沈殿してくるものを共有する。その共有した「仕方」が、人間のなかから静かな「ひとり」となってひろがってくる。
あたたかさ。ひとがら--というものかもしれない。
絵沢萠子、國村隼や、ちらっと顔を見せた友近らが感じさせる何か--その何かのなかにある「仕方」があるのだ。
大竹しのぶが宮崎あおいに伝えようとしているのも、そういう「仕方」である。「生き方」と言い換えることもできるけれど「生き方」と言ってしまうと、重苦しくなってしまう何か。「こんなふうにしたらええやんか」というときの「ふう」に通じる、ぼんやりしたもの。ぼんやりしているけれど、言っている本人にははっきりとわかっていることがら。わかりすぎているから、うまくことばにならない思想そのものとしての「仕方」。
それは、この映画の舞台になっている不思議な「街並み」(家の構造)そのものでもある。(あ、話がもとにもどってしまった……。)
クライマックスは、大竹しのぶが母にもかかわらず、娘の宮崎あおいに向かって「長い間お世話になりました」とあいさつするシーンである。結婚し、家を出る娘が両親にあいさつするように、大竹しのぶは宮崎あおいにあいさつする。「これまでしあわせだった。ありがとう」という、そのあいさつの「仕方」。そういう「仕方」でしか伝えられないものがあるのだ。
言われた宮崎あおいが、「何なの」という。大竹しのぶが「こういうの、いっぺんしてみたかったんよ」とこたえる。これは、もちろん、互いの「照れ隠し」のことばであるけれど、あいさつも含め、その照れ隠しも「仕方」なのである。その後の「白無垢に鼻水がついた」という話の転換も「仕方」なのである。
「仕方」がきちんとしていると、何かが伝わる。「仕方」をきちんと引き継いでいるのが「大阪」という土地かもしれない。派手さはないが、「大阪文化」というもの、その底力をていねいにすくいとった映画だと思う。
*
とても気に入っているのだが、採点が辛いのは、宮崎あおいがかかえる問題--その紹介の仕方が、ちょっと長すぎる。くどすぎる。説明しすぎる。「過去」をひとつづきの時間のなかで見せてしまうと、それは別の「映画中映画」のように浮き上がってしまう。「過去」はストーリーとしてではなく、役者の「肉体」として表現すべきものであると私は思う。
桐谷健太のジェームス・ディーン(金髪)と奇妙なジーンズスタイルも、おばあちゃんとの話を「ことば」でストーリーにしてしまっているのが残念である。
「過去」というストーリーは、國村隼と宮崎あおいの釣り堀での会話ぐらいの、さらっとしてもの、対話のなかでふっと浮き上がってくるものにしないと、映画の「いま」が壊れてしまう。(これが「-★」の理由。)
そういう意味では、絵沢萠子の描き方は、この映画にふさわしいと思う。「過去」はいっさい説明されない。けれど、大竹しのぶの家に、自分のつくったおかずを運んだり、宮崎あおいにあれこれ注意する「仕方」のなかに、そのひとの「過去」を感じさせる。それが、いい。
*
ラストシーンは、とても気に入っている。「酒井家のしあわせ」でもラストシーンにびっくりしたが、今回も、あ、 100点つたようかなあ、と思うくらい好きである。(これが「+★」理由--具体的には、以下のようなこと。)
大竹しのぶが結婚した--ということが、くらしに影響していない。大竹しのぶが、あと1年も生きられないということが、くらしに影響していない。自分の家でもないのに、國村隼は「眼鏡なかったか?」と朝の食卓(準備)に入り込む。まるで、その家の父親である。絵沢萠子も、おかずを持ってくる。何も変わっていないどころか、以前よりも濃密な人間関係になっている。くらしの「仕方」が全体をつらぬいて、人間ではなく「仕方」が生きている。生きつづける。
「眼鏡、あったよ」
宮崎あおいが見つけ出すのは、國村隼が置き忘れた眼鏡ではなく、いきることの「仕方」そのものである。
 | 酒井家のしあわせ [DVD]日活このアイテムの詳細を見る |



























