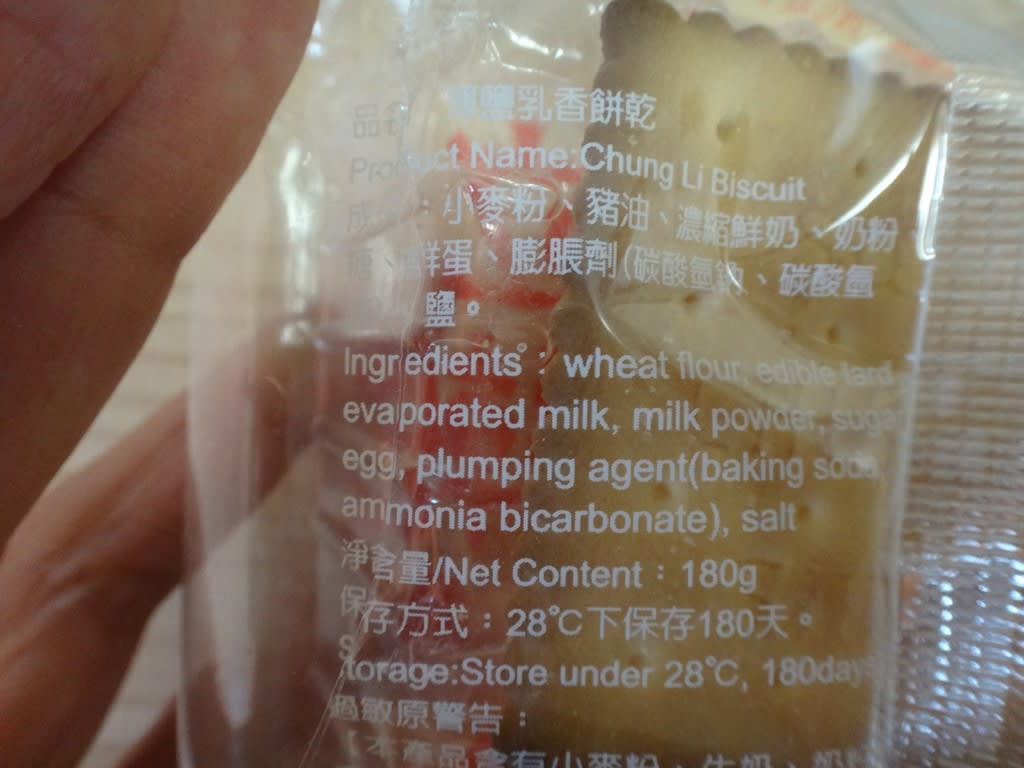TVや音響機器周辺は、機材や設置方法など、これまでコツコツと変更を加えてきました。
・ブラウン管TVとアンプをつなげて、TVがくっきりいい音に(2014.4)
・ブラウン管TVが故障、薄型TV(敢えてプラズマ)購入(2014.6)
・ダンナサマのアンプ修理(2014.6)
・薄型TVを壁掛けに(2014.10)
・戸棚をリメイクして、オーディオ機器棚を自作(2014.10)
・CD(ソフト)を、物置部屋からダンナサマのデスクそばにお引越し(2015.3)
・ダンナサマの大きいスピーカー修理
・オーディオ機器棚に引出とりつけ(2015.7)
・AmazonFire TV Stick 購入(2018.4)
・TVの音出力をアンプにつなげるためのデジタルアナログオーディオコンバーター購入(2018.5)
Amazon Fire TV Stickは、なんだか画期的。
Amazon提供の映画コンテンツが多数見られるほか、パソコンで見ているもの(Youtubeやらじるらじるなど)がTV画面で見られるのです。
この導入後、ダンナサマが一気にTV漬けに。
(危機感を感じるほどなので、最近は控えるように誘導中)
ほぼ満足だったのですが、ダンナサマはCDの音質にやや不満があったようでした。
DVD&VHSプレーヤーを、CDプレーヤーとして使っていたのですが、音質がいまひとつなのだとか。
ダンナサマ:「ちゃんとしたCDプレーヤー、欲しいなあ」
Fujika:「どうじょ、買えば~。ただし、今の棚に収まるようにしてね」
ダンナサマ:「そうねえ」
という訳で行動には移していませんでしたが、最近突然目覚めてしまった模様。
ダンナサマ:「明日荷物とどくからね!」
Fujika:「え?何買ったの? あ、こないだ話に出たまくら?」
ダンナサマ:「ちがーう。そんなものじゃなくて、兼ねてから欲しかったものなの」
Fujika:「何かあったっけ・・。ああ。そういえば。あれね。CDの。ちゃんと棚に収まるサイズでしょうね?
(この前勝手に買ってたシャンパングラスが棚に収まらない背の高さだったので、イマイチ信用できないんだよなあ)」
ダンナサマ:「だいじょぶだいじょぶ。アンプくらいのサイズだから。」
Fujika:(ほんとかなあ)
無事届いたので、4/7-8の週末に、セッティングをすることにしました。
ついでに、TVの後ろの窓を掃除。多少結露があったようで、サッシにカビがついていました・・・。
垂らしていた布は撤去し、新たに板をはめ込んで内窓状態に。気密性アップすれば結露しにくいはず。
TVの取り付け位置もちょっと上に。ケーブルは見えないように。
など、いろいろと微調整をしました。
DVD/VHSプレーヤーは、もっぱらCDとDVDを再生するために使っていました。
(VHS再生機能は故障しており、VHSプレーヤーは別途あって、残してあります。)
今回これを外したことで、DVDソフトを再生する機械がなくなってしまいましたが、おそらくパソコンで再生して、それをTVにミラーリングすることで見られるはず。(Amazon Fire TV Stick、すごいです。ミラーリング用のアプリは既にインストール済み)
FMチューナーも、Amazon Fire TV Stick を使ってらじるらじる経由でラジオが聞けるし、この際お役御免にしました。
ダンナサマの8mmのソフト(映画など)が数本ありますが、本当に必要なものだけ、どこかにダビングを頼むなりなんなりして、8㎜デッキは処分する予定。
3つも機械を外したので、裏面の配線はだいぶスッキリしたとのことです。