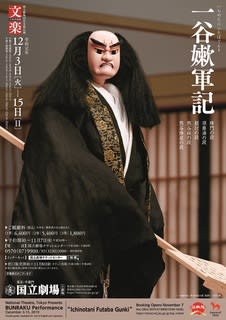チャップリンの映画「街の灯」を脚色した素晴らしい歌舞伎。
和製チャップリン宜しく、幸四郎が、泣き笑いのしみじみと心に染みる芸の新境地を開いた素晴らしい舞台で、チョビ髭を付けて、小さな帽子に大きな靴、ひょこひょこ歩く特異な姿で、世界中の人々を笑いの渦に巻き込んだチャップリンを彷彿とさせる至芸を披露している。
「街の灯」は1931年1月にアメリカで公開され、この歌舞伎の原作の「蝙蝠の安さん」を、木村錦花が読売新聞に連載を始めたのは同年7月で、歌舞伎は8月で、この映画が日本で公開されたのは、権利金の折り合いがつかず、1934年だと言うから、実際に映画を見た15代市村羽左衛門や、2代目市川猿之助から、荒かたの筋を聞いて、それに基づいて書いたのだと言う。
主人公は、歌舞伎の人気作「与話情浮名横櫛」の「蝙蝠の安五郎」とかで、映画「街の灯」の舞台を江戸に置き換えた形だが、放浪者の安さんが、街で出会った盲目の花売り娘お花に一目ぼれして、目の治療代を工面するために奔走する泣き笑いのラブコメディは、「街の灯」そのままである。
放浪者の蝙蝠の安さんは、街角でひっそりと花を売る盲目の花売り娘のお花に出会って、一目惚れする。安さんが、橋の下のドヤで憩っていると、金持ちの上総屋新兵衛が、妻に先立たれて絶望し、酒に酔って身投げしようとしたので、止めて助ける。安さんを気に入った新兵衛は、友人として家に迎え入れ歓迎するのだが、酔いが醒めると酔っていた時の記憶を全く失う悪い癖がある。安さんは、酔っ払って機嫌が良くなった新兵衛から、お花の目の治療費の5両をもらうのだが、寝込んで入る隙に、泥棒が入って、正気に戻った新兵衛が5両がないと言い出し、泥棒と勘違いされたので、遁走する。 逃げながら、出会ったお花に、その5両を手渡す。
その前に、お花の治療代欲しさに、賞金付き相撲に登場して負けると言う何とも締まらないドタバタ喜劇があって面白い。
その後、目が治って立派な花屋を営んでいるお花の前に、相変わらず見すぼらしい風来坊姿の安さんが現れ、可哀そうにと、菊の花と小銭を貰うのだが、触れた手と声の感触で、お花は、その風来坊が、裕福な大人だと思い込んでいた恩人であることに気付いて、ハッとするが、安さんは、苦し紛れの微笑をお花に返して、静かに消えて行く。
この何とも言えない悲しくも甘酸っぱい複雑な表情に、幸四郎は、万感の思いを込めて、チャップリンに思いを馳せたのであろう。
花売り娘の坂東新悟、上総屋新兵衛の猿弥、大家勘兵衛の大谷友右衛門などの助演陣が、良い味を出していて楽しませてくれる。
さて、チャップリンだが、色々、若い頃に観たが、最も印象深いのは、
1940年『独裁者』The Great Dictator
流石に、チャップリンで、あの時代に、反ヒトラー映画を、よく作ったと思う。
初期の無声映画に何とも言えない懐かしさがあって、好きである。
和製チャップリン宜しく、幸四郎が、泣き笑いのしみじみと心に染みる芸の新境地を開いた素晴らしい舞台で、チョビ髭を付けて、小さな帽子に大きな靴、ひょこひょこ歩く特異な姿で、世界中の人々を笑いの渦に巻き込んだチャップリンを彷彿とさせる至芸を披露している。
「街の灯」は1931年1月にアメリカで公開され、この歌舞伎の原作の「蝙蝠の安さん」を、木村錦花が読売新聞に連載を始めたのは同年7月で、歌舞伎は8月で、この映画が日本で公開されたのは、権利金の折り合いがつかず、1934年だと言うから、実際に映画を見た15代市村羽左衛門や、2代目市川猿之助から、荒かたの筋を聞いて、それに基づいて書いたのだと言う。
主人公は、歌舞伎の人気作「与話情浮名横櫛」の「蝙蝠の安五郎」とかで、映画「街の灯」の舞台を江戸に置き換えた形だが、放浪者の安さんが、街で出会った盲目の花売り娘お花に一目ぼれして、目の治療代を工面するために奔走する泣き笑いのラブコメディは、「街の灯」そのままである。
放浪者の蝙蝠の安さんは、街角でひっそりと花を売る盲目の花売り娘のお花に出会って、一目惚れする。安さんが、橋の下のドヤで憩っていると、金持ちの上総屋新兵衛が、妻に先立たれて絶望し、酒に酔って身投げしようとしたので、止めて助ける。安さんを気に入った新兵衛は、友人として家に迎え入れ歓迎するのだが、酔いが醒めると酔っていた時の記憶を全く失う悪い癖がある。安さんは、酔っ払って機嫌が良くなった新兵衛から、お花の目の治療費の5両をもらうのだが、寝込んで入る隙に、泥棒が入って、正気に戻った新兵衛が5両がないと言い出し、泥棒と勘違いされたので、遁走する。 逃げながら、出会ったお花に、その5両を手渡す。
その前に、お花の治療代欲しさに、賞金付き相撲に登場して負けると言う何とも締まらないドタバタ喜劇があって面白い。
その後、目が治って立派な花屋を営んでいるお花の前に、相変わらず見すぼらしい風来坊姿の安さんが現れ、可哀そうにと、菊の花と小銭を貰うのだが、触れた手と声の感触で、お花は、その風来坊が、裕福な大人だと思い込んでいた恩人であることに気付いて、ハッとするが、安さんは、苦し紛れの微笑をお花に返して、静かに消えて行く。
この何とも言えない悲しくも甘酸っぱい複雑な表情に、幸四郎は、万感の思いを込めて、チャップリンに思いを馳せたのであろう。
花売り娘の坂東新悟、上総屋新兵衛の猿弥、大家勘兵衛の大谷友右衛門などの助演陣が、良い味を出していて楽しませてくれる。
さて、チャップリンだが、色々、若い頃に観たが、最も印象深いのは、
1940年『独裁者』The Great Dictator
流石に、チャップリンで、あの時代に、反ヒトラー映画を、よく作ったと思う。
初期の無声映画に何とも言えない懐かしさがあって、好きである。