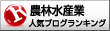世界的な穀物高騰の中で、もっとも値上がりをしているのがお米である。日本では、トウモロコシが値上がりしただの、大豆や小麦が高騰したと騒ぐ。なぜお米を騒がない? 自給しているからである。
世界的な穀物高騰の中で、もっとも値上がりをしているのがお米である。日本では、トウモロコシが値上がりしただの、大豆や小麦が高騰したと騒ぐ。なぜお米を騒がない? 自給しているからである。
食糧危機など、日光量が多く降水量の多い日本では生じえないことである。食料を海外に依存する政策を選択した、為政者の非先見性が今日の現状を生んでいるだけである。
 そのお米であるが、世界的な高騰とは全く逆の動きをしているのがわが国である。わずか12年前には生産者価格が、60キロ当たり2万円していたのが現在は1万3千円程度である。米作り農家がが急速に減少するのも当たり前である。
そのお米であるが、世界的な高騰とは全く逆の動きをしているのがわが国である。わずか12年前には生産者価格が、60キロ当たり2万円していたのが現在は1万3千円程度である。米作り農家がが急速に減少するのも当たり前である。
おかげで、国際価格と一時は12倍もあると、財界から叩かれていた格差は2~3倍程度にまでなった。ものによっては、逆転しているものもある。賃金の国際価格 を見ると、いかに日本の農民がこの社会で虐げられているかが解る。
 米に限ったことではない。これは教訓にすぎない。あらゆる農産物に明日にでも起きかねないことである。
米に限ったことではない。これは教訓にすぎない。あらゆる農産物に明日にでも起きかねないことである。
穀物高騰の世界情勢は、食料が戦略物資としての意味をさらに高くしていることを意味している。食糧を自給しない国家は、独立国家としての資質を備えていない。
強制的に食糧生産を止めさせた休耕地を復活させ、お米主体の食生活に切り替えれば、いつ でも自給可能である。少し長い目をもった視点さえあれば、いつでも可能なことである。
でも自給可能である。少し長い目をもった視点さえあれば、いつでも可能なことである。
更に動物蛋白と脂質を主体にした、グルメ志向は国民の健康をも損なうのである。米主体の食生活は、国土を保全することにもつながるし温室効果ガスの排出も抑制する。輸入食料は、輸入と同時に大量の温室効果ガスをも排出する。
今こそ、小麦や大豆や畜産製品の値上がりをすんなり受け入れ、日本の農民と農村を支援し、国民の健康を考え、国内で食糧自給を真剣に考える時期である。
しかしながら、農水省は、このほど長年行ってきた「米の消費動向調査」を打ち切ったのである。何で??