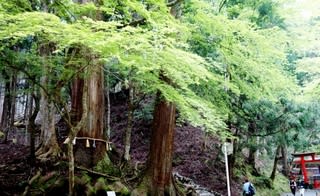私の庭には、今、5種類の赤いばらの花が咲き始めている。
赤いバラ(Red Rose)の花言葉は、タキイのHPによると、
「I love you(あなたを愛してます)」「love(愛情)」「beauty(美)」「passion(情熱)」「romance(ロマンス)」
赤いバラのつぼみ(Red Rose Bud)は、
「pure and lovely(純粋と愛らしさ)」「innocent love(純粋な愛)」「young and beautiful(若く美しい)」
と言うことである。
私には、passionと言うのが、一番あっているように思うのだが、素晴らしい花ことばである。
さて、私のばらだが、同じ赤いばらと言っても、この5株だけでも、かなりの違いがある。
一番深紅と言うか、色の濃いのは、イングリッシュローズのダッシー・バッセルである。

赤いばらで、大きくて風格のあるのは、やはり、HTのベルサイユの薔薇であろう。
発表された直後に、京成バラ園で大苗を買って植えたのが、活着しなかったので、新苗を改めて植えたのが、今、大きくなって開花している。
14~5センチの剣弁高芯咲で、ばららしいばらと言えばよいのであろうか、とにかく、一輪挿しにもよく似合う。

もう一つのHTは、これもメイアンのばらだが、ルージュ・ロワイヤルで、花はやや小ぶりながら、照葉が美しく、かすかに、芳香がして良い。


私が、2本も枯らしてダメにしたのが、イングリッシュローズのファルスタッフで、なぜか、この花は気に入っている。
ロンドンで、最初に見たRSCのシェイクスピア戯曲が、ヘンリー4世で、ハル王子を放蕩三昧に引きずり込んだ無頼漢の飲んだくれのファルスタッフに、強烈な印象を持ったのだが、その後、「ウインザーの陽気な女房たち」、そして、そのオペラ版ヴェルディの「ファスタッフ」を見て、その泣き笑いの生きざまに、興味を感じた。
エリザベス一世女王が、シェイクスピアに、ファルスタッフを主人公にした恋の物語を書いて欲しいと言ったので生まれたのが、「ウインザーの陽気な女房たち」だとか。
ストラトフォード・アポン・エイヴォンの大劇場前の公園に、ファルスタッフの銅像が立っているのだが、このファルスタッフは、英国でも、最も人気の高いキャラクターの一人だと言うことである。
この写真は、咲き始めなので、雰囲気は分からないのだが、堂々としたカップ咲きの花で、デビッド・オースティンは、気品のある姿と性格を持った大輪だと言う。
これが、何故、ファルスタッフなのか、分からない。

もう一つのイングリッシュローズの赤い花は、ウィリアム・シェイクスピア2000。
ファルスタッフの生みの親と言う訳ではないが、綺麗な花である。


赤い花ではないが、表はビロードのような奇麗な深紅で、裏が淡いオレンジ色のキャプリス・ド・メイアンも、私にとっては、長い付き合いで、毎年、綺麗な花を咲かせてくれると嬉しい。
まだ、蕾がかたくて咲いていないのは、レッド・レオナルド・ダヴィンチ。
ばらは、バラ色と言って、ピンクのばらが美しいが、愛の象徴のような赤いばらの魅力も、捨てがたいと思う。


(追記)
13日現在のファルスタッフとシェイクスピアは次の通り。


赤いバラ(Red Rose)の花言葉は、タキイのHPによると、
「I love you(あなたを愛してます)」「love(愛情)」「beauty(美)」「passion(情熱)」「romance(ロマンス)」
赤いバラのつぼみ(Red Rose Bud)は、
「pure and lovely(純粋と愛らしさ)」「innocent love(純粋な愛)」「young and beautiful(若く美しい)」
と言うことである。
私には、passionと言うのが、一番あっているように思うのだが、素晴らしい花ことばである。
さて、私のばらだが、同じ赤いばらと言っても、この5株だけでも、かなりの違いがある。
一番深紅と言うか、色の濃いのは、イングリッシュローズのダッシー・バッセルである。

赤いばらで、大きくて風格のあるのは、やはり、HTのベルサイユの薔薇であろう。
発表された直後に、京成バラ園で大苗を買って植えたのが、活着しなかったので、新苗を改めて植えたのが、今、大きくなって開花している。
14~5センチの剣弁高芯咲で、ばららしいばらと言えばよいのであろうか、とにかく、一輪挿しにもよく似合う。

もう一つのHTは、これもメイアンのばらだが、ルージュ・ロワイヤルで、花はやや小ぶりながら、照葉が美しく、かすかに、芳香がして良い。


私が、2本も枯らしてダメにしたのが、イングリッシュローズのファルスタッフで、なぜか、この花は気に入っている。
ロンドンで、最初に見たRSCのシェイクスピア戯曲が、ヘンリー4世で、ハル王子を放蕩三昧に引きずり込んだ無頼漢の飲んだくれのファルスタッフに、強烈な印象を持ったのだが、その後、「ウインザーの陽気な女房たち」、そして、そのオペラ版ヴェルディの「ファスタッフ」を見て、その泣き笑いの生きざまに、興味を感じた。
エリザベス一世女王が、シェイクスピアに、ファルスタッフを主人公にした恋の物語を書いて欲しいと言ったので生まれたのが、「ウインザーの陽気な女房たち」だとか。
ストラトフォード・アポン・エイヴォンの大劇場前の公園に、ファルスタッフの銅像が立っているのだが、このファルスタッフは、英国でも、最も人気の高いキャラクターの一人だと言うことである。
この写真は、咲き始めなので、雰囲気は分からないのだが、堂々としたカップ咲きの花で、デビッド・オースティンは、気品のある姿と性格を持った大輪だと言う。
これが、何故、ファルスタッフなのか、分からない。

もう一つのイングリッシュローズの赤い花は、ウィリアム・シェイクスピア2000。
ファルスタッフの生みの親と言う訳ではないが、綺麗な花である。


赤い花ではないが、表はビロードのような奇麗な深紅で、裏が淡いオレンジ色のキャプリス・ド・メイアンも、私にとっては、長い付き合いで、毎年、綺麗な花を咲かせてくれると嬉しい。
まだ、蕾がかたくて咲いていないのは、レッド・レオナルド・ダヴィンチ。
ばらは、バラ色と言って、ピンクのばらが美しいが、愛の象徴のような赤いばらの魅力も、捨てがたいと思う。


(追記)
13日現在のファルスタッフとシェイクスピアは次の通り。