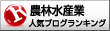食糧は人が生きてゆく上で欠かすことができないものである。人類はこれを商品化して、特定の人たちに作ってもらうシステムを作った。食糧は、量として倍も消費できないし、3割も少なくすることもできない。安定供給が求められる。
直接生命をつかさどるものであり、質も問われるものである。地形や歴史や風土、さらに毎年の気象にも影響を受けて生産されるものである。
商品として見た場合、工業製品や商業製品とは全く異なるものである。
「私は××で食っている」とか「これを飯のタネにしている」というように、生きてゆく上で最低限欠かすことのできない、商品なのである。
日本の農業が国際化の嵐の中で、減少の一途をたどっている。食糧の国際価格を決めているのは、アメリカやオーストラリアやブラジルそれに中国やタイなどである。
前者は、産業革命が起きた後に、先住民族の土地を暴力的に収奪し、広大な面積を強大な重機で農地にしたものである。単位労働あたりの収量・収益は格段に高くなる。大型化が農業の生きる道と、経済学者に幻想をいだかせる。
後者のタイなどは極めて安価な人件費と、コメ作付などに適した気候風土が安価なコメを生産しているのである。前世紀ではこれらの国を、先進国と称する国家は植民地にしていた。そのことを思えば、安価な労賃はそれでも改善されたと言える。ガーナのココアのココア生産などは例外として。
最近中国も人件費が高くなり、アメリカや日本の製品の下請け生産が行き詰っている。このことは、経済力が上がれば人々が豊かになり、当然の結果である。
もう少し先を見れば、やがて世界の労賃は平準化するであろう。少なくとも、下請けさせるうま味はなくなってくる。
このことは、後者の国々から購入している農産物は、やがて高価と言われる日本国内の生産額に近づくことになると思われる。
アメリカなど前者の国々は、安価な穀物などを生産しているようであるが、工業的農業は環境にやさしくなく、単位面積当たりの収量も少ないのである。
こうした大量投資と大量収益計算で攻防を繰り返す、一見農業と思われる食料生産企業は、生産価格を抑えるためなら何でもやる。遺伝子組み換えも化学肥料も農薬も使い放題である。他国では承認されない化学製品や薬品を、政治的に承認させ合法化もするのである。
いずれに時期に、僅か200年程度の歴史しかない前者の、工業的食糧生産は行き詰まることになる。彼らは「食べ物」を作っているのではなく、「金になる物」を作っているからである。儲からなければ簡単に生産から離脱する。
後者の国々は経済発展を遂げると、農業の担い手が減少して自国消費でいっぱいになるだろう。安価な食糧を提供してくれる保証はない。
日本が食料を自給しなければならない理由は、国際化による賃金の平準化と環境問題にある。TPPは、国家や地域や環境を考慮しない、短期的収益を追求する無関税システムである。