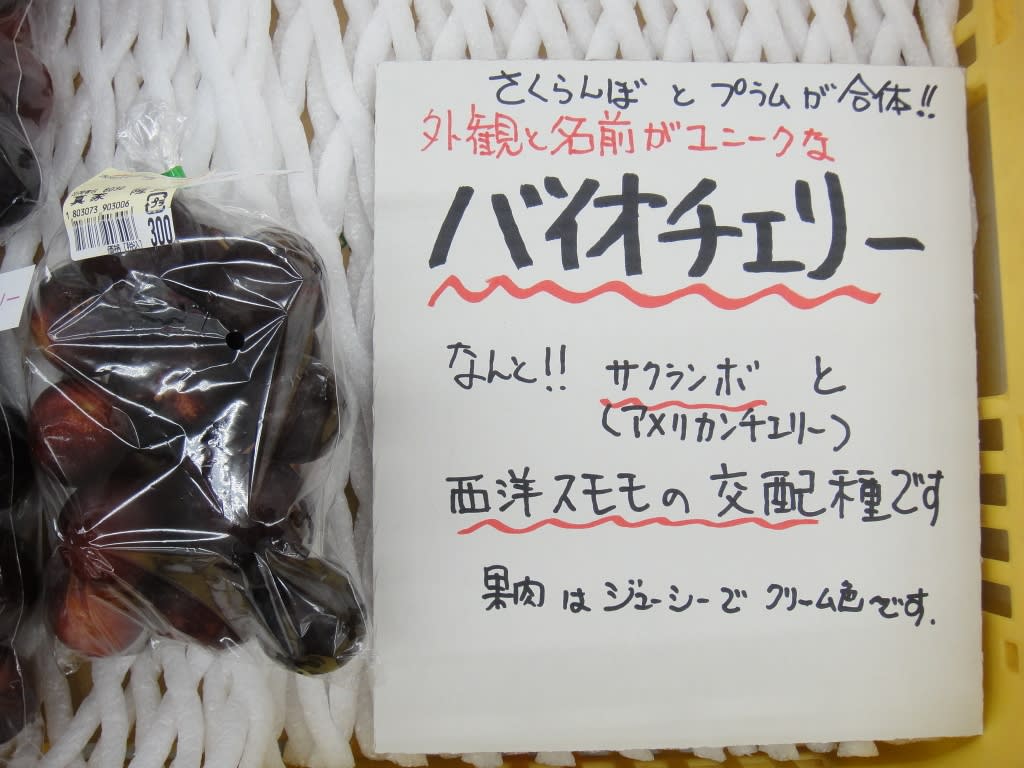今年は梅が大豊作で、いくらでもあるような状態でした。
ちょくちょく加工するものの、摘むほうが簡単なため、家に常にザルいっぱい分の梅が置いてあるような状態。
新しい梅も摘んできたし、前に摘んだのはしなびてきたし処分してしまおうかな?
しなびて・・・って、むしろ水分がほどよく抜けているということでは?
むしろいいことかも。
梅から水分を抜くといえば梅干し。半干し梅で梅干しを作ります。
 |
しなびて一回り小さくなった梅です。
でも最終的に干すし、実はこれを使えばいいのでは。
|
 |
初回はこのくらい。
(あとからもう1回分漬けました)
|
 |
袋に入れて塩(12%程度)をふり、真空パック器でなるべく脱気します。これを冷蔵庫で保管。重石はなし。
梅酢があがり次第、再度脱気。
|
 |
途中、2袋を1袋にまとめ、赤紫蘇も入れました。
冷蔵庫で保管し、空気も抜いておくと、全くカビの心配がいらず存在を忘れていられます。
|
冷蔵庫の背景と化して忘れかけていましたが、そうだ、土用干ししなくては。
土用っていつ?
調べてみたら2014年は7月29日だそうです。
(特に調べなくてもスーパーにウナギがどっさり並ぶから、そこから推定できたかも)
まあそのあたりで、スッキリ晴れた日ならいつでもいいかなとは思っていましたが、奇しくも土用の当日(7/29)、干しはじめました。
 |
赤梅干しのはずなのですが、えらく黄色いです。染まっていません。
ところどころ濃い色のものは、皮が少し敗れているもの。赤紫蘇の色が果肉に沁みてしっかり染まっていますが、大半は黄色っぽいです。
|
 |
梅酢から取り出した梅は、ぽちゃぽちゃのタプタプ。
小龍包をつまんでいるような感じでした。
そーっと扱って並べるのに結構時間がかかります。
|
 |
梅酢と紫蘇も干してみました。
|
全然赤くないので、1日干したあと、再びたっぷりの梅酢に浸しておきました。
色素がまだ出るかと、紫蘇も浸し直し。
この状態で1日放置。
翌々日(7/31)、再び干します。
 |
1日目よりはだいぶ赤くなったかな。
|
 |
梅干しがザルにくっついているところは、格子状に染め残っています。
ザルの方は順調に赤くなってて、梅じゃなくてザルを梅酢で染めているような・・・。
|
土用干し二日目の晩は、ザルのまま室内にとりこみました。
もう一日干します。土用干し三日目。
 |
もう少し赤くしてみようと、さっと梅酢にくぐらせて干すことにしました。
あと、日々ザルが染まるばかりなので、オーブンペーパーを敷いてみました。
|
 |
ペーパーと梅がくっついているので、一晩室内でこのままおいておきます。
翌日には紙から綺麗にとり外せます。
こんな感じで干しあがりってことでどうでしょうか。
|
 |
梅3キロ分くらいの梅干しと、梅酢。
|
 |
割と梅干しらしく出来上がったと思います。
|
実は、梅干しは塩辛すぎてそのままではあまり食べません。(味見もちょっと避けてしまうくらい)
でも、数年前思いついたスペシャル塩抜き方法で塩抜きすると、甘酸っぱくて食べやすくなります。
次(?)の記事で、おいしい塩抜き梅の方法をご紹介します。
(そんな大した方法じゃないです。)
==============
■■梅干し2014作り方メモ
■使った梅
・摘んできた梅を洗ってからザルに数日置いておき、黄色く熟し、かつ傷みがないものを使う。
(傷のある梅は、放置している間に傷んできてわかる)
数日おくとしなびかけてくるが、それはほどよく水分が抜けて都合がよいと考えた。
収穫のタイミングに応じて、2回に分けて塩漬けした。
各1.5キロ程度だったので(メモ紛失)、合計3キロくらい。
・梅を水に漬けておく、という方法もあるが特にそれはしなかった。
・梅のヘタは取り除いた。アクが出るため、と書いてある場合もあるが、こんな小さなカケラのアクなど大したことないはず。むしろぽろりと外れたヘタが、極薄の皮を破ってしまうのを防ぐためだと思う。
■塩分濃度・重石
確か1回目は13%くらい?。2回目は12%だったか10%だったか。(メモ紛失)
冷蔵庫で漬けるつもりだったので低くしてみた。
呼び水として、梅ジャム用にゆでた梅をざるにあげた際に滴った梅の水分も使った。
(梅+呼び水)×塩分濃度=塩の重さ
ビニールで漬ける漬物の要領で、袋の中の空気を抜くようにし、重石はなし。
保管場所は冷蔵庫内。空きに応じて野菜室だったり、普通の場所だったり。
■紫蘇
7月上旬だったか、縮緬タイプの赤紫蘇1袋分(百円ちょい)を購入。(少なかった気がする)
葉っぱをちぎって計量。
18%の塩の半量で揉んで、ぎゅっと絞る。
さらに残りの塩で揉んで、もう一度ぎゅっと絞る。ゴルフボール大になった。
漬物袋を用意し、2袋に分かれていた梅を1袋にまとめ、ここに紫蘇を投入。
引き続き冷蔵庫野菜室で漬けこみ。
■土用干し・完成
7/29 土用干し1日目。
袋からとりだし、ざるにのせて朝から干しはじめ。
とてもぽちゃぽちゃで、小龍包のよう。皮を破らないようにそっと扱う必要あり。
早朝から干すつもりが、そっと扱うのに手間取りかなり遅い干しはじめになった。
表面が乾いた頃(昼くらい)に裏返した。
梅酢、紫蘇も干してみた。
夜みたところ色が薄かったため、 再び梅酢に浸すことに。紫蘇も梅酢に戻す。
(翌日はずっと梅酢に浸しっぱなし)
7/31 土用干し2日目。
梅酢から梅を取出し、ざるにのせて朝から干す。
確かこの日も昼くらいに裏返した。
夜はとりこみ、ざるにのせたまま室内に置いておく。
8/1 土用干し3日目。
梅酢にさっとくぐらせ、ざるの上にオーブンペーパーを敷きそこに干す。
途中、一度か2度裏返した。ペーパーにひっついているものは無理に剥がさずそのままにした。
朝から夕方まで干し、夜は室内に。
翌日、梅が再びしっとりしてペーパーから剥がし易くなったところで瓶などに収納。
■反省
・数段階に分けて少しずつ塩漬けしていくのはよかった。
最初に出た梅酢を呼び水にするといいかも。
・真空パック器を使って袋漬け&冷蔵庫保存というのもよかった。
ジップロックのジップのところはわずかだが液漏れするので、ちゃんとシールする方がいい。
・漬けこみ時の塩分濃度はだいぶ下げたはずだが、梅酢に浸しなおしたせいかどうか、とても塩辛い、普通の梅干しになった。
・赤紫蘇が少なかったかも。もう1袋使ってもよかったか。
■参考にしたサイト
・赤紫蘇の塩もみ