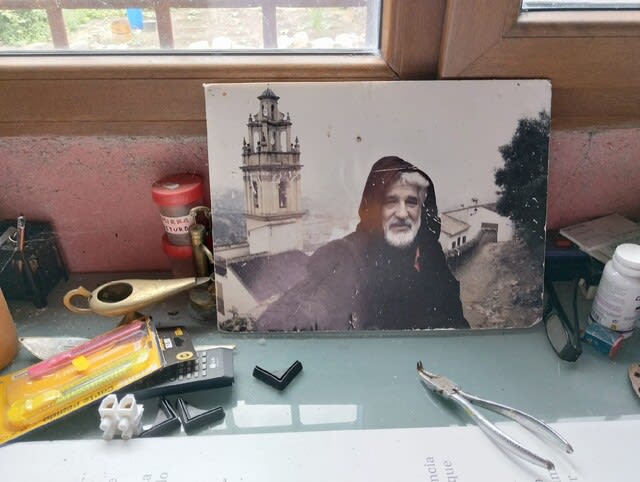池田清子「小さい子供のように」、杉恵美子「蛍火」、徳永孝「雨の日の窓」、木谷明「あの時から」、青柳俊哉「窓」(朝日カルチャー講座・福岡、2022年07月18日)
受講生の作品。
小さい子供のように 池田清子
小さい子供のように
楽しい時は 楽しいと詩いたい
悲しい時は 悲しいと詩いたい
淋しい時 淋しいと詩いたい
せつない時も
むなしい時も
思いが言葉にならない時も
小さい子供のように
ただ ただ 大きい声で
泣きながら詩いたい
二連目の「思いが言葉にならない時」が、とてもいい。それで、受講生に「思いがが言葉にならない時」とはどういう時か、質問してみた。ほかのことばで(自分のことばで)言い直すと、どうなるか。
たとえば「楽しい時」「悲しいと時」「淋しい時」「せつない時」「むなしい時」は、思いがことばになるのか。「楽しい」「悲しい」「淋しい」「せつない」「むなしい」は池田にとって「言葉」なのか。
最後に「泣く」という動詞が出てくる。「楽しい時」は泣かずに笑うかもしれない。しかし、うれし泣きというものもある。「悲しいと時」「淋しい時」「せつない時」「むなしい時」は泣くかもしれない。
なにげないことばだが、いろいろな感情(名づけることのできない感情)を「思いが言葉にならない」と言い直した瞬間に、感情が凝縮する。感情が凝縮するから「大きい声」になる。
「言葉」と「声」が対比されることで、「声」の方が「肉体」に近い感じがつたわってくる。
*
蛍火 杉恵美子
大きな変動の中で
小さな決意と小さな落胆
瞬間を埋める
少しの共感と少しの慈しみ
この世の呼吸を引き受けて
闇の中に凛と
光るものに
出会う時
池田の詩が「楽しい時」「悲しいと時」と「時」を並列しながら感情を対比させているのに対し、杉は「大きな」「小さな」「少し」を手がかりに感情や意思を結びつけている。そうしておいて、「この世の呼吸を引き受けて」ということばを動かす。この「呼吸」は、なんだろう。「決意」「落胆」「共感」「慈しみ」というようなことばでは言いあらわすことのできない何かである。池田が書いていた「声」に似ている。「呼吸」は、この場合、そっと吸い込み、すっと吐き出す。そのとき「声」のかわりに、「声を殺した」何かが出て行く。
この肉体の動きというか、呼吸する肉体といっしょに動くこころを「凛」と呼んでいる。蛍を見ながら、そういう「凛とした」一瞬を思い出しているのだろう。
最終行の「出会う時」の「時」という終わり方に余韻がある。その「時」、杉は「呼吸」と「凛」の関係に気づいたのだろう。「時」と書くことで、杉の意識が杉自身へ向かっている、杉の中で凝縮していることがわかる。
*
雨の日の窓 徳永孝
外は雨
窓ガラスを流れ下(お)ちる無数の水滴
いくつかが群れるように降りていく
こちらではぽつんと一滴 自分のペースで
それらを追い越し
急ぎ降りていく水滴達
後になり先になり
互いに競い合うように
しばし留まりまた流れていく者
先行く水滴を追いかける者
並行して流れる二つの水滴
いつの間にか一諸になっている者達
そのままずっと並び流れていく者達
不意に相手を置き去りにし先急ぐ者
尽きることなく過ぎていく
それぞれの水滴の様(さま)
雨が止めば
全て終るのだろうが
このままいつまでも続くような思いで
今はただ眺めている
二連目「こちらではぽつんと一滴 自分のペースで」の「こちら」と「自分」の結びつきが、この詩を支えている。「あちら」ではなく「こちら」だから「自分」なのである。誰かに、あるいは何かに、ここでは雨の水滴だが、それに感情移入した時、その対象が「自分」になる。感情移入をスムーズにさせることばが「こちら」であり「自分」。
「こちら」も「自分」も、この詩は成立する。つまり、その一行を省略し、二連目と三連目を結合しても「意味」は変わらない。雨の日に、窓を水滴が走るように落ちていくという状況は変わらない。しかし、感情移入の「度合い」が違ってくる。
感情移入の強さが、雨(粒)/水滴を「もの」ではなく「者」と呼ばせている。
最終連に「こちら」ということばはないが、眺めている「こちら」(室内)が暗示されている。感情移入した後、放心している。このあと徳永は、完全に「自分」にもどらなければならないのだが、いまは、放心している。
この詩には、池田のつかっていた「ただ」ということばが、やはりつかわれている。「ただ」と「ことばもなく、放心している」状態かもしれない。
*
あの時から 木谷明
梅雨が好き なのは
涼しくて 雨は降ってて
いうことは何もない からかな
洗濯もしない あわててしない
梅雨ではないけれど
腰高の窓から
大粒の雨が燦然と降っていた外の世界
綺羅綺羅 黙って
あの時は 知らなかった 雨だけを 見ていた
黙って
雨を好きになった時
「ことばもなく、放心している」を木谷は「黙って」と言っているかもしれない。そして、それをさらに「好き」という感情で言いあらわしている。「好き」とは自分の心が勝手にどこかへ行ってしまって、そこへ「来い」と呼んでいることかもしれない。そこへ「行く」と自分は自分ではなくなる。これはたいへんなことなのだが、「放心」しているから、たいへんであるとも気がつかない。
二連目の「洗濯もしない あわててしない」が不思議な効果をもたらしている。何もしない。ただ「放心」している。そして、自分ではなくなっていく。
自分ではなくなっていくのだけれど、そのあと、それを思い出して「雨を好きになった時」と「時」へ引き返す。杉の書いていた「時」と同じ使い方だが、これも効果的だ。自省するこころというか、自分自身をみつめる静かさがある。
四連目の「腰高の窓」の「腰高」は最近は聞かないことばだが、なんとなく「時代/過去」を感じさせて、最終行の「時」と、意味ではなく、ちょっと違うところでことばを呼応させている。そこに不思議な、ことばの豊かさがある。
*
窓 青柳俊哉
雪でつくられた窓
窓枠の中へ迎えいれ
去っていくものの肌を
霧が運んでいく
すべての他者にわたしがあり
永劫のわたしはいない
他者にはみえないわたしという窓に
無限をわたる光がとけている
未知のわたしへふきわたっていく
柔らかい濃霧の肌触り
わたしにしいられる窓の
永劫の雪の肌ざわり
詩を書く時、「課題」を出すわけではないが、なぜか、その日に集まってくる詩には共通するものがある。「窓」は徳永と木谷の詩にも登場した。この「窓」を青柳は「他者にはみえないわたしという窓」という具合につかっているが、これを「窓枠」と読み、ここから「枠」を取り出せば、杉の書いていた自他の区別、あるいはそれを超える「呼吸」とのつながりを読むことができるかもしれない。
「すべての他者にわたしがあり/永劫のわたしはいない」という深い哲学は、世界全体と自己との融合への入り口である。ことばにしているが、それこそ池田の書いている「言葉にならない」世界である。ことばにすると、矛盾する。ここでは「わたしがあり」「わたしはいない」という矛盾が同居している。もちろん、それには前提条件があるから矛盾であるとは断定できないのだが、そういうことば(論理)を超えて動いているのが詩である。
「すべての他者にわたしがあり」からはじまる五行は、一行一行が書き換え不能の真実であり、だからこそ論理がつかみにくい。一行ずつに立ち止まり、一行ずつに納得すればいい。もちろん納得ではなく否定という形でもいいが、大事なのは、五行全体をむりやり「論理」にしてしまわないことだ。
それこそ、ここには「時」が書かれているのだ。