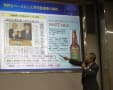京大の先生方が、大学で生まれた新技術を引っさげて東京に売り込みに来た。12ケースの新技術の内、9ケースは未発表で本邦初公開と言うことでもあり、多くの科学者や技術者が集まって熱心に発表に聞き耳を立てていた。
京大は総合大学なので、技術開発については、理学、工学、農学のほかにも、医学部のメディカル・バイオ、それに、ソフトウエア・コンテンツ関連もあるので、これらを統合しての話であるが、産官学連携や知財管理等に関して全学上げて体制を整備し、積極的に取り組み始めたようである。
シリコンバレーから巻き起こったアメリカのITデジタル革命も正にスタンフォード大学から始動したようなもので、日本の動きは何十年も遅れた感じであるが、
日本も、国立大学が独立行政法人化し、経産省、文科省等やその関連の政府機関が積極的に科学技術の振興やイノベーション戦略を推進し始めてから、大学発の発明発見・知財等が注目され始め、活発に事業化が図られるようになってきた。
MOTの普及の一環でもあるのであろうか、新技術を発表する京大の学者達も、結構、自分たちの新発明の技術についての事業化については、熱意を示していて、時代も変わったものだと思って聞いていた。
新技術の説明については、土木工学系、情報通信系、医学・バイオ系、理工学系の新素材や新技術などバラエティに富んでいたが、門外漢の私には良く分からない分野の話なので、フォローするのが大変であったが、予定があって、後半の新素材など理工学系の斬新な発明について聴講をミスったのが残念であった。
問題は、新しい発見や発明が行われてシーズがいくら沢山生まれて来ても、これが、イノベーションとして実用化、事業化されるまでには大変な過程を経なければならないと言うことである。
あの超有名商品になっている3Mのポストイットにしても、接着技術の開発に失敗した技術を逆利用したイノベーションなのだが、実用化されるまでには大変な紆余曲折を経て随分な時間を要したと聞く。
まして、用途の特定出来ない新技術の発明についての実用化については、周辺技術の開発や製品化、事業採算の見込み等あらゆる条件が成熟しない限り実現は難しい。
それに、電話とラジオのように、発明の意図と実際の実用とが全く逆転して実用化されることなど、思いがけない形でイノベーションが起こる事もある。
ところで、京大では、新しい理工学系の拠点として開発された桂キャンパス周辺が、科学技術の発明発見拠点としてだけではなく、R&D,新産業のインキュベーションやベンチャー拠点などとして総合的に開発されて行くようであるが、非常に素晴らしいことである。
元々、京都はベンチャーは勿論、伝統技術と最新の技術を駆使した優良な新産業が生まれ出る土壌であり、今でも、技術に優れた優良企業の多くが京都を拠点にしている。
この京大で生まれつつある優良な新しい新発見や新発明については、グローバル時代であるから、日本企業の開発・イノベーション化については多くを期待出来ないので、世界に向かって英語で情報を発信してパートナーを探すべきだと思う。
何時も思うのだが、理工学系だけではなく、文科系も含めて京大にはユニークな知の集積が充満しているので、これを如何に外に向かって発信して活性化すべきか、もっと頭を使って考えるべきである。
ドラッカーの言を待つまでもなく、大学に一番欠けているのは、マネジメントの意識とその能力である。
京大は総合大学なので、技術開発については、理学、工学、農学のほかにも、医学部のメディカル・バイオ、それに、ソフトウエア・コンテンツ関連もあるので、これらを統合しての話であるが、産官学連携や知財管理等に関して全学上げて体制を整備し、積極的に取り組み始めたようである。
シリコンバレーから巻き起こったアメリカのITデジタル革命も正にスタンフォード大学から始動したようなもので、日本の動きは何十年も遅れた感じであるが、
日本も、国立大学が独立行政法人化し、経産省、文科省等やその関連の政府機関が積極的に科学技術の振興やイノベーション戦略を推進し始めてから、大学発の発明発見・知財等が注目され始め、活発に事業化が図られるようになってきた。
MOTの普及の一環でもあるのであろうか、新技術を発表する京大の学者達も、結構、自分たちの新発明の技術についての事業化については、熱意を示していて、時代も変わったものだと思って聞いていた。
新技術の説明については、土木工学系、情報通信系、医学・バイオ系、理工学系の新素材や新技術などバラエティに富んでいたが、門外漢の私には良く分からない分野の話なので、フォローするのが大変であったが、予定があって、後半の新素材など理工学系の斬新な発明について聴講をミスったのが残念であった。
問題は、新しい発見や発明が行われてシーズがいくら沢山生まれて来ても、これが、イノベーションとして実用化、事業化されるまでには大変な過程を経なければならないと言うことである。
あの超有名商品になっている3Mのポストイットにしても、接着技術の開発に失敗した技術を逆利用したイノベーションなのだが、実用化されるまでには大変な紆余曲折を経て随分な時間を要したと聞く。
まして、用途の特定出来ない新技術の発明についての実用化については、周辺技術の開発や製品化、事業採算の見込み等あらゆる条件が成熟しない限り実現は難しい。
それに、電話とラジオのように、発明の意図と実際の実用とが全く逆転して実用化されることなど、思いがけない形でイノベーションが起こる事もある。
ところで、京大では、新しい理工学系の拠点として開発された桂キャンパス周辺が、科学技術の発明発見拠点としてだけではなく、R&D,新産業のインキュベーションやベンチャー拠点などとして総合的に開発されて行くようであるが、非常に素晴らしいことである。
元々、京都はベンチャーは勿論、伝統技術と最新の技術を駆使した優良な新産業が生まれ出る土壌であり、今でも、技術に優れた優良企業の多くが京都を拠点にしている。
この京大で生まれつつある優良な新しい新発見や新発明については、グローバル時代であるから、日本企業の開発・イノベーション化については多くを期待出来ないので、世界に向かって英語で情報を発信してパートナーを探すべきだと思う。
何時も思うのだが、理工学系だけではなく、文科系も含めて京大にはユニークな知の集積が充満しているので、これを如何に外に向かって発信して活性化すべきか、もっと頭を使って考えるべきである。
ドラッカーの言を待つまでもなく、大学に一番欠けているのは、マネジメントの意識とその能力である。