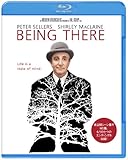石井久美子「生き字引」ほか(「火曜日」113 、2013年02月28日発行)
石井久美子「生き字引」は亡くなった父のことを書いている。「火曜日」にはほかに2篇の作品があるが、その2篇も父のことを書いている。「生き字引」がいちばん印象に残った。
「分かる」というのは不思議なことだと思う。「分かる」は「正しい」かどうかではなく、信じられるかどうか、納得できるかどうかなのである。そして、そのとき「信じられる」「納得できる」は、そのことばが語る「こと」ではなく、そのことばを語った「ひと」なのである。抽象的な「こと」ではなく、いま、目の前にいる「ひと」という肉体なのである。
これは--なんというか、「非哲学的」「非論理的」な「事実」なのだが、だから、そこに「真実」がある。で、この「真実」を「愛」と呼んだりするのだが。まあ、そんなことを書いてしまうと、どこか「きれいごと」になってしまいそうだが。でも、書いたおきたいなあ。最後の「間違っていてもいいから」は、私の書いていることを叩き壊して、そこに生き残る。そう思うから。
「間違っていてもいいから」。ひとはいつだって「間違い」か「正しい」かを問題にしない。というよりも、もしかすると「間違っている」からこそ、わかり、また信じるのかもしれない。
父に聞いて「わかった」ことを誰かに言う。そして、その「答え」を、たとえば学校で教室で先生に、あるいは友だちに「それは間違っている」と指摘される。そういうことは、多くのひとが経験すると思う。そして、その瞬間、恥ずかしくなったり、「お父さんは、もう、でたらめばかり言って信用できない」と思い、家に帰ってお父さんに苦情を言う、ということもするかもしれない。そういうとき、「お父さん」がしっかりと「わかる」。「肉体」として生きている実感が、「肉体」のなかに生まれてくる。そして、生きつづける。この「実感」に「間違い」はない。絶対的に「正しい」。だから、教えてもらったことが「間違っている」としても、それを越えることができるのだ。
石井の詩は、いわゆる「現代詩」ではないかもしれない。けれど、いいなあ、こういう実感が正直にあふれてくる詩は。
*
村中秀雄「ことばは」は、「わからない」。
「わからない」のだけれど、いいかえると、「流通言語」になるように、主語と述語の関係を明確にし、「意味」を散文化して言いなおすことはできないのだけれど。
冬の裸の木のように、ただそこに存在する、そういう「ことば」でありたい。何があってもじっとしていれば大丈夫。荒れ狂う天気も過ぎ去る。「ことば」はたえることができる。たえて、生き残る。何も言わず、黙っている冬の裸の木、その木にも、聞こえないけれどほんとうは「声」がある。「ことば」がある。その力を、村中は、こういう詩を書くことで「共有」している。共有することで、村中は木が「わかる」。
それはもしかしたら、石井の父が言ったように「間違っているかもしれん」ことだけれど、それが間違っていたとしても、それはそれでいい。「わかる」ことが大事なのだ。
あらゆることが、そうなのだと思う。詩を読む。その読み方は「間違っているかもしれない」。けれど、間違いなど、どうでもいい。「わかる」ということが大事なのであり、その「わかる」は他人には関係がない。読んだ人間が「わかる」と実感できるかどうかだけである。だから「わからない」という言い方でしか「わかる」ことができないということもある。言い換えると「間違える」という言い方で「わかる」ということもある。
石井久美子「生き字引」は亡くなった父のことを書いている。「火曜日」にはほかに2篇の作品があるが、その2篇も父のことを書いている。「生き字引」がいちばん印象に残った。
生き字引のような父だった
分からないことがあれば
いつ聞いてもめんどうがらず
丁寧に教えてくれた
最後にたいてい
「間違っているかもしれんで」
と言ってたっけな
突然旅立ってしまった
父の代わりとなる人がおらず
分からないこと
ネットで調べてみたりするけど
読んでもよく分からない
やっぱりお父さんの声で聞きたいよ
間違っていてもいいから
「分かる」というのは不思議なことだと思う。「分かる」は「正しい」かどうかではなく、信じられるかどうか、納得できるかどうかなのである。そして、そのとき「信じられる」「納得できる」は、そのことばが語る「こと」ではなく、そのことばを語った「ひと」なのである。抽象的な「こと」ではなく、いま、目の前にいる「ひと」という肉体なのである。
これは--なんというか、「非哲学的」「非論理的」な「事実」なのだが、だから、そこに「真実」がある。で、この「真実」を「愛」と呼んだりするのだが。まあ、そんなことを書いてしまうと、どこか「きれいごと」になってしまいそうだが。でも、書いたおきたいなあ。最後の「間違っていてもいいから」は、私の書いていることを叩き壊して、そこに生き残る。そう思うから。
「間違っていてもいいから」。ひとはいつだって「間違い」か「正しい」かを問題にしない。というよりも、もしかすると「間違っている」からこそ、わかり、また信じるのかもしれない。
父に聞いて「わかった」ことを誰かに言う。そして、その「答え」を、たとえば学校で教室で先生に、あるいは友だちに「それは間違っている」と指摘される。そういうことは、多くのひとが経験すると思う。そして、その瞬間、恥ずかしくなったり、「お父さんは、もう、でたらめばかり言って信用できない」と思い、家に帰ってお父さんに苦情を言う、ということもするかもしれない。そういうとき、「お父さん」がしっかりと「わかる」。「肉体」として生きている実感が、「肉体」のなかに生まれてくる。そして、生きつづける。この「実感」に「間違い」はない。絶対的に「正しい」。だから、教えてもらったことが「間違っている」としても、それを越えることができるのだ。
石井の詩は、いわゆる「現代詩」ではないかもしれない。けれど、いいなあ、こういう実感が正直にあふれてくる詩は。
*
村中秀雄「ことばは」は、「わからない」。
ことばは
どちらかと言えばやさしく
いばっているより裸木のあの
わかりやすさがいい。
アルプスの峰のように
厚い氷のカーテンを重ねた冬の雲が
南の空を--
天が荒れ狂っても
じっとしておれば怖くないんだ、と
黙って輝いている
「わからない」のだけれど、いいかえると、「流通言語」になるように、主語と述語の関係を明確にし、「意味」を散文化して言いなおすことはできないのだけれど。
冬の裸の木のように、ただそこに存在する、そういう「ことば」でありたい。何があってもじっとしていれば大丈夫。荒れ狂う天気も過ぎ去る。「ことば」はたえることができる。たえて、生き残る。何も言わず、黙っている冬の裸の木、その木にも、聞こえないけれどほんとうは「声」がある。「ことば」がある。その力を、村中は、こういう詩を書くことで「共有」している。共有することで、村中は木が「わかる」。
それはもしかしたら、石井の父が言ったように「間違っているかもしれん」ことだけれど、それが間違っていたとしても、それはそれでいい。「わかる」ことが大事なのだ。
あらゆることが、そうなのだと思う。詩を読む。その読み方は「間違っているかもしれない」。けれど、間違いなど、どうでもいい。「わかる」ということが大事なのであり、その「わかる」は他人には関係がない。読んだ人間が「わかる」と実感できるかどうかだけである。だから「わからない」という言い方でしか「わかる」ことができないということもある。言い換えると「間違える」という言い方で「わかる」ということもある。
 | 幸せのありか―れお君といっしょに |
| 石井久美子 | |
| 編集工房ノア |