監督・脚本・音楽・声の出演 アリ・フォルマン
アニメとは知らなかった。最初は、いつになったら実写になるのだろうと思いながら見ていた。ドキュメンタリーであるとも知らなかったので、見ているうちに、ドキュメンタリーならではの「事実」の力に引き込まれて行った。
でも、まあ、この映画の最大の魅力は独特のアニメだろう。その映像だろう。まるで実写映像のコントラストを大きくして、影と光で表現しなおしたような絵。あるいは、版画のような、といってもいいかもしれない。線の描写が強い。そのリアルさは、3Dアニメやコンピューターグラフィックスのリアルさとはまったく別。夢--いや、悪夢のリアルさである。そして、その悪夢を印象づけるのが、光と影に二分割されたような映像のなかにあって、目だけがまるで実写のように生々しいのである。
映画の内容は、映像そのままに「悪夢」である。
映画監督である主人公が、自分の体験したはずのベイルートの住民虐殺の記憶を、友人を訪ね歩きながら取り戻す。住民虐殺という「輪郭」(アニメで言うと、黒い線の部分だね)ははっきりしているが、その「内部」が空白である。(アニメの、黒い輪郭に囲まれた、たとえば、主人公の顔--それには「起伏」がない。「肌」のつながりがない。輪郭の内側は、文字通り白い「空白」なのである。)主人公は、その「空白」を埋めたいと思っている。それは言い換えると、顔の「空白」を表情で埋めるということかもしれない。表情というのは、ただ単に顔の表面にあるのではなく、人間の「内部」から生まれてくる。体験、記憶、というものがあって、はじめて顔が顔になる。
記憶を取り戻す--という監督のこころみは、彼自身の「表情」を取り戻すというこころみでもあるのだ。映画の最後が虐殺された少女の「表情」のアップで終わるのは、この「表情」を取り戻すというこころみと関係があるのだ。虐殺に関係した監督の「表情」は虐殺された少女の「表情」を手にいれることで、はじめて光と影で二分割されたアニメの顔からほんものの顔になるのだ。--記憶を取り戻すとは、自分自身が関係した虐殺の犠牲者の「顔」のすべてを自分の顔・表情として、自分の「顔」として受け入れること、虐殺の犠牲者の「顔」を生きることなのだ。
監督に最初に相談に訪れる友人が、ベイルートで殺した26匹の犬の顔をすべて覚えているというが、虐殺に関係した監督は、虐殺された人々の顔をひとりも覚えていなかった。他人のいのちを奪ったのに、そのひとの顔の記録さえない。ひとには名前があり、また同時に顔がある。顔によって、ひとはひとになる。そのことを思うとき、このアニメの「絵」そのものが、ひとつの「思想」であることがわかる。
実写をなぞったようなアニメ。実写を光と影のコントラスト、輪郭と空白にしてしまった登場人物(おそらく実在の人物)--彼らもまた「顔・表情」を失った不完全な存在である。不完全、というのは「実写・実物」に対して不完全という意味である。重要な「顔」「表情」をなくしている、という意味である。
監督は、登場人物を、そういう不完全なアニメの映像にすることで、登場人物(彼自身を含めて)を告発しているのである。ベイルート虐殺に関係するすべての人間を告発しているのである。彼らはすべて「表情」をうしなった人間である、と。「表情」を取り戻すためには、虐殺された人々の顔・表情を「アニメ」ではなく、実写としてリアルに思い出し、それを自分自身の「肉体」にしなくてはならない、と。
アニメであることが、この映画の場合、思想そのものなのだ。告発そのものなのだ。
アニメだけに限らず、表現とは何か、ということを問いかける映画でもある。私たちの、ことば、記憶、感情--それはいったい何なのか、という問いを含んだ強烈な映画である。表現の表層と、表現の内容の関係はどうあるべきなのか、という問いを含んだ映画でもある。
自分で何かを表現したいと思う人は必ず見るべき映画である。
(キネマ旬報のベスト10に入っていた映画である。福岡では、いま、ようやく上映されている。)
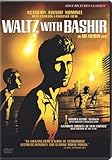 | Waltz with Bashir [DVD] [Import]このアイテムの詳細を見る |


















