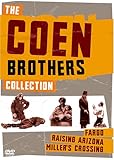季村敏夫『ノミトビヒヨシマルの独言』(7)(書肆山田、2011年01月17日発行)
季村敏夫『ノミトビヒヨシマルの独言』には書かれていることと書かれていないことがある。ことばなのだから、それはだれの詩、だれの文学作品でもそうなのだが、そのことを感じさせることばは意外と少ない。つまり、あ、ここには書かれていないことがある、それを感じよ、という声がはっきりと聞こえる作品は少ない。季村の詩からは、その「書かれていないことを感じよ」という強い声がする。
「骨片の月」の書き出し。
二度目の没落--と書いてあるが、一度目は何か。それは書いていない。二度目と「茶番の始まり」はたぶん重複する。同じ「意味」であると想像できる。けれども、それはどういうことなのか、この書き出しだけではわからない。わからないように、書いているのである。季村は。
なぜか。
書き出しの「二度」がキーワードである。あらゆることは、二度起きる。最低、二度起きる。一度目は、実際の「事件」(できごと)として。二度目は、それを語ること--ことばによって。
季村は『日々の、すみか』(書肆山田)で「ことばはおくれてやってくる」と書いた。阪神大震災のことを書いた詩集だが、たしかにことばは遅れてやってくる。今度の東日本巨大地震でも、被災者の女性が「ことばにならない。初めてのことだもの」というようなことを言っていたが、ことばはたしかにすぐにはことばにならない。どう言っていいのかわからないことがある。わかるまで、ひとは、それを自分の肉体の中にしまいこんでおくしかない。
二度目。それは、ことばによって始まるのだ。
そういうことを、季村は書こうとしている。
「一、二、三、四/ひい、ふう、みい、よう、」がなんの数なのかわからない。あとで季村はわかるように書いているが、最初は、わからないように書いている。これは、それがなんの掛け声なのか、なぜ中国語と日本語(それも、あえて、ひい、ふう、みい、よう、)なのか。
それは、季村にはわかっている。わかっているけれど、わかりたくないことばでもあるのだ。わかりたくない声でもあるのだ。わからない、知らない、ということで、ことばを遠ざけたい。「二度目」であることばを遠ざけることで、「一度目」の「事件(できごと)」を拒みたいのだ。
そして季村が、聞き取ってもらいたいのは、「一度目」の「できごと」でもなければ、「二度目」のことば、声でもない--「二度目」を拒絶したい、「二度目」を拒絶することで「一度目」を遠ざけない、ないものにしたい、という強い願いである。
それはかなわぬ願いである。起きたことは必ずことばになる。一度目は必ず二度目になる。かなむぬ願いであっても、それを願わずにはいられない。
そういうとき、ことばは、大きく変化する。
「臀部」「便器」という人間の「肉体」に深く関係していることがら、それも「汚いもの」と、「銀河」が突然対比させられる。「銀河」は「臀部」「便器」とは対極にあるものである。汚れていない。あくまでも純粋に、そして非情に輝いている。
人間は、どんなことでもする。してしまう。そのとき、その人間の行為、行動の奥にも「銀河」の法則、宇宙の真理は動いているのか。
そう自分自身に問いかけてみるとき(季村は、ことばを書きながら、まず自分に問いかけている。その問いが、同時に読者への問いにもなる)、季村の見ているのは「銀河」のことばである。「一度」起き、「二度目」に繰り返され、さらには何度でも繰り返されて動いていくことばではなく、「一度」起きたら、それが「永遠」であるような、つまり何度ことばをかえて言いなおしてみても、「一度」自体は絶対にかわならい輝きとしてのことばである。そのことばで「一度目」を洗い流すと、次のようなことばが、断片として残される。
動詞(述語)を取り払った「名詞」。
ことばが、そんなふうに洗い流されるとき、たしかに「銀河」は存在するのだと思う。向き合うべきことばがあるのだと思う。ことばに向き合い、自分をととのえ、鍛え直していくための何かがあるのだと思う。
「銀河」は非情である。人間に何もしてくれない。けれど、何もしてくれないものも、それ自体は何もしないわけではなく、ちゃんと動いている。自分の「法則」にしたがって動いている。その「法則」に向き合えることばを探さなければならないのだ。
「一度目」は「事件(できごと)」として生まれる。「二度目」は、その「事件」を目撃したものの「ことば」として起きる。そして、その「目撃証言」が「他人」のことばであるとき、当事者はそれを拒絶することができる。自分のことばで、他人の「二度目」のことばを拒絶し、自分自身で「二度目」のことばで「事件」をととのえることができるし、そうしなければならないのだ。
この「事件」をととのえるというのは、しかし、過酷なことである。自分の都合のいいようにことばを組み立てれば、それは「自己弁護」になってしまって、「事実」から遠ざかる。「銀河」から遠ざかる。事件を洗い流し、「もの」そのものにしなければならない。
と、中国語と日本語で、違っていてはいけないのだ。違う表現が成り立つとき、それは「事件」を「誤記」していることになる。
「誤記」には、いくつもの種類がある。そして、そのうちの「濁った誤記」という「二度目」によって、何かが「没落」させられる。--その没落から、立ち上がるために、真の「二度目」のことばが必要になる。
季村は、それを探しながら書いている。
季村の詩には、書かれていることと書かれていないことがある。そして、その書かれていないことは、探しながら書く、書きながら探すしかないものなのである。季村は、書かれないもの(まだ書くことのできないもの)を探しながら書く--そのときの、声にならない声に耳を澄ませよ、そんなふうにしてことばと向き合え、と私たちを静かに叱責している。書かれていないこと、こそが、詩、なのである。「声」をもとめる「声」にこそ、「銀河」なのである。私たちを、宇宙へ導いてくれる力なのである。
季村敏夫『ノミトビヒヨシマルの独言』には書かれていることと書かれていないことがある。ことばなのだから、それはだれの詩、だれの文学作品でもそうなのだが、そのことを感じさせることばは意外と少ない。つまり、あ、ここには書かれていないことがある、それを感じよ、という声がはっきりと聞こえる作品は少ない。季村の詩からは、その「書かれていないことを感じよ」という強い声がする。
「骨片の月」の書き出し。
二度目の没落へ。かつて喝破された茶番の始まりとして。弛緩し、
ふやけてしまった皮膚が、これほどまでにあらわになったことは、
かつて一度たりともなかった。
二度目の没落--と書いてあるが、一度目は何か。それは書いていない。二度目と「茶番の始まり」はたぶん重複する。同じ「意味」であると想像できる。けれども、それはどういうことなのか、この書き出しだけではわからない。わからないように、書いているのである。季村は。
なぜか。
書き出しの「二度」がキーワードである。あらゆることは、二度起きる。最低、二度起きる。一度目は、実際の「事件」(できごと)として。二度目は、それを語ること--ことばによって。
季村は『日々の、すみか』(書肆山田)で「ことばはおくれてやってくる」と書いた。阪神大震災のことを書いた詩集だが、たしかにことばは遅れてやってくる。今度の東日本巨大地震でも、被災者の女性が「ことばにならない。初めてのことだもの」というようなことを言っていたが、ことばはたしかにすぐにはことばにならない。どう言っていいのかわからないことがある。わかるまで、ひとは、それを自分の肉体の中にしまいこんでおくしかない。
二度目。それは、ことばによって始まるのだ。
そういうことを、季村は書こうとしている。
一(イー)、二(アル)、三(サン)、四(スウ)、
ひい、ふう、みい、よう、
今しがた臀部を受け入れていた便器のなかにも、銀河は潜んでいる
のだろうか。起床。整頓。朝食。清掃。やがて屈伸運動を繰り返す
頭上、寝ぼけた明烏(あけがらす)。
「一、二、三、四/ひい、ふう、みい、よう、」がなんの数なのかわからない。あとで季村はわかるように書いているが、最初は、わからないように書いている。これは、それがなんの掛け声なのか、なぜ中国語と日本語(それも、あえて、ひい、ふう、みい、よう、)なのか。
それは、季村にはわかっている。わかっているけれど、わかりたくないことばでもあるのだ。わかりたくない声でもあるのだ。わからない、知らない、ということで、ことばを遠ざけたい。「二度目」であることばを遠ざけることで、「一度目」の「事件(できごと)」を拒みたいのだ。
そして季村が、聞き取ってもらいたいのは、「一度目」の「できごと」でもなければ、「二度目」のことば、声でもない--「二度目」を拒絶したい、「二度目」を拒絶することで「一度目」を遠ざけない、ないものにしたい、という強い願いである。
それはかなわぬ願いである。起きたことは必ずことばになる。一度目は必ず二度目になる。かなむぬ願いであっても、それを願わずにはいられない。
そういうとき、ことばは、大きく変化する。
今しがた臀部を受け入れていた便器のなかにも、銀河は潜んでいる
のだろうか。
「臀部」「便器」という人間の「肉体」に深く関係していることがら、それも「汚いもの」と、「銀河」が突然対比させられる。「銀河」は「臀部」「便器」とは対極にあるものである。汚れていない。あくまでも純粋に、そして非情に輝いている。
人間は、どんなことでもする。してしまう。そのとき、その人間の行為、行動の奥にも「銀河」の法則、宇宙の真理は動いているのか。
そう自分自身に問いかけてみるとき(季村は、ことばを書きながら、まず自分に問いかけている。その問いが、同時に読者への問いにもなる)、季村の見ているのは「銀河」のことばである。「一度」起き、「二度目」に繰り返され、さらには何度でも繰り返されて動いていくことばではなく、「一度」起きたら、それが「永遠」であるような、つまり何度ことばをかえて言いなおしてみても、「一度」自体は絶対にかわならい輝きとしてのことばである。そのことばで「一度目」を洗い流すと、次のようなことばが、断片として残される。
起床。整頓。朝食。清掃。やがて屈伸運動を繰り返す
頭上、寝ぼけた明烏。
動詞(述語)を取り払った「名詞」。
ことばが、そんなふうに洗い流されるとき、たしかに「銀河」は存在するのだと思う。向き合うべきことばがあるのだと思う。ことばに向き合い、自分をととのえ、鍛え直していくための何かがあるのだと思う。
「銀河」は非情である。人間に何もしてくれない。けれど、何もしてくれないものも、それ自体は何もしないわけではなく、ちゃんと動いている。自分の「法則」にしたがって動いている。その「法則」に向き合えることばを探さなければならないのだ。
「一度目」は「事件(できごと)」として生まれる。「二度目」は、その「事件」を目撃したものの「ことば」として起きる。そして、その「目撃証言」が「他人」のことばであるとき、当事者はそれを拒絶することができる。自分のことばで、他人の「二度目」のことばを拒絶し、自分自身で「二度目」のことばで「事件」をととのえることができるし、そうしなければならないのだ。
この「事件」をととのえるというのは、しかし、過酷なことである。自分の都合のいいようにことばを組み立てれば、それは「自己弁護」になってしまって、「事実」から遠ざかる。「銀河」から遠ざかる。事件を洗い流し、「もの」そのものにしなければならない。
イー、アル、サン、スウ、
ひい、ふう、みい、よう、
と、中国語と日本語で、違っていてはいけないのだ。違う表現が成り立つとき、それは「事件」を「誤記」していることになる。
「誤記」には、いくつもの種類がある。そして、そのうちの「濁った誤記」という「二度目」によって、何かが「没落」させられる。--その没落から、立ち上がるために、真の「二度目」のことばが必要になる。
季村は、それを探しながら書いている。
季村の詩には、書かれていることと書かれていないことがある。そして、その書かれていないことは、探しながら書く、書きながら探すしかないものなのである。季村は、書かれないもの(まだ書くことのできないもの)を探しながら書く--そのときの、声にならない声に耳を澄ませよ、そんなふうにしてことばと向き合え、と私たちを静かに叱責している。書かれていないこと、こそが、詩、なのである。「声」をもとめる「声」にこそ、「銀河」なのである。私たちを、宇宙へ導いてくれる力なのである。
 | 日々の、すみか |
| 季村 敏夫 | |
| 書肆山田 |