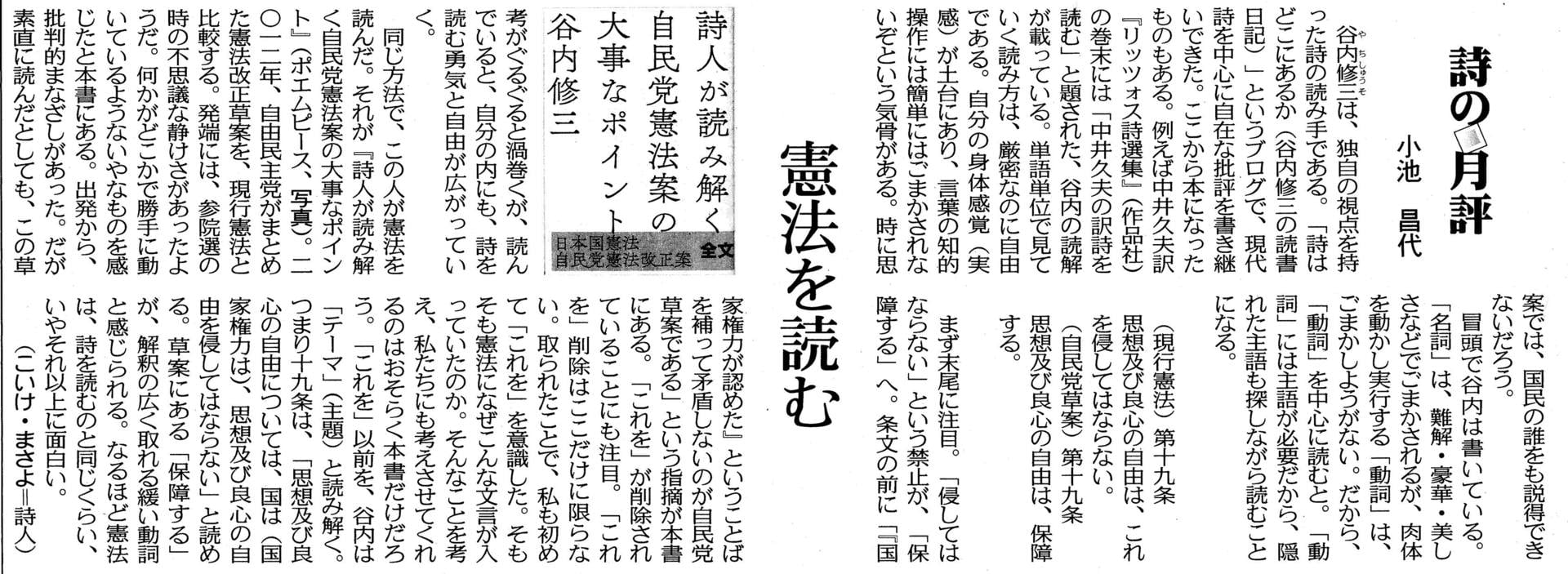谷元益男『滑車』(思潮社、2016年10月30日)
谷元益男『滑車』は『水源地』につづく詩集。読みながら、私はとまどってしまう。「あとがき」に、こう書いてある。
この狭い村で、生まれて死んで逝く、多くのいきものの「日常」を視たい。生まれることの喜びよりも、死のなげきの方が多い、小さな「村」の人々。
私は北陸の貧しい集落で育ったので、谷元が書いている「日常」はある程度理解できる。しかし、その「日常」は私の知っているいまの北陸の集落とはぜんぜん違う。「記憶の集落」にしか見えない。
「記憶の集落」とは、いまのことばでつかみとった集落ではなく、過去のことばでつかみとった集落。「過去のことば」が動いている。見知ったことば、言い換えると「流通言語」が動いている。
だから、とまどう。
詩集に書かれていることがらは『水源地』と同様に、読者にすばやく届くだろう。読者の記憶を揺さぶり、生と死を考えさせてくれるだろう。しかし、いま多くの「村」で起きていることと、どれだけ「正直」にむすびついているだろうか。
山奥の村では老人だけが取り残されて暮らしている。これは、いま現実に起きている事実である。しかし、山奥で、妻を獣と間違えて撃ってしまう男を、私は「現実」として想像できない。
腰が曲がっても、老女は山奥へ「仕事」をしにゆく。山菜取りか、キノコ取りか、たきぎ拾いか。私の田舎ではもうそんなことはしない。山菜取りも山の奥までは入らず、畑、田んぼ仕事の帰りに道端で取るくらいだ。腰が曲がっていては山の斜面は危なすぎる。
銃をつかう男は50年前にはひとりいたが、いまはいないだろう。物騒すぎる。妻が腰が曲がっているなら、夫も腰が曲がっている。猟にはいかないだろう。銃で仕留められる確率はとても低い。猟に行けるような体力が老人には残っていない。
年取った二人にできることは、庭先の畑で、手入れをあまりしなくても育つ野菜をつくり、食べることくらい。先日、すとうやすお「さやえんどうをつむ」を読んだが、それが老人にできることである。すとうは「肉体」をきちんと描いていたが、谷元は「肉体のいま」を描いていない。
もっと具体的に見てみる。
老人が銃を撃つ。狙った「獲物」はどれくらいの距離にいるのだろうか。百メートル? まさか。私は三十メートル以内だと思う。「獣/けもの」ということばが出てくるが、イノシシ、鹿の類ではなく、狙いはうさぎ、きつねの類だろう。イノシシを狙うときは、ひとりでは行かない。重くて持ち帰れない。三十メートル以内、小さな動物を目で確認して銃を撃つ。そうであるなら、妻も見える。谷元が書いている「誤射」を私は想像することができない。
女が最後の悲鳴をあげる。連が変わって(時差があって)、「近寄ってきた男は とっさに/銃を放り投げた」。殺したのが妻だとわかったからだが、えっ、と思う。女が悲鳴を上げたのなら、悲鳴を聞いたときに「獣/けもの」ではないことがわかる。ひとは驚き、銃を放り投げ、女の方へ駆け寄るの。銃をもったまま近づいていくとは、とても思えない。犬にも倒れたのが飼い主であるとわかる。立ち去りはしないだろう。「女の最後の悲鳴を 二匹の犬がくわえて/地を這うように駆けていく」ことはないだろう。
男が狙った「獣」が百メートル先で、悲鳴が小さな声で、男には聞こえないということがあるかもしれない。しかし、先にも書いたが、そんな具合に老人が猟をするとは思えない。老女がそんな場所で仕事をするとも思えない。
谷元は「事実」ではなく、「ストーリー」を書いているのかもしれない。それならそれでかまわないが、なぜ、いま、こういう「ストーリー」が必要なのか。疑問だ。
この作品は「ストーリー」が極端に展開された作品なのかもしれない。他の作品にも、私は「ストーリー」を感じてしまう。「死のなげき」が強調されていると感じてしまう。
すとうの「さやえんどうをつむ」には、小さな仕事の「喜び」が書かれていた。「死」は書かれていないが、静かな「死」を感じさせるものがあった。「いま」を受け入れて生きている。「受け入れる」という生き方に「死」が含まれていると、私は感じた。
谷元の作品は、「いま」を受け入れるというよりも、「いま」をわざとらしくつくりだしている。「わざと」書くのは「現代詩」ではあるけれど、私はとても違和感をおぼえる。
谷元の書いている悲劇はいまの「山村」では起きない。目に見えない、言い換えると「流通言語」ではとらえきれない悲劇がしずかに「山村」をむしばんでいる。
谷元益男『滑車』は『水源地』につづく詩集。読みながら、私はとまどってしまう。「あとがき」に、こう書いてある。
この狭い村で、生まれて死んで逝く、多くのいきものの「日常」を視たい。生まれることの喜びよりも、死のなげきの方が多い、小さな「村」の人々。
私は北陸の貧しい集落で育ったので、谷元が書いている「日常」はある程度理解できる。しかし、その「日常」は私の知っているいまの北陸の集落とはぜんぜん違う。「記憶の集落」にしか見えない。
「記憶の集落」とは、いまのことばでつかみとった集落ではなく、過去のことばでつかみとった集落。「過去のことば」が動いている。見知ったことば、言い換えると「流通言語」が動いている。
だから、とまどう。
詩集に書かれていることがらは『水源地』と同様に、読者にすばやく届くだろう。読者の記憶を揺さぶり、生と死を考えさせてくれるだろう。しかし、いま多くの「村」で起きていることと、どれだけ「正直」にむすびついているだろうか。
沢の声
人里はなれた山奥に
分け入った女は 斜面で死んだ
被いかぶさる枝をかきわけ
水源地に向かう途中
首に鈴をつけた足の長い犬が
女の前を通りぬけた
犬が女にけしかけるように動いた瞬間
銃声が深い沢をぬい
波打った
穂を拾うように
腰の曲がった女は
猛犬に追われる獣にまちがわれ 撃たれたのだ
切り立つ沢は
わずかに流れる水と 老女の血で
褐色に変わり
女の最後の悲鳴を 二匹の犬がくわえて
地を這うように駆けていく
近寄ってきた男は とっさに
銃を放り投げた
吐き出した地声が斜面を
岩となってころがっていく
男が 抱き抱えた女は
妻だったのだ
すでに息は絶え
曲がった腰骨が
牙のように とがっていた
男が 水源にむかって
けもののように叫んだとき
山も
ひざまずき 崩れはてた
山奥の村では老人だけが取り残されて暮らしている。これは、いま現実に起きている事実である。しかし、山奥で、妻を獣と間違えて撃ってしまう男を、私は「現実」として想像できない。
腰が曲がっても、老女は山奥へ「仕事」をしにゆく。山菜取りか、キノコ取りか、たきぎ拾いか。私の田舎ではもうそんなことはしない。山菜取りも山の奥までは入らず、畑、田んぼ仕事の帰りに道端で取るくらいだ。腰が曲がっていては山の斜面は危なすぎる。
銃をつかう男は50年前にはひとりいたが、いまはいないだろう。物騒すぎる。妻が腰が曲がっているなら、夫も腰が曲がっている。猟にはいかないだろう。銃で仕留められる確率はとても低い。猟に行けるような体力が老人には残っていない。
年取った二人にできることは、庭先の畑で、手入れをあまりしなくても育つ野菜をつくり、食べることくらい。先日、すとうやすお「さやえんどうをつむ」を読んだが、それが老人にできることである。すとうは「肉体」をきちんと描いていたが、谷元は「肉体のいま」を描いていない。
もっと具体的に見てみる。
老人が銃を撃つ。狙った「獲物」はどれくらいの距離にいるのだろうか。百メートル? まさか。私は三十メートル以内だと思う。「獣/けもの」ということばが出てくるが、イノシシ、鹿の類ではなく、狙いはうさぎ、きつねの類だろう。イノシシを狙うときは、ひとりでは行かない。重くて持ち帰れない。三十メートル以内、小さな動物を目で確認して銃を撃つ。そうであるなら、妻も見える。谷元が書いている「誤射」を私は想像することができない。
女が最後の悲鳴をあげる。連が変わって(時差があって)、「近寄ってきた男は とっさに/銃を放り投げた」。殺したのが妻だとわかったからだが、えっ、と思う。女が悲鳴を上げたのなら、悲鳴を聞いたときに「獣/けもの」ではないことがわかる。ひとは驚き、銃を放り投げ、女の方へ駆け寄るの。銃をもったまま近づいていくとは、とても思えない。犬にも倒れたのが飼い主であるとわかる。立ち去りはしないだろう。「女の最後の悲鳴を 二匹の犬がくわえて/地を這うように駆けていく」ことはないだろう。
男が狙った「獣」が百メートル先で、悲鳴が小さな声で、男には聞こえないということがあるかもしれない。しかし、先にも書いたが、そんな具合に老人が猟をするとは思えない。老女がそんな場所で仕事をするとも思えない。
谷元は「事実」ではなく、「ストーリー」を書いているのかもしれない。それならそれでかまわないが、なぜ、いま、こういう「ストーリー」が必要なのか。疑問だ。
この作品は「ストーリー」が極端に展開された作品なのかもしれない。他の作品にも、私は「ストーリー」を感じてしまう。「死のなげき」が強調されていると感じてしまう。
すとうの「さやえんどうをつむ」には、小さな仕事の「喜び」が書かれていた。「死」は書かれていないが、静かな「死」を感じさせるものがあった。「いま」を受け入れて生きている。「受け入れる」という生き方に「死」が含まれていると、私は感じた。
谷元の作品は、「いま」を受け入れるというよりも、「いま」をわざとらしくつくりだしている。「わざと」書くのは「現代詩」ではあるけれど、私はとても違和感をおぼえる。
谷元の書いている悲劇はいまの「山村」では起きない。目に見えない、言い換えると「流通言語」ではとらえきれない悲劇がしずかに「山村」をむしばんでいる。
 | 滑車 |
| 谷元 益男 | |
| 思潮社 |