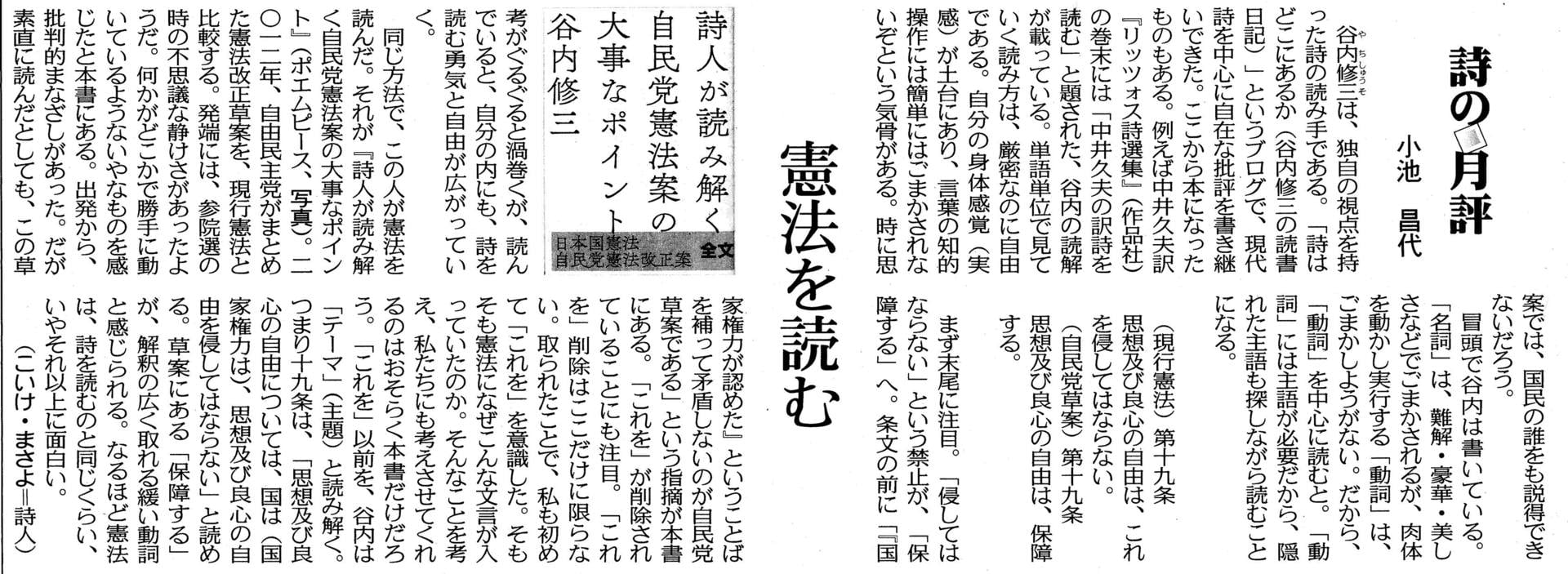板垣憲司『落日の駅、水際で呼ぶ人』(思潮社、2016年10月25日発行)
板垣憲司は第53回現代詩手帖賞(2015年)受賞者。選者は中本道代、中尾太一。
ことばが「詩」になりすぎているかなあ、と思う。
胡桃を叩く翡翠の旅情
やみくもに片鱗を遺す
冬至(葉あかりに至ると
内訌の砂の運びまで
仄かになる
巻頭の「旅情」の書き出し。「胡桃」ということばから始まるためか、あるいは「旅(情)」ということばのせいか、私はふと平出隆を思い出す。ことばの切り詰め方、「あいまい」をそぎ落としていくリズムが似ているかなあ、とも思う。ことばの切り詰め方というのは、逆に言うと、ことばからことばへの飛躍ということでもあるのだが。つまり、切断と接続の仕方。「内訌の砂の運びまで」という一行をまねて言えば、「ことばの運び」(ことばの内部の運び)というか、「ことばの内部」と「ことばの内部」の通い合わせ方(和音の作り方)が、私の記憶の中にある平出と似ている。読みながら、「新しい詩人」を読んでいるというよりも、何か70年代の「新しさ」を読んでいる感じ……。
で、略歴を見たら(私はあまり「略歴」を読んだりしないのだが、気になって読んでしまった)、1947年生まれ。わっ、平出よりも年上だ(たぶん)。詩作に「学生時代に情熱をそそいだ」と書いているから、70年代に詩を書いていたということだろう。平出よりも先に詩を書いていたかもしれない。平出と詩を書きはじめた時期が重なるかもしれない。
ちょっと余分なことを書きすぎたかな。
ことばの接続と切断。大雑把に書きすぎたと思うので、言いなおそう。
胡桃を叩く翡翠の旅情
やみくもに片鱗を遺す
この二行を読むとき、「遺す」という動詞が妙に気になる。動詞なのに動詞という感じがしない。「名詞」と言いなおした方がいいくらい。「遺す」の「主語」がわからないためである。「主語」がないまま「遺っている」という「状態」が書かれているように感じるのだ。
「主語」が切断されて、消えている。
これは、こう言いなおすことができる。「遺す」が「遺っている」のだとしたら「何」が「遺っている」のか。つまり、そのとき「主語/主題」は何なのか。これも、実はよくわからない。
「片鱗」とは何の片鱗か。胡桃か。翡翠か。たぶん「旅情」の片鱗だろう。そうすると「旅情」というものが「遺っている」のか。
ここから、私は一行目に帰る。そして「旅情」というのは「名詞」だけれど、この詩では辞書で調べたままの「品詞」が通じるのか。ほんとうに「名詞」なのか、少し疑問に思う。「遺す」が「動詞」ではなかったように、「旅情」は「名詞」ではないのかもしれない。「旅情」の方が「動詞」なのかもしれない。言い換えると「旅情」のなかには、何かが動いている。動くことで「(旅)情」になっている。「情」とは「動く」ものである。「動く」ことで「情」になる。ここには「動き」が書かれているのではないか。
「胡桃を叩く翡翠」とは「翡翠が胡桃を叩く」の倒置法だが、倒置法によって「動詞」が隠され「名詞」が前面に出てくる。そういう動きが、そのまま「旅情」の「情」の動きなのだ。「倒置法」がいたるところに潜んでいて(隠されていて)、「名詞」と「動詞」を入れ換える。「名詞」は「動詞」として読まなければならない。「動詞」は「名詞」として読み直さなければならない。そういう意識の操作のなかに「切断/接続」があり、それが「詩」をつくっているという感じなのである。
冬至(葉あかりに至ると
内訌の砂の運びまで
仄かになる
ここには「至る」と「運ぶ」という「動詞」の逆転がある。ふつうは、「運ぶ」、そして「至る」という具合に動く。ここでは「至る」ことによって「運ぶ」という「過去」が見える。意識される。そういう変化が「仄かになる」という形で示される。「明らかになる」ではなく「仄かになる」。半分隠される。「冬至(葉あかり」という、丸カッコの受けのない奇妙な表現も、そういう「半分隠す」感じを強くする。
この「知的操作」が平出を思い出させるのかもしれない。「ことばの操作」を「知的」であると感じさせる方法が平出を思い起こさせるのかもしれない。
でも、この「動詞」と「名詞」の入れ換えを平出がやっていたとは思わない。だから、板垣は、たしかに平出とは違うのだと思う。(これは、私の「記憶の印象/今の印象」であって、実際に平出との比較は、ここではしない。)
私が板垣のことばに魅力を感じるのは、「離島の合図」次のような部分。
眼は青く 海の、象られた渦
横顔のように
やがて 崩れ 壊れ、視野をひらく
かすかな、 ( 望郷 の静脈を
鎮める潮目で、玻璃の林を、抜ける)
何を書いてあるのか「意味」をつかみとることはできない。「切断」と「接続」が「論理」をつくっているとは思えない。
私が感じるのは、先に書いたことの繰り返しになるが「名詞」と「動詞」が「学校文法」どおりではないということ。そこに板垣の「詩」がある。
「渦」は「名詞」だが、そこに「静止して存在」するのではない。「渦を巻く」というのでもない。「象られた渦」とは「渦」が何かを「象る」という形で再読されるべきなのである。「渦」が海の中にあるのではなく、「渦」そのものが「海」をつくっていく。生み出していく。「象っていく」。そういう動きがある。
それが「視野をひらく」。「渦」は「崩れる」。「渦」は「壊れる」。そういう「動き」そのものが「視野をひらく」と呼ばれるのだが、このとき「視野」とは「海」そのものである。「海がひらかれる」のだ。「ひらかれたもの」として「海」がある。「ひらく」という「動詞」でおわっているが、これは「ひらかれたもの」という「名詞」である。「海」のことである。
「名詞」と「動詞」が、世界の「未分化」の領域で交錯し、入れ代わり、「詩」として生み出されてくる。入れ換えながら再読するとき、ことばが強く激しく動き出す。
「渦/海」はさらに言いなおされる。書き直される。
「望郷」は「望郷」という「名詞」ではない。故郷を「思う」という「情」の「動き」そのものである。「渦」が「崩れ 壊れ」るは、「渦」が「鎮まる」ということである。「鎮める」と「鎮まる」は違うが、どちられ「海」という「名詞/状態」へと統一されていく。
さらに(ほんとうは逆の順序で書いた方がよかったのかもしれないが)、この「鎮める/鎮まる」という「動詞」のなかには「静脈」という「名詞」がある。「静脈」のなかの「静」が「鎮める/鎮まる」を呼び出している。「静脈」によって荒々しいものが切断され「鎮める/鎮まる」へと接続される。この変化を、板垣は「抜ける」という「動詞」で引き継ぐが、「抜ける」は「抜けつつある」という持続する運動ではなく、「ぬけて/至る(到達する)」、つまり「到達点」という「名詞」を含んでいる。
この「名詞/動詞」、「動詞/名詞」の交錯と融合を、どこまで再読し続けるか、そのことを板垣に問われている気がする。
どう読んだか。ほんとうは、もっともっと丁寧に書かなければいけないのだが、この板垣の詩集の文字は、私には小さすぎる。読むのがとてもつらい。
中途半端になってしまうが、「名詞/動詞」、「動詞/名詞」の「切断/接続」の綿密な動きの中に、板垣の強い力を感じたとだけ書いておくことにする。目の状態がいいときをみはからって、また読み直したい。