監督 クリスチャン・カリオン 出演 エミール・クストリッツァ、ギヨーム・カネ、アレクサンドラ・マリア・ララ、インゲボルガ・ダプコウナイテ、ウィレム・デフォー
エミール・クストリッツァは「アンダー・グラウンド」の監督である。調べてみたらいろいろな映画に出ているが、記憶に残っていない。意識してみるのは今回が初めてである。顔と体型がなかなかいい。余分なものがある。それが自ら選んで「スパイ」になるという役どころに奥行きを与えている。ショーン・コネリーやマット・デイモンとは違ったセックス・アピールがある。女を引きつける、というよりも、セックスのあとも関係を他人に気づかれない、関係を隠し通せるという「うさんくさい」ものを持っている。(映画のハイライト--ソ連の機密を盗み出すとき、愛人が部屋にはいってくる。それをあしらうシーンが、堂にいっている。あ、スパイとは、こういうことをするのか。これがスパイか、とうなってしまう。)そして、その「うさんくさい」風貌とは逆に、声が実に清潔である。まっすぐである。ためらいがない。この声で「嘘」を語られたら、ちょっと見抜けないだろうなあ。(演技で、そういう声を出しているのかもしれないが……。)
一方のギヨーム・カネは逆に「透明」である。「うさんくささ」がない。
これは、とてもおもしろい組み合わせである。「透明」なの人間は「うさんくささ」に押し切られる。「うさんくささ」に抵抗するものを「透明」なのものは持ち合わせていないのである。スパイに利用され、まきこまれていくことを、それを誰にも知られてはいけないのだが、妻に簡単に見破られてしまう。そして、そこでも「透明」な人間らしく、うろたえてしまう。
おもしろいのは、この「透明」で、繊細で、弱い男の存在によって、「うさんくさい」男の、内部の「透明さ」が照らしだされることである。ソニーのウォークマン、クィーンの音楽--知りもしないものを口にするとき、そこから家族(特に息子)に対する純粋な愛情があふれだす。ギヨーム・カネには、その純粋さは見えていないのだが、その見えていないことがスクリーンに映し出されると、観客には、ギヨーム・カネの見なかった「透明さ」があざやかな光のように伝わってくる。エミール・クストリッツァが内部に抱え込んでいる美しいものが瞬間的に姿を見せる。(これが最後に感動的な父と子の抱擁のシーンに結晶する。)
あ、まるで、エミール・クストリッツァという役者は、それ自体エミール・クストリッツァの映画みたいである。猥雑で、うさんくさくて、その内部に鮮烈な透明さをかかえている。しかも、それをまっすぐに投げかけてくる。猥雑をまといながら、それを動かしているのは純情であることを教えてくれる。
不思議がひとつ残る。この映画の主人公の、危険な行為、危険に満ちたスパイ行為を、たったひとりで実行するときの、その「孤高」の精神がどこから生まれてきたのか、よくわからない。しかし、それはきっと誰にもわからないものなのかもしれない。人間の「本質」の問題なのかもしれない。その、最後にふっと浮かんでくる不思議を、エミール・クストリッツァは演じている瞬間は感じさせない。スクリーンにいる間は感じさせない。映画が終わったあと、ふと、思う不思議さなのだ。
これはすごいことだなあ、と思う。
私の感じたのは映画を見ての感想だけれど、実際に「フェアウェル」に会った人たちは、その不思議をどんなふうに理解したのだろう。世界を作り替えてしまった男の不思議を、いったいどんなふうに理解したのだろう。
まあ、これは映画を超えた問題だね。役者を超えた問題である。
しかし、びっくりだなあ。アメリカの「スターウォーズ計画」ははったりだったのか。はったりがペレストロイカを推進させ、ベルリンの壁を崩壊させる引金だったのか。レーガン大統領、そのハリウッド映画の見せ方などには笑えるが、クィーンやウォークマンなどの「時代」を描く姿勢がていねいなだけに、「国家」のはったり(アメリカのはったり)が生々しく浮かび上がる。そうか、「歴史」はそんなふうにして動いたのか、とあらためて気づかされた。そういえば、「スターウォーズ計画」はどうなったのかなあ、そうだったのか、と納得してしまった。(歴史や国際政治に詳しい人なら知っていることなのかもしれないけれど。)
--現代政治、国際政治の「お勉強」にもなる映画でした。はい。
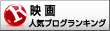
エミール・クストリッツァは「アンダー・グラウンド」の監督である。調べてみたらいろいろな映画に出ているが、記憶に残っていない。意識してみるのは今回が初めてである。顔と体型がなかなかいい。余分なものがある。それが自ら選んで「スパイ」になるという役どころに奥行きを与えている。ショーン・コネリーやマット・デイモンとは違ったセックス・アピールがある。女を引きつける、というよりも、セックスのあとも関係を他人に気づかれない、関係を隠し通せるという「うさんくさい」ものを持っている。(映画のハイライト--ソ連の機密を盗み出すとき、愛人が部屋にはいってくる。それをあしらうシーンが、堂にいっている。あ、スパイとは、こういうことをするのか。これがスパイか、とうなってしまう。)そして、その「うさんくさい」風貌とは逆に、声が実に清潔である。まっすぐである。ためらいがない。この声で「嘘」を語られたら、ちょっと見抜けないだろうなあ。(演技で、そういう声を出しているのかもしれないが……。)
一方のギヨーム・カネは逆に「透明」である。「うさんくささ」がない。
これは、とてもおもしろい組み合わせである。「透明」なの人間は「うさんくささ」に押し切られる。「うさんくささ」に抵抗するものを「透明」なのものは持ち合わせていないのである。スパイに利用され、まきこまれていくことを、それを誰にも知られてはいけないのだが、妻に簡単に見破られてしまう。そして、そこでも「透明」な人間らしく、うろたえてしまう。
おもしろいのは、この「透明」で、繊細で、弱い男の存在によって、「うさんくさい」男の、内部の「透明さ」が照らしだされることである。ソニーのウォークマン、クィーンの音楽--知りもしないものを口にするとき、そこから家族(特に息子)に対する純粋な愛情があふれだす。ギヨーム・カネには、その純粋さは見えていないのだが、その見えていないことがスクリーンに映し出されると、観客には、ギヨーム・カネの見なかった「透明さ」があざやかな光のように伝わってくる。エミール・クストリッツァが内部に抱え込んでいる美しいものが瞬間的に姿を見せる。(これが最後に感動的な父と子の抱擁のシーンに結晶する。)
あ、まるで、エミール・クストリッツァという役者は、それ自体エミール・クストリッツァの映画みたいである。猥雑で、うさんくさくて、その内部に鮮烈な透明さをかかえている。しかも、それをまっすぐに投げかけてくる。猥雑をまといながら、それを動かしているのは純情であることを教えてくれる。
不思議がひとつ残る。この映画の主人公の、危険な行為、危険に満ちたスパイ行為を、たったひとりで実行するときの、その「孤高」の精神がどこから生まれてきたのか、よくわからない。しかし、それはきっと誰にもわからないものなのかもしれない。人間の「本質」の問題なのかもしれない。その、最後にふっと浮かんでくる不思議を、エミール・クストリッツァは演じている瞬間は感じさせない。スクリーンにいる間は感じさせない。映画が終わったあと、ふと、思う不思議さなのだ。
これはすごいことだなあ、と思う。
私の感じたのは映画を見ての感想だけれど、実際に「フェアウェル」に会った人たちは、その不思議をどんなふうに理解したのだろう。世界を作り替えてしまった男の不思議を、いったいどんなふうに理解したのだろう。
まあ、これは映画を超えた問題だね。役者を超えた問題である。
しかし、びっくりだなあ。アメリカの「スターウォーズ計画」ははったりだったのか。はったりがペレストロイカを推進させ、ベルリンの壁を崩壊させる引金だったのか。レーガン大統領、そのハリウッド映画の見せ方などには笑えるが、クィーンやウォークマンなどの「時代」を描く姿勢がていねいなだけに、「国家」のはったり(アメリカのはったり)が生々しく浮かび上がる。そうか、「歴史」はそんなふうにして動いたのか、とあらためて気づかされた。そういえば、「スターウォーズ計画」はどうなったのかなあ、そうだったのか、と納得してしまった。(歴史や国際政治に詳しい人なら知っていることなのかもしれないけれど。)
--現代政治、国際政治の「お勉強」にもなる映画でした。はい。
 | アンダーグラウンド [DVD]パイオニアLDCこのアイテムの詳細を見る |



















