監督 三池崇史 出演 役所広司、山田孝之、伊勢谷友介、松方弘樹、松本幸四郎、稲垣吾郎、市村正親
この映画がおもしろいのは、ストーリーがわかっていること。観客に、ではなく、登場人物に、わかっていること。
役所広司をはじめとする13人は稲垣吾郎を殺すことで彼らのストーリーが完結することを知っている。完結させるために集まった。一方、市村正親の方は13人がもくろんでいるストーリーを知っていて、それをどう突き破るかを考える。稲垣吾郎を殺させない、というのが市村正親のストーリーであり、そのストーリーを役所広司も知っている。矛盾するストーリーがぶつかり、どちらかのストーリーにならないといけない、ということは役所広司も市村正親も知っている。
能天気なことにというべきなのか、「主役」の稲垣吾郎だけがストーリーを知らない。役所広司が自分を殺そうとしていることも、市村正親がそれを阻止しようとしていることも知らない。ただ、市村正親が自分を守るために存在しているということだけを知っている。
だからこそ、実際の死闘がはじまったとき、稲垣吾郎は思わず「本音」を言ってしまう。「おもしろいのう。いままで生きてきた中でいちばん楽しい」。稲垣吾郎は「観客」のようにストーリーを見ている。役所広司、市村正親らの死闘を映画を見るように、ストーリーの展開の一部を見るように見てしまう。
観客とは、まあ、そういうものなのである。
で、その観客(稲垣吾郎)を、どうやって「現実」へ引きこむか--ということに重なるようにして、観客(私を含む映画館に来ているほんとうの「観客」)をスクリーンに引きこむために、脚本家、監督、出演者はあれこれと工夫を凝らす。
今回の場合、成功の第一は脚本にある。最初に書いたように、役所広司も市村正親もストーリーを知っている。いわば「ネタバレ」の映画である。登場人物がストーリーを最初から知っているのだから、当然、それを見るほんものの観客もストーリーを知っている。次に何が起きるか、ではなく、「どんなふうに」それが起きるかだけを楽しめる。ストーリーはあるのだけれど、ストーリーは関係ないのだ。映像だけが、役者の顔だけが、この映画の醍醐味なのだ。
最後の50分(と言われているが、測ったわけではないので、知らない)のアクションについては多くのひとが語るだろうから、役者の「顔」について書いておこう。
役所広司の顔にはどこかぬけたところがある。騙されていても、それを信じ込むような人間性が残っている。「さゆり」の、おんなに言い寄られたとき、脚本を読んでいるから振られるとわかっているはずなのに、まるで騙されていることに気づかず、その気になる役所広司の顔は傑作である。あの顔が、役所の持ち味である、と私は思うのだが、その、一種、ふわーっとした感じが、あいまいな「ふところ」を、「広い」ふところにかえる。13人という集団を「ふところ」によってまとめるという感じにする。
なかなかやってこない稲垣吾郎、市村正親の行列に、待ち伏せというストーリーに疑心暗鬼になる仲間に、「あせるな」と「待つ」ことを諭す。そのたとえに「釣り」などを持ち出し、気持ちを「戦」からそらす。集中ではなく、ときに意識をほどく--その、ほどかれた意識のひろがりを、「広いふところ」「度量」というのだが……。
一方、市村正親は、広がりを拒絶する顔である。集中する。稲垣吾郎に集中する。あらゆることを稲垣吾郎に集中させる。行列が分断され、人数が減ってしまえば、あらたにひとがそろうまで待って動く。常に「集中」の密度を一定に高める。それは一種の「狭量」なのだが、それが市村正親の目と、顔の小ささ(役所広司に比べると顔の大きさが半分に感じられてしまう)に凝縮する。マンガで書くと、きっと市村正親の顔の大きさ(面積)は役所広司の半分以下である。
もうひとり、稲垣吾郎は、「おれはスマップ、本式の役者じゃないからね」と別次元の顔をしている。この別次元の顔が、なぜかストーリーにぴったりあてはまる。役所広司のやっていることも、市村正親のやっていることも関係ない。おれはおれの好きなことをやる。まさに、暴君だねえ。史上最大の暴君だねえ。市村正親に「迷わずに愚かな道を選べ」なんていうところはぞくぞくするねえ。市村正親の顔と噛み合わない--そこが、この映画を活性化させている。稲垣吾郎だけが白い服というのも、ひとりだけ特別に浮かび上がって効果的だ。単に身分をあらわしている以上の効果がある。白に、血の赤も似合うからねえ。
役所広司の「度量」の顔が、その「度量」のなかに13人を抱き込むのに対し、市村正親の「狭量」の顔が、「狭量」を焦点として 300人を集結しようとするが、たずなを絞りきれない。そればかりか「背後」に隠れていなければならないはずの稲垣吾郎は勝手に「狭い」背中からはみだしていってしまう。
結局、役所広司は13人で戦っているのに、市村正親はひとりで戦っている。こりゃあ、負けるね。
顔についてばかり書いたので、ちょっと脚本にも。
伏線でいちばん気に入っているのは、役所広司たちが道場で訓練をするところ。武士道精神できれいに戦うのではない。「そこで足を払え」などと、勝つために何をすればいいかを身につける。役所広司はそのときはそれを見ているだけだが、これがクライマックスでちゃんと生かされている。役所広司は市村正親に「道場でなら、おれとおまえは五分だが、ここでは違う」と言うやいなや、足で泥をはね上げ、目つぶしをくらわせて切りかかる。こういうのは、好きだなあ。いきなり泥をはねあげ、目つぶしをくらわせると「やぼ」だけれど、伏線があると、それが「肉体」になる。「思想」になる。「生きる」ために何をすべきか、いちばん大切な「いのち」を守るために有効なものこそ「思想」なのだという哲学に変わる。そして、これがまたこの映画のというか役所広司が具現化する全体のストーリーを貫く「思想」でもある。いちばん大切なふつうの人々のいのちを守るためにすること、それは武士道(市村正親が具現化するもの)よりも「有効」である。
なんて、書いてしまうと、映画がつまらなくなるから、ここの部分は忘れて映画を見てください。役所広司、市村正親、稲垣吾郎の顔の違いを楽しんでください。
*
下にリンクしている「十三人の刺客」は「原作」。
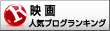
この映画がおもしろいのは、ストーリーがわかっていること。観客に、ではなく、登場人物に、わかっていること。
役所広司をはじめとする13人は稲垣吾郎を殺すことで彼らのストーリーが完結することを知っている。完結させるために集まった。一方、市村正親の方は13人がもくろんでいるストーリーを知っていて、それをどう突き破るかを考える。稲垣吾郎を殺させない、というのが市村正親のストーリーであり、そのストーリーを役所広司も知っている。矛盾するストーリーがぶつかり、どちらかのストーリーにならないといけない、ということは役所広司も市村正親も知っている。
能天気なことにというべきなのか、「主役」の稲垣吾郎だけがストーリーを知らない。役所広司が自分を殺そうとしていることも、市村正親がそれを阻止しようとしていることも知らない。ただ、市村正親が自分を守るために存在しているということだけを知っている。
だからこそ、実際の死闘がはじまったとき、稲垣吾郎は思わず「本音」を言ってしまう。「おもしろいのう。いままで生きてきた中でいちばん楽しい」。稲垣吾郎は「観客」のようにストーリーを見ている。役所広司、市村正親らの死闘を映画を見るように、ストーリーの展開の一部を見るように見てしまう。
観客とは、まあ、そういうものなのである。
で、その観客(稲垣吾郎)を、どうやって「現実」へ引きこむか--ということに重なるようにして、観客(私を含む映画館に来ているほんとうの「観客」)をスクリーンに引きこむために、脚本家、監督、出演者はあれこれと工夫を凝らす。
今回の場合、成功の第一は脚本にある。最初に書いたように、役所広司も市村正親もストーリーを知っている。いわば「ネタバレ」の映画である。登場人物がストーリーを最初から知っているのだから、当然、それを見るほんものの観客もストーリーを知っている。次に何が起きるか、ではなく、「どんなふうに」それが起きるかだけを楽しめる。ストーリーはあるのだけれど、ストーリーは関係ないのだ。映像だけが、役者の顔だけが、この映画の醍醐味なのだ。
最後の50分(と言われているが、測ったわけではないので、知らない)のアクションについては多くのひとが語るだろうから、役者の「顔」について書いておこう。
役所広司の顔にはどこかぬけたところがある。騙されていても、それを信じ込むような人間性が残っている。「さゆり」の、おんなに言い寄られたとき、脚本を読んでいるから振られるとわかっているはずなのに、まるで騙されていることに気づかず、その気になる役所広司の顔は傑作である。あの顔が、役所の持ち味である、と私は思うのだが、その、一種、ふわーっとした感じが、あいまいな「ふところ」を、「広い」ふところにかえる。13人という集団を「ふところ」によってまとめるという感じにする。
なかなかやってこない稲垣吾郎、市村正親の行列に、待ち伏せというストーリーに疑心暗鬼になる仲間に、「あせるな」と「待つ」ことを諭す。そのたとえに「釣り」などを持ち出し、気持ちを「戦」からそらす。集中ではなく、ときに意識をほどく--その、ほどかれた意識のひろがりを、「広いふところ」「度量」というのだが……。
一方、市村正親は、広がりを拒絶する顔である。集中する。稲垣吾郎に集中する。あらゆることを稲垣吾郎に集中させる。行列が分断され、人数が減ってしまえば、あらたにひとがそろうまで待って動く。常に「集中」の密度を一定に高める。それは一種の「狭量」なのだが、それが市村正親の目と、顔の小ささ(役所広司に比べると顔の大きさが半分に感じられてしまう)に凝縮する。マンガで書くと、きっと市村正親の顔の大きさ(面積)は役所広司の半分以下である。
もうひとり、稲垣吾郎は、「おれはスマップ、本式の役者じゃないからね」と別次元の顔をしている。この別次元の顔が、なぜかストーリーにぴったりあてはまる。役所広司のやっていることも、市村正親のやっていることも関係ない。おれはおれの好きなことをやる。まさに、暴君だねえ。史上最大の暴君だねえ。市村正親に「迷わずに愚かな道を選べ」なんていうところはぞくぞくするねえ。市村正親の顔と噛み合わない--そこが、この映画を活性化させている。稲垣吾郎だけが白い服というのも、ひとりだけ特別に浮かび上がって効果的だ。単に身分をあらわしている以上の効果がある。白に、血の赤も似合うからねえ。
役所広司の「度量」の顔が、その「度量」のなかに13人を抱き込むのに対し、市村正親の「狭量」の顔が、「狭量」を焦点として 300人を集結しようとするが、たずなを絞りきれない。そればかりか「背後」に隠れていなければならないはずの稲垣吾郎は勝手に「狭い」背中からはみだしていってしまう。
結局、役所広司は13人で戦っているのに、市村正親はひとりで戦っている。こりゃあ、負けるね。
顔についてばかり書いたので、ちょっと脚本にも。
伏線でいちばん気に入っているのは、役所広司たちが道場で訓練をするところ。武士道精神できれいに戦うのではない。「そこで足を払え」などと、勝つために何をすればいいかを身につける。役所広司はそのときはそれを見ているだけだが、これがクライマックスでちゃんと生かされている。役所広司は市村正親に「道場でなら、おれとおまえは五分だが、ここでは違う」と言うやいなや、足で泥をはね上げ、目つぶしをくらわせて切りかかる。こういうのは、好きだなあ。いきなり泥をはねあげ、目つぶしをくらわせると「やぼ」だけれど、伏線があると、それが「肉体」になる。「思想」になる。「生きる」ために何をすべきか、いちばん大切な「いのち」を守るために有効なものこそ「思想」なのだという哲学に変わる。そして、これがまたこの映画のというか役所広司が具現化する全体のストーリーを貫く「思想」でもある。いちばん大切なふつうの人々のいのちを守るためにすること、それは武士道(市村正親が具現化するもの)よりも「有効」である。
なんて、書いてしまうと、映画がつまらなくなるから、ここの部分は忘れて映画を見てください。役所広司、市村正親、稲垣吾郎の顔の違いを楽しんでください。
*
下にリンクしている「十三人の刺客」は「原作」。
 | 十三人の刺客 [DVD]TOEI COMPANY,LTD.(TOE)(D)このアイテムの詳細を見る |

















