監督 フランク・ダラボン 出演 ティム・ロビンス、モーガン・フリーマン、ウィリアム・サドラー
このシーンはいいなあ、大好きだなあと言わずにはいられないシーンがある。ティム・ロビンスが「フィガロの結婚」のレコードを見つける。そばにプレーヤーがある。我慢しきれずに、レコードをかける。それからマイクをとおして刑務所中に放送する。
オペラを見たことのない人ばかり(たぶん)の刑務所。突然流れてくる歌声。みんな耳を澄ましている。それが何かわからない。わからないけれど、モーガン・フリーマンは、それがみんなのこころに届いているのを実感する--というようなナレーションが重なる。このシーンが、ほんとうに美しい。
「フィガロの結婚」をなぜかけたのか--そのために独房に入れられ、やっと独房からティム・ロビンスがでてきたとき、モーガン・フリーマンがたずねる。ティム・ロビンスは、「誰の心にも、他人が触れることのできないもの(不可侵のもの)がある。希望がある。それに触れるのが音楽である」というようなことを言う。
これは、この映画のテーマでもあるのだけれど、私はティム・ロビンスが語ったこととは別に、希望について考えた。
世界にはわからないものがある。知らないことがある。そういうものに人間は触れることができる。そして、そのわからないもの、知らないもの--それを何だろうと思うこころこそ「希望」だと思う。
わからない何か、知らない何か--それに触れ、それについていくこと(それに導かれるままに行動すること)。その結果、何が起きるかわからない。自分がどうなってしまうかわからない。それでも、どうなってもかまわないと決意して、知らないものについていくこと。それが、「希望」だ。
ティム・ロビンスは脱獄を計画する。その計画が実現するかどうかは、わからない。そんなことをしたことがない。そういうことがあることは知っているが、ほんとうは知らない。体験したことがない。わからないけれど、知らないけれど、やってみる。
そのことをすれば、自分が自分でいられなくなる。
この映画では、具体的には、ティム・ロビンスは脱獄したあとは、それまでの「名前」「身分」をすっかり捨ててしまって「別人」という形で、「自分が自分でいられなくなる」という状態を表現している。
「無実」が証明され、判決が取り消されない限りほんとうの解決ではない、という覚めた見方もあるかもしれないけれど、まあ、そんなことはどうでもいい。
わからないもの、知らないものに身をまかせ、自分が自分でなくなる--そのときの「自由」を「希望」というのだ、とつげるメルヘンなのである。この映画は。
ストーリーそのものが、そういうふうに展開していくけれど、私は、そのストーリー全体よりも、「フィガロの結婚」のシーンが好きなのだ。あのシーンがすべてを象徴している。刑務所の塀を越え、空の高みへ登り、どこまでも広がっていく音楽--その音に耳をすますとき、「いま」「ここ」にないもの、そしてそれまでどこにもなかったものが、たしかにこころに触れてくるのである。
(「午前十時の映画祭」33本目)
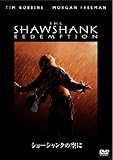 | ショーシャンクの空に [DVD]ワーナー・ホーム・ビデオこのアイテムの詳細を見る |


















