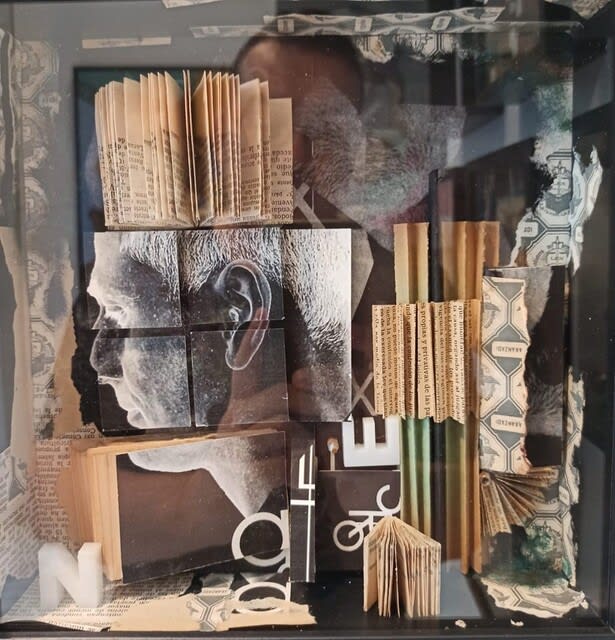川邉由紀恵「草の根」(「どぅるかまら」33、2023年01月10日発行)
「どぅるかまら」には、田中澄子、齋藤恵子といった、とても行儀のいい詩があって、そこから違うところで感想を書いてみたくなる。
川邉由紀恵「草の根」が「行儀が悪い」というのではないけれど、
秋のゆうぐれのやよい坂の下の空き地にはとなりにある
銭湯ののこり湯がひよひよと低みのほうにしみでていて
その粘土質のうえにはひめ芝やかたばみスギナぜにごけ
という具合に一行の長さをそろえてことばが動いていく。この形式(?)へのこだわりは、行儀がいいのかもしれないが、その行儀のよさを装うために、ひらがなと漢字がテキトウ(?)につかいわけられ、「ひよひよ」というような、わかったようなわからないことばがさしはさまれ、さらには「その」という指示詞があったかと思うと、かたばみスギナぜにごけカタカナを読点がわりにつかっているところもある。
ぬこうとしてみると草はすると抜けそうでうす桃いろの
しめったほそい根のようなものがでてきそうなのである
けれどもたどりくだっていくうちにその根はながくなり
さらに、あ、珍しく行がきっちり終わってると思わせて、接続詞でつながる部分もある。書き写しているうちに、変なものに巻き込まれてしまう。
ことばが「草の根」になって、ことばの「土」のなかを伸びていく。
これは、それを引っ張りだして書いたものなのか、それとももぐりこんで書いたものなのか。
まあ、どうでもいい。
どうでもいいことを、よくもまあ、飽きずに書いたね、と思う。もちろん、この詩から、「行儀のいい」批評を書いてみることもできると思うが、きょうは、そういう気持ちになれない。ただ、この「行儀の悪い」、つまり「意味」なんてどうでもいい。「意味」に要約してもなんの意味もないことを書いていることばの、そばにいるのがなんとなく楽しい。
私は意地悪な人間だから、この詩をテキストにして、詩の講座で、「銭湯ののこり湯がひよひよと低みのほうにしみでていて、の『ひよひよ』を自分のことばでいいなおすと、どうなる?」とか「ぬこうとしてみると草はすると抜けそうでうす桃いろの、の『ぬこうとしてみる』と『抜けそうで』の、ひらがなと漢字のつかいわけはどうしてだと思う?」という質問をしてみるのだ。
きっと、だれも、明確に答えられない。
私は、この「わかったようで、わからない」(逆に言うと、書いてあることが一言もわからないとは言えない妙な感覚)のなかにこそ、詩があると感じている。
それは何と言えばいいのか「自己」と「非自己」の出会いであり、自己が自己であるか問われる瞬間なのだと思う。川邉のことばと、自分のことばを区別する(あるいは識別すると言えばいいのか)、何か「基準」や「原則」のようなものはあるのか。実際に川邉と向き合っているとして、そのとき、「肉体」は離れているから別々の人間(別々に動くことができるから、別の人間)ということができる。このとき「空間」(距離)というものが、変な言い方だが、ひとつの「識別の基準」になる。
それは、「ことば」の場合はどうなのか。
書くとめんどうになるので書かないが。
「書かない」といいながら、思いっきり飛躍というか、脱線してしまって書くと。
私は、その「ことば」の問題を考えているうちに、「肉体」の「自己」「非自己」も、識別はあやしいものだという「結論」に達してしまうのだ。
もし、私が川邉と向き合っているとしたら、それは私の意識が川邉をそこに存在させている。何らかの必然があって、そこに川邉という別個の肉体が存在しているように「認識」している(ことばにしている)だけなのではないか。
この世界は、ほんとうはごちゃごちゃの「ことば」が入り乱れているだけのものであり、その「ごちゃごちゃ」に耐えるだけの力のない意識(精神)が、「行儀のいい」形にととのえることで、わかったふりをしているのではないのか。
ここには私とは別の人間、川邉がいて、私とは全く関係のないことを考えている、と世界を整理すると、合理的でとてもすっきりする。しかし、この合理性はまったくのでたらめかもしれない。整理してしまえば私の脳は安心して、手抜きする。脳は、いつでも手抜きして、自分の都合のいいように考えてしまうものなのだ。
そうなると……。
世界が存在していると、私の脳は錯覚しているだけで、世界は存在しない。「ことば」が及ぶ範囲を「世界」と仮定して、自分が生きているつもりになっているだけ、というようなことを考えてしまうのである。
何が書いてあるのか、他人(読んだひと)には、わからないだろうなあ。当然だよなあ。私はわかって書いているわけではなく、わからないから、書いている。わかっているなら、書く必要はない。わかっているなら、わからなくなるために書く。
これが感想か、これが批評か。たぶん、ね。こういうことばを引き出す力が川邉の詩にはある、ということ。
**********************************************************************
★「詩はどこにあるか」オンライン講座★
メール、skypeを使っての「現代詩オンライン講座」です。
メール(宛て先=yachisyuso@gmail.com)で作品を送ってください。
詩への感想、推敲のヒントをメール、ネット会議でお伝えします。
★メール講座★
随時受け付け。
週1篇、月4篇以内。
料金は1篇(40字×20行以内、1000円)
(20行を超える場合は、40行まで2000円、60行まで3000円、20行ごとに1000円追加)
1週間以内に、講評を返信します。
講評後の、質問などのやりとりは、1回につき500円。
★ネット会議講座(skypeかgooglemeet使用)★
随時受け付け。ただし、予約制。
週1篇40行以内、月4篇以内。
1回30分、1000円。
メール送信の際、対話希望日、希望時間をお書きください。折り返し、対話可能日をお知らせします。
費用は月末に 1か月分を指定口座(返信の際、お知らせします)に振り込んでください。
作品は、A判サイズのワード文書でお送りください。
少なくとも月1篇は送信してください。
お申し込み・問い合わせは、
yachisyuso@gmail.com
また朝日カルチャーセンター福岡でも、講座を開いています。
毎月第1、第3月曜日13時-14時30分。
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1
電話 092-431-7751 / FAX 092-412-8571
*
オンデマンドで以下の本を発売中です。
(1)詩集『誤読』100ページ。1500円(送料別)
嵯峨信之の詩集『時刻表』を批評するという形式で詩を書いています。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072512
(2)評論『中井久夫訳「カヴァフィス全詩集」を読む』396ページ。2500円(送料別)
読売文学賞(翻訳)受賞の中井の訳の魅力を、全編にわたって紹介。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073009
(3)評論『高橋睦郎「つい昨日のこと」を読む』314ページ。2500円(送料別)
2018年の話題の詩集の全編を批評しています。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168074804
(4)評論『ことばと沈黙、沈黙と音楽』190ページ。2000円(送料別)
『聴くと聞こえる』についての批評をまとめたものです。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073455
(5)評論『天皇の悲鳴』72ページ。1000円(送料別)
2016年の「象徴としての務め」メッセージにこめられた天皇の真意と、安倍政権の攻防を描く。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072977
問い合わせ先 yachisyuso@gmail.com