監督・脚本 ジャン=ピエール・ジュネ 出演 ダニー・ブーン、ドミニク・ピノン、アンドレ・デュソリエ、ニコラ・マリエ、ジャン=ピエール・マリエル、ヨランド・モロー
ジャン=ピエール・ジュネの映画を最初に見たのは「デリカテッセン」(★★★★★)である。そのときからジュネの映画の色調は変わっていない。茶色く錆びている。古びている。しかし、美しい。考えてみれば、古びるということは存在しないということではない。逆である。古びるということは、その「もの」に古びる力があるということ、古びても「もの」は存在しつづけることができるということである。その古びたもののなかにある力をどうやって引き出すことができるか。ジュネはそのことを考えつづけているように思う。
主人公は流れ弾を頭の中に抱え込んでいる。彼らの仲間はホームレスである。廃品を活用して「城」を築き、生活を維持している。ストーリーは主人公の頭の中の「流れ弾」をつくった武器会社と、主人公の父親のいのちを奪った地雷製造の武器会社への復讐という形をとって動いていくが、そういう「平和主義」のメッセージよりも、古びたもののいのちの輝きの方がはるかにおもしろい。
「デリカテッセン」でも登場したノコギリのバイオリンというのは、この映画にも登場する。それは「古びたもの」とは少し違うが、そこにあるものをそれ自体としてではなく、別の可能性として活用するという意味では、つかわれなくなったいのち(古いいのち)の活用である。
彼らの生活の中では、あらゆるものが「廃品」であるが、そのバイオリンのノコギリと同じように、あらゆるものが新しい。さまざまなものを組み合わせてつくったおもちゃだけではなく、蜂のつまった壜という「武器」さえ、古くて新しい。大砲のつつのなかに人間が入って弾丸として飛んでゆくという方法さえ、古くて新しい。そんなものをだれもつかわないということは、そういうものにたいする「防御」をだれもしないということであり、その盲点をついて攻撃できる「新しい武器」なのだ。
こういう映画は、ストーリーは脇役である。主役は、ストーリーとは関係ない小道具である。
そうした小道具で私がいちばん気に入ったのは、最後に出てくる洋服のダンスである。主人公たちのホームレスには、当然男がいて、女がいる。そこに「恋愛」が入り込む。つまりカップルができる。でも、あぶれるひとも当然出てくる。発明家(?)のおじいさんは、あぶれた男だ。女がいない。ペアになれない。そこでおじいさんは、ハンガーにブラウスとスカートをまとわせ、ダンスをさせる。機械仕掛けの踊る洋服である。これが実に楽しい。生きている人間以上にいきいきと動く。
このおじいさんの発明には、奇妙なドラム叩きのおもちゃもある。廃品が金属の太鼓をかたかたと叩くのである。ノコギリのバイオリンもそうだけれど、ジュネはノイズを音楽として楽しむ感覚を持っている。(フランス人は、こういう感覚が強いのか、ジャンク・タチも現実に存在するノイズを音楽として巧みにつかっている。ジュネは年齢的に言うと、タチの後継者ということになるかもしれない。)
もちろんストーリーとからんでくる小道具もある。パイプがそれである。
パイプは、ジュネの大好きなもののひとつのようである。もしかすると、パイプがジュネの「思想」(肉体)かもしれない。パイプを掃除機につないでコレクションを盗む。また、パイプをつまらせて爆発を起こさせる、という重要な役割をこの映画では果たしている。
パイプは空洞だが、その空洞は何かと何かをつなぐ。その中を「いのち」が動いていく。人間の体は「血管」というパイプのなかを血が流れ、いのちを守っているし、胃腸というパイプには食べ物が通って、出て行く。空洞を何かが通ることで、そのパイプを抱え込んでいるものは生きている、ということかもしれない。
意識的なパイプのほかに、無意識的なパイプというか、パイプの変形も映画には登場する。「デリカテッセン」では建物の内部にはりめぐらされたパイプが「音楽」の通路として巧みにつかわれていた。この映画にも、その流れが残っている。この映画では、パイプは煙突という形で登場している。煙突からマイクを進入させ、盗聴する。
これは、どんなものにも何かと何かをつなぐものがありうる、という思想を具現化しているかもしれない。
でも、そんな面倒なことはジュネはいいたくないのだろうなあ。
煙突のシーンで忘れられないのは、ヘリウムガス(だったっけ?)で遊ぶシーンである。パイプで吸引できなかったコレクションは風船に結びつけて窓からとばして盗む。その風船に入っているガス。それを吸って声を出すと、声が変わる。その変わった声を煙突をとおして、下にいる仲間に仕事がうまくいったと伝える。遊びで煙突パイプを「音楽」の通路にしてしまうのだ。
いいなあ、こういう徹底した思想は。
*
「デリカテッセン」「エイリアン」(3だったっけ?)「ミックマック」とつづく色の統一も、私はとても気に入っている。錆びた色だが、その色はこれから崩れていく色ではない。むしろ時間とともにさらに強くなっていく色だ。色がものそのものにかわっていくような、強い印象がある。
こういうこだわりは「趣味」と呼ばれるものかもしれない。
「趣味」というと軽い感じがするが、たぶん、それは「ことば」が正確につかわれてこなかったからなのだと思う。明確な「趣味」には不思議な力がある。ひとのなかにある「パイプ」が「もの」にまでつながっている。ひとの「いのち」が「もの」に流れている。そう感じさせるものが「趣味」ということばに値するものなのだ。
「趣味」を持っている監督というのは、おもしろい。
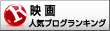
ジャン=ピエール・ジュネの映画を最初に見たのは「デリカテッセン」(★★★★★)である。そのときからジュネの映画の色調は変わっていない。茶色く錆びている。古びている。しかし、美しい。考えてみれば、古びるということは存在しないということではない。逆である。古びるということは、その「もの」に古びる力があるということ、古びても「もの」は存在しつづけることができるということである。その古びたもののなかにある力をどうやって引き出すことができるか。ジュネはそのことを考えつづけているように思う。
主人公は流れ弾を頭の中に抱え込んでいる。彼らの仲間はホームレスである。廃品を活用して「城」を築き、生活を維持している。ストーリーは主人公の頭の中の「流れ弾」をつくった武器会社と、主人公の父親のいのちを奪った地雷製造の武器会社への復讐という形をとって動いていくが、そういう「平和主義」のメッセージよりも、古びたもののいのちの輝きの方がはるかにおもしろい。
「デリカテッセン」でも登場したノコギリのバイオリンというのは、この映画にも登場する。それは「古びたもの」とは少し違うが、そこにあるものをそれ自体としてではなく、別の可能性として活用するという意味では、つかわれなくなったいのち(古いいのち)の活用である。
彼らの生活の中では、あらゆるものが「廃品」であるが、そのバイオリンのノコギリと同じように、あらゆるものが新しい。さまざまなものを組み合わせてつくったおもちゃだけではなく、蜂のつまった壜という「武器」さえ、古くて新しい。大砲のつつのなかに人間が入って弾丸として飛んでゆくという方法さえ、古くて新しい。そんなものをだれもつかわないということは、そういうものにたいする「防御」をだれもしないということであり、その盲点をついて攻撃できる「新しい武器」なのだ。
こういう映画は、ストーリーは脇役である。主役は、ストーリーとは関係ない小道具である。
そうした小道具で私がいちばん気に入ったのは、最後に出てくる洋服のダンスである。主人公たちのホームレスには、当然男がいて、女がいる。そこに「恋愛」が入り込む。つまりカップルができる。でも、あぶれるひとも当然出てくる。発明家(?)のおじいさんは、あぶれた男だ。女がいない。ペアになれない。そこでおじいさんは、ハンガーにブラウスとスカートをまとわせ、ダンスをさせる。機械仕掛けの踊る洋服である。これが実に楽しい。生きている人間以上にいきいきと動く。
このおじいさんの発明には、奇妙なドラム叩きのおもちゃもある。廃品が金属の太鼓をかたかたと叩くのである。ノコギリのバイオリンもそうだけれど、ジュネはノイズを音楽として楽しむ感覚を持っている。(フランス人は、こういう感覚が強いのか、ジャンク・タチも現実に存在するノイズを音楽として巧みにつかっている。ジュネは年齢的に言うと、タチの後継者ということになるかもしれない。)
もちろんストーリーとからんでくる小道具もある。パイプがそれである。
パイプは、ジュネの大好きなもののひとつのようである。もしかすると、パイプがジュネの「思想」(肉体)かもしれない。パイプを掃除機につないでコレクションを盗む。また、パイプをつまらせて爆発を起こさせる、という重要な役割をこの映画では果たしている。
パイプは空洞だが、その空洞は何かと何かをつなぐ。その中を「いのち」が動いていく。人間の体は「血管」というパイプのなかを血が流れ、いのちを守っているし、胃腸というパイプには食べ物が通って、出て行く。空洞を何かが通ることで、そのパイプを抱え込んでいるものは生きている、ということかもしれない。
意識的なパイプのほかに、無意識的なパイプというか、パイプの変形も映画には登場する。「デリカテッセン」では建物の内部にはりめぐらされたパイプが「音楽」の通路として巧みにつかわれていた。この映画にも、その流れが残っている。この映画では、パイプは煙突という形で登場している。煙突からマイクを進入させ、盗聴する。
これは、どんなものにも何かと何かをつなぐものがありうる、という思想を具現化しているかもしれない。
でも、そんな面倒なことはジュネはいいたくないのだろうなあ。
煙突のシーンで忘れられないのは、ヘリウムガス(だったっけ?)で遊ぶシーンである。パイプで吸引できなかったコレクションは風船に結びつけて窓からとばして盗む。その風船に入っているガス。それを吸って声を出すと、声が変わる。その変わった声を煙突をとおして、下にいる仲間に仕事がうまくいったと伝える。遊びで煙突パイプを「音楽」の通路にしてしまうのだ。
いいなあ、こういう徹底した思想は。
*
「デリカテッセン」「エイリアン」(3だったっけ?)「ミックマック」とつづく色の統一も、私はとても気に入っている。錆びた色だが、その色はこれから崩れていく色ではない。むしろ時間とともにさらに強くなっていく色だ。色がものそのものにかわっていくような、強い印象がある。
こういうこだわりは「趣味」と呼ばれるものかもしれない。
「趣味」というと軽い感じがするが、たぶん、それは「ことば」が正確につかわれてこなかったからなのだと思う。明確な「趣味」には不思議な力がある。ひとのなかにある「パイプ」が「もの」にまでつながっている。ひとの「いのち」が「もの」に流れている。そう感じさせるものが「趣味」ということばに値するものなのだ。
「趣味」を持っている監督というのは、おもしろい。
 | デリカテッセン 【ベスト・ライブラリー 1500円:コメディ映画特集】 [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| ジェネオン・ユニバーサル |


















