監督 ローラン・カンテ 出演 フランソワ・ベゴドー
映画なのだが、映画を見ている感じがしない。教室の様子があまりにリアルなので、まるでその教室にいる気持ちになる。
国語(フランス語)教師と中学生の、互いに相手を信頼しない。
興味深いのは、フランス語がかわってきているという事実である。なかに接続法をめぐるやりとりが出てくる。日本語には接続法がないが、国語がこの接続法をもっているか、もっていないかというのは思考の基本、哲学にかかわる問題である。その接続法をめぐって、生徒が「そんな気取った言い方をいまはだれもしない」という。これは、正確には「だれもしない」ではなく、そんな言い方はしたくないという主張である。教師の方でも「スノップに聞こえるかもしれない、気取って聞こえるかもしれないが云々」というようなことをいう。
これは、この映画の、ある意味での「テーマ」だと思った。直感的に、そう感じた。
接続法にはいろいろな用法があるが、簡単に言えば「事実」ではないものを語るのに接続法がつかわれる。生徒たちは、それを拒絶する。ただ「事実」だけを問題にしている。その「事実」をどんなふうに整理し、論理建て、そこから「世界」をつくりあげるかというようなことは考えない。拒絶する。彼らは、自分たちが差別されている。抑圧されている。大人によって、ある「形式」を強いられている。そして、それは「接続法」のように、具体的にはみえない。ことばのなかの文法のように、みえない力で、抑圧してくる。みえない力なので、生徒たちは、それとどう戦っていいかわからない。わからないから、ただ不満をぶつける。だらしない形で反抗する。「規制」からずるずるはみだすことだけを生きる頼りにしようとしているさえみえる。
大人は(フランス語教師は)、「世界」は見えるものと見えないものから成り立っている。直説法で表現できる世界は、いわば「見える」世界だが、世界を支配しているのはそういう「見える事実」ではなく、「事実を奥で動かす見えない力」である、と大人は考える。そして、その「見えない力」のいちばん大きなものは、「現実」をある仮定のもとで統一しようとする力--理想(夢想)である。そこに存在しないものを「出現」させるための「方法」である。
このぶつかり合いは、とてもおもしろい。
このぶつかり合いは、そして、最初は噛み合わない。けれど、教師がだらしない女子生徒ふたりを「タペス(?)」とかなんとか呼んだ瞬間から、激しく噛み合うというか、衝突する。フランス語はわからないので「タペス」だったかどうかもはっきりしないが、日本語の字幕では「娼婦」「情婦」「売春婦」というような訳がついていた。女子生徒のだらしない態度を、まるで「娼婦・情婦」のようだと教師が口走ってしまう。
「侮蔑である」と生徒はいっせいに批判する。
それに対して教師は、それは「比喩」であって、直接女子生徒を「情婦・娼婦・売春婦」と言ったわけではない、という。
生徒たちが「事実」として問題にしていることを、教師は「事実」ではなく「比喩」(仮定、接続法)の世界であると言うことで、言い逃れようとする。生徒たちは、そのとき、その「言い逃れ」を問題にする。「娼婦」ということばをつかい、生徒を定義づけたというのは「事実」である。「娼婦」ということばをどういう「意味」でつかったか、なぜそのことばをつかったかは問題ではない。「事実」だけが問題なのだ。言ったことをなぜ、「言った」と言わないのか。ごまかすのか。
大人たちは、簡単に言えば「事実」をごまかすために、ことばをつかう。その最たるものが「接続法」である。中学生たちは、そう考えている。
この、「ことば」の闘いを、中学生たちは、どうやったら勝ち抜いていけるか。中学生にかぎらず、移民国家であるフランスの、フランスに住む移民はどうやって勝ち抜いていける。自分たちのことばを確立できるか。
この映画は、結局「接続法」が勝ちを収める形でしめくくられているが、それを肯定しているわけではない。「接続法」が勝ちを収めているが、そんなものを生徒たちは納得していない。そして観客も納得しないことを前提として、終わる。
つまり、観客にこの問題をどうやって乗り切れるか、乗り越えるつもりかと問いかけて終わる。
これは、難しい。
いま大阪地検特捜部の証拠隠滅や小沢議員の資金問題がニュースになっているが、そこでも「事実」とそれを「語ることば」が最終的に問題になる。ことばとは「事実」であると同時に「世界」の「仮説」である。「仮説」をどうやって「事実」にしていくか。そこに「世界」の問題がある。
一方に「仮説」を「世界」にかえていくときの、独自の「文法」(文体)がある。他方に、「文体」を拒絶して「事実」を積み重ねようとする「未生の文体」がある。
どちらに与するか。
--いや、その「未生の文体」のために、ひとりひとりが何をできるか。そういうことを、映画は問いかけているように思える。
映画の舞台は、パリ20区の、移民が大勢いる中学校だが、それは映画が映画になるための舞台であって、そこで起きていること(起きたこと)は、世界のいたるところで起きているのである。
*
抽象的に書きすぎてしまった。
この映画の魅力は、なによりも中学生である。逸脱する中学生の姿は、最近では日本の映画では「告白」に描かれている。しかし、それはあまりに紋切り型だ。逸脱が演じられているだけだ。しかし、「パリ20区」は違う。まるで脚本が(ストーリーが)ないかのように中学生たちが動く。次に何が起きるかわからない。実際、そこにあるのは「接続法」で制御されたストーリーではなく、伏線もなにもなく、ただ「事実」がある。中学生がいる。彼らは大人を信用していないという「事実」だけがある。大人を信用しないことだけが、彼らの生きる方法であり、思想なのだ。
この中学生を「移民」と置き換えてみると、いまの世界がリアルになるかもしれない。移民は「国家」という「接続法」で制御で成り立つものを信じない。いま、彼の目の前のだれかが彼に対して何をするか、という「事実」だけと真剣に向き合う。
「事実」と「事実」の直接的な触れ合いから、そこにまた「事実」をつくっていく--そのことが生きるということなのだ。「移民」という状況を生きるときには。
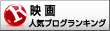
映画なのだが、映画を見ている感じがしない。教室の様子があまりにリアルなので、まるでその教室にいる気持ちになる。
国語(フランス語)教師と中学生の、互いに相手を信頼しない。
興味深いのは、フランス語がかわってきているという事実である。なかに接続法をめぐるやりとりが出てくる。日本語には接続法がないが、国語がこの接続法をもっているか、もっていないかというのは思考の基本、哲学にかかわる問題である。その接続法をめぐって、生徒が「そんな気取った言い方をいまはだれもしない」という。これは、正確には「だれもしない」ではなく、そんな言い方はしたくないという主張である。教師の方でも「スノップに聞こえるかもしれない、気取って聞こえるかもしれないが云々」というようなことをいう。
これは、この映画の、ある意味での「テーマ」だと思った。直感的に、そう感じた。
接続法にはいろいろな用法があるが、簡単に言えば「事実」ではないものを語るのに接続法がつかわれる。生徒たちは、それを拒絶する。ただ「事実」だけを問題にしている。その「事実」をどんなふうに整理し、論理建て、そこから「世界」をつくりあげるかというようなことは考えない。拒絶する。彼らは、自分たちが差別されている。抑圧されている。大人によって、ある「形式」を強いられている。そして、それは「接続法」のように、具体的にはみえない。ことばのなかの文法のように、みえない力で、抑圧してくる。みえない力なので、生徒たちは、それとどう戦っていいかわからない。わからないから、ただ不満をぶつける。だらしない形で反抗する。「規制」からずるずるはみだすことだけを生きる頼りにしようとしているさえみえる。
大人は(フランス語教師は)、「世界」は見えるものと見えないものから成り立っている。直説法で表現できる世界は、いわば「見える」世界だが、世界を支配しているのはそういう「見える事実」ではなく、「事実を奥で動かす見えない力」である、と大人は考える。そして、その「見えない力」のいちばん大きなものは、「現実」をある仮定のもとで統一しようとする力--理想(夢想)である。そこに存在しないものを「出現」させるための「方法」である。
このぶつかり合いは、とてもおもしろい。
このぶつかり合いは、そして、最初は噛み合わない。けれど、教師がだらしない女子生徒ふたりを「タペス(?)」とかなんとか呼んだ瞬間から、激しく噛み合うというか、衝突する。フランス語はわからないので「タペス」だったかどうかもはっきりしないが、日本語の字幕では「娼婦」「情婦」「売春婦」というような訳がついていた。女子生徒のだらしない態度を、まるで「娼婦・情婦」のようだと教師が口走ってしまう。
「侮蔑である」と生徒はいっせいに批判する。
それに対して教師は、それは「比喩」であって、直接女子生徒を「情婦・娼婦・売春婦」と言ったわけではない、という。
生徒たちが「事実」として問題にしていることを、教師は「事実」ではなく「比喩」(仮定、接続法)の世界であると言うことで、言い逃れようとする。生徒たちは、そのとき、その「言い逃れ」を問題にする。「娼婦」ということばをつかい、生徒を定義づけたというのは「事実」である。「娼婦」ということばをどういう「意味」でつかったか、なぜそのことばをつかったかは問題ではない。「事実」だけが問題なのだ。言ったことをなぜ、「言った」と言わないのか。ごまかすのか。
大人たちは、簡単に言えば「事実」をごまかすために、ことばをつかう。その最たるものが「接続法」である。中学生たちは、そう考えている。
この、「ことば」の闘いを、中学生たちは、どうやったら勝ち抜いていけるか。中学生にかぎらず、移民国家であるフランスの、フランスに住む移民はどうやって勝ち抜いていける。自分たちのことばを確立できるか。
この映画は、結局「接続法」が勝ちを収める形でしめくくられているが、それを肯定しているわけではない。「接続法」が勝ちを収めているが、そんなものを生徒たちは納得していない。そして観客も納得しないことを前提として、終わる。
つまり、観客にこの問題をどうやって乗り切れるか、乗り越えるつもりかと問いかけて終わる。
これは、難しい。
いま大阪地検特捜部の証拠隠滅や小沢議員の資金問題がニュースになっているが、そこでも「事実」とそれを「語ることば」が最終的に問題になる。ことばとは「事実」であると同時に「世界」の「仮説」である。「仮説」をどうやって「事実」にしていくか。そこに「世界」の問題がある。
一方に「仮説」を「世界」にかえていくときの、独自の「文法」(文体)がある。他方に、「文体」を拒絶して「事実」を積み重ねようとする「未生の文体」がある。
どちらに与するか。
--いや、その「未生の文体」のために、ひとりひとりが何をできるか。そういうことを、映画は問いかけているように思える。
映画の舞台は、パリ20区の、移民が大勢いる中学校だが、それは映画が映画になるための舞台であって、そこで起きていること(起きたこと)は、世界のいたるところで起きているのである。
*
抽象的に書きすぎてしまった。
この映画の魅力は、なによりも中学生である。逸脱する中学生の姿は、最近では日本の映画では「告白」に描かれている。しかし、それはあまりに紋切り型だ。逸脱が演じられているだけだ。しかし、「パリ20区」は違う。まるで脚本が(ストーリーが)ないかのように中学生たちが動く。次に何が起きるかわからない。実際、そこにあるのは「接続法」で制御されたストーリーではなく、伏線もなにもなく、ただ「事実」がある。中学生がいる。彼らは大人を信用していないという「事実」だけがある。大人を信用しないことだけが、彼らの生きる方法であり、思想なのだ。
この中学生を「移民」と置き換えてみると、いまの世界がリアルになるかもしれない。移民は「国家」という「接続法」で制御で成り立つものを信じない。いま、彼の目の前のだれかが彼に対して何をするか、という「事実」だけと真剣に向き合う。
「事実」と「事実」の直接的な触れ合いから、そこにまた「事実」をつくっていく--そのことが生きるということなのだ。「移民」という状況を生きるときには。


















