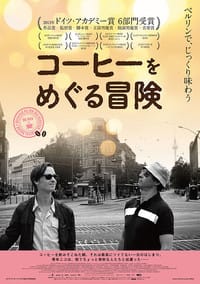中井久夫訳カヴァフィスを読む(18) 2014年04月09日(水曜日)
「デメトリオス王」はプルータルコスの『デメトリオスの生涯』に対して異議を唱えた詩。「王よりもむしろ俳優のごとく、彼、王の衣を鼠色の上衣に替えて密かに落ち行きぬ。」を引用したあとで詩をはじめている。王なのに、まるで俳優みたいじゃないか、というのがプルータルコスの意見なのだが、
同じように「俳優」という比喩をつかっているのだが、どこがプルータルコスと違うか。プルータルコスは「王の衣」と簡単にいってしまっているところを、カヴァフィスは「金色の長衣裳」「紫の長靴」と具体的に描写している。さらに「脱ぎ」「投げ捨て」と、王衣を捨てるときの肉体の動きを書いている。「密かに」という抽象的なことばも「忍び足で」と肉体の動きを引き出す形で書いている。
一方、プルータルコスが「鼠色の上衣」と具体的に書いているのに対して、カヴァフィスは「質素な服」と書いているだけである。
ふたつを比べると、プルータルコスの方は、逃げた王の「手配書」のように見える。逃げている王の姿が見える。ところがカヴァフィスのことばでは、逃げる前の王の姿の方がくっきりと見える。金色の長衣と紫の長靴。それが王である。
威厳のあった王を忘れない--そこに、カヴァフィスの姿勢がうかがえる。王を思い出すのは、彼が王だからである。逃げてしまえば王ではないのだから、そういものは語る必要がないとも言っているようだ。
でも、なぜ、「俳優」という同じ比喩をつかったのだろう。
「劇果てて」に秘密(カヴァフィスの思想)があるかもしれない。プルータルコスは「劇果てて(劇がおわった)」とは書いていない。カヴァフィスは、ひとつの「こと」が終わったとはっきり認識している。
これは逆に言えば、現実(政治/戦争)というものは「劇」に過ぎないとカヴァフィスが認識しているということかもしれない。シェークスピアではないが「世界は舞台」なのだ。そこでは次々に登場人物があらわれる。役が終わればさっさと消える。それでよい、と思っている。
詩のなかのことばでは「脱ぎ」「投げ捨て」と「着けて」の対立、「急ぎ」と「忍び足」の対立が、「こと」の緊迫を伝えていておもしろい。肉体が動いているのがわかる魅力的なことばの選択だ。
「デメトリオス王」はプルータルコスの『デメトリオスの生涯』に対して異議を唱えた詩。「王よりもむしろ俳優のごとく、彼、王の衣を鼠色の上衣に替えて密かに落ち行きぬ。」を引用したあとで詩をはじめている。王なのに、まるで俳優みたいじゃないか、というのがプルータルコスの意見なのだが、
金色の長衣を脱ぎ、
紫の長靴を投げ捨て、
急ぎ、質素な衣服をつけて、
忍び足で去った。
劇果てて、俳優が
衣裳を換えて去るように--。
同じように「俳優」という比喩をつかっているのだが、どこがプルータルコスと違うか。プルータルコスは「王の衣」と簡単にいってしまっているところを、カヴァフィスは「金色の長衣裳」「紫の長靴」と具体的に描写している。さらに「脱ぎ」「投げ捨て」と、王衣を捨てるときの肉体の動きを書いている。「密かに」という抽象的なことばも「忍び足で」と肉体の動きを引き出す形で書いている。
一方、プルータルコスが「鼠色の上衣」と具体的に書いているのに対して、カヴァフィスは「質素な服」と書いているだけである。
ふたつを比べると、プルータルコスの方は、逃げた王の「手配書」のように見える。逃げている王の姿が見える。ところがカヴァフィスのことばでは、逃げる前の王の姿の方がくっきりと見える。金色の長衣と紫の長靴。それが王である。
威厳のあった王を忘れない--そこに、カヴァフィスの姿勢がうかがえる。王を思い出すのは、彼が王だからである。逃げてしまえば王ではないのだから、そういものは語る必要がないとも言っているようだ。
でも、なぜ、「俳優」という同じ比喩をつかったのだろう。
「劇果てて」に秘密(カヴァフィスの思想)があるかもしれない。プルータルコスは「劇果てて(劇がおわった)」とは書いていない。カヴァフィスは、ひとつの「こと」が終わったとはっきり認識している。
これは逆に言えば、現実(政治/戦争)というものは「劇」に過ぎないとカヴァフィスが認識しているということかもしれない。シェークスピアではないが「世界は舞台」なのだ。そこでは次々に登場人物があらわれる。役が終わればさっさと消える。それでよい、と思っている。
詩のなかのことばでは「脱ぎ」「投げ捨て」と「着けて」の対立、「急ぎ」と「忍び足」の対立が、「こと」の緊迫を伝えていておもしろい。肉体が動いているのがわかる魅力的なことばの選択だ。