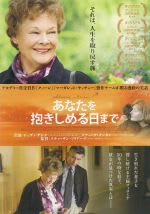田原「田原詩集(現代詩文庫205 )」(思潮社、2014年03月30日発行)
田原「田原詩集(現代詩文庫205 )」は、一冊(全作品)を読み終わってから感想を書こうと思っていた。ところが、最初の一篇でつまずいてしまった。全部読み通してからではなく、この一篇にこだわりたくなった。「夢のなかの木」。
その百年の大木は
私の夢の中に生えた
緑色の歯である
深夜 それは風に
容赦なく根こそぎにされた
3行目の「緑色の歯」。「葉」ではなく「歯」。ここに、つまずく。つまり、私の「流通言語」が否定される。拒絶される。拒絶されながら、瞬間的に、それで「いい」、「歯でいい」と思う。
歯のイメージが、私の肉体をひっかきまわす。歯のイメージが、私の肉体が何をおぼえているかを問いつめてくる。私の肉体がおぼえているのは……。
こどもの歯が生えてきて、生え揃うその口を思う。歯が生えてきて、舌が歯にぶつかる。そのころから、こどもの「ことば」は動きはじめる。歯がないと、声はことばにならない。歯という障害物(?)が口の大きさを限定し、そこからことばが生まれてくる--というわけではないかもしれないが、ふと「歯」と「ことば」の関係を思った。「肉体」が「歯」と「ことば」の出合いのなかに引き戻される感じがした。
歯としての大木。木としての歯。それは何を噛むのか。何に噛み付き、何を食べるのか。空を食べる。風を食べる。風を食べて枝を四方に広げ、空を食べて枝を天にのばす。木は大きな口となり、宇宙を食べる。そうやって、ことばになっていく木。
動物的な木。
歯によって、木は植物から動物にかわる。獣に変わる。ことばによって、木は植物から、獣にかわり、人間にかわる。
私は木が動物だと思ったことはなかった。私のふるさとには大きなケヤキの木があり、私はその木だ大好きだ。それこそ百年の大木なのだが、その木を動物のように見たことはなかった。けれど、動物であるかもしれない。だから、あんなにあたたかい。木に触れると、獣のようにあたたかい--というようなことも、ふと思った。
それが、夢のなかで、深夜、風にさらわれる。空にさらわれる。しかし、それはほんとうにさらわれたのか。
風は狂った獅子のように
木を掴んで空を飛んでゆく
夢の中で 私は
強引に移植されようとする木の運命を
推測できない
「強引に移植されようとする木の運命」ということばには「受け身」があり、木はさらわれたのだという印象があるが、「風は狂った獅子のように/木を掴んで空を飛んでゆく」からは、私は「受け身」を感じない。「風」が主語であり、「獅子のように」の「獅子」は風の比喩なのだが、私には木が獅子になり、風のように飛んでゆくと感じに見えてしまう。木と風は「獅子」のなかで一体になり、空を飛んでゆく。そのとき「獅子」は私のイメージでは「ライオン」ではなく「龍」である。「龍」ということばなどどこにも書いてないのだが、私は「龍」を思ってしまう。田原が中国人だからだろうか。
「強引に移植されようとする木の運命を/推測できない」と田原は書いているが、これは龍になって飛んでゆく木が、どこまで飛んでゆくのか、どこに降り立って暴れるつもりなのかわからないということを、別の形で書いたのではないのか。
1連目。最初の2行で木が(大地に)生えた、と書く。しかし、その連の終わりの2行では木は根こそぎにされたと書く。ひとつの連のなかで反対の動きが同居している。この反対の動きを「物語」のなかに入れてしまうと、生えている木が根こそぎにされたということになるが、どうも、そんな単純な「時間(物語)」におさまりきれないものがある。「歯」という強烈な比喩が「物語(時間)」を拒絶している。
反対のものをつなぐ何かが田原の中にある。反対のものがひとつになることで田原をつくっている。
2連目も、風にさらわれる木がどこに移植されるのかという「受け身」の「物語」にしてまうと落ち着いてしまうが、空を飛ぶと大地に植えられるとでは反対の動きなのだから、それを「物語の経済学」に納めてしまっては、詩を読んだことにならないのではないかと思う。
「夢の中で 私は」という行を中心に、前半の2行と後半の2行は激しくぶつかりあっている。その激突を「物語」に納めてしまうと、詩が詩ではなくなる。激しいぶつかりあい、そのなかでイメージが叩き壊され、同時にその破壊のなかで何かが誕生する。その誕生を見逃してしまう。
「夢の中で 私は」というのは何気ないことばだが、これが、この詩のキーワード(キーセンテンス)である。夢の中で田原は、激しい矛盾にもまれ、まったく新しい命を感じている。
この詩のなかには「夢の中で 私は」が次々と描かれている。これから書く詩の後半は1連が4行で書かれているが、ほんとうは5行である。中央に「夢の中で 私は」が省略されている。そして1連目、「緑色の歯である」も実は、
夢の中で 私は緑色の歯である
なのである。1連目に「夢の中で 私は」が省略されているのは、直前に「私の夢の中に」があるからだ。夢の中に百年の大木が生えた。それは緑色の歯である、ではなく、そのとき「夢の中で 私は 百年の大木の形をした緑色の歯」であるというのだ。
木になって、ことばを発する。ことばで宇宙に噛みつく。そして咀嚼し、育っていく大木としての歯。口。ことば。それは、いま、空を飛ぶ龍になって別の土地をめざしている。あたらしい食べ物をめざしている。そういう姿が思い浮かぶ。
そうすると、これは田原の自画像かもしれない。中国で生まれ、日本へやってきた(やってくる)田原。中国語で育った田原が日本語を食べながら、さらに大きな木になる。巨大な龍になる。どんな龍になれるか、夢想しているのである。夢想はどんな巨大なものでも、同時に不安をともなう。その不安が「受け身」という形にことばを動かしてしまうので、たぶん、誤読する。しかし、ここにある「受け身」は仮の姿だ。ほんとうは激しい「能動」が隠されている。
木がないと
私の空は崩れ始める
木がないと
私の世界は空っぽになる
この対句は「夢の中で 私は」を必要としていないように見える。しかし、これは「現実」のことではなく「想像」のことである。木と空、木と世界の関係を、心象として語っている。心象は「夢」のようにもの、「現実」そのものではない。
木がないと
「夢の中の」私の空は崩れ始める
「夢の中で 私は」
木がないと
「夢の中の」私の世界は空っぽになる
夢の中に木がないと、私は崩れはじめ、私は空っぽになる、と田原は言っているのである。詩の経済学が「夢の中で 私は」の重複を拒むのだが、それを未整理な状態にもどすと、私が書きなおしたような形になると思う。
以下は、このイメージを別な形で言いなおしたものである。
木は私の夢路にある暖かい宿場だ
その梢で囀る鳥の鳴き声を私は聞き慣れている
その木陰で涼んだり雨宿りする人々 そして
葉が迎える黎明に私は馴染んでいる
木が夢の中で消えた後
ケシの花は毒素を吐き出し
木が夢の中で消えた後
馬車も泥濘(ぬかるみ)にはまった
木がないと私は
鳥の囀りに残る濃緑を追憶するしかない
木がないと
私は 木が遠方で育つのを祈るほかない
最後の連についてだけ書いておこう。もし私(田原)が新しい土地(日本)で百年の大木になれないなら、私は鳥のさえずりを聞きながら中国にある大木(中国での田原自身)を追憶するしかない。もし私が新しい土地で百年の大木になれないなら、もっと違う遠方の土地へ再び「獅子」になって飛んでゆき、そこで育つことを考えなければならない--夢の中で私(田原)はそう思った。そして、このときの木(大木)というのは、比喩であって、それが指し示しているのは「ことば」である。「ことば」は世界に噛み付く歯であり、世界をかみ砕き、のみこむ力である。田原は強靱な歯をもったことばの大木を夢みている。
田原は「ことば」になりいたいのだ。どこの土地であろうと、「ことば」になろうと考えている。ことばの「百年の大木」になろうと夢みている。
これは「自己宣言」のような作品でもある。
*
歯は中国語ではどんなイメージを持っているのだろうか。ふいに気になって漢和辞典(大修館書店「新漢語林」)を引いてみた。いわゆる口のなかの歯のほかに、齢(よわい)、数、さいころ、たぐい、という意味のほかに、なんと「しるす(記す)。記録する」という意味がある。私は無意識に「ことば」という表現をつかったが、田原が「歯」と書くとき、このイメージが影響しているかもしれない。で、その「記す、記録する」の例だと思うのだが「歯録」ということばがあるもの知った。「集めしるす。書きおさめる。」
あ、中国人なのだ、と思った。
こんなところまでふつうはことばが動いていかない。無教養な私は、感想を書き終わって辞書を引いて、そうか、と思ってしまった。(教養のある人なら、「歯」につまずかずに、すぐに「ことば」を連想したかもしれないが。)
感想を書く前に、「つまずいた」と感じた瞬間に漢和辞典で「歯」を調べれば、もっとちがった感想が書けたかもしれない。きょうの「日記」は書き直した方が読みやすくなるかもしれない。けれど、私は、そのとき感じたことは間違いを含んでいても、間違いをしてしまうだけの何かほんとうのものがあってのことだと思うので、書きなおさない。書き直してしまうと、そのとき感じたことに対して何か嘘をついているように思うので。