陶山エリ「人と逢った」(「現代詩講座」@リードカフェ、2015年10月21日)
「現代詩講座」は、詩を持ち寄り、それを読み、感想を語る。まず一通り目をとおして、そのあと作者の朗読を聞く。そのあとすぐに一人ずつ感想を語る。じっくりとは考えない。読んだ瞬間(聞いた瞬間)に感じたことを語る。そうやって詩を探すのだが、だんだん何かが分かりはじめる、自分のからだになじんでくる、という変化が楽しい。
どんなふうに展開するか。おおざっぱに再現してみた。
私も、「口紅は……せめぎあい」までが非常におもしろいと思う。口紅とくちびるは音が似ていて、口紅の色とくちびるの色が入り乱れて、何かわからなくなるのが楽しい。「わからない」のだけれど、その「わからない」を突き破って動いていく何かがある。「ちから」が動いている。
もう一か所、「本日のクレームブリュレは……」の一行も、とてもおもしろいと感じる。
<質 問>この行は男性から見て、どう? おいしいとやさしくなれる?
<受講者1>なんとなくわかるけれど……。
実は私は「あまりに美味しくて」「一瞬やさしいひとでいられそう」の「美味しくて」と「やさしい」の結びつきが、私には、昔はわからなかった。「おいしい(たぶん、甘い)」と「やさしい」はたしかに「共通感覚」なのだろうけれど、それが「体感(実感)」としてはなかなか理解できなかった。
ジョン・トラボルタの出た「マイケル」という映画がある。トラボルタは「天使」の役。ジャーナリストが「天使」を探しに行く。その途中、女性記者が田舎の家の近くでバターの匂い(甘い香り)に気づき、夢中になる。一瞬、「天使」を探していることを忘れる。そのために男の同僚からバカにされるのだが、その瞬間、夢中になる女の姿をとおして、あ、これが女の感覚か、女なのかと気がついた。それを思い出した。いやな男をウィリアム・ハートがやったのだが、彼の「こんなときにバターの甘い匂いなんてどうでもいいじゃないか」という「合理的(?)」な批判があって、初めて、女の「甘い匂い」に対する執着(愛着?)がはっきりわかってびっくりした。
女性の監督の作品だが、そうか、女性から見ると、男の態度というのは、このウィリアム・ハートの態度なんだな。そして、それは女にとっては、気に食わないことなんだな、とわかった。
さらに、「天使」と旅をする途中のクレープ屋。トラボルタが、店にある全部の種類のクレープを注文しよう(食べよう)というと、いあわせた女たちが夢中になる。盛り上がる。この感覚。そこに「やさしさ」がある。「やさしさ」が「あまい」といっしょになって動いている。この「やさしさ/あまさ」への夢中の感覚、それが女独特の感じでおもしろいなあ、というようなことを話していると……。
という指摘があった。
えっ、ここで、こんなことを考えるのか?
そうか、「一瞬」をほんとうの「一瞬」と読んだのか、と私は驚いてしまった。
私は「2時間」を「一瞬」という「比喩」として語っているのだと思って読んでいた。あるいは「一瞬」を「2時間」と呼んでいるのだと思っていた。この区別のなさというか、融合した感じが「美味しくて」と「やさしい」のまじり具合にもにていると思ったのだが、「美味しくて/やさしい」が「一体」であることが当然と感じる女性は、逆に「2時間」と「一瞬」のぶつかりあいが気になるのか。
よく見ると、三連目の最終行と四連目の最終行の二行以外には「一瞬」ということばがある。けれど、「2時間くらいなら一瞬」ということばの結びつき以外では、このとき詩を読んだ誰も、そのことに気がつかなかった。「一瞬」はまるで書かれていないかのように読み落とされていた。
「2時間」と「一瞬」が矛盾しているという指摘がなかったら、そのまま気づかないままだったかもしれない。繰り返される「一瞬」よりも、繰り返されない個別のことばの方に意識がひっぱられていた。
この指摘はおもしろい。
陶山の詩の特徴、陶山の詩が「陶山節」といわれるゆえんは、ことばのねじれにある。ねじれは「連続」でもある。ところが「瞬間」というのは逆のイメージである。つながっていない。切断されている。「ねじれ」の連続のなかに、何かが瞬間的にしぼりこまれる。その「一瞬」を「一瞬」ではなく、別の「あざやか」なことばで感じる。「一瞬」ということばは、「あざやかな」何かを照らすスポットライトのようなものである。
何が印象に残るだろう。
「噛み殺す」ということばかもしれない。「ロザリオ」かもしれない(このことばは、しばしば陶山の詩に登場する)。あるいは「ルージュ・ココ」「ルージュ・アリュール」かもしれない。「クリームブリュレ」かもしれない。
そこにありながら、「あくびを噛み殺す」という「肉体」を見て、それに嫌悪(?)を感じた(ひとを噛み殺したくなった)という感情のストーリーを破っていく「もの」の存在。ストーリーからの「逸脱」が、詩として印象に残る。何かが持続しながら、何かが逸脱していく。そして、その逸脱がいつのまにか「本流」というか、いちばん大事なものになっていく、というのが陶山の詩に多いのだけれど、今回の詩は、「ストーリー」はそのまま「持続」の形で残っている。「一瞬」が「持続」している。
種明かしをするように、陶山はそう語った。
「作為」が「一瞬」にこめられている。「わざと書くのが現代詩」と定義したのは西脇順三郎だが、その「わざと」がここにある。
あ、これはおもしろいなあ。何に変えられるだろう。
「講座」でもその話をしたが、言い換えられることばが見つからなかった。それは逆に言えば、この詩では「一瞬」がキーワードとして、詩にしっかり絡みついているということだろう。
「わざと」書いた「一瞬」が詩そのものをつかんでいる。
そういう「作為」に満ちた詩なのだが、陶山はどこで悩んだだろう。書くときに苦労したのはどこだろう。
私も、そう思う。散文から「逸脱」し、飛躍する。その瞬間に、散文ではとらえることのできない何かが噴出する。それは「意味」としてとらえ直そうとすると、めんどうくさい。わからないまま、あ、おもしろい、と思えば、それが詩なのだ。ここが好き、と思い、その好きなところで立ち止まって、その「好き」を十分味わえばいい。
*
谷内修三詩集「注釈」発売中
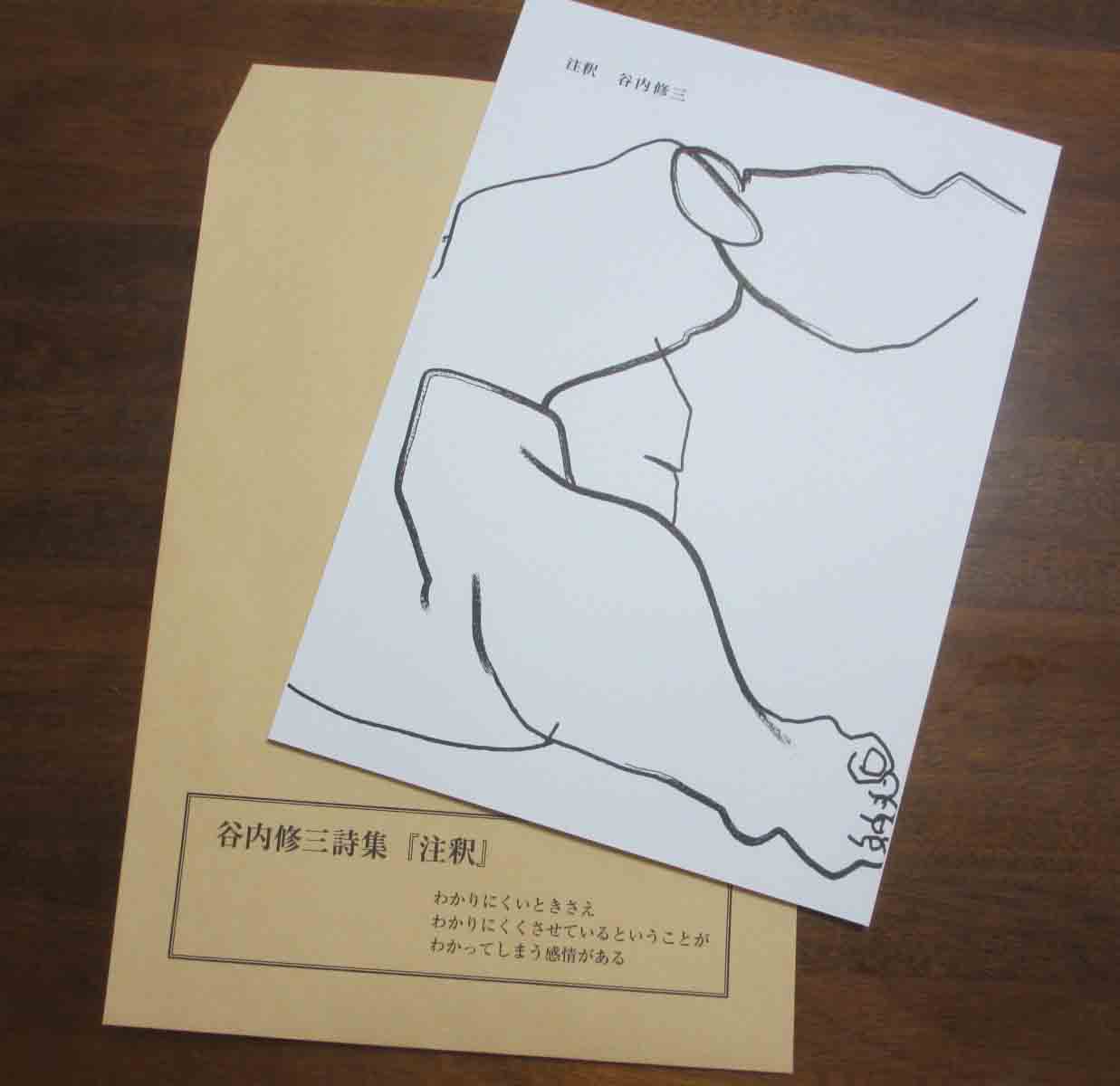
谷内修三詩集「注釈」(象形文字編集室)を発行しました。
2014年秋から2015年春にかけて書いた約300編から選んだ20篇。
「ことば」が主役の詩篇です。
B5版、50ページのムックタイプの詩集です。
非売品ですが、1000円(送料込み)で発売しています。
ご希望の方は、
yachisyuso@gmail.com
へメールしてください。
なお、「谷川俊太郎の『こころ』を読む」(思潮社、1800円)と同時購入の場合は2000円(送料込)、「リッツォス詩選集――附:谷内修三 中井久夫の訳詩を読む」(作品社、4200円)と同時購入の場合は4300円(送料込)、上記2冊と詩集の場合は6000円(送料込)になります。
支払方法は、発送の際お知らせします。
「現代詩講座」は、詩を持ち寄り、それを読み、感想を語る。まず一通り目をとおして、そのあと作者の朗読を聞く。そのあとすぐに一人ずつ感想を語る。じっくりとは考えない。読んだ瞬間(聞いた瞬間)に感じたことを語る。そうやって詩を探すのだが、だんだん何かが分かりはじめる、自分のからだになじんでくる、という変化が楽しい。
どんなふうに展開するか。おおざっぱに再現してみた。
人と逢った 陶山エリ
逢った人があくびを噛み殺すその気づかいに一瞬窓の外を見るその気づかいが一瞬映り込む窓にわたしならもっと
もっと上手に噛み殺せる一瞬離れるロザリオ
一瞬動いた感情の比喩として当てがうロザリオ一瞬そうしてみたかった
今日の口紅はどうですかルージュ・ココにしようかルージュ・アリュールにしようか一瞬獣になって迷いました
口紅は色でしかない色はくちびるでしかないとくちびるは一瞬色に色はくちびるに互いの一瞬の歪みを押しつけ合いせめぎあい飲み物が空になるのを一瞬盗み見る度くすんでくる時間に気づかない一瞬が窓の内側にいる
本日のクレームブリュレはあまりに美味しくて2時間くらいなら一瞬やさしいひとでいられそう
そう一瞬考えるにはあまりに日はあまりに無表情に落ちてしまいました
探しても一瞬見つかるわけがないロザリオを探さなくてもどんな感情の比喩にしたいのか一瞬忘れてしまっても忘れてしまうにはすっかり
すっかり人と逢った日は抜け落ちてしまいました
一瞬と逢った日と人と逢った日
一瞬噛み殺してください
一瞬手放すという比喩に変えられてもかまわないそう伝えるにはあまりに
逢った人はあまりに鮮やかに窓に映り込む
<受講者1>「噛み殺す」があくびから始まり、人間にまでたどりつく。
変化していくのがおもしろい。
口の役割も、噛むだけではなく「飲む」も出てくる。
会話のせめぎ合いに発展するのがおもしろい。
<受講者2>ことばが蛇のようにからまり動いていく。
二連目の「口紅は色でしかない」から「せめぎあい」までがおもしろい。
「噛む」が強く、過激になっていくのがいい。
ただ三連目の「そう一瞬考えるには……」は一瞬動きが止まる。
<受講者3>陶山節、ことばが動いている。
私も、「口紅は……せめぎあい」までが非常におもしろいと思う。口紅とくちびるは音が似ていて、口紅の色とくちびるの色が入り乱れて、何かわからなくなるのが楽しい。「わからない」のだけれど、その「わからない」を突き破って動いていく何かがある。「ちから」が動いている。
もう一か所、「本日のクレームブリュレは……」の一行も、とてもおもしろいと感じる。
<質 問>この行は男性から見て、どう? おいしいとやさしくなれる?
<受講者1>なんとなくわかるけれど……。
実は私は「あまりに美味しくて」「一瞬やさしいひとでいられそう」の「美味しくて」と「やさしい」の結びつきが、私には、昔はわからなかった。「おいしい(たぶん、甘い)」と「やさしい」はたしかに「共通感覚」なのだろうけれど、それが「体感(実感)」としてはなかなか理解できなかった。
ジョン・トラボルタの出た「マイケル」という映画がある。トラボルタは「天使」の役。ジャーナリストが「天使」を探しに行く。その途中、女性記者が田舎の家の近くでバターの匂い(甘い香り)に気づき、夢中になる。一瞬、「天使」を探していることを忘れる。そのために男の同僚からバカにされるのだが、その瞬間、夢中になる女の姿をとおして、あ、これが女の感覚か、女なのかと気がついた。それを思い出した。いやな男をウィリアム・ハートがやったのだが、彼の「こんなときにバターの甘い匂いなんてどうでもいいじゃないか」という「合理的(?)」な批判があって、初めて、女の「甘い匂い」に対する執着(愛着?)がはっきりわかってびっくりした。
女性の監督の作品だが、そうか、女性から見ると、男の態度というのは、このウィリアム・ハートの態度なんだな。そして、それは女にとっては、気に食わないことなんだな、とわかった。
さらに、「天使」と旅をする途中のクレープ屋。トラボルタが、店にある全部の種類のクレープを注文しよう(食べよう)というと、いあわせた女たちが夢中になる。盛り上がる。この感覚。そこに「やさしさ」がある。「やさしさ」が「あまい」といっしょになって動いている。この「やさしさ/あまさ」への夢中の感覚、それが女独特の感じでおもしろいなあ、というようなことを話していると……。
<受講者2>「2時間くらい」と「一瞬」が矛盾している。
という指摘があった。
えっ、ここで、こんなことを考えるのか?
そうか、「一瞬」をほんとうの「一瞬」と読んだのか、と私は驚いてしまった。
私は「2時間」を「一瞬」という「比喩」として語っているのだと思って読んでいた。あるいは「一瞬」を「2時間」と呼んでいるのだと思っていた。この区別のなさというか、融合した感じが「美味しくて」と「やさしい」のまじり具合にもにていると思ったのだが、「美味しくて/やさしい」が「一体」であることが当然と感じる女性は、逆に「2時間」と「一瞬」のぶつかりあいが気になるのか。
<受講者2>この詩には「一瞬」がたくさんある。一個、二個、三個、四個。
四個ある。あ、もっとある。
よく見ると、三連目の最終行と四連目の最終行の二行以外には「一瞬」ということばがある。けれど、「2時間くらいなら一瞬」ということばの結びつき以外では、このとき詩を読んだ誰も、そのことに気がつかなかった。「一瞬」はまるで書かれていないかのように読み落とされていた。
「2時間」と「一瞬」が矛盾しているという指摘がなかったら、そのまま気づかないままだったかもしれない。繰り返される「一瞬」よりも、繰り返されない個別のことばの方に意識がひっぱられていた。
<受講者1>最終行には「一瞬」というこことばのかわりに「鮮やか」がある。
「あざやか」と「一瞬」は同じ。「一瞬」は「鮮やか」
この指摘はおもしろい。
陶山の詩の特徴、陶山の詩が「陶山節」といわれるゆえんは、ことばのねじれにある。ねじれは「連続」でもある。ところが「瞬間」というのは逆のイメージである。つながっていない。切断されている。「ねじれ」の連続のなかに、何かが瞬間的にしぼりこまれる。その「一瞬」を「一瞬」ではなく、別の「あざやか」なことばで感じる。「一瞬」ということばは、「あざやかな」何かを照らすスポットライトのようなものである。
何が印象に残るだろう。
「噛み殺す」ということばかもしれない。「ロザリオ」かもしれない(このことばは、しばしば陶山の詩に登場する)。あるいは「ルージュ・ココ」「ルージュ・アリュール」かもしれない。「クリームブリュレ」かもしれない。
そこにありながら、「あくびを噛み殺す」という「肉体」を見て、それに嫌悪(?)を感じた(ひとを噛み殺したくなった)という感情のストーリーを破っていく「もの」の存在。ストーリーからの「逸脱」が、詩として印象に残る。何かが持続しながら、何かが逸脱していく。そして、その逸脱がいつのまにか「本流」というか、いちばん大事なものになっていく、というのが陶山の詩に多いのだけれど、今回の詩は、「ストーリー」はそのまま「持続」の形で残っている。「一瞬」が「持続」している。
陶山 「瞬間」ということばを10個以上つかって詩を書く。
そういう課題を与えられたらと仮定した書いた。
種明かしをするように、陶山はそう語った。
「作為」が「一瞬」にこめられている。「わざと書くのが現代詩」と定義したのは西脇順三郎だが、その「わざと」がここにある。
<受講者3>「一瞬」のすべてを、他のべつのことばに変えてみたくなる。
あ、これはおもしろいなあ。何に変えられるだろう。
「講座」でもその話をしたが、言い換えられることばが見つからなかった。それは逆に言えば、この詩では「一瞬」がキーワードとして、詩にしっかり絡みついているということだろう。
「わざと」書いた「一瞬」が詩そのものをつかんでいる。
そういう「作為」に満ちた詩なのだが、陶山はどこで悩んだだろう。書くときに苦労したのはどこだろう。
陶山 2連目。自分でも書いていてわからなくなった。
他にことばが見つからない。
「獣」は推敲で書き直した。「獣」ということばですっきりした。
<受講者3>「獣」だから「散文」から詩になった。
私も、そう思う。散文から「逸脱」し、飛躍する。その瞬間に、散文ではとらえることのできない何かが噴出する。それは「意味」としてとらえ直そうとすると、めんどうくさい。わからないまま、あ、おもしろい、と思えば、それが詩なのだ。ここが好き、と思い、その好きなところで立ち止まって、その「好き」を十分味わえばいい。
*
谷内修三詩集「注釈」発売中
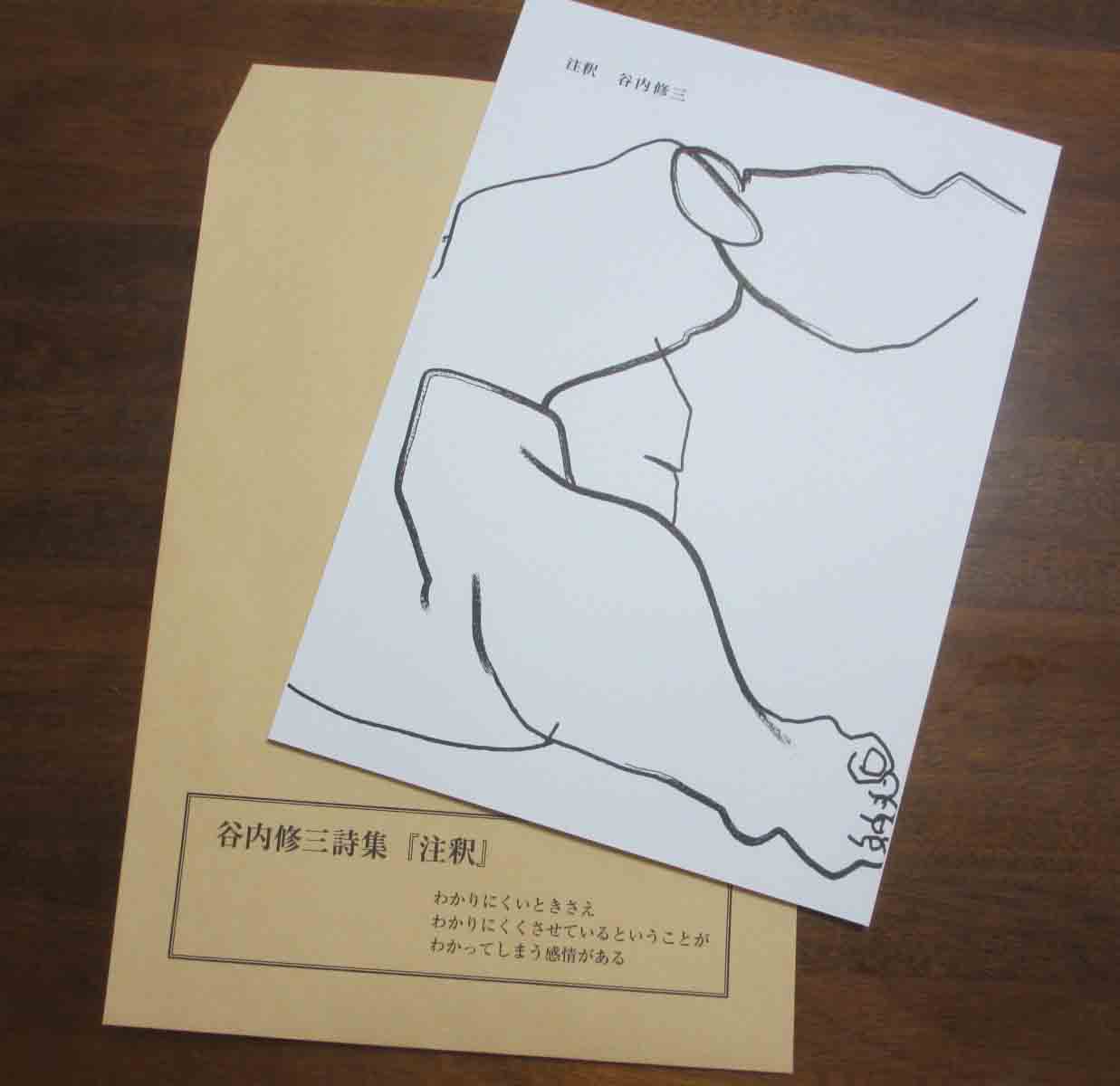
谷内修三詩集「注釈」(象形文字編集室)を発行しました。
2014年秋から2015年春にかけて書いた約300編から選んだ20篇。
「ことば」が主役の詩篇です。
B5版、50ページのムックタイプの詩集です。
非売品ですが、1000円(送料込み)で発売しています。
ご希望の方は、
yachisyuso@gmail.com
へメールしてください。
なお、「谷川俊太郎の『こころ』を読む」(思潮社、1800円)と同時購入の場合は2000円(送料込)、「リッツォス詩選集――附:谷内修三 中井久夫の訳詩を読む」(作品社、4200円)と同時購入の場合は4300円(送料込)、上記2冊と詩集の場合は6000円(送料込)になります。
支払方法は、発送の際お知らせします。


















