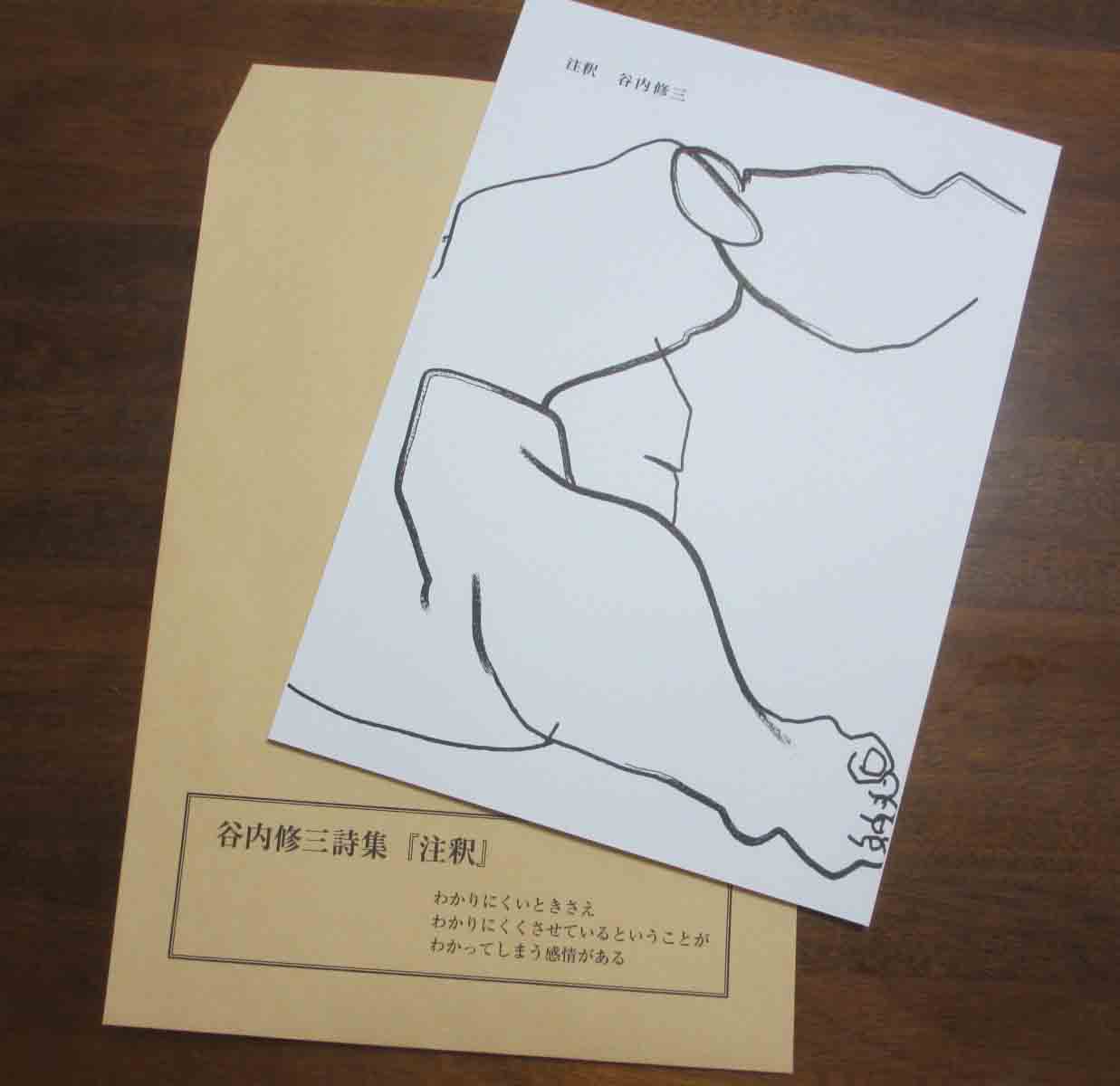監督 エドワード・ベルガー 出演 イボ・ピッツカー、ゲオルグ・アームズ、ルイーズ・ヘイヤー
育児を放棄した母親と二人のこどものストーリーだが、兄の行動をカメラはひたすら追っている。弟の世話をし、母親のことを気にかけている。幼いときから、弟の世話をするんだよ、と言い聞かされてきたのだろう。世話をしつづける過程で身につけてきた「暮らし方(生き方)」の強さがある。何もできない弟を助けないことには、弟は生きていけないということを知って、そう知った分だけ強くなっている。そして、ここで身につけた「強さ」が、いわば「あだ」のように働いている。母親さえも、彼にとっては「弱者」なのである。少年が支えなければ生きていけない。
あ、つらいねえ。
なんといっても、こども。母親に甘えたい。どんなにつらくても、母親が大好き。そして、母親も自分のことを大好きと信じ込んでいる。
その少年が、預けられた施設をぬけ出し、弟といっしょに母親を探し回る。幼い弟を世話しながら、必死に街をさまよう。母の友だちは誰だったか、母の愛人は誰だったか、どこで働いていたか、覚えていることを思い出しながら訪ね歩く。その「肉体」の動きに、ひっぱりこまれる。「全身」で考え、「全身」で動く。その「真剣」に引きずり込まれる。ほかのものが見えなくなる。
あ、逆だ。その「真剣」が照らし出す「社会」が見えてきて、ぞっとして、思わず少年になってしまうと言えばいいかもしれない。少年から見た「社会」の「絶望的な奇妙さ」が見えてくる。
誰一人、少年たちに「親身」にならない。母親の昔の愛人(レンタカーの経営者)が少し親切なくらい。ほかの人たちは「自分のこどもではない」から関係ない、と冷たく突き放している。夜の街をさまよっている、駐車場の壊れた車のなかで眠っている、その姿を見かけても、だれも「どうしたのか」とは問わない。何か手助けできることはないのか、とは問わない。母のアパートの住人たちも、まるで少年がいないかのように振る舞っている、というか、まったく姿をあらわさない。
うーん。
「こどもは地域の宝」ということばが昔は日本にあったが、(最近では地域でこどもを見守る、という温かさは日本からも消えてしまったが)、ヨーロッパではどうなんだろう。そういう「地域の力」というものは、世界から消えてしまったのか。
そんなことはないだろう、と思う。
この映画は、少年の目から見た「世界」に限定しているのである。
少年は、すでに、なんというか「自立」している。他人と接するとき「垣根」を持っている。それは少年が施設に入ったときに「いじめ」にあうシーンに象徴されている。「自立」が「すました」感じ、ひとりだけ「いい子」の感じになってあらわれる。それが嫌われる。みんな、だれかに甘えたい。その欲望を抱えて苦しんでいる。少年だけが「甘え」から「自立」しているように見える。幼い弟を世話しつづけてきた過程で身につけた「自立」である。
それが、ある意味で、「おとな(地域)」を遠ざける。少年が「遠ざけた」街が、少年のまわりでくりひろげられる。それが、この映画だね。
で、その少年が、どういう「目」で街を見ていたか。
これは映画の途中はなかなかわからなかった。母親を探す「真剣」しか見えなかったから。
ところが、ラスト。母親がアパートに帰っている。再会する。電話の話をする。そのとき、少年は母親が嘘をついていることを知る。それからの「目つき」の変化がすごい。「甘え」が消え「信頼」が消える。「自立」に拍車がかかる。母親が信頼に足る人間なのかどうかを見据える。顔が、がらりと変わるのである。
そうか、少年は、母親以外の人間(社会)を、こういう目で見ていたのか。「おとな」の目をして、社会を見ていたのか。相手を見ながら、相手がどういう人間であるかを「判断」する。そういう目をしていたのか。だからこそ、大人たちは少年に声をかけられなかったのかもしれない。
弟といっしょのシーン、弟を世話するときの目しかこころに残っていないかったが、これがほんとうの少年の目だったのだ。(施設でけんかするとき、施設のひとと話すとき、あるいは母親の友だちを訪ね歩くとき、そういえば、こういう目をしていた、と少しずつ思い出すのだが……。)
最後、少年は、母を棄てる。母からも「自立」する。そして施設へもどることを決意する。弟をいっしょにつれていく。施設は嫌い。そこには「愛情」がない。しかし、そこには「嘘」もない。母親のように「嘘」をつかない。その「嘘のなさ」に少年は「自立」のすべてをかける。
とても厳しい映画だ。
(2015年10月04日、KBCシネマ1)
*
「映画館に行こう」にご参加下さい。
映画館で見た映画(いま映画館で見ることのできる映画)に限定したレビューのサイトです。
https://www.facebook.com/groups/1512173462358822/
育児を放棄した母親と二人のこどものストーリーだが、兄の行動をカメラはひたすら追っている。弟の世話をし、母親のことを気にかけている。幼いときから、弟の世話をするんだよ、と言い聞かされてきたのだろう。世話をしつづける過程で身につけてきた「暮らし方(生き方)」の強さがある。何もできない弟を助けないことには、弟は生きていけないということを知って、そう知った分だけ強くなっている。そして、ここで身につけた「強さ」が、いわば「あだ」のように働いている。母親さえも、彼にとっては「弱者」なのである。少年が支えなければ生きていけない。
あ、つらいねえ。
なんといっても、こども。母親に甘えたい。どんなにつらくても、母親が大好き。そして、母親も自分のことを大好きと信じ込んでいる。
その少年が、預けられた施設をぬけ出し、弟といっしょに母親を探し回る。幼い弟を世話しながら、必死に街をさまよう。母の友だちは誰だったか、母の愛人は誰だったか、どこで働いていたか、覚えていることを思い出しながら訪ね歩く。その「肉体」の動きに、ひっぱりこまれる。「全身」で考え、「全身」で動く。その「真剣」に引きずり込まれる。ほかのものが見えなくなる。
あ、逆だ。その「真剣」が照らし出す「社会」が見えてきて、ぞっとして、思わず少年になってしまうと言えばいいかもしれない。少年から見た「社会」の「絶望的な奇妙さ」が見えてくる。
誰一人、少年たちに「親身」にならない。母親の昔の愛人(レンタカーの経営者)が少し親切なくらい。ほかの人たちは「自分のこどもではない」から関係ない、と冷たく突き放している。夜の街をさまよっている、駐車場の壊れた車のなかで眠っている、その姿を見かけても、だれも「どうしたのか」とは問わない。何か手助けできることはないのか、とは問わない。母のアパートの住人たちも、まるで少年がいないかのように振る舞っている、というか、まったく姿をあらわさない。
うーん。
「こどもは地域の宝」ということばが昔は日本にあったが、(最近では地域でこどもを見守る、という温かさは日本からも消えてしまったが)、ヨーロッパではどうなんだろう。そういう「地域の力」というものは、世界から消えてしまったのか。
そんなことはないだろう、と思う。
この映画は、少年の目から見た「世界」に限定しているのである。
少年は、すでに、なんというか「自立」している。他人と接するとき「垣根」を持っている。それは少年が施設に入ったときに「いじめ」にあうシーンに象徴されている。「自立」が「すました」感じ、ひとりだけ「いい子」の感じになってあらわれる。それが嫌われる。みんな、だれかに甘えたい。その欲望を抱えて苦しんでいる。少年だけが「甘え」から「自立」しているように見える。幼い弟を世話しつづけてきた過程で身につけた「自立」である。
それが、ある意味で、「おとな(地域)」を遠ざける。少年が「遠ざけた」街が、少年のまわりでくりひろげられる。それが、この映画だね。
で、その少年が、どういう「目」で街を見ていたか。
これは映画の途中はなかなかわからなかった。母親を探す「真剣」しか見えなかったから。
ところが、ラスト。母親がアパートに帰っている。再会する。電話の話をする。そのとき、少年は母親が嘘をついていることを知る。それからの「目つき」の変化がすごい。「甘え」が消え「信頼」が消える。「自立」に拍車がかかる。母親が信頼に足る人間なのかどうかを見据える。顔が、がらりと変わるのである。
そうか、少年は、母親以外の人間(社会)を、こういう目で見ていたのか。「おとな」の目をして、社会を見ていたのか。相手を見ながら、相手がどういう人間であるかを「判断」する。そういう目をしていたのか。だからこそ、大人たちは少年に声をかけられなかったのかもしれない。
弟といっしょのシーン、弟を世話するときの目しかこころに残っていないかったが、これがほんとうの少年の目だったのだ。(施設でけんかするとき、施設のひとと話すとき、あるいは母親の友だちを訪ね歩くとき、そういえば、こういう目をしていた、と少しずつ思い出すのだが……。)
最後、少年は、母を棄てる。母からも「自立」する。そして施設へもどることを決意する。弟をいっしょにつれていく。施設は嫌い。そこには「愛情」がない。しかし、そこには「嘘」もない。母親のように「嘘」をつかない。その「嘘のなさ」に少年は「自立」のすべてをかける。
とても厳しい映画だ。
(2015年10月04日、KBCシネマ1)
*
「映画館に行こう」にご参加下さい。
映画館で見た映画(いま映画館で見ることのできる映画)に限定したレビューのサイトです。
https://www.facebook.com/groups/1512173462358822/