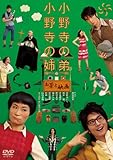谷川俊太郎(詩)川島小鳥(写真)『おやすみ神たち』(5)(ナナロク社、2014年11月01日発行)
「今朝」は「タマシヒ」と対になっているのかもしれない。この詩も裏側が少し透けて見える紙に印刷されている。ただし、印刷の「表/裏」が違う。「タマシヒ」は活字が印刷されている表面がつるつるしている。一般的に紙の表という場合、こちらが表だと思う。「今朝」は「裏側」、手触りがざらざらしている。紙質の違う本を読んでいると、そういうことも気になってくる。そして、その触覚(肉体)の感じが、ことばを読むときの感覚にも跳ね返ってくる。
「今朝」は「タマシイ」に比べて「ざらざら」している、と思う。でも、その「ざらざら」って何だろう。
「質感に触れる」ということばが出てくるが、「ざらざら」は質感だね。「タマシイ」がざらざら? 違うだろうなあ。
「今朝」と「タマシヒ」の詩のいちばんの違いは、そこに「私」が登場するか登場しないかである。「今朝」には「私」が書かれている。「タマシヒ」には「私」ということばは書かれていなかった。
そのため「タマシヒ」では、「タマシヒ」と「私」の区別がつかなかった。知らず知らずに「タマシヒ」を「私の肉体の奥(深部)」という具合に置き換えて読んでしまっていた。「タマシヒ」と「私」を一体のものとして読んでいた。
けれど、「今朝」ではそういう混同は起きない。「私」が「タマシヒ」について考えている。主語と目的語が分離している。この「分離感」が「ざらざら」の一歩(?)である。
で、「考える」ので、そのとき、ことばもかなり変化する。「恃まず」という「意味」を説明しようとすると、すっとは出て来ないようなことばがある。「質感」「未生」「静謐」という漢字熟語もある。「タマシヒ」は読んで書き取りをやらせたら中学生なら書き取れるだろう。でも「今朝」はきっと無理。「恃まず」で躓き、「未生」でも戸惑い、「静謐」になると「読んだことはあるけれど」と怒るかもしれないなあ。
ここには、ふつうに暮らしているときにつかわないことばがつかわれている。ふつうには話さないことばがつかわれている。その「違和感」が「ざらざら」かもしれない。
で、そのふつうにはつかわないことばで、何かを考える。--ちょっと「精神的」だね。ふつうから離れ、孤立、孤独な感じ。この「孤」が「ざらざら」かな。
紙の「ざらざら」も紙の分子(?)の突起が孤立している、べったりとつながっていないから「ざらざら」なんだろうな。
この「孤立/孤独」は、何かを考えるときには必要なことなのかもしれない。人といっしょにいて考えるのではなく、ひとりになって考える。そして、その「ひとりになる」というのは、自分自身からも離れて「もうひとりの私」になることかもしれない。「私」について、「もうひとりの私」になって、考える、見つめなおす。
「私」自身が分離して、「ざらざら」になっている。
で、「ざらざら」になって、その「ざらざら」をさらに見つめると、「ざらざら」の隙間(私ともうひとりの私の隙間)から、何かが見えるような感じがする。「ざらざら」は「亀裂」、「亀裂」からはそれまで見えなかったものが「見える」。
ことばにならないことば(未生のことば)が、その沈黙の、さらに向こうの静謐のなかに「ある」ような感じ。それが「タマシヒ」かもしれない。「タマシヒ」が「雑音の中から/澄んだ声が聞こえる」といった、その「澄んだ」が「静謐」なのかもしれない。
こんなふうにして、「タマシヒ」の最終連を書き換えると、「今朝」と「タマシヒ」がぴったり重なるように思える。
ふたつの詩は、ひとつの世界の表と裏という感じがする。表裏一体。それが印刷してある紙面の「紙質」と重なって、「肉体」の感触(ざらざら)といっしょになって動く。
表裏一体について、もう少し考えてみる。「ざらざら」から離れて考えてみる。
「今朝」の二連目、四連目に「タマシヒ」ということばが出てくる。この「タマシヒ」はだれの「タマシヒ」だろう。
「タマシヒ」という詩には「私」ということばがなかったけれど、私は何となく「私のタマシヒ」と思って読んでしまった。「私」と「タマシヒ」を区別しなかった。
けれど、「今朝」に書かれている「タマシヒ」は「私」ということばがあるにもかかわらず「私のタマシヒ」という感じがしない。二連めの「タマシヒ」には「私の」ということばをつけても違和感がないが、最後の「タマシヒ」を「私のタマシヒ」と読んでしまう気持ちになれない。
こんな具合にすると、なんといえばいいのか、谷川が、自分は他人とは違うんだぞ、と言っているような感じになる。「はい、そうですか」と思わず言い返したくなる感じなのだが、そこに「私の」がないので、すっと読める。
固有の(私の)タマシヒではなく、「タマシヒ」というものを一般的に(抽象的に?)考えようとしている。「私の」ではなく、人が「タマシヒ」と呼んでいるものは何か、ということを「純粋に」考えようとしていると感じる。
このとき、私も「もうひとりの私」になっているのかもしれない。私から「もうひとりの私」が分離するのを体験しているのかもしれない。
あ、そうすると、これもやっぱり「ざらざら」か。
この詩の紙からかすかに透けて見えるもの。白いのは川かな、山の中を流れる川の写真かな……と思ってページをめくると、不思議な滝。私の予想は半分当たって、半分外れたのかな? 山の右側は太陽のせいで(逆光のせいで)輪郭(稜線)がはっきりしないが、それはそのまま「今朝」の詩の裏側の白いページにつながっていて、あ、この白いページは逆光か。逆光では、そこに何かがあるのはわかるけれど、そのものを明確に見ることができない。「タマシヒ」と、そんなふうにして逆光のなかで感じる「存在感」のようなもの?
写真の逆光(白い部分)には、その次の詩の文字が裏返しになって動いているのが見える。それについては、またあした(あるいは後日に)、書こう。
「谷川俊太郎の『こころ』を読む」はアマゾンでは入手しにくい状態が続いています。
購読ご希望の方は、谷内修三(panchan@mars.dti.ne.jp)へお申し込みください。1800円(税抜、郵送無料)で販売します。
ご要望があれば、署名(宛名含む)もします。
「今朝」は「タマシヒ」と対になっているのかもしれない。この詩も裏側が少し透けて見える紙に印刷されている。ただし、印刷の「表/裏」が違う。「タマシヒ」は活字が印刷されている表面がつるつるしている。一般的に紙の表という場合、こちらが表だと思う。「今朝」は「裏側」、手触りがざらざらしている。紙質の違う本を読んでいると、そういうことも気になってくる。そして、その触覚(肉体)の感じが、ことばを読むときの感覚にも跳ね返ってくる。
「今朝」は「タマシイ」に比べて「ざらざら」している、と思う。でも、その「ざらざら」って何だろう。
生け垣に沿って老人が歩いてゆく
それを見ている私がいる
言葉を恃(たの)まずにこの世の質感に触れる
タマシヒというもの
老人と私を点景とする情景を見ている
もうひとりの私もいる
限りなく沈黙に近づきながら
未生の言葉を孕(はら)む静謐(せいひつ)はタマシヒのもの
「質感に触れる」ということばが出てくるが、「ざらざら」は質感だね。「タマシイ」がざらざら? 違うだろうなあ。
「今朝」と「タマシヒ」の詩のいちばんの違いは、そこに「私」が登場するか登場しないかである。「今朝」には「私」が書かれている。「タマシヒ」には「私」ということばは書かれていなかった。
そのため「タマシヒ」では、「タマシヒ」と「私」の区別がつかなかった。知らず知らずに「タマシヒ」を「私の肉体の奥(深部)」という具合に置き換えて読んでしまっていた。「タマシヒ」と「私」を一体のものとして読んでいた。
けれど、「今朝」ではそういう混同は起きない。「私」が「タマシヒ」について考えている。主語と目的語が分離している。この「分離感」が「ざらざら」の一歩(?)である。
で、「考える」ので、そのとき、ことばもかなり変化する。「恃まず」という「意味」を説明しようとすると、すっとは出て来ないようなことばがある。「質感」「未生」「静謐」という漢字熟語もある。「タマシヒ」は読んで書き取りをやらせたら中学生なら書き取れるだろう。でも「今朝」はきっと無理。「恃まず」で躓き、「未生」でも戸惑い、「静謐」になると「読んだことはあるけれど」と怒るかもしれないなあ。
ここには、ふつうに暮らしているときにつかわないことばがつかわれている。ふつうには話さないことばがつかわれている。その「違和感」が「ざらざら」かもしれない。
で、そのふつうにはつかわないことばで、何かを考える。--ちょっと「精神的」だね。ふつうから離れ、孤立、孤独な感じ。この「孤」が「ざらざら」かな。
紙の「ざらざら」も紙の分子(?)の突起が孤立している、べったりとつながっていないから「ざらざら」なんだろうな。
この「孤立/孤独」は、何かを考えるときには必要なことなのかもしれない。人といっしょにいて考えるのではなく、ひとりになって考える。そして、その「ひとりになる」というのは、自分自身からも離れて「もうひとりの私」になることかもしれない。「私」について、「もうひとりの私」になって、考える、見つめなおす。
「私」自身が分離して、「ざらざら」になっている。
で、「ざらざら」になって、その「ざらざら」をさらに見つめると、「ざらざら」の隙間(私ともうひとりの私の隙間)から、何かが見えるような感じがする。「ざらざら」は「亀裂」、「亀裂」からはそれまで見えなかったものが「見える」。
ことばにならないことば(未生のことば)が、その沈黙の、さらに向こうの静謐のなかに「ある」ような感じ。それが「タマシヒ」かもしれない。「タマシヒ」が「雑音の中から/澄んだ声が聞こえる」といった、その「澄んだ」が「静謐」なのかもしれない。
ヒトが耳を通して
タマシヒで聞こうとすると
雑音の中から
静謐が聞こえてくる
こんなふうにして、「タマシヒ」の最終連を書き換えると、「今朝」と「タマシヒ」がぴったり重なるように思える。
ふたつの詩は、ひとつの世界の表と裏という感じがする。表裏一体。それが印刷してある紙面の「紙質」と重なって、「肉体」の感触(ざらざら)といっしょになって動く。
表裏一体について、もう少し考えてみる。「ざらざら」から離れて考えてみる。
「今朝」の二連目、四連目に「タマシヒ」ということばが出てくる。この「タマシヒ」はだれの「タマシヒ」だろう。
「タマシヒ」という詩には「私」ということばがなかったけれど、私は何となく「私のタマシヒ」と思って読んでしまった。「私」と「タマシヒ」を区別しなかった。
けれど、「今朝」に書かれている「タマシヒ」は「私」ということばがあるにもかかわらず「私のタマシヒ」という感じがしない。二連めの「タマシヒ」には「私の」ということばをつけても違和感がないが、最後の「タマシヒ」を「私のタマシヒ」と読んでしまう気持ちになれない。
限りなく沈黙に近づきながら
未生の言葉を孕む静謐は私のタマシヒのもの
こんな具合にすると、なんといえばいいのか、谷川が、自分は他人とは違うんだぞ、と言っているような感じになる。「はい、そうですか」と思わず言い返したくなる感じなのだが、そこに「私の」がないので、すっと読める。
固有の(私の)タマシヒではなく、「タマシヒ」というものを一般的に(抽象的に?)考えようとしている。「私の」ではなく、人が「タマシヒ」と呼んでいるものは何か、ということを「純粋に」考えようとしていると感じる。
このとき、私も「もうひとりの私」になっているのかもしれない。私から「もうひとりの私」が分離するのを体験しているのかもしれない。
あ、そうすると、これもやっぱり「ざらざら」か。
この詩の紙からかすかに透けて見えるもの。白いのは川かな、山の中を流れる川の写真かな……と思ってページをめくると、不思議な滝。私の予想は半分当たって、半分外れたのかな? 山の右側は太陽のせいで(逆光のせいで)輪郭(稜線)がはっきりしないが、それはそのまま「今朝」の詩の裏側の白いページにつながっていて、あ、この白いページは逆光か。逆光では、そこに何かがあるのはわかるけれど、そのものを明確に見ることができない。「タマシヒ」と、そんなふうにして逆光のなかで感じる「存在感」のようなもの?
写真の逆光(白い部分)には、その次の詩の文字が裏返しになって動いているのが見える。それについては、またあした(あるいは後日に)、書こう。
 | おやすみ神たち |
| 谷川 俊太郎,川島 小鳥 | |
| ナナロク社 |
 | 谷川俊太郎の『こころ』を読む |
| クリエーター情報なし | |
| 思潮社 |
「谷川俊太郎の『こころ』を読む」はアマゾンでは入手しにくい状態が続いています。
購読ご希望の方は、谷内修三(panchan@mars.dti.ne.jp)へお申し込みください。1800円(税抜、郵送無料)で販売します。
ご要望があれば、署名(宛名含む)もします。