ヌリ・ビルゲ・ジェイラン監督「雪の轍」(★★★★)

監督 ヌリ・ビルゲ・ジェイラン 出演 ハルク・ビルギナー、メリサ・ソゼン、デメット・アクバァ
トルコ・カッパドキアの洞窟ホテルを舞台に、元俳優でトルコ演劇史を書こうとしている男、その妻、男の妹(離婚して帰ってきている)の三人の確執を描いている。ほかにも登場人物はいるのだが、基本は三人である。いや、「相手を受けいれない」という「性格(人格)」が三様に(あるいは他の登場人物を含めた人数の数だけのあり方として)描かれるといえばいいのか。まるで一人一人が「洞窟」に閉じこもって、そこから他人を見ている感じである。他人を受けいれるも何も、自分の「洞窟」から出て行かないのだから、これでは「和解」というものはありえない。「他者」を受けいれるということは、自分が無防備になることなのだが、三人ともことばで「洞窟」をつくって、そこから出て行かない。常に自分の「論理」という「洞窟」へ引きこもり、相手を批判する。この緊張感は、なかなかつらい。「台詞」を追いかけるのが、つらい。その「台詞」がどれも「自己主張」の繰り返しであるのが、さらにつらい。
私は、その緊迫したことばのぶつかりあいよりも、字幕を読まなくてもすむことばのないシーンにひかれた。特に野生の馬をつかまえるシーンがすごい。トルコの馬を最初に見たのはユルマズ・ギュネイ監督「路」。競馬馬と違って人工的な感じがしなくて、体が流れるように美しい。今回登場する馬も美しい。その美しい馬が首に輪をかけられ、川のなかで半分おぼれさせるように苦しめられる。苦しくなって、暴れる力がなくなったところをひきあげる。川からひきあげられて、足をおり、馬はやっと息をしている。その肉体の苦悩が美しい。苦しみが、見ている私にじかに響いてくる。馬にあわせて息をしてしまいそうなくらいである。映画を見ているうちに、その苦しい肉体のあえぎが、若い妻の苦悩と重なってくる。あ、あの白い馬は妻なのだ、と思えてくる。映画のなかでは、男が妻を「自分のことを籠の鳥と思っているか」というようなことばで批判するが、「籠の鳥」では瀕死の苦しみと重ならない。それで、なおのこと妻が白い馬に見える。この馬は、最後に野にかえされるのだが、このことも馬こそが妻の「象徴」だったのだと思わせる。
「象徴」という点から映画を振り返ると、冒頭近く、こどもの投石で割られる車の窓ガラス。あれは主人公の男の「象徴」である。蜘蛛の素状にひびが入る。まだ、かろうじて砕けずに「一枚」につながっている。車のガラスは取り替えがきくが、男のこころは取り替えがきかない。他人のことばの礫を受けて、ひびのはいったこころ。それをそのまま、そっとつなぎとめるように、抱え込むしかない。このガラスのひびのつらさは、男にとっては取り換えようのないガラスなのに、他人からはそうは見えないことだ。「こころ」は見えない。ことばの礫がこころを傷つけた瞬間は、男の反応によって男が傷ついたことはわかるが、次の瞬間に男が反論すると、もうガラスは取り換えられていつものガラスにもどってしまったようにしか見えない。映画のなかでは、車のガラスは取り換えられ、それにひびが入ったということは忘れられてしまう。言われれば思い出すが、車の外形からは、その記憶は消えている。実際、男の「こころの傷」は瞬間瞬間に、消えてしまう形で描かれる。男は妻のように「涙」で悲しみをあらわすこともない。
厖大な「台詞」の一方、ことばではない表現をする登場人物がいる。車に石を投げた少年。彼はほとんどことばを口にしない。無言の、じっと見つめる目が少年のことばである。男に謝罪のキスをするはずが、失神して倒れる。そのときの、男の「論理」とは無縁の目。さらに若い妻が少年の家に大金を持っていく。その大金を父親が暖炉へ放り込み燃やしてしまう。それをドアの隙間からじっと見ているときの目。見ることが少年にとって「世界」を受けいれることなのだ。だから、失神したときの目は、「謝罪するという論理(世界のあり方)」を拒絶(拒否)しているということでもある。少年は主要な登場人物ではないかもしれないが、重要である。
映画は、この少年の目をカメラにしているわけではないが、少年の目のように、そこにある「世界」をそのまま「映像」として受けいれている。カメラはことばで世界を批判しない。「洞窟」のなかにも入るが、「洞窟」からも出てゆく。カッパドキアの風景をまるごととらえ、そのなかで動き気象(雪)の変化もとらえれば、水の動きもとらえる。それは、登場人物の「心情」とは無関係に、全体的な美しさでそこにある。存在すること事態が美しさになっている。ことばにしないことが、美しさを尊厳にまで高めている。
私は目が悪いので、途中から字幕を読むのをやめてしまったが、最初から字幕を読まないで見ていたら、印象が違ってきたかもしれない。この映画のつかみとった厳しい美しさが、もっと生々しくつたわってきたかもしれない。「字幕の台詞」というのは、だいたいおぼえらていられない。見終わったあとは、ほとんど忘れている。しかし、台詞は忘れているが、ストーリーはおぼえている。台詞とはその程度のものだから、こういう台詞が主体になった映画でも、映像に集中してみれば、そこに起きていることはわかる。役者の肉体の動きが、観客の肉体がおぼえていることを刺戟し、男と妻がけんかしている、みんな自己主張するばかりで他人のことを思っていない、ということがわかる。字幕に頼らずに映画を見れば、きっと★5個の映画にかわるだろう。
(KBCシネマ2)

監督 ヌリ・ビルゲ・ジェイラン 出演 ハルク・ビルギナー、メリサ・ソゼン、デメット・アクバァ
トルコ・カッパドキアの洞窟ホテルを舞台に、元俳優でトルコ演劇史を書こうとしている男、その妻、男の妹(離婚して帰ってきている)の三人の確執を描いている。ほかにも登場人物はいるのだが、基本は三人である。いや、「相手を受けいれない」という「性格(人格)」が三様に(あるいは他の登場人物を含めた人数の数だけのあり方として)描かれるといえばいいのか。まるで一人一人が「洞窟」に閉じこもって、そこから他人を見ている感じである。他人を受けいれるも何も、自分の「洞窟」から出て行かないのだから、これでは「和解」というものはありえない。「他者」を受けいれるということは、自分が無防備になることなのだが、三人ともことばで「洞窟」をつくって、そこから出て行かない。常に自分の「論理」という「洞窟」へ引きこもり、相手を批判する。この緊張感は、なかなかつらい。「台詞」を追いかけるのが、つらい。その「台詞」がどれも「自己主張」の繰り返しであるのが、さらにつらい。
私は、その緊迫したことばのぶつかりあいよりも、字幕を読まなくてもすむことばのないシーンにひかれた。特に野生の馬をつかまえるシーンがすごい。トルコの馬を最初に見たのはユルマズ・ギュネイ監督「路」。競馬馬と違って人工的な感じがしなくて、体が流れるように美しい。今回登場する馬も美しい。その美しい馬が首に輪をかけられ、川のなかで半分おぼれさせるように苦しめられる。苦しくなって、暴れる力がなくなったところをひきあげる。川からひきあげられて、足をおり、馬はやっと息をしている。その肉体の苦悩が美しい。苦しみが、見ている私にじかに響いてくる。馬にあわせて息をしてしまいそうなくらいである。映画を見ているうちに、その苦しい肉体のあえぎが、若い妻の苦悩と重なってくる。あ、あの白い馬は妻なのだ、と思えてくる。映画のなかでは、男が妻を「自分のことを籠の鳥と思っているか」というようなことばで批判するが、「籠の鳥」では瀕死の苦しみと重ならない。それで、なおのこと妻が白い馬に見える。この馬は、最後に野にかえされるのだが、このことも馬こそが妻の「象徴」だったのだと思わせる。
「象徴」という点から映画を振り返ると、冒頭近く、こどもの投石で割られる車の窓ガラス。あれは主人公の男の「象徴」である。蜘蛛の素状にひびが入る。まだ、かろうじて砕けずに「一枚」につながっている。車のガラスは取り替えがきくが、男のこころは取り替えがきかない。他人のことばの礫を受けて、ひびのはいったこころ。それをそのまま、そっとつなぎとめるように、抱え込むしかない。このガラスのひびのつらさは、男にとっては取り換えようのないガラスなのに、他人からはそうは見えないことだ。「こころ」は見えない。ことばの礫がこころを傷つけた瞬間は、男の反応によって男が傷ついたことはわかるが、次の瞬間に男が反論すると、もうガラスは取り換えられていつものガラスにもどってしまったようにしか見えない。映画のなかでは、車のガラスは取り換えられ、それにひびが入ったということは忘れられてしまう。言われれば思い出すが、車の外形からは、その記憶は消えている。実際、男の「こころの傷」は瞬間瞬間に、消えてしまう形で描かれる。男は妻のように「涙」で悲しみをあらわすこともない。
厖大な「台詞」の一方、ことばではない表現をする登場人物がいる。車に石を投げた少年。彼はほとんどことばを口にしない。無言の、じっと見つめる目が少年のことばである。男に謝罪のキスをするはずが、失神して倒れる。そのときの、男の「論理」とは無縁の目。さらに若い妻が少年の家に大金を持っていく。その大金を父親が暖炉へ放り込み燃やしてしまう。それをドアの隙間からじっと見ているときの目。見ることが少年にとって「世界」を受けいれることなのだ。だから、失神したときの目は、「謝罪するという論理(世界のあり方)」を拒絶(拒否)しているということでもある。少年は主要な登場人物ではないかもしれないが、重要である。
映画は、この少年の目をカメラにしているわけではないが、少年の目のように、そこにある「世界」をそのまま「映像」として受けいれている。カメラはことばで世界を批判しない。「洞窟」のなかにも入るが、「洞窟」からも出てゆく。カッパドキアの風景をまるごととらえ、そのなかで動き気象(雪)の変化もとらえれば、水の動きもとらえる。それは、登場人物の「心情」とは無関係に、全体的な美しさでそこにある。存在すること事態が美しさになっている。ことばにしないことが、美しさを尊厳にまで高めている。
私は目が悪いので、途中から字幕を読むのをやめてしまったが、最初から字幕を読まないで見ていたら、印象が違ってきたかもしれない。この映画のつかみとった厳しい美しさが、もっと生々しくつたわってきたかもしれない。「字幕の台詞」というのは、だいたいおぼえらていられない。見終わったあとは、ほとんど忘れている。しかし、台詞は忘れているが、ストーリーはおぼえている。台詞とはその程度のものだから、こういう台詞が主体になった映画でも、映像に集中してみれば、そこに起きていることはわかる。役者の肉体の動きが、観客の肉体がおぼえていることを刺戟し、男と妻がけんかしている、みんな自己主張するばかりで他人のことを思っていない、ということがわかる。字幕に頼らずに映画を見れば、きっと★5個の映画にかわるだろう。
(KBCシネマ2)
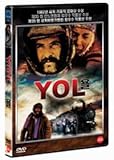 | Yol DVD [DVD, For All Regions, NTSC] |
| クリエーター情報なし | |
| メーカー情報なし |




















