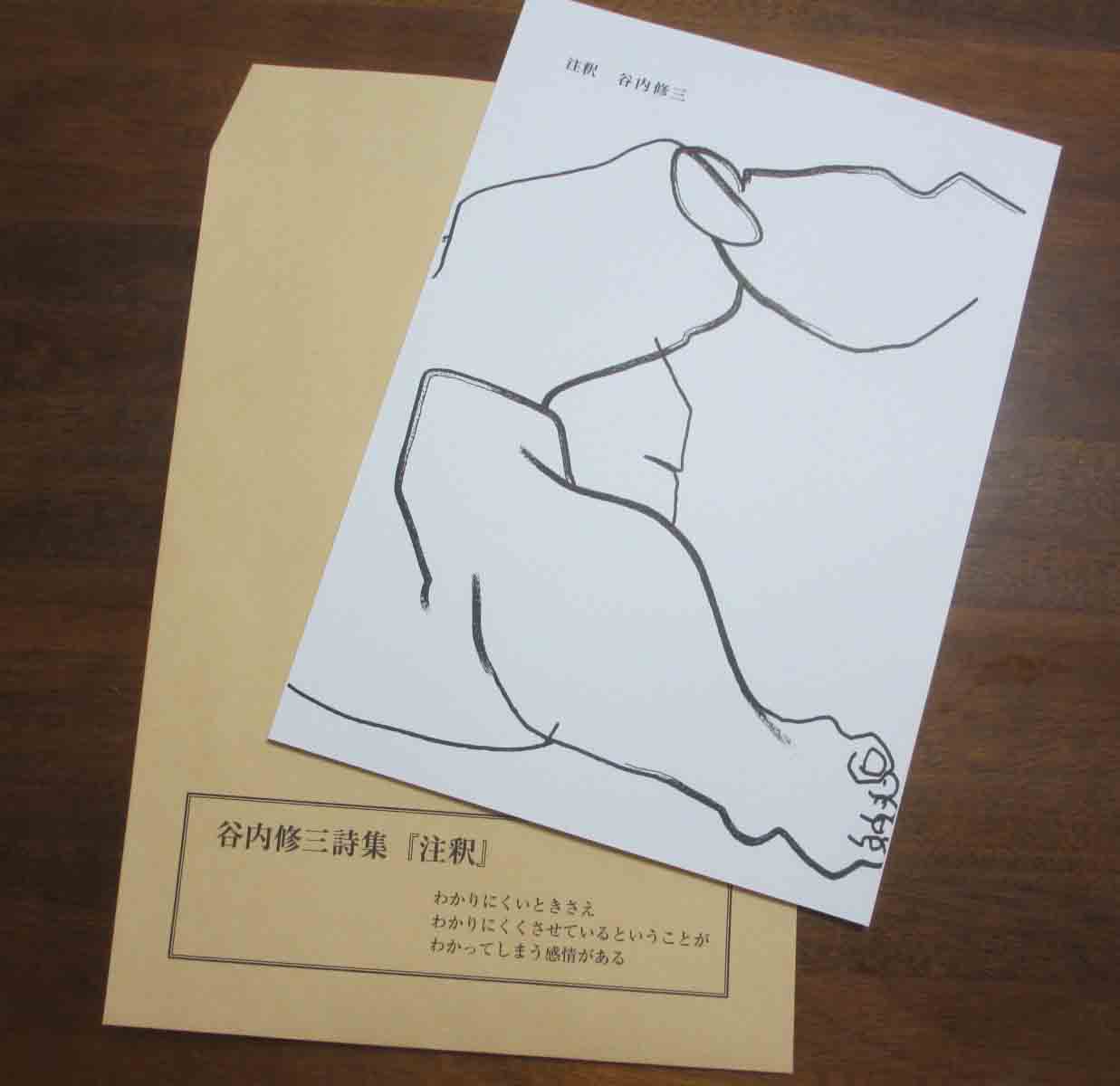監督 オリバー・ヒルシュビーゲル 出演 クリスティアン・フリーデル、カタリーナ・シュトラー、ブルクハルト・クラウスナー
「ヒトラー暗殺、13分の誤算」というタイトルから推測すると、なぜ13分の誤差が生じたのか、という謎解きを期待してしまうのだが……。まあ、ヒトラーは暗殺されなかったのだから、その理由(原因)を知ったところでおもしろくはない。それよりも、そうかヒトラー暗殺計画があったのか、ということに驚く。さらに驚くのは、その計画を立て、実行したのが組織に属さない「ひとり」ということである。
音楽が好きで、女が好きで、「全体主義(ナチス)」は嫌いという青年。
最初の方に「女好き」が、ていねいに描かれる。恋人がいるのに、ほかの女に目移りする。人妻にもこころが動く。からだも動く。二人目の恋人に「だれそれ(一人目の女)は恋人じゃないの?」と問われて「自由が好きなんだ」と答えているが、この「自由」が彼の行動のキーワードだ。
最初の方に青年は時計職人として出てくる。そのあと家具職人として出てくる。時計職人(時計の修理)も家具職人(家具作り)も、ひとりでできる仕事である。ひとりで全体を見渡しながらものをつくる。そこにも他人から支配されないという「自由」がある。音楽は共同作業だけれど、彼のやっている音楽には指揮者はいない。互いの音を聞きながら、自分の音を出す。自分のパーツの楽器は自分で弾く。他人に手伝ってもらうわけではない。自分の仕事をていねいにやれば、他人と共同して楽しい音楽ができあがる。ここにも「個人主義」と「自由主義」がある。
共産党には投票するが、共産党員ではない。共産党員の仲間から助けを求められれば助ける。しかし、「組織」には属さず、あくまで「ひとり」として行動する。「自由」な「ひとり」というのが、青年の生き方であるということが、さりげなく描かれている。
暗殺計画よりも、「全体主義(ナチス)」がドイツを覆っていくとき、こういう人間がいたということが、とても興味深い。ドイツ人のすべてがナチスだったわけではない。そして、そういう人間を作り上げるのが「仕事」であるというのも、興味深い。時計職人、家具職人という仕事が彼を「ひとり」で生きることを育てる。共同で何かをするとしても、それは「音楽」のように、互いの存在を認め合いながらのことであって、だれかに指揮されて動くわけではない。
互いの存在を認め合いながら--ということについては、とてもおもしろいシーンがある。青年の最終的な恋人となる人妻との出会い。タンゴを踊るシーン。女の方が青年を挑発してくるのだが、それを受け止めながら肉体が互いに反応して動く。そこではセックスはおこなわれないが、セックスよりも濃密な「関係」がそこに生まれてくる。「一対一」が互いを育てるのである。
青年が求めているのは、あくまで「一対一」の関係である。
ヒトラー暗殺も、彼にとっては「一対一」のことなのである。ヒトラーを殺す。そして「自由」になる。それが青年の目的だ。
「誤算」があるとしたら「13分」ではなく、ヒトラーを暗殺できず、他人を殺してしまったことである。恋人だけではなく、家族など、他人を巻き込んでしまったことである。「一対一」でやろうとしても、社会が「一対一」を許さない。
これはヒトラー側からの、暗殺計画の取り調べについても言える。青年がひとりでやった、と主張しても、「ひとり」を認めない。背後に組織があるはずだ、と考え、問いつめる。「ナチス対共産党」という構図の中で暗殺計画をとらえようとする。ひとりでできるはずがないと考えるのではなく、そういうことをする人間が「ひとり」であることを許さない、という感じ。どんな人間も「組織」に属している。ナチスに反対する人間は共産党に属しているはず、と考える。
これはユダヤ人に対する態度そのものとも言える。「ひとり」を認めない。ユダヤ人という組織(?)は認めるが、個人は存在を認めない。「ひとり」が何をするかは問題ではない。「組織」が問題なのだ。「全体主義者」は他者をも「全体」として見てしまう。
ここに青年の「視点」とナチスの視点の違いがある。
ここから奇妙な歪みが起きる。
青年は暗殺計画をひとりで実行する。その「事実」を将校のひとりが認めてしまう。組織的犯罪ではなく、個人的犯罪であると、青年の言い分を認めてしまう。そうすると、こんどはナチスがその将校を追い詰めていく。具体的には描かれていないが、その将校は処刑されてしまう。彼の事実認識(青年の行動に対する認識は)間違っていない。将校が侵した間違いは、ナチス(ヒトラー)が求めていた「答え」を読み違えたことである。ヒトラーは、暗殺計画が「組織」によっておこなわれた、という答えを求めていた。ヒトラーに歯向かう人間を「組織」ごと壊滅したい。「組織」を壊滅したいのであって、「個人」を殺したいのではない。「組織」を破壊するのなら一回でできるが、「個人」を殺すためには「ひとりずつ」殺さなければならない。これは、きりがない。
ユダヤ人虐殺を思い浮かべるといい。ひとりずつ殺していては厖大な時間と人手がいる。ガス室で一気に殺してしまえば、ひとりひとりと向き合うこともない。「個人」の尊厳というものが「頭」から抜け落ちてしまう。「個人」を忘れてしまうと、ひとは平気で暴力的になれるということかもしれない。
映画に即して言い直すと、青年を取り調べるときナチスは拷問をするが、それは青年の肉体を痛めつけているのではない。青年を人間ではなく、「組織」と見ているから平気で暴力を振るえるのである。また青年は拷問が彼ひとりに対しておこなわれているときは耐えられるが、それが恋人という別のひとりに広がっていくことには耐えられず、自白をはじめる。すべてを「ひとり」で受け止めるために自白するのである。だれかに、自分のしたことを波及させない。
と、考えてくると。
この映画は、私たちに「個人」であれ、「ひとり」であれ、と呼びかけているのかもしれない。「組織」に身を隠すな。「ひとり」として行動しろ、と呼びかけているようにもみえる。日本のいまの政治状況を思うとき、特にそういう見方をしたくなる。「ひとり」が自由に集まり、また「ひとり」にもどっていく。そういう「闘い方」が必要な時代なのだと思う。
ストーリーに沿ったことばかり書いてしまったが。
青年が取り調べの過程で思い出す「故郷」の風景が美しい。そこで暮らすひとの暮らしが、酔っ払いを含めて美しい。人間的だ。特に一瞬描写された森と雨の風景、雨が木々のあいだを立ち上り白く空気が濁るシーンにうなってしまった。そういう美しい暮らしにまで侵入してきて人間を破壊するのが「全体主義」(一億なんとか主義)である。
(2015年10月18日、天神東宝4)
*
「映画館に行こう」にご参加下さい。
映画館で見た映画(いま映画館で見ることのできる映画)に限定したレビューのサイトです。
https://www.facebook.com/groups/1512173462358822/
「ヒトラー暗殺、13分の誤算」というタイトルから推測すると、なぜ13分の誤差が生じたのか、という謎解きを期待してしまうのだが……。まあ、ヒトラーは暗殺されなかったのだから、その理由(原因)を知ったところでおもしろくはない。それよりも、そうかヒトラー暗殺計画があったのか、ということに驚く。さらに驚くのは、その計画を立て、実行したのが組織に属さない「ひとり」ということである。
音楽が好きで、女が好きで、「全体主義(ナチス)」は嫌いという青年。
最初の方に「女好き」が、ていねいに描かれる。恋人がいるのに、ほかの女に目移りする。人妻にもこころが動く。からだも動く。二人目の恋人に「だれそれ(一人目の女)は恋人じゃないの?」と問われて「自由が好きなんだ」と答えているが、この「自由」が彼の行動のキーワードだ。
最初の方に青年は時計職人として出てくる。そのあと家具職人として出てくる。時計職人(時計の修理)も家具職人(家具作り)も、ひとりでできる仕事である。ひとりで全体を見渡しながらものをつくる。そこにも他人から支配されないという「自由」がある。音楽は共同作業だけれど、彼のやっている音楽には指揮者はいない。互いの音を聞きながら、自分の音を出す。自分のパーツの楽器は自分で弾く。他人に手伝ってもらうわけではない。自分の仕事をていねいにやれば、他人と共同して楽しい音楽ができあがる。ここにも「個人主義」と「自由主義」がある。
共産党には投票するが、共産党員ではない。共産党員の仲間から助けを求められれば助ける。しかし、「組織」には属さず、あくまで「ひとり」として行動する。「自由」な「ひとり」というのが、青年の生き方であるということが、さりげなく描かれている。
暗殺計画よりも、「全体主義(ナチス)」がドイツを覆っていくとき、こういう人間がいたということが、とても興味深い。ドイツ人のすべてがナチスだったわけではない。そして、そういう人間を作り上げるのが「仕事」であるというのも、興味深い。時計職人、家具職人という仕事が彼を「ひとり」で生きることを育てる。共同で何かをするとしても、それは「音楽」のように、互いの存在を認め合いながらのことであって、だれかに指揮されて動くわけではない。
互いの存在を認め合いながら--ということについては、とてもおもしろいシーンがある。青年の最終的な恋人となる人妻との出会い。タンゴを踊るシーン。女の方が青年を挑発してくるのだが、それを受け止めながら肉体が互いに反応して動く。そこではセックスはおこなわれないが、セックスよりも濃密な「関係」がそこに生まれてくる。「一対一」が互いを育てるのである。
青年が求めているのは、あくまで「一対一」の関係である。
ヒトラー暗殺も、彼にとっては「一対一」のことなのである。ヒトラーを殺す。そして「自由」になる。それが青年の目的だ。
「誤算」があるとしたら「13分」ではなく、ヒトラーを暗殺できず、他人を殺してしまったことである。恋人だけではなく、家族など、他人を巻き込んでしまったことである。「一対一」でやろうとしても、社会が「一対一」を許さない。
これはヒトラー側からの、暗殺計画の取り調べについても言える。青年がひとりでやった、と主張しても、「ひとり」を認めない。背後に組織があるはずだ、と考え、問いつめる。「ナチス対共産党」という構図の中で暗殺計画をとらえようとする。ひとりでできるはずがないと考えるのではなく、そういうことをする人間が「ひとり」であることを許さない、という感じ。どんな人間も「組織」に属している。ナチスに反対する人間は共産党に属しているはず、と考える。
これはユダヤ人に対する態度そのものとも言える。「ひとり」を認めない。ユダヤ人という組織(?)は認めるが、個人は存在を認めない。「ひとり」が何をするかは問題ではない。「組織」が問題なのだ。「全体主義者」は他者をも「全体」として見てしまう。
ここに青年の「視点」とナチスの視点の違いがある。
ここから奇妙な歪みが起きる。
青年は暗殺計画をひとりで実行する。その「事実」を将校のひとりが認めてしまう。組織的犯罪ではなく、個人的犯罪であると、青年の言い分を認めてしまう。そうすると、こんどはナチスがその将校を追い詰めていく。具体的には描かれていないが、その将校は処刑されてしまう。彼の事実認識(青年の行動に対する認識は)間違っていない。将校が侵した間違いは、ナチス(ヒトラー)が求めていた「答え」を読み違えたことである。ヒトラーは、暗殺計画が「組織」によっておこなわれた、という答えを求めていた。ヒトラーに歯向かう人間を「組織」ごと壊滅したい。「組織」を壊滅したいのであって、「個人」を殺したいのではない。「組織」を破壊するのなら一回でできるが、「個人」を殺すためには「ひとりずつ」殺さなければならない。これは、きりがない。
ユダヤ人虐殺を思い浮かべるといい。ひとりずつ殺していては厖大な時間と人手がいる。ガス室で一気に殺してしまえば、ひとりひとりと向き合うこともない。「個人」の尊厳というものが「頭」から抜け落ちてしまう。「個人」を忘れてしまうと、ひとは平気で暴力的になれるということかもしれない。
映画に即して言い直すと、青年を取り調べるときナチスは拷問をするが、それは青年の肉体を痛めつけているのではない。青年を人間ではなく、「組織」と見ているから平気で暴力を振るえるのである。また青年は拷問が彼ひとりに対しておこなわれているときは耐えられるが、それが恋人という別のひとりに広がっていくことには耐えられず、自白をはじめる。すべてを「ひとり」で受け止めるために自白するのである。だれかに、自分のしたことを波及させない。
と、考えてくると。
この映画は、私たちに「個人」であれ、「ひとり」であれ、と呼びかけているのかもしれない。「組織」に身を隠すな。「ひとり」として行動しろ、と呼びかけているようにもみえる。日本のいまの政治状況を思うとき、特にそういう見方をしたくなる。「ひとり」が自由に集まり、また「ひとり」にもどっていく。そういう「闘い方」が必要な時代なのだと思う。
ストーリーに沿ったことばかり書いてしまったが。
青年が取り調べの過程で思い出す「故郷」の風景が美しい。そこで暮らすひとの暮らしが、酔っ払いを含めて美しい。人間的だ。特に一瞬描写された森と雨の風景、雨が木々のあいだを立ち上り白く空気が濁るシーンにうなってしまった。そういう美しい暮らしにまで侵入してきて人間を破壊するのが「全体主義」(一億なんとか主義)である。
(2015年10月18日、天神東宝4)
*
「映画館に行こう」にご参加下さい。
映画館で見た映画(いま映画館で見ることのできる映画)に限定したレビューのサイトです。
https://www.facebook.com/groups/1512173462358822/
 | インベージョン [Blu-ray] |
| クリエーター情報なし | |
| ワーナー・ホーム・ビデオ |