井坂洋子「回転」(「一個」5、2015年秋発行)
井坂洋子「回転」は、ことばが速い。軽快である。そして明確だ。
一連目は、銀行や病院の情景。そうと、すぐにわかる。銀行、病院と書いてあるし。で、二連目、突然「場」が変わるのだが、その「場」については説明されない。ただ、その「場」にあって、「あの場」である、銀行や病院を思い出した。いや、そうではなくて、「あの感じ」を思い出した。
一連目で「場」や「状況」を書きながら、二連目では「感じ」に変わっている。
「場」は「ソファー」によって引き継がれるが、ぱっと、捨てられ、「感情」に変わる。このスピードがとてもいい。
「感情」を前面に出しながら、三連目で、「場」にもどる。。
「焼きつくされた」と「遺族」が、そこが火葬場であることを告げる。そうだねえ、火葬場でも呼ぶねえ。「内野さまぁ」か。
そういう「状況/場」を銀行、病院と結びつけるのは、「不謹慎」かもしれないが、そういう「不謹慎」をしてしまうのが、人間である。「状況」にどっぷりとつかるだけが人間ではない。
この「裏切り」のスピードも、とても速い。速すぎて、「裏切り」に対して怒るよりも、なんだか「おかしい」気持ち、笑いたいような気持ちになる。「生きているなあ」という感じがするのである。
最終連の「感情の袋」は「涙(袋)」を思いおこさせる。「水位の上下」も「涙」を連想させる。でも、涙にくれるわけではない。泣いていればいいというものでもない。いや、泣く前にすることがある。
呼ばれれば、お骨を拾いに行かなければならない。「行くしかない/行くしかない」の繰り返しのなかに、ことばにならない「感じ」がある。「無」の感じがある。
銀行で呼ばれるときの「現実」そのもの感じ、それから火葬場で呼ばれるときの「無」の感じ。その激しい変化。そして、その中央で、どん、と居座っている「あの感じ」ということば。
うーん。
それらは、すべて「あの」と言い換えることができる。
「あの」というのは、知っている、かつて体験したことがある、ということを思い出すから、「あの」になる。
知っている、わかっている、でも、ことばにならない。ついつい「あの(とか、あれ、とか……)」という。そういうときの「あの」の「芽生え」のようなもの。
この詩は「あの」を書いたのだ。書いているのだ。「あの」を、井坂は発見したのだ。それが、この詩を「産んでいる」。形にしている。その「産む」スピードが速い、と言い換えることもできる。
速すぎて、「肉体」のどの部分が刺激されたのか、よくわからない。「あ、もう一度」と言ってみたい快感がある。もう一度「あの」に刺激されると、いってしまいそう……。そういうセックスの感じ。「ことばの肉体」がセックスしている気持ちになる。
あ、私の感想は、なんだか抽象的すぎるかなあ。「分節/未分節」ということばをつかわずに書くと、こうなってしまう。
谷内修三詩集「注釈」発売中
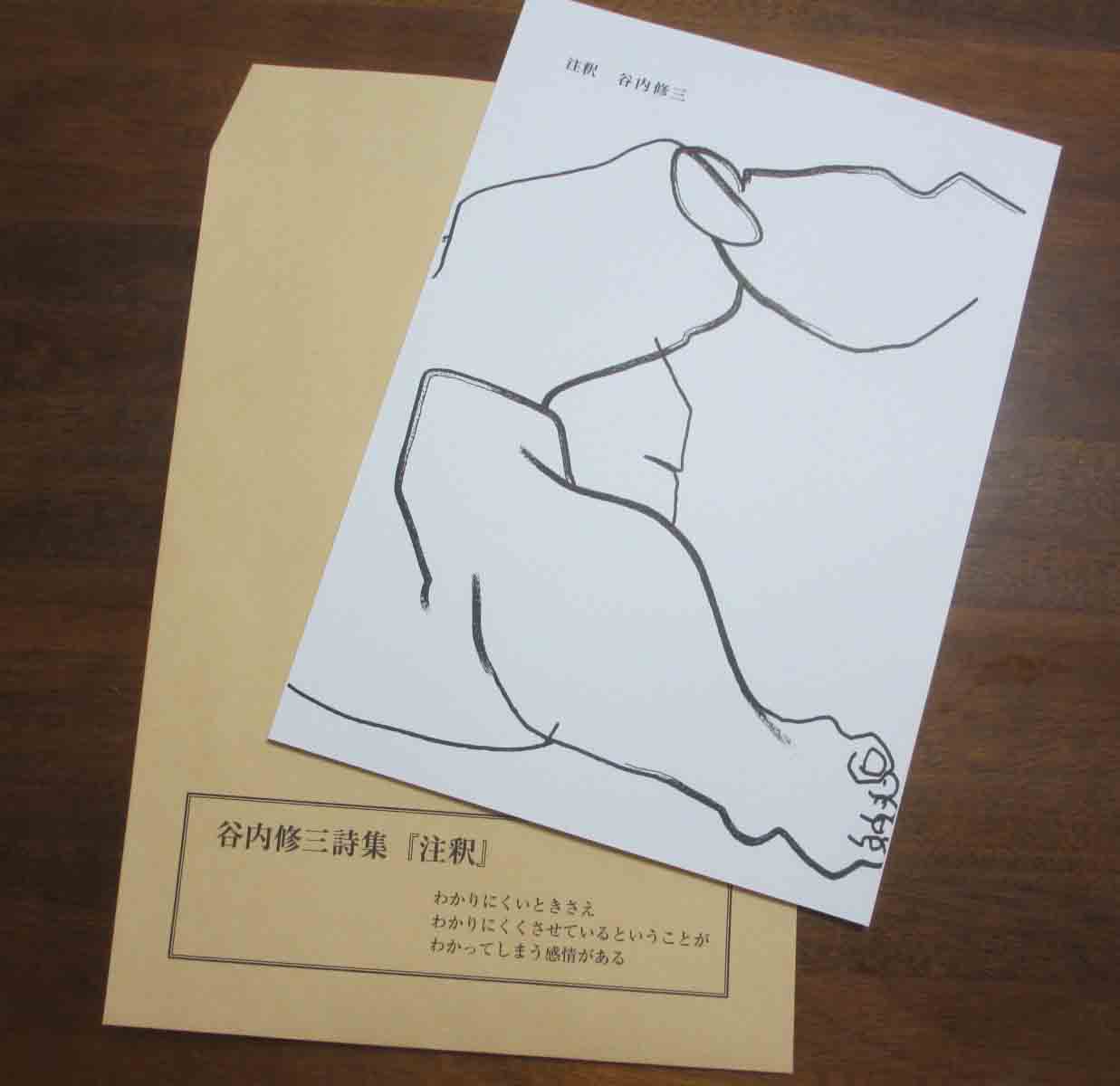
谷内修三詩集「注釈」(象形文字編集室)を発行しました。
2014年秋から2015年春にかけて書いた約300編から選んだ20篇。
「ことば」が主役の詩篇です。
B5版、50ページのムックタイプの詩集です。
非売品ですが、1000円(送料込み)で発売しています。
ご希望の方は、
panchan@mars.dti.ne.jp
へメールしてください。
なお、「谷川俊太郎の『こころ』を読む」(思潮社、1800円)と同時購入の場合は2000円(送料込)、「リッツォス詩選集――附:谷内修三 中井久夫の訳詩を読む」(作品社、4400円)と同時購入の場合は4500円(送料込)、上記2冊と詩集の場合は6000円(送料込)になります。
支払方法は、発送の際お知らせします。
井坂洋子「回転」は、ことばが速い。軽快である。そして明確だ。
40番のカードをおもちのお客さま5番の窓口におこしください
内野さまぁ
と銀行の窓口がよんでいる
内野さまぁ
と病院の受付け窓口がよんでいる
よばれるまでは
ソファーにすわって待っているあの感じ
焼きつくされれば遺族がよばれ
私が消失したことをたしかめることになり
社会はそうやって回転を保っている
感情の袋、袋のなかの水位の上下動も関係なく
よばれれば立ちあがり窓口まで行くしかない
行くしかない
一連目は、銀行や病院の情景。そうと、すぐにわかる。銀行、病院と書いてあるし。で、二連目、突然「場」が変わるのだが、その「場」については説明されない。ただ、その「場」にあって、「あの場」である、銀行や病院を思い出した。いや、そうではなくて、「あの感じ」を思い出した。
一連目で「場」や「状況」を書きながら、二連目では「感じ」に変わっている。
「場」は「ソファー」によって引き継がれるが、ぱっと、捨てられ、「感情」に変わる。このスピードがとてもいい。
「感情」を前面に出しながら、三連目で、「場」にもどる。。
「焼きつくされた」と「遺族」が、そこが火葬場であることを告げる。そうだねえ、火葬場でも呼ぶねえ。「内野さまぁ」か。
そういう「状況/場」を銀行、病院と結びつけるのは、「不謹慎」かもしれないが、そういう「不謹慎」をしてしまうのが、人間である。「状況」にどっぷりとつかるだけが人間ではない。
この「裏切り」のスピードも、とても速い。速すぎて、「裏切り」に対して怒るよりも、なんだか「おかしい」気持ち、笑いたいような気持ちになる。「生きているなあ」という感じがするのである。
最終連の「感情の袋」は「涙(袋)」を思いおこさせる。「水位の上下」も「涙」を連想させる。でも、涙にくれるわけではない。泣いていればいいというものでもない。いや、泣く前にすることがある。
呼ばれれば、お骨を拾いに行かなければならない。「行くしかない/行くしかない」の繰り返しのなかに、ことばにならない「感じ」がある。「無」の感じがある。
銀行で呼ばれるときの「現実」そのもの感じ、それから火葬場で呼ばれるときの「無」の感じ。その激しい変化。そして、その中央で、どん、と居座っている「あの感じ」ということば。
うーん。
それらは、すべて「あの」と言い換えることができる。
「あの」というのは、知っている、かつて体験したことがある、ということを思い出すから、「あの」になる。
知っている、わかっている、でも、ことばにならない。ついつい「あの(とか、あれ、とか……)」という。そういうときの「あの」の「芽生え」のようなもの。
この詩は「あの」を書いたのだ。書いているのだ。「あの」を、井坂は発見したのだ。それが、この詩を「産んでいる」。形にしている。その「産む」スピードが速い、と言い換えることもできる。
速すぎて、「肉体」のどの部分が刺激されたのか、よくわからない。「あ、もう一度」と言ってみたい快感がある。もう一度「あの」に刺激されると、いってしまいそう……。そういうセックスの感じ。「ことばの肉体」がセックスしている気持ちになる。
あ、私の感想は、なんだか抽象的すぎるかなあ。「分節/未分節」ということばをつかわずに書くと、こうなってしまう。
 | 詩はあなたの隣にいる (単行本) |
| 井坂 洋子 | |
| 筑摩書房 |
谷内修三詩集「注釈」発売中
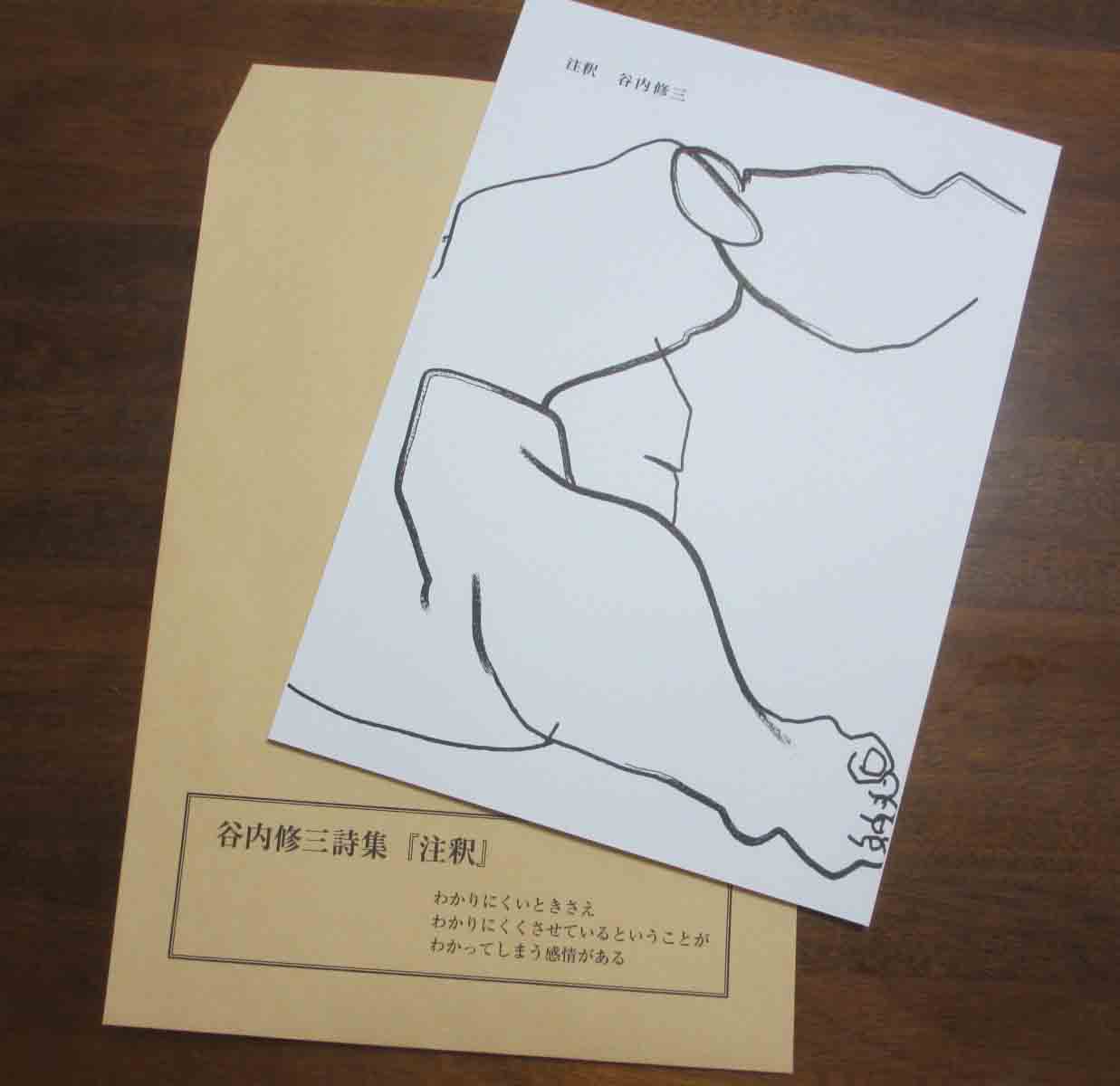
谷内修三詩集「注釈」(象形文字編集室)を発行しました。
2014年秋から2015年春にかけて書いた約300編から選んだ20篇。
「ことば」が主役の詩篇です。
B5版、50ページのムックタイプの詩集です。
非売品ですが、1000円(送料込み)で発売しています。
ご希望の方は、
panchan@mars.dti.ne.jp
へメールしてください。
なお、「谷川俊太郎の『こころ』を読む」(思潮社、1800円)と同時購入の場合は2000円(送料込)、「リッツォス詩選集――附:谷内修三 中井久夫の訳詩を読む」(作品社、4400円)と同時購入の場合は4500円(送料込)、上記2冊と詩集の場合は6000円(送料込)になります。
支払方法は、発送の際お知らせします。



















