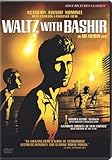海埜今日子『セボネキコウ』(2)(砂子屋書房、2010年01月10日発行)
ことばは何と出会うのか。--きのう書いたことは、もうすっかり忘れて、また海埜今日子『セボネキコウ』を読みながら、ふと、そんなことばがわいて出てくる。ことばが発せられるとき、ことばは「もの」と出会っているのか、「意味」と出会っているのか。ことばは、ことばと出会っているのかもしれない。ことばはことばと出会いたくて動いていくのかもしれない。
「まつよいまちぐさ」。このタイトル。「まつよいぐさ」「よいまちぐさ」。ふたつのことばが出会っている。それは「待宵草」「宵待草」かもしれない。そのふたつがどう違うかわからない。同じものなのか。それとも似ているだけのものなのか。同じものなら、なぜ、違った呼び方をするのか……。たとえ同じであっても、違ったふうに呼んでみたい--そういう欲望がことばを生み出すのか。でも、なぜ、違ったふうに呼んでみたいのだろう。
わからないけれど、なぜか、その違ったふうに呼んでみたいという欲望と、詩の欲望は似ていると思う。人間が体験することは、どれもこれもというか、だれもかれも似ている。似ているけれど、それを「同じ」にはしたくない。「同じ」ものにしないためには、違った「名前」が必要だ。その「名前」のようなものが詩なのか。
だが、まったく新しいことばでは、同じだけれど違うということにはならない。どうやって、同じだけれど違う、違うけれど同じという世界へ入っていけるだろうか。
海埜は、ことばとことばを出会わせること、その出会いのなかの、なにか「自分を忘れてしまう瞬間」のようなものをつかみとって、そこからことばを動かしている。そういう印象がある。
「自分を忘れてしまう瞬間」と書いたけれど、これは、つまり……。たとえば、あなたが誰かと出会う。その瞬間、「私は誰それである」という意識が一瞬消えて、「あれ、あれは誰?」と思う瞬間のようなものである。意識が「他者」に集中する。その瞬間、「私は誰それである」という思いは、すこし引き下がっている。そして、それが誰であるかわかったとき、「私」が「私の奥」から新しく生まれてくる。特に、それが恋が生まれる瞬間には。知らない相手--知らないのだが、その知らない相手に対して、いままでの私が一瞬、消え、この人が好きという気持ちをもって新しく生まれてくる。
そういう「忘我(ちょっと大げさかもしれないけれど)」と「私の誕生」--そういうものが、海埜のことばのなかにはある。海埜の詩のなかでは、ことばがことばと出会い、そこからことばの恋愛がはじまり、ことばの「肉体関係」がひろがり、新しいことばを生み出しもする。
海埜の意識がどうであれ、海埜のことばを読むと、私のなかで一瞬「忘我」のときが生じる、と言いなおせば正確になるのか。
ととえばいま引用した部分の、「いわをもとめるずれのまにまに」は「違和を求めずれの間に間に」ということかもしれない。「ずれ」は「間」があってはじめて生まれるものであるということ、そしてその「ずれ」というのは「違和感」に通じることを思うと、そんなふうに理解すべきなのかもしれないが、私の意識というか、ことばはいま書いたことがらへ直線的につながらない。そのまえに「げきついされた(撃墜された?)」ということばがあるせいだろう。「岩を求める」と読んでしまう。さらには「岩を求めずれる間に間に」と読んでしまう。「いわ」ということばが、「違和」と「岩」を出会わせる。「いわ」という音のなかで「違和」と「岩」が出会い「求めるずれ」が「求めずれる」と動いていく。
そして。
ここから先に書くことは、きっと海埜には予想外のことだろうと思うのだが。
「違和」が「岩」にかわり、「求めるずれ」が「求めずれる」、その「間に間に」とことばが動いていくとき、私の「肉体」は「岩」を「男根」と読み替えて、これらの行をセックス描写として味わおうとするのだ。
2行目の「ひろげたむね」が「肉体の交合」、セックスを感じさせ、それが「いわ」を「違和」であると同時に「岩(巨大な、固い、男根)」にしてしまう。
「撃墜された」のは「あなた(男)」なのか「わたし(女)」なのか、それとも両方なのか--それは、まあ、あとからどうとでも説明がつく。恋というものは、どうとでも説明できるものである。「たしょうのえん」は「他生の縁」であり「多少の縁」でもある。少ない縁なら、より多くの縁にしようと、ひとは一回かぎりの「縁」をセックスによって濃密に、そして繰り返される縁にしようとするのかもしれない。
セックス(あるいは恋愛)というものは「ずれ」からはじまる。最初から完全に重なり合うわけではない。「男」「女」という差異があって、「ずれ」があって、出会うということ--合致の瞬間があり、その出会いがさらに、いままで意識してこなかった「ずれ」をみつめさせることになる。「ずれ」の増幅。そして、その「ずれ」のなかで、あれこれ動き回り、何かを一致させる。「肉体」をというより「快感」を。自分から出てしまって、まったく別人に生まれ変わる--そのエクスタシーを一致させようとする。
--こんなことを、海埜は考えていないかもしれない。しかし、作者が考えていないことを考えさせる、感じさせてしまうものが、詩なのである。(あるいは文学なのである。)余分なことを考えさせる、感じさせるものが詩なのである。
だいたい、詩の出発というか、詩を書くというのも、現実の「必要」からはみ出すものがあってのことである。現実にはなんの役にも立たないこと、感じなくていいこと、考えなくていいことを、感じ、考えてしまった--だから、それをことばにする。それが詩である。それを読めば、読者の方だって、余分なことを考える。余分なことというのは、どうしたって、きわめて個人的なことである。
為政者(権力者?)が文学とかセックスとかを制限しようとするのは、ひとりひとりが、余分なことを考え、感じることに夢中になると、全体の収拾がつかなくなるからだね。--まあ、これは余分なことだけれど。
ここに書かれていることは何だろう。セックスの描写だろうか。私はそう思って読んでしまうが、そのとき、ことばは人間の行動というか、肉体の動き、感情の動きを正確に(?)描写しようとしているのだろうか。いや、海埜は、正確に描写しようとする意図をもって、ことばを動かしているのだろうか。別な言い方をすると、海埜のことばは、ここでは「もの」(もの、といっても、男女の肉体、男女の感情のことだけれど)と重なろうとしているのだろうか。海埜のことばは「もの」とセックスしているのだろうか。
私には、そんなふうには感じられない。
ことばはことばと出会いたがって動いている。ことばは、そこに描かれる対象としてのセックス行為とセックスしようとしていない。ことばは、まだ、ここに存在しないことばとセックスしたがっている。そして、そのために男と女にセックスをさせている。男女のセックスがあり、それがことばで描写されるのではなく、ことばがことばとセックスしたくて、人間の肉体を、その出会いのために(その描写のために)利用している。
そんなことはありえない。現実にはありえない。現実に、ことばがことばを欲情し、そのために肉体を従事させるというようなことはありえない。ことばのために、人間が、そのことばに合うようにセックスするなんてことはありえない--といえばありえないことなのだけれど、そういうありえないことが、ここでは起きている。
詩の世界では、そういうことが起きるのだ。
ことばが現実を整える--ということが起きるのだ。ことばが肉体をととのえるということが、起きうるのだ。
ことばはことばを求めて、かってに動いていく。そのことを、私は特に、
という行に感じた。
何、これ? 「もっけい」で何? 何かの誤植?
わかります?
私はまったくわからず、久々に辞書までひっぱりだしてしまった。知らないことばに出会ったとき、私は、まあ、読んでいるうちにきっとわかる。大事なことばなら、きっとそれは何度か別なことばに言いなおされるはずだから、そのときわかればいい--そう考えて、辞書などひかない。辞書は、もっています、というだけのためにしかおいていない。その辞書を引いてみた。
「黙契」。
どうやら、このことばらしい。
私はこのことばをはじめて知ったが、海埜は(あるいは海埜のことばは)、「もっけい」を知っていた。そして、そのことばと出会いたくて蠢いて蠢いて、まさぐってまさぐってまさぐって、そのことばを詩のなかに引き出したのだ。
そうとしか考えられない。なぜなら--ねえ、セックスの最中に「肉体」が「黙契」なんてことばを思いつく? 思いつかないよ。「あ、」とか「う、」とか、ことば以前の「こえ」でせいいっぱいで、そんなややこしいことばをいう暇などない。
でも、ことばは、そういことばを求めるのだ。まるで、新しい体位を試みるように、その新しい体位によって、何か、今まで以上のことが起きるかもしれないなんて思いながら。
ことばに「思い」なんてない、というかもしれないけれど、ほら確か、北川透はことばにも肉体があり、セックスもする。ことばは人間がする、あるいは人間だけがしないあらゆることをする、と書いていた。
「さきほこり」は「咲き誇り」なら「花」、「裂き(割き)誇り」なら「男根」。「あなた あな」の「あな」は「あな(た)」と言おうとしたのか、それとも「穴」なのか。「いわ」は「違和」から「岩」に、そして最後は「祝って」と祝福にかわる。祝祭にかわる。
きのう、たしか「船酔い」ということばをつかったが、海埜のことばを旅すると「船酔い」はいつのまにか、「ことば酔い」にかわる。それは、強烈である。だからついつい酔っぱらって、大酒飲みのように、私は「本性」をさらけだしてしまう。
「見苦しい」感想かもしれないけれど--酔ってしまったら、まあ、酔いにまかせて書いてしまうしかない。嘔吐してしまうしかない。
ことばは何と出会うのか。--きのう書いたことは、もうすっかり忘れて、また海埜今日子『セボネキコウ』を読みながら、ふと、そんなことばがわいて出てくる。ことばが発せられるとき、ことばは「もの」と出会っているのか、「意味」と出会っているのか。ことばは、ことばと出会っているのかもしれない。ことばはことばと出会いたくて動いていくのかもしれない。
「まつよいまちぐさ」。このタイトル。「まつよいぐさ」「よいまちぐさ」。ふたつのことばが出会っている。それは「待宵草」「宵待草」かもしれない。そのふたつがどう違うかわからない。同じものなのか。それとも似ているだけのものなのか。同じものなら、なぜ、違った呼び方をするのか……。たとえ同じであっても、違ったふうに呼んでみたい--そういう欲望がことばを生み出すのか。でも、なぜ、違ったふうに呼んでみたいのだろう。
わからないけれど、なぜか、その違ったふうに呼んでみたいという欲望と、詩の欲望は似ていると思う。人間が体験することは、どれもこれもというか、だれもかれも似ている。似ているけれど、それを「同じ」にはしたくない。「同じ」ものにしないためには、違った「名前」が必要だ。その「名前」のようなものが詩なのか。
だが、まったく新しいことばでは、同じだけれど違うということにはならない。どうやって、同じだけれど違う、違うけれど同じという世界へ入っていけるだろうか。
海埜は、ことばとことばを出会わせること、その出会いのなかの、なにか「自分を忘れてしまう瞬間」のようなものをつかみとって、そこからことばを動かしている。そういう印象がある。
「自分を忘れてしまう瞬間」と書いたけれど、これは、つまり……。たとえば、あなたが誰かと出会う。その瞬間、「私は誰それである」という意識が一瞬消えて、「あれ、あれは誰?」と思う瞬間のようなものである。意識が「他者」に集中する。その瞬間、「私は誰それである」という思いは、すこし引き下がっている。そして、それが誰であるかわかったとき、「私」が「私の奥」から新しく生まれてくる。特に、それが恋が生まれる瞬間には。知らない相手--知らないのだが、その知らない相手に対して、いままでの私が一瞬、消え、この人が好きという気持ちをもって新しく生まれてくる。
そういう「忘我(ちょっと大げさかもしれないけれど)」と「私の誕生」--そういうものが、海埜のことばのなかにはある。海埜の詩のなかでは、ことばがことばと出会い、そこからことばの恋愛がはじまり、ことばの「肉体関係」がひろがり、新しいことばを生み出しもする。
よるをうってはきりきりと
ひろげたむねのかんじょうから
ああ あなたです
となりのようなまちをふきこむ
げきついされた たしょうのえん
いわをもとめるずれのまにまに
あたしたち ひきとめようとしていたという
あしたのやくそくはここでこぼれた
海埜の意識がどうであれ、海埜のことばを読むと、私のなかで一瞬「忘我」のときが生じる、と言いなおせば正確になるのか。
ととえばいま引用した部分の、「いわをもとめるずれのまにまに」は「違和を求めずれの間に間に」ということかもしれない。「ずれ」は「間」があってはじめて生まれるものであるということ、そしてその「ずれ」というのは「違和感」に通じることを思うと、そんなふうに理解すべきなのかもしれないが、私の意識というか、ことばはいま書いたことがらへ直線的につながらない。そのまえに「げきついされた(撃墜された?)」ということばがあるせいだろう。「岩を求める」と読んでしまう。さらには「岩を求めずれる間に間に」と読んでしまう。「いわ」ということばが、「違和」と「岩」を出会わせる。「いわ」という音のなかで「違和」と「岩」が出会い「求めるずれ」が「求めずれる」と動いていく。
そして。
ここから先に書くことは、きっと海埜には予想外のことだろうと思うのだが。
「違和」が「岩」にかわり、「求めるずれ」が「求めずれる」、その「間に間に」とことばが動いていくとき、私の「肉体」は「岩」を「男根」と読み替えて、これらの行をセックス描写として味わおうとするのだ。
2行目の「ひろげたむね」が「肉体の交合」、セックスを感じさせ、それが「いわ」を「違和」であると同時に「岩(巨大な、固い、男根)」にしてしまう。
「撃墜された」のは「あなた(男)」なのか「わたし(女)」なのか、それとも両方なのか--それは、まあ、あとからどうとでも説明がつく。恋というものは、どうとでも説明できるものである。「たしょうのえん」は「他生の縁」であり「多少の縁」でもある。少ない縁なら、より多くの縁にしようと、ひとは一回かぎりの「縁」をセックスによって濃密に、そして繰り返される縁にしようとするのかもしれない。
セックス(あるいは恋愛)というものは「ずれ」からはじまる。最初から完全に重なり合うわけではない。「男」「女」という差異があって、「ずれ」があって、出会うということ--合致の瞬間があり、その出会いがさらに、いままで意識してこなかった「ずれ」をみつめさせることになる。「ずれ」の増幅。そして、その「ずれ」のなかで、あれこれ動き回り、何かを一致させる。「肉体」をというより「快感」を。自分から出てしまって、まったく別人に生まれ変わる--そのエクスタシーを一致させようとする。
--こんなことを、海埜は考えていないかもしれない。しかし、作者が考えていないことを考えさせる、感じさせてしまうものが、詩なのである。(あるいは文学なのである。)余分なことを考えさせる、感じさせるものが詩なのである。
だいたい、詩の出発というか、詩を書くというのも、現実の「必要」からはみ出すものがあってのことである。現実にはなんの役にも立たないこと、感じなくていいこと、考えなくていいことを、感じ、考えてしまった--だから、それをことばにする。それが詩である。それを読めば、読者の方だって、余分なことを考える。余分なことというのは、どうしたって、きわめて個人的なことである。
為政者(権力者?)が文学とかセックスとかを制限しようとするのは、ひとりひとりが、余分なことを考え、感じることに夢中になると、全体の収拾がつかなくなるからだね。--まあ、これは余分なことだけれど。
ふさいだ ひらいた さいくるです
そでのふれあうおわりをひもとき
あたしたち はじまりをもとめてよるをおう
きょうのかんじょうはここでもがく
いわをもくだく ひとよかぎりのあいかたです
ああ あなた あなたがさきます
くさびたち じかんをとおしてかいわをまつ
ひとこともふれられないぶん かぜをかぐ
ひとりでにおちないぶんだけ もっけいですから
いわかんをぎりぎりまでといつめたかった
まつよいぐさ いちめんでけよこたえて
よいまちがお あわててなんどもふりかえって
ここに書かれていることは何だろう。セックスの描写だろうか。私はそう思って読んでしまうが、そのとき、ことばは人間の行動というか、肉体の動き、感情の動きを正確に(?)描写しようとしているのだろうか。いや、海埜は、正確に描写しようとする意図をもって、ことばを動かしているのだろうか。別な言い方をすると、海埜のことばは、ここでは「もの」(もの、といっても、男女の肉体、男女の感情のことだけれど)と重なろうとしているのだろうか。海埜のことばは「もの」とセックスしているのだろうか。
私には、そんなふうには感じられない。
ことばはことばと出会いたがって動いている。ことばは、そこに描かれる対象としてのセックス行為とセックスしようとしていない。ことばは、まだ、ここに存在しないことばとセックスしたがっている。そして、そのために男と女にセックスをさせている。男女のセックスがあり、それがことばで描写されるのではなく、ことばがことばとセックスしたくて、人間の肉体を、その出会いのために(その描写のために)利用している。
そんなことはありえない。現実にはありえない。現実に、ことばがことばを欲情し、そのために肉体を従事させるというようなことはありえない。ことばのために、人間が、そのことばに合うようにセックスするなんてことはありえない--といえばありえないことなのだけれど、そういうありえないことが、ここでは起きている。
詩の世界では、そういうことが起きるのだ。
ことばが現実を整える--ということが起きるのだ。ことばが肉体をととのえるということが、起きうるのだ。
ことばはことばを求めて、かってに動いていく。そのことを、私は特に、
ひとりでにおちないぶんだけ もっけいですから
という行に感じた。
何、これ? 「もっけい」で何? 何かの誤植?
わかります?
私はまったくわからず、久々に辞書までひっぱりだしてしまった。知らないことばに出会ったとき、私は、まあ、読んでいるうちにきっとわかる。大事なことばなら、きっとそれは何度か別なことばに言いなおされるはずだから、そのときわかればいい--そう考えて、辞書などひかない。辞書は、もっています、というだけのためにしかおいていない。その辞書を引いてみた。
「黙契」。
どうやら、このことばらしい。
私はこのことばをはじめて知ったが、海埜は(あるいは海埜のことばは)、「もっけい」を知っていた。そして、そのことばと出会いたくて蠢いて蠢いて、まさぐってまさぐってまさぐって、そのことばを詩のなかに引き出したのだ。
そうとしか考えられない。なぜなら--ねえ、セックスの最中に「肉体」が「黙契」なんてことばを思いつく? 思いつかないよ。「あ、」とか「う、」とか、ことば以前の「こえ」でせいいっぱいで、そんなややこしいことばをいう暇などない。
でも、ことばは、そういことばを求めるのだ。まるで、新しい体位を試みるように、その新しい体位によって、何か、今まで以上のことが起きるかもしれないなんて思いながら。
ことばに「思い」なんてない、というかもしれないけれど、ほら確か、北川透はことばにも肉体があり、セックスもする。ことばは人間がする、あるいは人間だけがしないあらゆることをする、と書いていた。
ひとばんまじかにさきほこり ふるえるばめん
ああ かきけしたくない あなた あな
ますますかんじょう いわってやまないくさでした
「さきほこり」は「咲き誇り」なら「花」、「裂き(割き)誇り」なら「男根」。「あなた あな」の「あな」は「あな(た)」と言おうとしたのか、それとも「穴」なのか。「いわ」は「違和」から「岩」に、そして最後は「祝って」と祝福にかわる。祝祭にかわる。
きのう、たしか「船酔い」ということばをつかったが、海埜のことばを旅すると「船酔い」はいつのまにか、「ことば酔い」にかわる。それは、強烈である。だからついつい酔っぱらって、大酒飲みのように、私は「本性」をさらけだしてしまう。
「見苦しい」感想かもしれないけれど--酔ってしまったら、まあ、酔いにまかせて書いてしまうしかない。嘔吐してしまうしかない。
| 共振―海埜今日子第一詩集海埜 今日子ダブリュネットこのアイテムの詳細を見る |