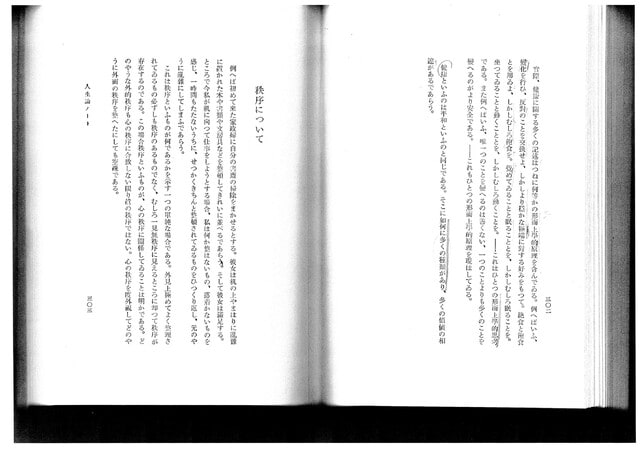「現代詩手帖」12月号(8)(思潮社、2022年12月1日発行)
山田兼二「病室のクリスマス・キャロル」。山田は、つい先日死んだ。この詩を書いたときは、生きている。あたりまえだが。入院中に書いた詩だ。
その最終連。
職員が数人 開け放した扉の外を往来しているが
だれも近づいてこない 呼ぶこともできない
どこからか鐘の音が聞こえてくる
クリスマス・キャロルが遠ざかって
一年が去っていく 遠く 遠く 明後日の方へ
「クリスマス・キャロルが遠ざかって」行く、と詩を終わらせることもできる。ふつうは、そう終わるかもしれない。しかし、山田は
一年が去っていく 遠く 遠く 明後日の方へ
と書き足している。この一行が、非常に重い。「明後日の方」と、時間的に「未来」であることが、さらに重い。
山田は、この一行を、力をふりしぼって、「わざわざ」書いたのである。この「わざわざ」書かれた一行のために、詩はある。この一行を受け止めるために、詩が必要だったのだ。
河津聖恵「鳥の悲しみ-雪中錦鶏図」。
一羽の鳥の悲しみが雪を柔らかに溶かしている
それとも 溶けかけた世界をふたたび凍りつかせているところか
「それとも……か」。これがこの詩のキーワードだ。「それとれ……か」は疑問であり、断定の回避である。あるいは保留というべきか。しかし、ほんとうか。逆に、それはより強い「断定」へ向かうための助走であるとも言うことができる。
分かるのは
いまもたった一羽の悲しみが秘かに世界を溶かしていること
あるいは凍りつかせていること
そして、その「断定」とは、何かを「固定」することではない。「分かる」とは、「あるいは」を発見するためには、「回避」、あるいは「迂回」が必要だということである。「迂回」することが、詩なのである。「迂回」の中に詩があるということである。
須永紀子「誕生」。
書かれていたかもしれない
「人間とこの世界についてのまだ語られていないこと
掬いとって並べなおす
「かもしれない」が「迂回」である。それは「まだ語られていない」という「不在」への接近である。迂回するとき、強く認識される「不在」。「不在の認識」が詩であるか。そうだと仮定して。
一文が次行を誘い
水平線をこえて
続いていくと思われた
私は、この「思われた」という表現が大嫌いである。なぜ「思った」ではいけないのか。「思われた」という「迂回」は、「わざと」か「わざわざ」か。たぶん「無意識」だろう。須永の癖(習慣)かもしれない。主観を押しつけないという、押しつけがましさ。このあいまいさは、
「人間とこの世界についてのまだ語られていないこと
の鍵括弧が閉ざされていないところにもあらわれている。拒否を拒んだ、「思われた」というあいまいな主観の押しつけ。と、書き続けてくると、「わざと」だな、と「思われてくる」。
ね、須永さん、いやでしょ、こんなふうに「思われてくる」なんて、書かれたら。
私は「わざと」、「わざわざ」、須永がいやがることを書いている。意識的に、である。この私の「意識的」な行為には、もちん詩は存在しない。「わざと」「わざわざ」だけが存在する。
**********************************************************************
★「詩はどこにあるか」オンライン講座★
メール、skypeを使っての「現代詩オンライン講座」です。
メール(宛て先=yachisyuso@gmail.com)で作品を送ってください。
詩への感想、推敲のヒントをメール、ネット会議でお伝えします。
★メール講座★
随時受け付け。
週1篇、月4篇以内。
料金は1篇(40字×20行以内、1000円)
(20行を超える場合は、40行まで2000円、60行まで3000円、20行ごとに1000円追加)
1週間以内に、講評を返信します。
講評後の、質問などのやりとりは、1回につき500円。
★ネット会議講座(skypeかgooglemeet使用)★
随時受け付け。ただし、予約制。
週1篇40行以内、月4篇以内。
1回30分、1000円。
メール送信の際、対話希望日、希望時間をお書きください。折り返し、対話可能日をお知らせします。
費用は月末に 1か月分を指定口座(返信の際、お知らせします)に振り込んでください。
作品は、A判サイズのワード文書でお送りください。
少なくとも月1篇は送信してください。
お申し込み・問い合わせは、
yachisyuso@gmail.com
また朝日カルチャーセンター福岡でも、講座を開いています。
毎月第1、第3月曜日13時-14時30分。
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1
電話 092-431-7751 / FAX 092-412-8571
*
オンデマンドで以下の本を発売中です。
(1)詩集『誤読』100ページ。1500円(送料別)
嵯峨信之の詩集『時刻表』を批評するという形式で詩を書いています。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072512
(2)評論『中井久夫訳「カヴァフィス全詩集」を読む』396ページ。2500円(送料別)
読売文学賞(翻訳)受賞の中井の訳の魅力を、全編にわたって紹介。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073009
(3)評論『高橋睦郎「つい昨日のこと」を読む』314ページ。2500円(送料別)
2018年の話題の詩集の全編を批評しています。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168074804
(4)評論『ことばと沈黙、沈黙と音楽』190ページ。2000円(送料別)
『聴くと聞こえる』についての批評をまとめたものです。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073455
(5)評論『天皇の悲鳴』72ページ。1000円(送料別)
2016年の「象徴としての務め」メッセージにこめられた天皇の真意と、安倍政権の攻防を描く。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072977
問い合わせ先 yachisyuso@gmail.com