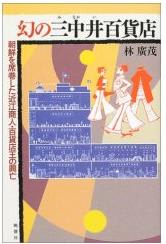
「幻の三中井百貨店」なる日本の書物の韓国語版を取り上げた
書評記事を読んだ。
その中で、韓国社会でよく見られる「日本隠し」の実態について
辛らつに指摘した部分に出くわした。
その書物の本題でもないし、ことあらためて感心させられるような
斬新な分析でもないが、「ヲタク」にとっては妙に印象に
残る言葉だった。
現代韓国社会の諸相を読み解く際の一つのキーワードが、この
「日本隠し」なのかもしれないと思った。
関連書評記事の一部を翻訳練習し記録する。なお、紙面の都合で
韓国語原文の引用は省いている。
・・・・・・・・・・
■ <本> 韓国の百貨店は「メイド・イン・ジャパン」
(ハンギョレ新聞 5月3日)
△「ミナカイ百貨店」(韓国版題名)/15000ウォン
一時期、「韓流」の話題で持ちきりだったが、その「韓流」の本場とも
言える当の韓国は、事実上、日本風、つまり「日流」が支配する
国なのかもしれない。アニメから文具のデザイン、映画、小説に
いたるまで韓国文化に染み込んだ「日流」は、韓国人が考えるより
はるかに広く深いものなのかもしれない。テレビの娯楽番組で
日本の番組の影響を受けていないものがどれくらいあるだろうか?
むしろ、大衆文化の分野は目に付きやすい方なのかもしれない。
1991年、韓国のCJ(第一製糖)は日本のライオン社が開発した
コンパクト洗剤「トップ」を「ビート」という商品名で韓国で発売し
シェア1位を獲得した。1993年、朝鮮ビールはサッポロビールの
黒ビール製造技術をプラントとともに導入し「ハイト」を誕生させた。
もともと朝鮮ビール自体がサッポロビールの前身である大日本
麦酒を引き継いだ会社だ。現代自動車の高級車「グレンジャー」は
三菱自動車の「デボネア」を車名だけ変え韓国で生産販売したもの
だったが、現在、ほとんど同じ技術で後続モデルの「XG」を生産
している。また、ロッテ百貨店は日本の業界最大手、高島屋の
ノウハウを開店から運営にいたるまで、そっくりそのまま導入した。
現代百貨店は、福岡の大丸百貨店の全面的な協力を取り付け
会社を立ち上げた。新世界百貨店は1980年代から三越百貨店の
全面的な運営指導を受けてきたが、現在も使っているソウル店
旧館は1930年に建設された三越京城店の建物だ。
本書「三中井百貨店」(論衡社刊)は、韓国企業がこのように
日本の技術やノウハウをそっくりそのまま導入しながら、日本との
関係を隠したまま、まるで仮面でも被るように韓国のものだと
宣伝している「日本隠し」の事例を数多く紹介している。
本書は、元々、マーケッティング・コンサルタントとして韓国の
有力企業数十社の諮問を受けアドバイスしてきた同志社大学の
ハヤシ・ヒロシゲ教授(ビジネス研究学科)が、書名に掲げた
三中井百貨店の誕生と没落の歴史をマーケッティング研究家の
視点で探り分析したものだ。
今では韓国人はもとより日本人の記憶からも完全に消え去って
しまった三中井百貨店の歴史は、日本の滋賀県の小さな呉服
雑貨店に始まる。第2次日韓協約により朝鮮が事実上、日本の
植民地に転落した1905年、大邱に進出した後、第2次
大戦で日本が敗北するまで三越などを抑え満州や中国にまで
支店を持つ朝鮮最大の百貨店にまで急成長を遂げた。
「社員は朝鮮・満州をあわせ4千人を超え、売り上げ総額は
子会社も含め年間1億円に上っていた。現在の貨幣価値に
換算すれば5千億円にあたる額で、当時、京都の5大百貨店の
2年分の売り上げに匹敵する規模だった」(本書より)。店舗数は
朝鮮に12店、満州・中国にそれぞれ3店ずつの計18店。解放前
からソウルに住んでいる老人なら「ミナカイ」の名が今でも記憶に
残っているに違いない。
十分な資金力もなかった日本の地方出身の4兄弟の商人が
いかにして朝鮮最大の百貨店を築き上げたのか?そして、
しのぎを削った三越や高島屋など他のライバルたちは生き残った
のに、なぜ三中井は永遠にその姿を消したのか?本書は
まさにその経緯を追跡する。著者は、2002年の3月以来、日韓を
又にかけ長期間にわたる現場取材を積み重ねた。
三中井が没落した直接的な原因は第2次大戦での日本の敗北に
よる組織の瓦解と資産没収であった。他の百貨店とは異なり
三中井は事業の本拠地を朝鮮に置いていた。三中井が再起でき
なかったのは、そうした理由とともに後継者の判断ミスが決定的な
要因だったと著者は分析する。しかし、三中井のノウハウの多くが
現代の韓国の百貨店に引き継がれているというのが著者の
考えだ。
-以下省略-
(終わり)![]() 参加カテゴリ:地域情報(アジア)/語学・英会話
参加カテゴリ:地域情報(アジア)/語学・英会話





















