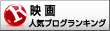三井葉子『人文』(3)(編集工房ノア、2010年06月01日発行)
ことばの鍛え方、ことばを自分自身のものにする方法にはいろいろあるだろう。論理的な文章をたくさん読む、感覚の鋭い表現に出会うたびにそれをメモして自分のものになるまでくりかえす、外国語を訳すということをやってみる--ひとは、それぞれに努力をすると思う。
三井の場合は、どうか。
いろいろな努力をしているのだろうけれど、私には、その努力のあとが見えない。
三井が努力をしていないというのではない。努力の仕方が、まるで山を歩いて、そこに自然に道ができるような努力の仕方なのである。山を歩くといっても、自分で新しい道をつくって歩くというのではない。だれかが歩いた跡がある。草が倒れている。だから、その上を歩いて行ってみる。そして、それは新しい道をつくるという「自覚」(意識)がつくるのではなく、あ、こっちの方がみんなが通りやすい。みんなが通っている、だから、そのひとになじんだ、ひとにやさしい道を歩く。--そういう感じだ。
もし三井に、努力というものがあるとすれば、それはひとに険しい道を避ける、ということだろうと思う。新しい独自の道ではなく、だれでもが通った道、その道をていねいに歩く。裸足で、足裏で、その道を踏みしめた人々の足裏を感じるように。ときには、足裏だけではなく、あ、ここのへこみはどうしたのだろう、としゃがんで手の平でふれてみる。耳を押し当てて、音が聞こえないか聞いてみる。ときには、残された小石を口に含んでなめてみる。そうやって、道の「歴史」を「肉体」のなかに取り込む。「肉体」に取り込んでいいものだけを、ていねいによりわける。そういう努力をしているのだと思う。努力という意識もなしに。
たとえば俳句。こういう言い方は俳句をやっているひとには迷惑かもしれないけれど、俳句は短い。無理をせずに、ぱっと読める。だれでもが五・七・五と指を折って、ことばを動かしている。それを三井もやってみる。だれもやらないことと、しゃかりきになって向き合って、力づくでなにかをするというのではなく、構えずに向き合い、そのことばのひとつひとつを「肉体」のなかに取り込んでいる。ひとつのことばが、どんな「肉体」をとおってきたのか、その「肉体」と自分の「肉体」は出会うことができるのか。もしかしたら、隠れてセックスできるのかなあ。ちょっと、なめてみてもいい? つねって意地悪してもいい? 返ってくる反応に「肉体」でこたえながら、三井は三井のことばをふくらませてきたのだと思う。
ほかの、まだ出会ったことのないことばが、ぽとんと三井の「肉体」の上に落ちてきたら、それを綿のように受け止めるため、ふくらませてきたのだと思う。新しいことばは、あ、この場所、ふわふわしていて気持ちがいい。下の方には栄養もたっぷりあるみたい。ここで根を張って、芽を出して、花を咲かせて、実を実らせたい--そんなふうに思えるような、ことばのための、ことばのやさしい「畑」。「道」なんだけれど、そのそばには何を育ててもいい「畑」があるような感じといえばいいのかなあ……。
こんなことは、いくら書いても、何も言ったことにはならないのだけれど。でも、「あまい豆」という詩に出会うと、あ、これこれ、この感じ--といいたくなる。
あ それで
思い出した
ことばは種だった
農民のふるいふるい族だろう わたしに
生きることは
種播く
ことだった
のだ
ことばは 種
芽が出る
はなが
咲いて
ことばといっしょに育ち
ことばと実り
それはそれはかみさまのなさるようなことをした
ことばは身体
え?
そう
よ
ことばは種だったのだ
わたしは枝を
出して枝のさきに
月を抱いた
ことばはしみじみと五体にしみとおって
種 播いたことも忘れているのか
ねえ
ほら
と
ぜんざい すする
あまい 割れた豆。
「種」と「ことば」と「わたしの身体」、それから「種から育った枝」の区別がなくなる。月だって、区別がない。
人間の仕事というものは、たしかに三井の書いているとおりだと思う。
私も農民のふるい子孫(?)なのでよくわかるが、種を買ってきて畑に植える。芽が出て、花が咲いて、実る。そのとき、育っているのはたとえばキュウリであり、ナスであり、オクラなのだが、それを見るとき、農民はいちいちことどにはしないけれど、あ、芽が出た、茎がのびた、つっかい棒をしなくっちゃ、ツルをはわせる竹を組まなくっちゃ、と思う。植えたキュウリやナスが育つのにあわせて、ことばもいっしょに育っている。ことばは、語られることはないけれど、「肉体」のなかに、何をすべきかという認識そのものとして育っている。
それはそれはかみさまのなさるようなこと
ほんとうにそう思う。私は特別な宗教を信じているわけではないけれど、たしかに植物が育ち、それにあわせてことばが育ち、それが組み合わさってものをつくるということになる、というのは「かみさまがなさること」。
いいなあ。
だれもが「かみさま」に触れ、そしてちょっぴり、「人間」の枠を超える。そして、ね。
ことばは種だったのだ
わたしは枝を
出して枝のさきに
月を抱いた
あ、こんなことまで、できてしまうのだ。遠い遠い空の彼方の月。それを、枝になって、抱き留める。そうすると、月はしみじみと「肉体」(三井は「五体」と書いている)にしみとおる。
ことばとなって。
まだ、ことばにならない、ことば以前のことばとなって。
それが「ことば以前のことば」なので、三井は、むりにそれをことばにはしない。いつか、だれかが、三井でなければ、 100年後、1000年後の、たとえば新しい「芭蕉」が三井の踏みしめた「足裏」を確かめるようにして、そのことばを踏み、美しいことばにするだろう。
そのときまで、三井は待っている。
「ぜんざい」なんかをすすりながら。「あまい 割れた豆」--って、これも、ねえ、「種」だよねえ。
*
「ことば」という表現は出てこない、「種」という表現も出てこない。けれど「柳のように揺れ」も、長い時間をかけて自然にうまれてきた「道」に通じるものをしっかりとつたえている。
衣類を整理している
二十年も四十年も前の
どれひとつとして気に入らぬものはない
気に染まないと思いつつ納ってあったもの
も
気に入る
この書き出しの「衣類」を「ことば(詩)」に置き換えてみると、三井の生き方がわかる。
自分で必要と思ってつくったもの、買ったもの。なんだか気持ちにしっくりしない、気に入らないと思っていたもの--そういうものも、長い暮らしの時間のなかで、その奥底で、しっかりとつながってい生きている。いつか芽を出したいと願っている「種」のようでもある。そして、それは知らないあいだに、小さな芽さえ伸ばしはじめている。
どれひとつとして 気に入らないものはない
そのとき
どき
考えながら
どこと
どこを
たとえば昭和三十年と六十年をあわせても
出合いものの
たとえば
筍と若布の炊き合わせのようによく似合って
ゆるまない
あ、すごい。昭和三十年のことばと六十年のことばが出会う。そこには、またあたらしい詩があるのだ。それは「ゆるまない」。ゆるみようがない。しっかりと、奥でつながっているのだから。ゆるまないどころか、新しく絡み合いながら、他のゆるんだところを引き締めるかもしれない。いや、ふるいものを突き破って、あっと驚かせるかもしれない。
こうして暮らしてきた
こうして繋いできたのだ と思う
風に揺れ
柳のように揺れ
五十年と七十年が出合っても いま はじまった恋愛みたいに
あたらしい
衣類の整理をしている
まもなく 引っ越しなので。
三井は、どんなことばも捨てずに「繋いできた」のだ。その「繋ぐ」ことのなかに、三井だけの「足裏」があるのではなく、出合ったこともないひとの「足裏」もある。だからこそ、「五十年」と「七十年」が出合うとき、そこに「見知らぬひと(その美しい足裏)」がふいにあらわれてきて、あたらしい恋愛がはじまる。こころがときめき、肉体がときめく。肉体がわかやぎ、華やぐ。
かっこいいなあ。
私は、もうほとんど「ストーカー」みたいにして三井の詩を、ことばを追いかけているけれど、「有罪」になっても、やめません。
引っ越したって、隠れたって、追いかけていきますからね。
と、「ストーカー宣言」をしておきます。ほんとうは、ストーカーなんて、味気ないことではなく、道行とか心中とか、古くてかっこいいことがしてみたいけれど……。