監督 クリストファー・ノーラン 出演 レオナルド・ディカプリオ、渡辺謙、エレン・ペイジ、マリアン・コティアール
映画になっていません。
夢の三層構造というアイデアはおもしろいのだけれど、それをことばで説明してしまってはねえ。現実と夢、さらにそれより深い夢、もっとも深い夢ではスピードが違うというんだけれど、映像ではぜんぜん差がないじゃないか。(唯一、車が橋から落ちるシーンだけがスローモーションで遅いけれど。)
どこまでが現実で、どこまでが夢か、ごっちゃになる--というのが「ミソ」らしいが、ほんとうに夢の「三層」が描かれているなら、それはごっちゃになりようがない。どの夢も同じレベルで表現されるから映像として区別がつかないだけ。映画が破綻している。さらに、映像として次元を差別化できないために、それをことばで説明している。最悪だねえ。脚本もひどければ、カメラもひどい。
それに。
こんなへたくそな脚本、カメラで、ほんとうに、いまスクリーンで描かれている夢が何段階の夢か、あるいは現実か、わからなくなるって、ほんとう?
宣伝文句に洗脳されているんじゃない? ことばを信じすぎているんじゃない?
これは、映画ではなく、小説なら、まだいくぶんおもしろくなったかもしれない。夢は映像に見えるけれど、実際は、ことばで見るんだろうなあ。何を、どう認識するか。その意識が短絡したり、間延びしたりして時間が複雑になる。入り組んだことばは、ことばの「深層」をえぐりつづけるからね。それに対して、映像は、別の映像をえぐりつづけるということはない。(ない、とは断言できないかもしれないけれど、それを映像で再現するのはむずかしいだろうなあ。せいぜいが、ある映像を、別の映像と錯覚する、というのが限度である。)
これに比べると(比べてはいけないんだろうけれど)、「脳内ニューヨーク」の方がはるかに「夢」の混乱を描いている。どっちが現実、どっちが「夢」(芝居という虚構)であるか、誰にでもわかるのに、わかっているはずなのに、その区別があいまいになっていく。だんだん「芝居」の方が「現実」になってゆく。しかも、「ことば」としてではなく、映像として。
*
この手の映画では、「マトリックス」がいちばんおもしろい。
何がおもしろいといって、そこでは「潜在意識」というような、ことばでしか表現できないものではなく、「肉体」が主役だった。「肉体」が「夢」のように動いた。弾丸を、スローモーションで、身を反らして寄せるシーンなんて、夢そのものでしょ? そして、そこでは「夢」のスピードが「現実」のスピードと違うことが、ちゃんと「肉体の映像」として表現されていた。
自分の肉体でまねしたくなるシーンがあった。観客の肉体をスクリーンに引きこむ映像があった。
「インセプション」には、そういう映像はない。ただ、ことばだけがある。ことば、ことば、ことば。
もし、この映画で、何がなんだかわからなくなる、どれが現実で、どれが表層の夢で、さらにどれが最深層の夢かわからなくなるとしたら、それは映像のせいではなく、映画を見ているとき、役者が話すことば(その意味)を理解できないからである。これは逆に言えば、この映画は映像を見せているのではなく、ことばで映像を説明しつづけているだけの紙芝居である、ということになる。
ラストシーンの、独楽が、まわりつづけるのか、とまって倒れるのか、わかる寸前で途切れる映像は、この映画のいいかげんさを象徴している。観客の判断にゆだねる、というのは聞こえはいいが、つくっている側が「答え」を出せなかっただけである。
*
なんだか感想を書いている内に怒りがこみあげてきた。「シャッターアイランド」と同様、ひどい映画である。
レオナルド・ディカプリオはもともと「透明」な役者である。「不透明」な役を「肉体」が受け入れない。「不透明」を背負いきれない。まあ、この映画は、ことばの映画だから、レオナルド・ディカプリオの「透明」な肉体が必要だった。「肉体」が前面に出てしまうと「ことば」が見えなくなるということかもしれない。でもね、それじゃあ、映画じゃないよ。
クレジットの最後になって、エディット・ピアフの歌が流れるのはなぜ? ピアフを演じたマリアン・コティアールが出ているから? 観客をばかにしていない?
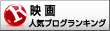
映画になっていません。
夢の三層構造というアイデアはおもしろいのだけれど、それをことばで説明してしまってはねえ。現実と夢、さらにそれより深い夢、もっとも深い夢ではスピードが違うというんだけれど、映像ではぜんぜん差がないじゃないか。(唯一、車が橋から落ちるシーンだけがスローモーションで遅いけれど。)
どこまでが現実で、どこまでが夢か、ごっちゃになる--というのが「ミソ」らしいが、ほんとうに夢の「三層」が描かれているなら、それはごっちゃになりようがない。どの夢も同じレベルで表現されるから映像として区別がつかないだけ。映画が破綻している。さらに、映像として次元を差別化できないために、それをことばで説明している。最悪だねえ。脚本もひどければ、カメラもひどい。
それに。
こんなへたくそな脚本、カメラで、ほんとうに、いまスクリーンで描かれている夢が何段階の夢か、あるいは現実か、わからなくなるって、ほんとう?
宣伝文句に洗脳されているんじゃない? ことばを信じすぎているんじゃない?
これは、映画ではなく、小説なら、まだいくぶんおもしろくなったかもしれない。夢は映像に見えるけれど、実際は、ことばで見るんだろうなあ。何を、どう認識するか。その意識が短絡したり、間延びしたりして時間が複雑になる。入り組んだことばは、ことばの「深層」をえぐりつづけるからね。それに対して、映像は、別の映像をえぐりつづけるということはない。(ない、とは断言できないかもしれないけれど、それを映像で再現するのはむずかしいだろうなあ。せいぜいが、ある映像を、別の映像と錯覚する、というのが限度である。)
これに比べると(比べてはいけないんだろうけれど)、「脳内ニューヨーク」の方がはるかに「夢」の混乱を描いている。どっちが現実、どっちが「夢」(芝居という虚構)であるか、誰にでもわかるのに、わかっているはずなのに、その区別があいまいになっていく。だんだん「芝居」の方が「現実」になってゆく。しかも、「ことば」としてではなく、映像として。
*
この手の映画では、「マトリックス」がいちばんおもしろい。
何がおもしろいといって、そこでは「潜在意識」というような、ことばでしか表現できないものではなく、「肉体」が主役だった。「肉体」が「夢」のように動いた。弾丸を、スローモーションで、身を反らして寄せるシーンなんて、夢そのものでしょ? そして、そこでは「夢」のスピードが「現実」のスピードと違うことが、ちゃんと「肉体の映像」として表現されていた。
自分の肉体でまねしたくなるシーンがあった。観客の肉体をスクリーンに引きこむ映像があった。
「インセプション」には、そういう映像はない。ただ、ことばだけがある。ことば、ことば、ことば。
もし、この映画で、何がなんだかわからなくなる、どれが現実で、どれが表層の夢で、さらにどれが最深層の夢かわからなくなるとしたら、それは映像のせいではなく、映画を見ているとき、役者が話すことば(その意味)を理解できないからである。これは逆に言えば、この映画は映像を見せているのではなく、ことばで映像を説明しつづけているだけの紙芝居である、ということになる。
ラストシーンの、独楽が、まわりつづけるのか、とまって倒れるのか、わかる寸前で途切れる映像は、この映画のいいかげんさを象徴している。観客の判断にゆだねる、というのは聞こえはいいが、つくっている側が「答え」を出せなかっただけである。
*
なんだか感想を書いている内に怒りがこみあげてきた。「シャッターアイランド」と同様、ひどい映画である。
レオナルド・ディカプリオはもともと「透明」な役者である。「不透明」な役を「肉体」が受け入れない。「不透明」を背負いきれない。まあ、この映画は、ことばの映画だから、レオナルド・ディカプリオの「透明」な肉体が必要だった。「肉体」が前面に出てしまうと「ことば」が見えなくなるということかもしれない。でもね、それじゃあ、映画じゃないよ。
クレジットの最後になって、エディット・ピアフの歌が流れるのはなぜ? ピアフを演じたマリアン・コティアールが出ているから? 観客をばかにしていない?
 | キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン [DVD]パラマウント ホーム エンタテインメント ジャパンこのアイテムの詳細を見る |

















