監督 クリス・バック 出演 クリステン・ベル、イディナ・メンゼル、ジョナサン・グロフ、サンティノ・フォンタナ

「アナと雪の女王」の前座(?)に短編「ミッキーのミニー救出大作戦」がついていて、これが非常におもしろかった。ミニーが悪党(?)にさらわれて、それをミッキーが助けに行くという定番のストーリーなのだが、とても楽しい。映画のスクリーンを利用して、スクリーンからはみ出してしまったミッキーとスクリーンの中の世界の絡み合い、ぱらぱら漫画の逆戻しからヒントをえて映画を逆戻したり、同じシーンを何度も繰り返したり。そうか。見るというのはストーリーを追うだけではなく、好きなシーン(おもしろいシーン)を何度でも繰り返し見るということなのか。わかっていても、おもしろい。わかっているから、おもしろい。ミニーが最後に救出されるのはわかっている。わかっているから、途中で大笑いしながら、その瞬間を楽しむことができる。--というのは、実は、あらゆる芸術に通じることなのではないだろうか。わからないことを知りたいのではない。わかっていることを、ゆっくり何度でも味わいたい。
などと書くとうるさくなってしまうが、いや、ほんとうに「これがアニメなんだ」ということを久々に感じた。
と、前書きはここまでにして。
「アナと雪の女王」の見どころは、雪と氷だな、やっぱり。途中で雪だるまがでてきて、ニンジンの鼻をつけてもらい、「色のない世界だから、こういう色がほしかった」というようなことを言うのだが、雪と氷はまさに色がない。白。透明。モノクロ映画にしてもいい世界なのだが、これをどんな具合にカラフルに見せるか。青、灰色、白、黒のバリエーションで世界をつくっていくのだが、うーん、すごいなあ。おもしろいなあ。氷の色はこんなに変化に富んでいたのか。
氷と雪との対比もとてもおもしろい。雪を描くことで、氷の感覚が一層研ぎ澄まされてくる。
雪は白くてやわらかくて、一片一片がさまざまな形をしている。一片一片を見れば美しい結晶をしている。氷は透明で硬く、一片一片というものがない。結晶が見えない。固まりだ。雪はそこにあるものを隠し、氷は氷の向こう側にあるものも見せてしまう。この質感もおもしろいなあ。
途中に女王を護る(?)雪だるまの怪物が出てくるが、これが氷ではなく雪であるところがところがおもしろい。氷だと自在に動けない? 動くたびにこわれる? でも、雪だって、固まりをしなやかに動かせるわけではない。けれど、氷に比べると動いてもいいかな、と感じさせる。こういう「感覚」はいいかげんなものなのだけれど、そういういいかげんな「感覚」を生きているのが人間なのだと思う。その雪だるまの怪物に追われて、アナと氷売りの青年ががけ下に落ちるけれど「雪は枕のようにやわらかい」というのも、この「感覚」の錯誤を利用しているね。
氷の方は動きのない「構築物」に活用される。それは何かゴシック建築のように、無闇に壮大な感じがする。何かを拒絶する。氷の尖った先端は凶器にもなる。
でも、そういうことは別にして。
この映画の女王の「魔法」は楽しいね。冒頭の、雪をつぎつぎに積もらさて妹のアナと遊ぶシーン。城からひとりで山へ逃げていくとき、海(湖?)を瞬時に凍らせてその上を走っていく。深い谷の上に氷の橋を気づいて、それをわたって行く。このときのスピード感あふれる影像がすばらしい。
このスピード感は「ミッキーのミニー救出大作戦」にもあって、このスピード感こそがアニメのいのちなのだと思った。実写(特撮を含む)だと、こういうスピードは難しい。人間が紛れ込むと、どうしても人間のスピードが基本になるので、リズムが悪くなる。架空の軽さがなくなる。1秒も2秒も遅くなるわけではないのだが。いろいろな特殊撮影を駆使しても、このスピード感だけはアニメには追いつけない。ということは、アニメの生き残る道は、このスピード感にあるということになるのだが……。(これを逆に利用したのが「マトリックス」で見せたスローモーションだね。人間が弾丸を身を反らしてよける。それをゆっくりとしたスピードで見せることで、観客の肉体が役者の肉体の動きをうこことができる。そして、その動きをやってみたいと思わせる。速かったら目に見えないし、真似できない。)
あ、脱線しつつあるかな?
脱線してしまおう。
たとえば氷の城で女王と殺し屋(?)が対決するシーン。これを人間が演じ、氷を特殊撮影で生み出した場合、その氷のスピードはアニメよりも遅くなると思う。アニメの速さだと、見ていて氷の危険な感じが強すぎる。アニメだから、この映画のスピードが許される。人間の眼がアニメの「省略」に慣れているのだ。人間だと、手の一瞬の動き、顔の一瞬の動きにも「情報」があふれて、それを読み取ろうと眼が無意識に動いてしまう。そのため氷の特撮のスピードを上げると、そこに「ずれ」が生まれて、ぎくしゃくする。アニメは「人物」の「情報」が省略されている。どんなに精密に描いても、そこには実写に比べると省略がある。それがどんなスピードでも許してしまう。
言い換えると、人間に不可能なスピードを、アニメは登場人物(キャラクター)の情報を省略することで可能にする。ミッキーが悪党を追いかけるとき、そこではアップでない限り眼の表情(情報)は省略される。手足の動きに限定して表現できる。ところが人間が演じてしまうと、とたえ顔のアップがなくても、そこに顔の表情という情報が入ってきて、それを観客は無意識に読み取って、その処理に時間がかかる。だから実写に組み合わせる特殊撮影は、どうしても人間のスピードという「限界」に縛られる。アニメには、その制限がない。
これはほかの状況でも言えるかもしれない。女王が雪山を歩いていく。歌いながら歩いていく。こういうシーンは人間が演じると、とたんに嘘っぽくなる。人間の手足、動きの情報が寒き山の中で歌うということと、奇妙にずれてしまう。肉体の記憶とあわない。
だから、とここで私はまた飛躍するのだが。
たとえば「レ・ミゼラブル」というミュージカル。あれは舞台だから劇的なのであって、実写の「映画」では非常に違和感がある。舞台では省略が生きている。観客は最初から省略を受け入れてみている。実写だと、背景の情報が人間を邪魔してしまう。この情報量を迫力と勘違いしてしまう批評がしばしば横行するけれど、「芝居」の本質と離れたことばだと思う。
ミュージカルは舞台とアニメに限る。それは背景の省略、人物の省略を舞台とアニメは最初から前提としているからである。省略した部分を観客と役者が想像力で補っていく。想像力を暴走させ、劇場そのものを「世界」にかえていくのが「舞台」芸術だ。
脱線しすぎたので、もう、ここで切り上げよう。
(2014年05月06日、ソラリアシネマ8)

「アナと雪の女王」の前座(?)に短編「ミッキーのミニー救出大作戦」がついていて、これが非常におもしろかった。ミニーが悪党(?)にさらわれて、それをミッキーが助けに行くという定番のストーリーなのだが、とても楽しい。映画のスクリーンを利用して、スクリーンからはみ出してしまったミッキーとスクリーンの中の世界の絡み合い、ぱらぱら漫画の逆戻しからヒントをえて映画を逆戻したり、同じシーンを何度も繰り返したり。そうか。見るというのはストーリーを追うだけではなく、好きなシーン(おもしろいシーン)を何度でも繰り返し見るということなのか。わかっていても、おもしろい。わかっているから、おもしろい。ミニーが最後に救出されるのはわかっている。わかっているから、途中で大笑いしながら、その瞬間を楽しむことができる。--というのは、実は、あらゆる芸術に通じることなのではないだろうか。わからないことを知りたいのではない。わかっていることを、ゆっくり何度でも味わいたい。
などと書くとうるさくなってしまうが、いや、ほんとうに「これがアニメなんだ」ということを久々に感じた。
と、前書きはここまでにして。
「アナと雪の女王」の見どころは、雪と氷だな、やっぱり。途中で雪だるまがでてきて、ニンジンの鼻をつけてもらい、「色のない世界だから、こういう色がほしかった」というようなことを言うのだが、雪と氷はまさに色がない。白。透明。モノクロ映画にしてもいい世界なのだが、これをどんな具合にカラフルに見せるか。青、灰色、白、黒のバリエーションで世界をつくっていくのだが、うーん、すごいなあ。おもしろいなあ。氷の色はこんなに変化に富んでいたのか。
氷と雪との対比もとてもおもしろい。雪を描くことで、氷の感覚が一層研ぎ澄まされてくる。
雪は白くてやわらかくて、一片一片がさまざまな形をしている。一片一片を見れば美しい結晶をしている。氷は透明で硬く、一片一片というものがない。結晶が見えない。固まりだ。雪はそこにあるものを隠し、氷は氷の向こう側にあるものも見せてしまう。この質感もおもしろいなあ。
途中に女王を護る(?)雪だるまの怪物が出てくるが、これが氷ではなく雪であるところがところがおもしろい。氷だと自在に動けない? 動くたびにこわれる? でも、雪だって、固まりをしなやかに動かせるわけではない。けれど、氷に比べると動いてもいいかな、と感じさせる。こういう「感覚」はいいかげんなものなのだけれど、そういういいかげんな「感覚」を生きているのが人間なのだと思う。その雪だるまの怪物に追われて、アナと氷売りの青年ががけ下に落ちるけれど「雪は枕のようにやわらかい」というのも、この「感覚」の錯誤を利用しているね。
氷の方は動きのない「構築物」に活用される。それは何かゴシック建築のように、無闇に壮大な感じがする。何かを拒絶する。氷の尖った先端は凶器にもなる。
でも、そういうことは別にして。
この映画の女王の「魔法」は楽しいね。冒頭の、雪をつぎつぎに積もらさて妹のアナと遊ぶシーン。城からひとりで山へ逃げていくとき、海(湖?)を瞬時に凍らせてその上を走っていく。深い谷の上に氷の橋を気づいて、それをわたって行く。このときのスピード感あふれる影像がすばらしい。
このスピード感は「ミッキーのミニー救出大作戦」にもあって、このスピード感こそがアニメのいのちなのだと思った。実写(特撮を含む)だと、こういうスピードは難しい。人間が紛れ込むと、どうしても人間のスピードが基本になるので、リズムが悪くなる。架空の軽さがなくなる。1秒も2秒も遅くなるわけではないのだが。いろいろな特殊撮影を駆使しても、このスピード感だけはアニメには追いつけない。ということは、アニメの生き残る道は、このスピード感にあるということになるのだが……。(これを逆に利用したのが「マトリックス」で見せたスローモーションだね。人間が弾丸を身を反らしてよける。それをゆっくりとしたスピードで見せることで、観客の肉体が役者の肉体の動きをうこことができる。そして、その動きをやってみたいと思わせる。速かったら目に見えないし、真似できない。)
あ、脱線しつつあるかな?
脱線してしまおう。
たとえば氷の城で女王と殺し屋(?)が対決するシーン。これを人間が演じ、氷を特殊撮影で生み出した場合、その氷のスピードはアニメよりも遅くなると思う。アニメの速さだと、見ていて氷の危険な感じが強すぎる。アニメだから、この映画のスピードが許される。人間の眼がアニメの「省略」に慣れているのだ。人間だと、手の一瞬の動き、顔の一瞬の動きにも「情報」があふれて、それを読み取ろうと眼が無意識に動いてしまう。そのため氷の特撮のスピードを上げると、そこに「ずれ」が生まれて、ぎくしゃくする。アニメは「人物」の「情報」が省略されている。どんなに精密に描いても、そこには実写に比べると省略がある。それがどんなスピードでも許してしまう。
言い換えると、人間に不可能なスピードを、アニメは登場人物(キャラクター)の情報を省略することで可能にする。ミッキーが悪党を追いかけるとき、そこではアップでない限り眼の表情(情報)は省略される。手足の動きに限定して表現できる。ところが人間が演じてしまうと、とたえ顔のアップがなくても、そこに顔の表情という情報が入ってきて、それを観客は無意識に読み取って、その処理に時間がかかる。だから実写に組み合わせる特殊撮影は、どうしても人間のスピードという「限界」に縛られる。アニメには、その制限がない。
これはほかの状況でも言えるかもしれない。女王が雪山を歩いていく。歌いながら歩いていく。こういうシーンは人間が演じると、とたんに嘘っぽくなる。人間の手足、動きの情報が寒き山の中で歌うということと、奇妙にずれてしまう。肉体の記憶とあわない。
だから、とここで私はまた飛躍するのだが。
たとえば「レ・ミゼラブル」というミュージカル。あれは舞台だから劇的なのであって、実写の「映画」では非常に違和感がある。舞台では省略が生きている。観客は最初から省略を受け入れてみている。実写だと、背景の情報が人間を邪魔してしまう。この情報量を迫力と勘違いしてしまう批評がしばしば横行するけれど、「芝居」の本質と離れたことばだと思う。
ミュージカルは舞台とアニメに限る。それは背景の省略、人物の省略を舞台とアニメは最初から前提としているからである。省略した部分を観客と役者が想像力で補っていく。想像力を暴走させ、劇場そのものを「世界」にかえていくのが「舞台」芸術だ。
脱線しすぎたので、もう、ここで切り上げよう。
(2014年05月06日、ソラリアシネマ8)
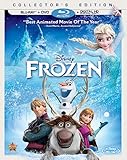 | Frozen(Blu-ray+DVD)北米版 2014 |
| クリエーター情報なし | |
| メーカー情報なし |

















