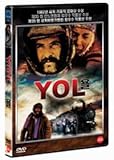高橋秀明「く」、鈴村和成「スキ、だ」(「イリプス Ⅱnd」16、2015年07月10日発行)
高橋秀明「く」は前半と後半では調子が違っている。高橋の書きたいことは後半にあるのかもしれないが、私には前半がおもしろかった。で、前半だけを引用し、感想を書く。
同じことを繰り返しているね。腰が曲がった状態を、立っている時は「く」の字、横になった時は「へ」の字と「視覚化」している。そして、その「視覚化」に「視えない天蚕糸」が絡んでくる。これがおかしい。「視えない天蚕糸」の存在によって「く」と「へ」がよりくっきりと見える。
さらにこれが「内在」という奇妙なことばにかわっていく。「身体に内在して」いるものは、外からは「見えない」。そとからは「く」「へ」の字にしか見えないけれど、身体のなかにも「く」「へ」の字はある。その「見えない」ものが見えるのは、それより先に「視えない天蚕糸」があるからだ。「視えない」という否定形で「存在」を確認している(見ている)からだ。
「見えるもの」(「く」「へ」の字)を通して、見えないものを見る。そういう習慣(?)がついてしまっているので、「見えない」はずの、「内在」する「く」「へ」も見える。
そう繰り返しておいて、前半の最後の二行。
私は笑ってしまった。
あ、これが書きたかったのか。「くるしみ」と「へたる」はどこか似ている。「くるしみ」つづけると、いきいきとした動きが「へたる」。「くるしみ」のなかには「へたる」が内在していて、それがやがて表に出てくる?
というようなことがいいたいのか、どうか。わからないけれど、その「く」と「へ」の「見えない」つながりが高橋のなかで完成しているのが「見える」。それがおかしい。楽しい。
*
鈴村和成「スキ、だ」は高橋とは違った「繰り返し」でできた詩だ。
あと八行ほど、同じ調子でつづく。「好き」ということばを繰り返している。ついでに「ダ」と言う音を繰り返している。ほんとうはどっちを繰り返しているのか。よくわからない。「つぶやき」「つぶつぶ」「ぶつぶつ」という音の遊びや、「好き」「オンナヘン」「女」「子」という文字遊びもある。
で、何がいいたい? 「意味」は? 「思想」は?
そんなものはないなあ。いや、あるのかもしれないが「意味/内容/思想」というようなものではなく、ただ繰り返して言ってみたかったという「欲望」があるんだろう。「欲望(本能)」というのはどこかで「肉体」とつながっているから、それはやっぱり「思想」なのだと思う。
私の知っていることばでは、この鈴村の「思想」を「見える」形で表現できないけれど、これは私のことばが無力というだけのこと。
これが鈴村の「ほんとう」かどうかわからないが、嘘だってかまわない。「電柱/霜柱」対比(嫌い/好き)のなかに、「へえぇ」と思わせるものがある。それは、私はこれまで「電柱」と「霜柱」を対比しようと思ったことはないということを思い出させるだけなのだが、そんなことをしたことがないと思うという意識のそこから「柱」という文字が共通してつかわれているなあ、とふと思ったりする。この「ふと」の感じの裏切りが、何と言えばいいのか、快感なのだ。「ダ」の繰り返しのリズムがあるから、よけいに快感なのだ。
考えて書いているのか、思いついたまま書いているのかわからないが、どちらにしろ、それがリズムにのっているのがいい。ことばと音が鈴村の「肉体」そのものになっている。
高橋秀明「く」は前半と後半では調子が違っている。高橋の書きたいことは後半にあるのかもしれないが、私には前半がおもしろかった。で、前半だけを引用し、感想を書く。
腰が「く」の字に曲がって
もどらない
階段を下りると
…く、く、く、く、
と移動する
俯せに横たわると
「く」の字は「へ」の字になる
視えない天蚕糸で腰を吊られ
横たわれば
腰を宙に吊られた俯せの姿のまま
立ち上がれば
背後から腰を引っ張られた姿のまま
伸びない「く」と「へ」が
身体に内在して
年年
屈曲を強める
同じことを繰り返しているね。腰が曲がった状態を、立っている時は「く」の字、横になった時は「へ」の字と「視覚化」している。そして、その「視覚化」に「視えない天蚕糸」が絡んでくる。これがおかしい。「視えない天蚕糸」の存在によって「く」と「へ」がよりくっきりと見える。
さらにこれが「内在」という奇妙なことばにかわっていく。「身体に内在して」いるものは、外からは「見えない」。そとからは「く」「へ」の字にしか見えないけれど、身体のなかにも「く」「へ」の字はある。その「見えない」ものが見えるのは、それより先に「視えない天蚕糸」があるからだ。「視えない」という否定形で「存在」を確認している(見ている)からだ。
「見えるもの」(「く」「へ」の字)を通して、見えないものを見る。そういう習慣(?)がついてしまっているので、「見えない」はずの、「内在」する「く」「へ」も見える。
そう繰り返しておいて、前半の最後の二行。
いつもくるしみ
いつかへたるために
私は笑ってしまった。
いつも「く」るしみ
いつか「へ」たるために
あ、これが書きたかったのか。「くるしみ」と「へたる」はどこか似ている。「くるしみ」つづけると、いきいきとした動きが「へたる」。「くるしみ」のなかには「へたる」が内在していて、それがやがて表に出てくる?
というようなことがいいたいのか、どうか。わからないけれど、その「く」と「へ」の「見えない」つながりが高橋のなかで完成しているのが「見える」。それがおかしい。楽しい。
*
鈴村和成「スキ、だ」は高橋とは違った「繰り返し」でできた詩だ。
好き、ダ。嫌い、ダ。足、好き、ダ。卵、好き、ダ。つぶやき、嫌い、
ダ。つぶつぶ、嫌い、だ。ぶつぶつ、嫌い、ダ。判子(ハンコ、嫌い、
だ。プラカード、嫌い、ダ。電柱も嫌い、ダ。霜柱、好き、ダ。嫌いと
いう言葉が、嫌い、ダ。スピーチ、嫌い、ダ。言葉、好き、ダ。猫、好
き、ダ。ケモノヘン、好き、ダ。好き嫌いが、好き、ダ。オンナヘン、
好き、ダ。大好き、ダ。ヘン、好き、ダ。ダ、好き、ダ。好きと言う言
葉、好き、ダ。という)が、嫌い、ダ。女の子という字、好き、ダ。好
(スキが、好き、ダ。好き好き(スキズキ、ダ。好(スき、好(スき、
あと八行ほど、同じ調子でつづく。「好き」ということばを繰り返している。ついでに「ダ」と言う音を繰り返している。ほんとうはどっちを繰り返しているのか。よくわからない。「つぶやき」「つぶつぶ」「ぶつぶつ」という音の遊びや、「好き」「オンナヘン」「女」「子」という文字遊びもある。
で、何がいいたい? 「意味」は? 「思想」は?
そんなものはないなあ。いや、あるのかもしれないが「意味/内容/思想」というようなものではなく、ただ繰り返して言ってみたかったという「欲望」があるんだろう。「欲望(本能)」というのはどこかで「肉体」とつながっているから、それはやっぱり「思想」なのだと思う。
私の知っていることばでは、この鈴村の「思想」を「見える」形で表現できないけれど、これは私のことばが無力というだけのこと。
電柱も嫌い、ダ。霜柱、好き、ダ。
これが鈴村の「ほんとう」かどうかわからないが、嘘だってかまわない。「電柱/霜柱」対比(嫌い/好き)のなかに、「へえぇ」と思わせるものがある。それは、私はこれまで「電柱」と「霜柱」を対比しようと思ったことはないということを思い出させるだけなのだが、そんなことをしたことがないと思うという意識のそこから「柱」という文字が共通してつかわれているなあ、とふと思ったりする。この「ふと」の感じの裏切りが、何と言えばいいのか、快感なのだ。「ダ」の繰り返しのリズムがあるから、よけいに快感なのだ。
タダ(只、好き、ダ。タグが好き、ダ。傍点が好き、ダ。そばかす、
好き、ダ。点、好き、ダ。点々、好き、ダ。々、が、好き、ダ。々。吃
り、が好き、ダ。ダ。
考えて書いているのか、思いついたまま書いているのかわからないが、どちらにしろ、それがリズムにのっているのがいい。ことばと音が鈴村の「肉体」そのものになっている。
 | ランボー全集 個人新訳 |
| アルチュール・ランボー | |
| みすず書房 |