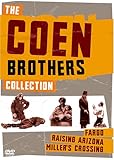『禮記』のつづき。「野原の夢」のつづき。
ここには、ヴェルレーヌ(ヴィオロンの音)が出てくる。マラルメも出てくる。アエキロスそれぞれに「音」ということばがついている。それは、たとえばヴェルレーぬが「ヴィオロン」のなかに「私」を見つけたということだ。そして、ヴィオロンになったということだ。
「音」は「私」と「もの」を結びつけるものである。「連結」そのものである。
視覚ではない。色でも形でも線でもない。「音」によって「私」は「私以外のもの」と連結し、「他者」になる。
西脇の夢はここにある。
前の連の「カーテンの後の音」「殺人」「こおろぎ」とつながれば、どうしてもそこにシェークスピアが思い浮かんでしまうが--それは無視しよう。マラルメもヴェルレーヌも無視しよう。そこには確かにマラルメもヴェルレーヌもシェークスピアもいるのだが、それを貫いて「音」がある。詩人が「音」を自分の「肉体」の中に取り込み、それをはきだす。
そのとき「音」は他者(もの)のものか「私」のものか。「秋の日のヴィオロンの/ためいきの」というとき、それは「ヴィオロン」なのかヴェルレーヌなのか、上田敏なのか。区別がつかない。「音」が動くと、そこからヴィオロンが生まれ、ため息が生まれ、ヴェルレーヌが生まれ、上田敏が生まれてくる。
そこに動いているのは「人間」という「音」なのだ。
「人間」は「音」なのだ。
この「音」を人間は、どうやって発見するのだろうか。これは難しい。人間の発する「音」は、どうやって生み出されるのだろうか。
私の書いていることは、たぶん、この文章を読んでいるひとにはわからないと思う。なぜなら、私にも、何を書いているかわからないからだ。
私にわかるのは、「音」が私の肉体のなかに入ってくるとき、うまくなじめるものとなじめないものがあるということだ。どうしても「好み」があるということだ。「好み」の「音」を通って、私のことばは動いていく。「事実」ではなく、「音」の好みに導かれて「音」がことばになる。
「私は私ではないものに/私を発見する」といっても、そのとき「音」が自分の「好み」どおりに響かないと、私は私以外のものに私を発見することもできないのである。
私が何かに(私以外のものに)私を発見するのではなく--「音」が私の代わりに私を発見してくるのである。私のなかに、知らず知らずにたまった「音」が。私のなかにたまった「音」と何かが響きあう--そのとき、ことばが動きだす。
そのことばの動きは「誤読」である。
そして「誤読」であることを承知で書くのだが、私は西脇の「音」に触れると、そこに私の肉体のなかにある「音」が瞬間的にととのえられ、音楽になるのを感じる。
--ということを、「野原の夢」の「音」をめぐる行から書きたいと思うのだが、どうにも書けないなあ……。

これは確かに
すべての音だ
私は私ではないものに
私を発見する音だ
これは秋の音だ
ヴィオロンの音だ
ガラスの空しい思いの
多摩の石の音だ
これはまたケヤキの木の音だ
マラルメの音だ
私の中に水が流れる音だ
アエキロスのカエルの音だ
これはまた衣を洗う音だ
冠を洗う音だ
カーテンの後の音だ
ああ あの毛髪のきらめきの音だ
ここには、ヴェルレーヌ(ヴィオロンの音)が出てくる。マラルメも出てくる。アエキロスそれぞれに「音」ということばがついている。それは、たとえばヴェルレーぬが「ヴィオロン」のなかに「私」を見つけたということだ。そして、ヴィオロンになったということだ。
「音」は「私」と「もの」を結びつけるものである。「連結」そのものである。
視覚ではない。色でも形でも線でもない。「音」によって「私」は「私以外のもの」と連結し、「他者」になる。
西脇の夢はここにある。
これからが大変に難しくなる
音が人間の音になる
すべての音は人間が恐れる音だ
殺人の音だ
こおろぎの音だ
ああ 音が去つていく
ただ一つ女の音が残る
ナデシコの静けさ
前の連の「カーテンの後の音」「殺人」「こおろぎ」とつながれば、どうしてもそこにシェークスピアが思い浮かんでしまうが--それは無視しよう。マラルメもヴェルレーヌも無視しよう。そこには確かにマラルメもヴェルレーヌもシェークスピアもいるのだが、それを貫いて「音」がある。詩人が「音」を自分の「肉体」の中に取り込み、それをはきだす。
そのとき「音」は他者(もの)のものか「私」のものか。「秋の日のヴィオロンの/ためいきの」というとき、それは「ヴィオロン」なのかヴェルレーヌなのか、上田敏なのか。区別がつかない。「音」が動くと、そこからヴィオロンが生まれ、ため息が生まれ、ヴェルレーヌが生まれ、上田敏が生まれてくる。
そこに動いているのは「人間」という「音」なのだ。
「人間」は「音」なのだ。
この「音」を人間は、どうやって発見するのだろうか。これは難しい。人間の発する「音」は、どうやって生み出されるのだろうか。
私の書いていることは、たぶん、この文章を読んでいるひとにはわからないと思う。なぜなら、私にも、何を書いているかわからないからだ。
私にわかるのは、「音」が私の肉体のなかに入ってくるとき、うまくなじめるものとなじめないものがあるということだ。どうしても「好み」があるということだ。「好み」の「音」を通って、私のことばは動いていく。「事実」ではなく、「音」の好みに導かれて「音」がことばになる。
「私は私ではないものに/私を発見する」といっても、そのとき「音」が自分の「好み」どおりに響かないと、私は私以外のものに私を発見することもできないのである。
私が何かに(私以外のものに)私を発見するのではなく--「音」が私の代わりに私を発見してくるのである。私のなかに、知らず知らずにたまった「音」が。私のなかにたまった「音」と何かが響きあう--そのとき、ことばが動きだす。
そのことばの動きは「誤読」である。
そして「誤読」であることを承知で書くのだが、私は西脇の「音」に触れると、そこに私の肉体のなかにある「音」が瞬間的にととのえられ、音楽になるのを感じる。
--ということを、「野原の夢」の「音」をめぐる行から書きたいと思うのだが、どうにも書けないなあ……。
 | 西脇順三郎詩集 (岩波文庫) |
| 西脇 順三郎 | |
| 岩波書店 |