監督 カン・ウソク 出演 パク・ヘイル、チョン・ジェヨン
村長を演じるチョン・ジェヨンが奇妙に印象に残る。山村を舞台にした30年前(?)の事件の秘密があばかれる--というストーリーもの(ミステリーもの?)である。私は、こういう映画は苦手で、途中で眠くなってしまうのだが、この映画は長い長い作品なのに、眠くならずに見てしまった。
村長(元刑事)の眼が、異常なのである。3人の凶悪者と女性をあやつって、村を支配しているのだが、主役のパク・ヘイルに対して、変に、やさしいというか、善良な態度をとる。まあ、隠したいことがあって、そうしているのだが、それが非常に不気味なのである。目付きに、彼の「歴史」が出ている。(あ、もちろん「役所」なんだろうけれど。)メーキャップで老人の役をやっているのだが、目だけが若いというか(当たり前だけれど)、生気をもったままなのが、とても効果的だ。
ただ、彼の演技が、他の凶悪3人組と、どうも合わない。3人組がただの乱暴な愚か者という感じで、ストーリーを単純にしている。村長以外は何も知らない--何も悪いことをしていない、と観客に分かってしまうのである。やくざ映画、マフィア映画でも、本当の悪人はボスだけで、あとは乱暴なだけだけれど、その乱暴なだけななかにも、何かしら手におえないという感じのものがあるけれど、この3人組には、それがない。
まあ、映画のストーリー上、そうなっているのかもしれないけれど、これではつまらない。「人間」が見えてこない。人間らしくない。
主役のパク・ヘイルは、なぜ、彼がこの村にいるのかわからない。父が死んで、その葬儀に。ついでに、ちょっと疑問があって……。というのだけれど、いくら「正義感」が強くても、30年も自分を省みなかった父のこと、その父のまわりに起きていることに、なぜ関心を持つ? その理由が、わからないねえ。チョン・ジェヨンの目付きとは違って、何も語らない目だ。
地下トンネルを含め、セットが軽いのも、映画をつまらなくしている。もっと、時間がたったもの、つかいこなされたもの、という感じがしないと……。
それに。
もしかすると、この映画が背景に利用している「祈祷院」の集団虐殺(集団自殺?)は韓国では有名な話なのかもしれないけれど、そういうことが起きるまでの過程がさらりとしか描かれていないのも、この映画をあじけなくしている。もっとも、それを描いてしまうと、また別の映画になってしまうのかもしれないけれど。
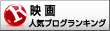
村長を演じるチョン・ジェヨンが奇妙に印象に残る。山村を舞台にした30年前(?)の事件の秘密があばかれる--というストーリーもの(ミステリーもの?)である。私は、こういう映画は苦手で、途中で眠くなってしまうのだが、この映画は長い長い作品なのに、眠くならずに見てしまった。
村長(元刑事)の眼が、異常なのである。3人の凶悪者と女性をあやつって、村を支配しているのだが、主役のパク・ヘイルに対して、変に、やさしいというか、善良な態度をとる。まあ、隠したいことがあって、そうしているのだが、それが非常に不気味なのである。目付きに、彼の「歴史」が出ている。(あ、もちろん「役所」なんだろうけれど。)メーキャップで老人の役をやっているのだが、目だけが若いというか(当たり前だけれど)、生気をもったままなのが、とても効果的だ。
ただ、彼の演技が、他の凶悪3人組と、どうも合わない。3人組がただの乱暴な愚か者という感じで、ストーリーを単純にしている。村長以外は何も知らない--何も悪いことをしていない、と観客に分かってしまうのである。やくざ映画、マフィア映画でも、本当の悪人はボスだけで、あとは乱暴なだけだけれど、その乱暴なだけななかにも、何かしら手におえないという感じのものがあるけれど、この3人組には、それがない。
まあ、映画のストーリー上、そうなっているのかもしれないけれど、これではつまらない。「人間」が見えてこない。人間らしくない。
主役のパク・ヘイルは、なぜ、彼がこの村にいるのかわからない。父が死んで、その葬儀に。ついでに、ちょっと疑問があって……。というのだけれど、いくら「正義感」が強くても、30年も自分を省みなかった父のこと、その父のまわりに起きていることに、なぜ関心を持つ? その理由が、わからないねえ。チョン・ジェヨンの目付きとは違って、何も語らない目だ。
地下トンネルを含め、セットが軽いのも、映画をつまらなくしている。もっと、時間がたったもの、つかいこなされたもの、という感じがしないと……。
それに。
もしかすると、この映画が背景に利用している「祈祷院」の集団虐殺(集団自殺?)は韓国では有名な話なのかもしれないけれど、そういうことが起きるまでの過程がさらりとしか描かれていないのも、この映画をあじけなくしている。もっとも、それを描いてしまうと、また別の映画になってしまうのかもしれないけれど。
 | シルミド / SILMIDO [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| アミューズソフトエンタテインメント |



















