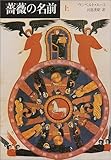鈴木志郎康「地図には載っていない」「二本の杖」(「現代詩手帖」2011年01月号)
鈴木志郎康「地図には載っていない」は奇妙な詩である。
1連目は、3連目で書かれている「草の詩」そのものだろう。2連目も「草の詩」の内容かもしれない。
雑草が地図に載っていないのは、それが細密な植物分布図(分布地図)でもないかぎり当然のことだろう。地図には動かないもの、ある程度の時間そこにあるものしか載っていない。時間とともにかわるもの(草のように生えたり枯れたりして存在が移り変わるもの)は載せようがない。
そんなことはわかってる。わかっているけれど、そのことを思ってしまった。だから、それをことばにする。「無意味」なことばを、無意味なまま、そこに存在させる。それが詩である。もしかすると、そのことばは「根を張」るかもしれない。雑草のように生きるかもしれない。詩として、生きるかもしれない。
--と、鈴木が考えたかどうかはわからないが、この夜中にふいに動いたことばをそのままとっておき、何とかしたいという気持ちはなかなかおもしろい。
そして、ここまでなら、私は別に(?)困らない。このあと、鈴木の詩はもう1連つづくのだ。
困ってしまった。これは何だろう。この「論理」は何だろう。雑草・ヒメジョオンが地図に載っていないのはなぜ? 雑草の「身体があやふやだから」? 雑草が地図に載っていないと猫や人が地図に載っていないを結びつけるのは何?
だいたい「ひと」が地図に載っていないのは、「ひと」の「身体があやふや」という理由からではないだろう。地図に「ひと」など載せない、というのが「地図」の文法だからだろう。植物も同じ。ふつうの地図には植物も載せないというのが、地図の文法、地図製作の論理である。
とても変である。鈴木の書いていることは変である。変というのは、「論理」がない、「意味」がないということでもある。
でも、ほんとうに意味がない? 論理がない?
私は迷ってしまうのである。
「身体があやふやだからか」の「あやふや」につまずいてしまう。「あやふや」ということばに触れて、鈴木の書いていることを信じてしまいそうになるのである。
「あやふや」を鈴木はどうとらえているのか。雑草のように、身体はある一定の期間を過ぎたら雑草が枯れるように死んでしまうから「あやふや」というのだろうか。
3連目が、急に気になるのである。
そこで具体的に書かれているのは「草の詩」であるが、詩にかぎらず、ふと何かが頭の中に鮮明に浮かび上がることがある。それはその瞬間とても重要なことに思える。かけがえのない何か、絶対にことばにしておかなければならない何かに見えることがある。でも、それは「翌朝起きて/憶えている」かどうかわからないものである。言い換えると、「あやふや」なものである。
そういうものがあるのだ。
そこにある。けれど、それはいつまでもありつづけるとはかぎらない。そういうものを「あやふや」と鈴木は呼んでいる。ヒメジョオンも、それについて思いめぐらしたことばも、ひとも(妻もわたしも、猫も)、確かにいま、ここに存在する。存在するけれども、存在しつづけるかどうかはわからない。--だから地図には載せない。うーん、それは「論理的」な説明だなあ。「あやふや」なものは地図には載せないというのは確かにいえることではあるなあ。
一方、ことばはどうだろう。ひとの考えは、夜中に目覚めて思いつく「詩」のように、ふいに消えるものもある。存在が「あやふや」であることもある。ところが、書かれてしまうと、それは「あやふや」ではなくなる。「意味・論理」は「あやふや」でも、そのことば自体は「あやふや」ではない。いつでも読むことができる。
そうすると、それは地図に載せてもいいもの? 地図に載っているもの?
いや、そうじゃないぞ。
詩はやっぱり「あやふや」なものなのである。だから、地図には載っていないのだ。どこかに「載る」ことで「定着」してしまっては、それはもう詩ではない--鈴木は、そういいたいのかもしれない。
ここから鈴木は、逆にことばを動かしていく。詩について語りはじめている。そこにある、けれども、それ以外は何の意味も持たない「あやふやなことば」、それが詩であるという方向に進んでいくのだと思う。
あらゆる「感動」を排除し、ただそこにある、わけのわからない「あやふやなことば」う詩として提出しようとしているのだ。ことばを解体し「あやふや」にしてしまうことこそ、詩なのである。
「二本の杖」は鈴木の実体験を描いているのだろうか。
最終行の疑問。答えられますか? 「あやふや」な気持ちになる。鈴木は、いま「あやふや」を書きたいんだなあと、思った。

鈴木志郎康「地図には載っていない」は奇妙な詩である。
庭には草が生えている
地図には載っていない
ああ
草が根を張っている
その草の名称は
ヒメジョオン
雑草だ
草の詩を作った
夜中目覚めて
頭の中に
でも
翌朝起きて
憶えているだろうか
起きて
メモして
また寝た
1連目は、3連目で書かれている「草の詩」そのものだろう。2連目も「草の詩」の内容かもしれない。
雑草が地図に載っていないのは、それが細密な植物分布図(分布地図)でもないかぎり当然のことだろう。地図には動かないもの、ある程度の時間そこにあるものしか載っていない。時間とともにかわるもの(草のように生えたり枯れたりして存在が移り変わるもの)は載せようがない。
そんなことはわかってる。わかっているけれど、そのことを思ってしまった。だから、それをことばにする。「無意味」なことばを、無意味なまま、そこに存在させる。それが詩である。もしかすると、そのことばは「根を張」るかもしれない。雑草のように生きるかもしれない。詩として、生きるかもしれない。
--と、鈴木が考えたかどうかはわからないが、この夜中にふいに動いたことばをそのままとっておき、何とかしたいという気持ちはなかなかおもしろい。
そして、ここまでなら、私は別に(?)困らない。このあと、鈴木の詩はもう1連つづくのだ。
そういえば
猫も
妻もわたしも
ひとはだれも
身体があやふやだからか
地図には載ってない
困ってしまった。これは何だろう。この「論理」は何だろう。雑草・ヒメジョオンが地図に載っていないのはなぜ? 雑草の「身体があやふやだから」? 雑草が地図に載っていないと猫や人が地図に載っていないを結びつけるのは何?
だいたい「ひと」が地図に載っていないのは、「ひと」の「身体があやふや」という理由からではないだろう。地図に「ひと」など載せない、というのが「地図」の文法だからだろう。植物も同じ。ふつうの地図には植物も載せないというのが、地図の文法、地図製作の論理である。
とても変である。鈴木の書いていることは変である。変というのは、「論理」がない、「意味」がないということでもある。
でも、ほんとうに意味がない? 論理がない?
私は迷ってしまうのである。
「身体があやふやだからか」の「あやふや」につまずいてしまう。「あやふや」ということばに触れて、鈴木の書いていることを信じてしまいそうになるのである。
「あやふや」を鈴木はどうとらえているのか。雑草のように、身体はある一定の期間を過ぎたら雑草が枯れるように死んでしまうから「あやふや」というのだろうか。
3連目が、急に気になるのである。
そこで具体的に書かれているのは「草の詩」であるが、詩にかぎらず、ふと何かが頭の中に鮮明に浮かび上がることがある。それはその瞬間とても重要なことに思える。かけがえのない何か、絶対にことばにしておかなければならない何かに見えることがある。でも、それは「翌朝起きて/憶えている」かどうかわからないものである。言い換えると、「あやふや」なものである。
そういうものがあるのだ。
そこにある。けれど、それはいつまでもありつづけるとはかぎらない。そういうものを「あやふや」と鈴木は呼んでいる。ヒメジョオンも、それについて思いめぐらしたことばも、ひとも(妻もわたしも、猫も)、確かにいま、ここに存在する。存在するけれども、存在しつづけるかどうかはわからない。--だから地図には載せない。うーん、それは「論理的」な説明だなあ。「あやふや」なものは地図には載せないというのは確かにいえることではあるなあ。
一方、ことばはどうだろう。ひとの考えは、夜中に目覚めて思いつく「詩」のように、ふいに消えるものもある。存在が「あやふや」であることもある。ところが、書かれてしまうと、それは「あやふや」ではなくなる。「意味・論理」は「あやふや」でも、そのことば自体は「あやふや」ではない。いつでも読むことができる。
そうすると、それは地図に載せてもいいもの? 地図に載っているもの?
いや、そうじゃないぞ。
詩はやっぱり「あやふや」なものなのである。だから、地図には載っていないのだ。どこかに「載る」ことで「定着」してしまっては、それはもう詩ではない--鈴木は、そういいたいのかもしれない。
ここから鈴木は、逆にことばを動かしていく。詩について語りはじめている。そこにある、けれども、それ以外は何の意味も持たない「あやふやなことば」、それが詩であるという方向に進んでいくのだと思う。
あらゆる「感動」を排除し、ただそこにある、わけのわからない「あやふやなことば」う詩として提出しようとしているのだ。ことばを解体し「あやふや」にしてしまうことこそ、詩なのである。
「二本の杖」は鈴木の実体験を描いているのだろうか。
左の股関節を手術した
人工股関節に置換して
リハビリ中
歩くのに
二本の杖を使っている
右の杖に力を入れて
前に進む
左の杖は支え
ところが左の杖に力を入れて
しまって
アイタタとなる
左脚に負担が掛かり
痛いのだ
力の入れ方を間違えたということ
この失敗を
笑ったものだろうか
最終行の疑問。答えられますか? 「あやふや」な気持ちになる。鈴木は、いま「あやふや」を書きたいんだなあと、思った。
 | 胡桃ポインタ―鈴木志郎康詩集 |
| 鈴木 志郎康 | |
| 書肆山田 |