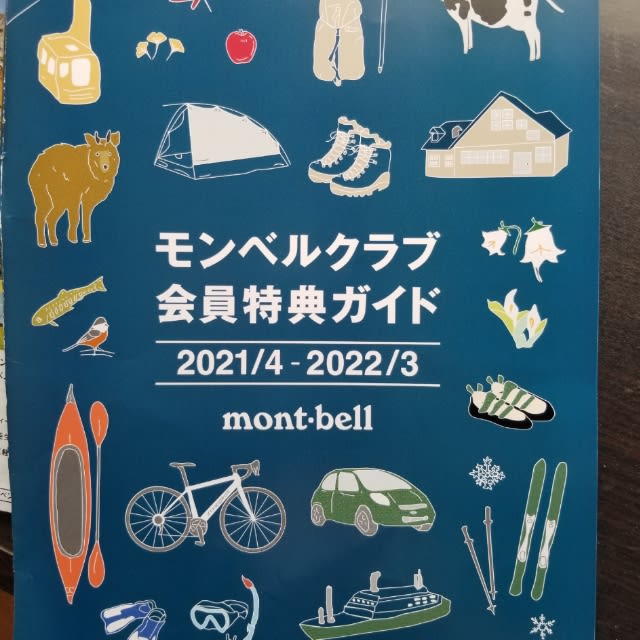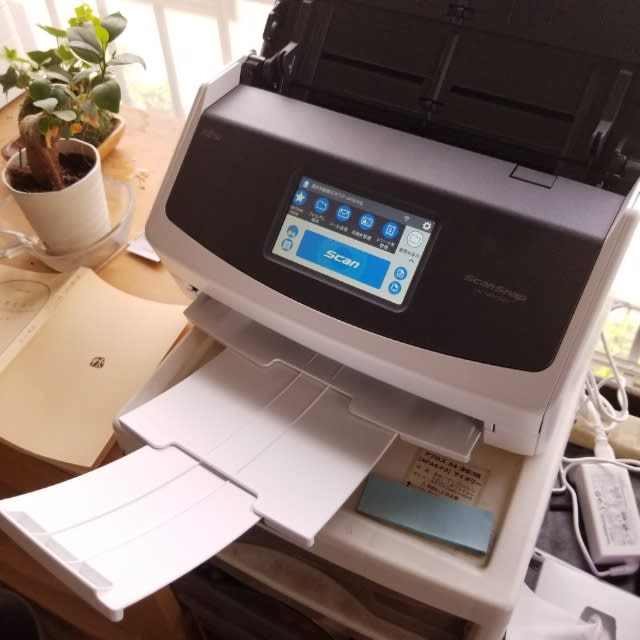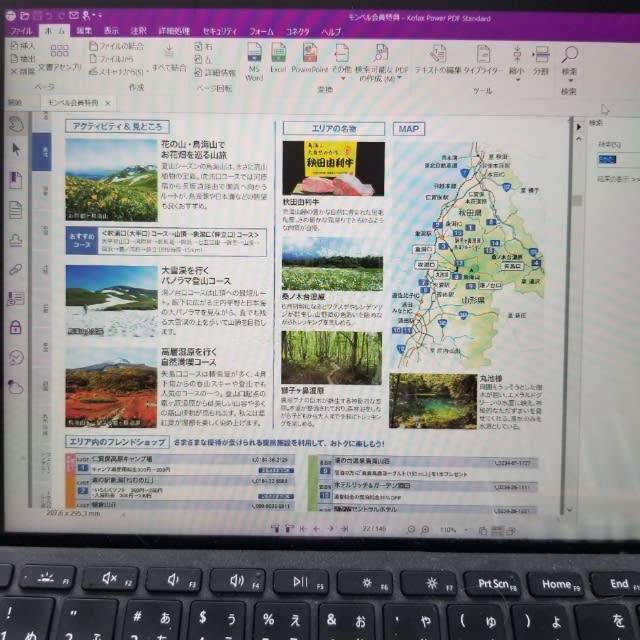現在メルマガに「サラリーマンOBの充実シニアライフ構築術」というタイトルで具体策を数回に分けて連載中です。
第1回目が「マネーライフプラン」で第2回目が「幸福寿命を延ばす」です。こちらはまもなく(6月1日)に公開される予定です。
その次のテーマとしては「口座情報や定期購入契約を可視化して家族にわかるようにしておく」というものですが、これだけでは面白味が乏しいので「やるべき終活・よく考えるべき終活」というタイトルで間口を広げてみることにしました。
というのは今マスコミは終活ブームで賑わっています。たとえば今発売されている週刊現代には「夫が亡くなった後妻が亡くなった後私はここで失敗した」という特集が組まれています。週刊ポストには「『子供のために』その気配りで大失敗!」という特集を組んでいます。
コロナウイルス感染防止のため、おうち時間が増える中「終活を始めようか?」という人が増えているのでしょう。マスコミ側も何回か使い回しが効くネタなので力を入れているのだと思います。
実はこの手の話にはサクセスストーリーとホラーストーリーの二つのストーリーがあります。サクセスストーリーはこうすればうまく行った、円満に解決したという話でホラーストーリーというのは、こうしたから失敗した(だからこうすることを避けなさい)という話です。
一般にセールスでインパクトがあるのはホラーストーリーです。「あなたのおうちのトイレで良い匂いがするとお客様が喜びますから芳香剤を買ってください」というのがサクセスストーリー。「あなたのおうちのトイレが臭いと近所で悪い噂が立ちますよ。だから消臭剤を買いなさい」というのがホラーストーリーです。
週刊誌の終活ストーリーも概ねホラー型が多いですね。我々には他人の失敗談を聞くと喜びを感じる感情が埋め込まれているのかもしれません。
さて終活の失敗例として出てくるのが、お葬式とお墓の問題です。
亡くなった本人としては良かれ、と思ってお葬式やお墓の段取りをつけてもそれが残された家族の重荷になってしまうという話です。例えば自分が自然が好きで遠くの田舎に埋葬を希望するが、残された家族はお墓参りに行くのが大変で困ってしまうという話を耳にします。
最近の週刊現代には、亡くなった夫が「クラッシックが好きだったので、葬儀は「音楽葬」にしてください」とエンディングノートに書き残し、それを見た奥さんが葬儀会社を駆けずり回るという話がでていました。どこの葬儀会社も音楽葬は難しいと断ってきたのです。
これらのエピソードは、葬儀やお墓についてクセの強い注文をエンディングノートに残すと残された家族が苦労することを示しています。
我々は「葬式やお墓は誰のためにあるのか?」ということを考えてみる必要があります。
日本の葬式では坊さんが来てお経を称えることが一般的ですが、本来の仏教には読経で死者が救われるという考え方はありません。
釈迦が80年の生涯で説いた教えは如何に生きるか?であり、如何に迷いから覚め悟りに至るかということで葬式や死者のための仏事を執り行ったことは一度もなかったと言われています(現在のヒンドゥ教の葬儀でも僧侶は参加しません)。
浄土真宗を開いた親鸞は「父母の孝養のために念仏を唱えたことは一度もない」と述べています。つまり死んだ人を幸福にすると信じられている追善供養など一度もしたことがないと断言しているのです。
以上のような先哲の教えを参考にするならば、葬儀に坊さんが来てお経を読む本来の目的は、死者の魂を成仏されるためではなく、残されたか人々に会者定離の真理を説き、必要以上の悲しみに陥ることを留めることにあることがわかります。
そしてお墓は残された者が死者の思い出を偲ぶ場と理解するべきでしょう。
もしこの考え方が正しいとすれば、葬式やお墓は残された人が便利なように取り計らうべきなのです。
なお「濃い宗教」の社会に生きている人々は葬礼が風習として定着しているので考える必要はありませんが、葬礼のあり方が揺れている現在に日本では自分たちで決めていかなければならないことが実に多いのです。
「終活」は重要ですが、残された家族のことを考慮しない終活は家族を困らせることになります。終活の中には熟慮が必要なものがあることを認識しておきましょう。